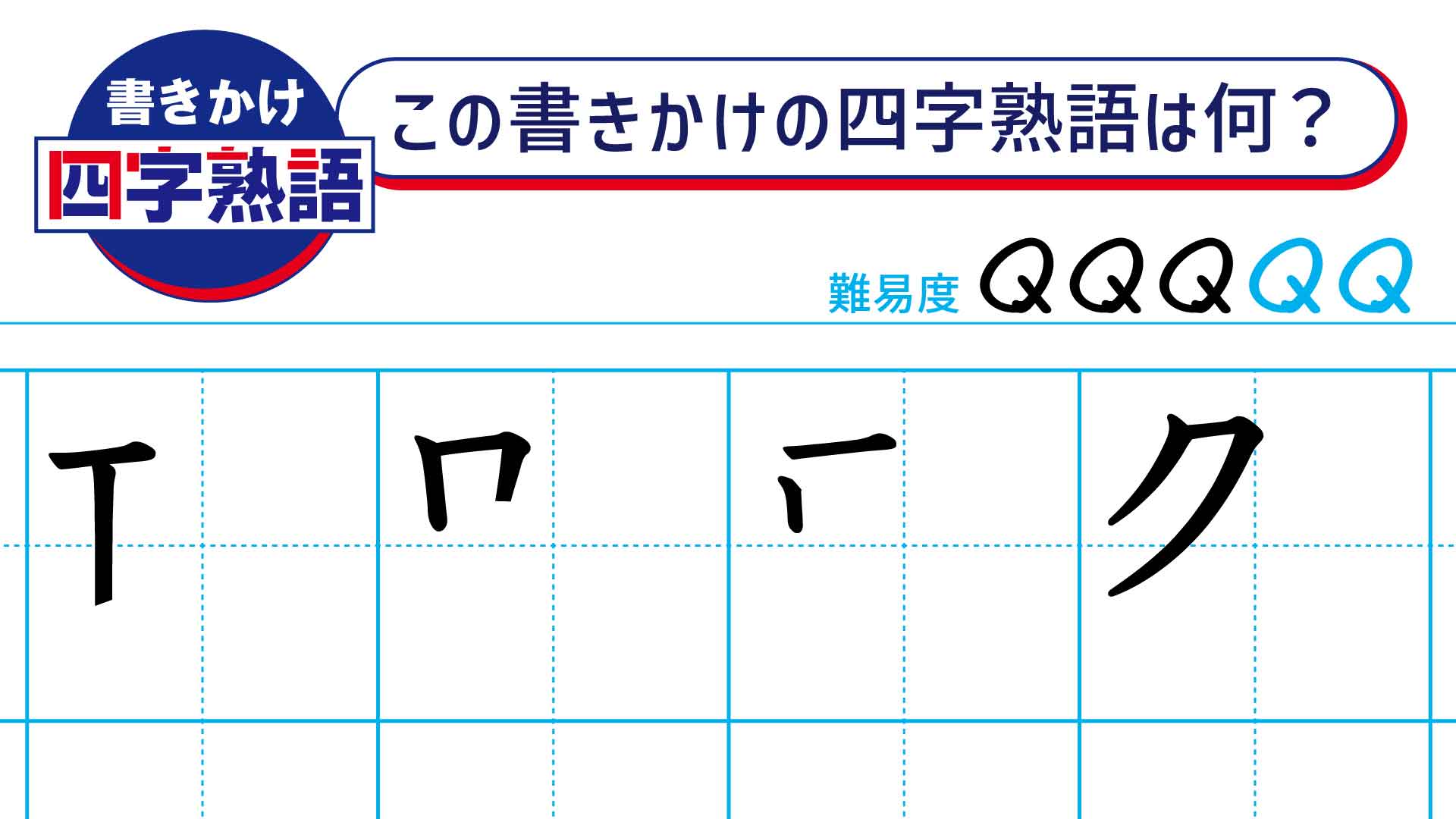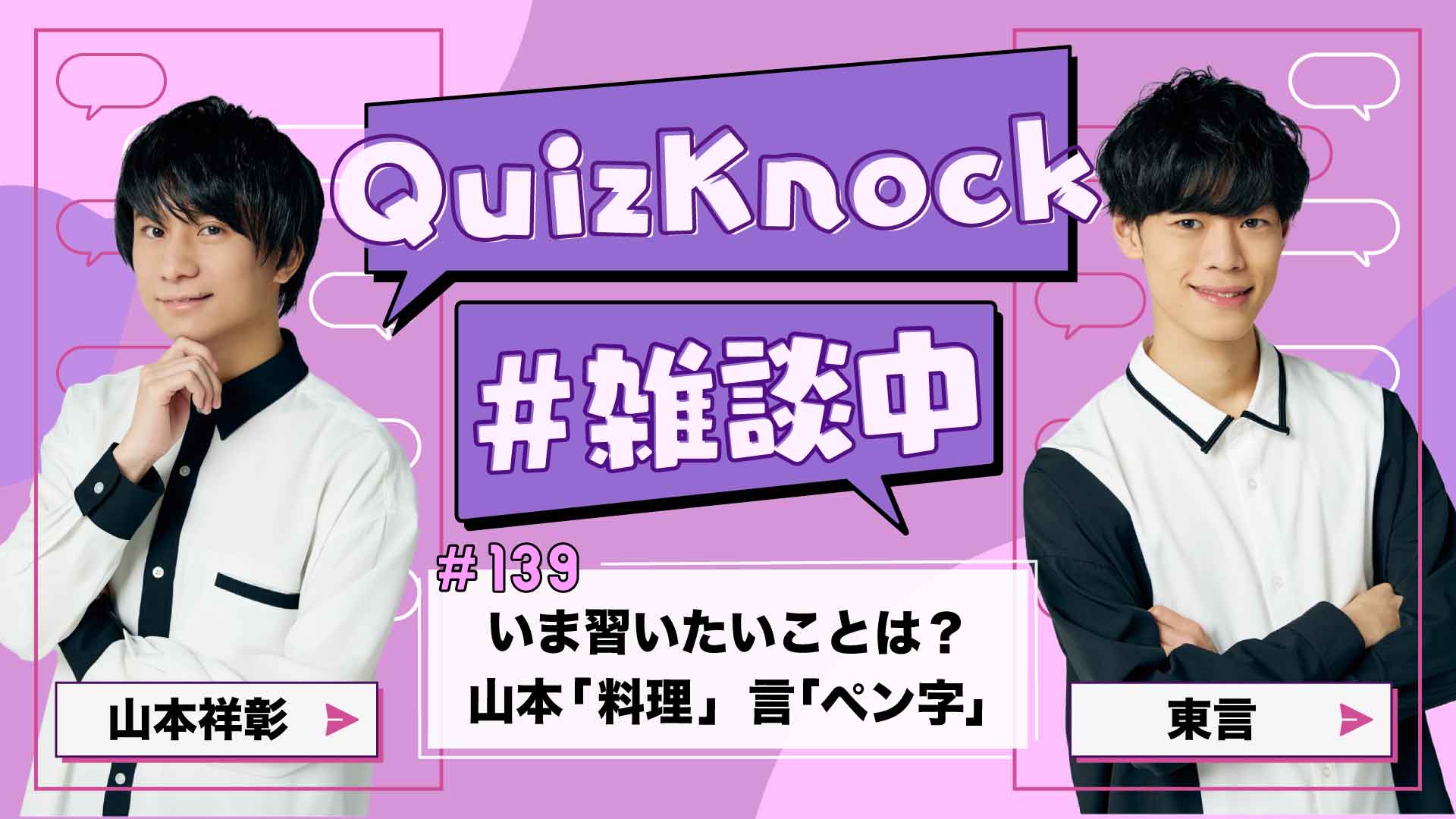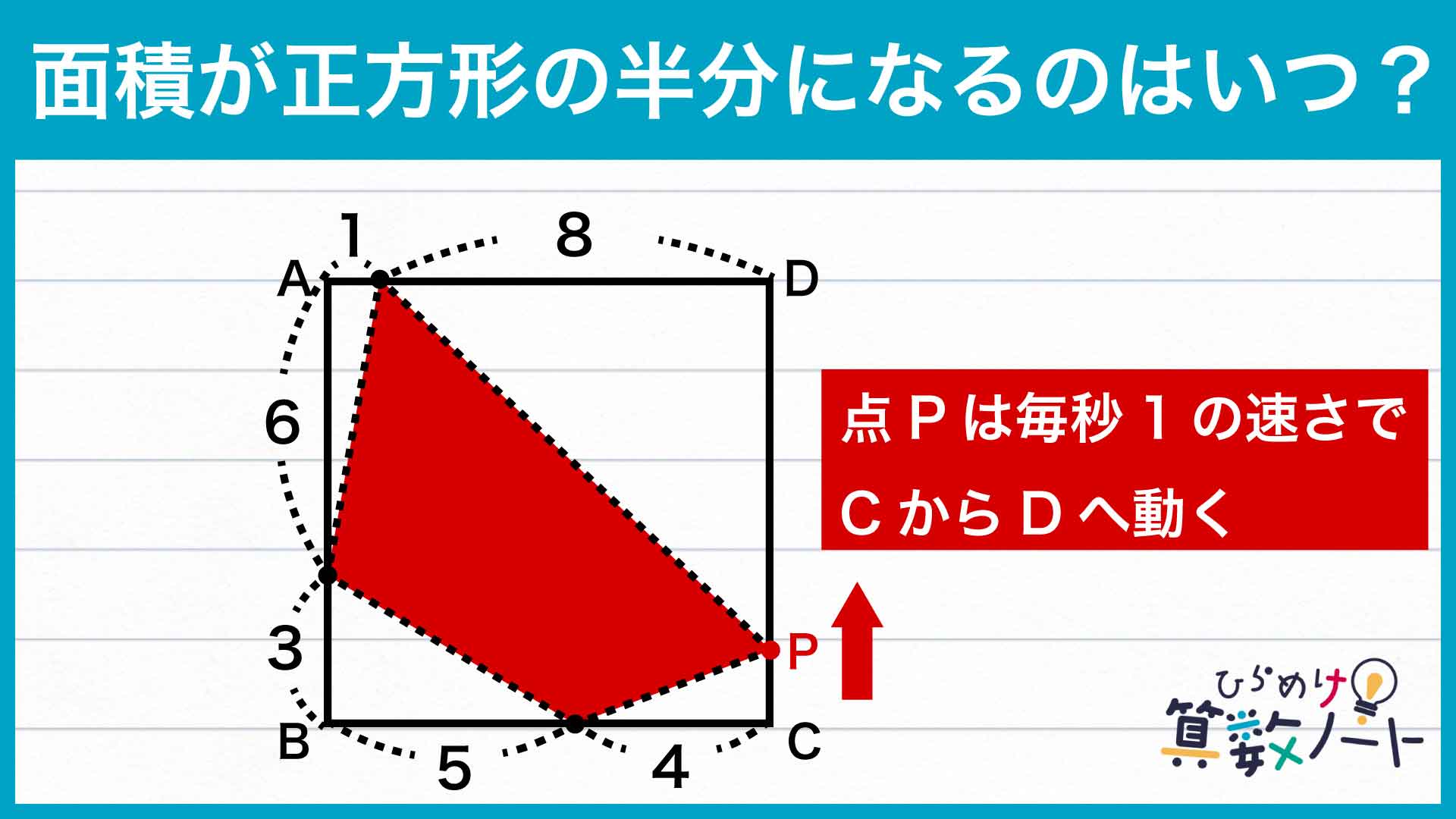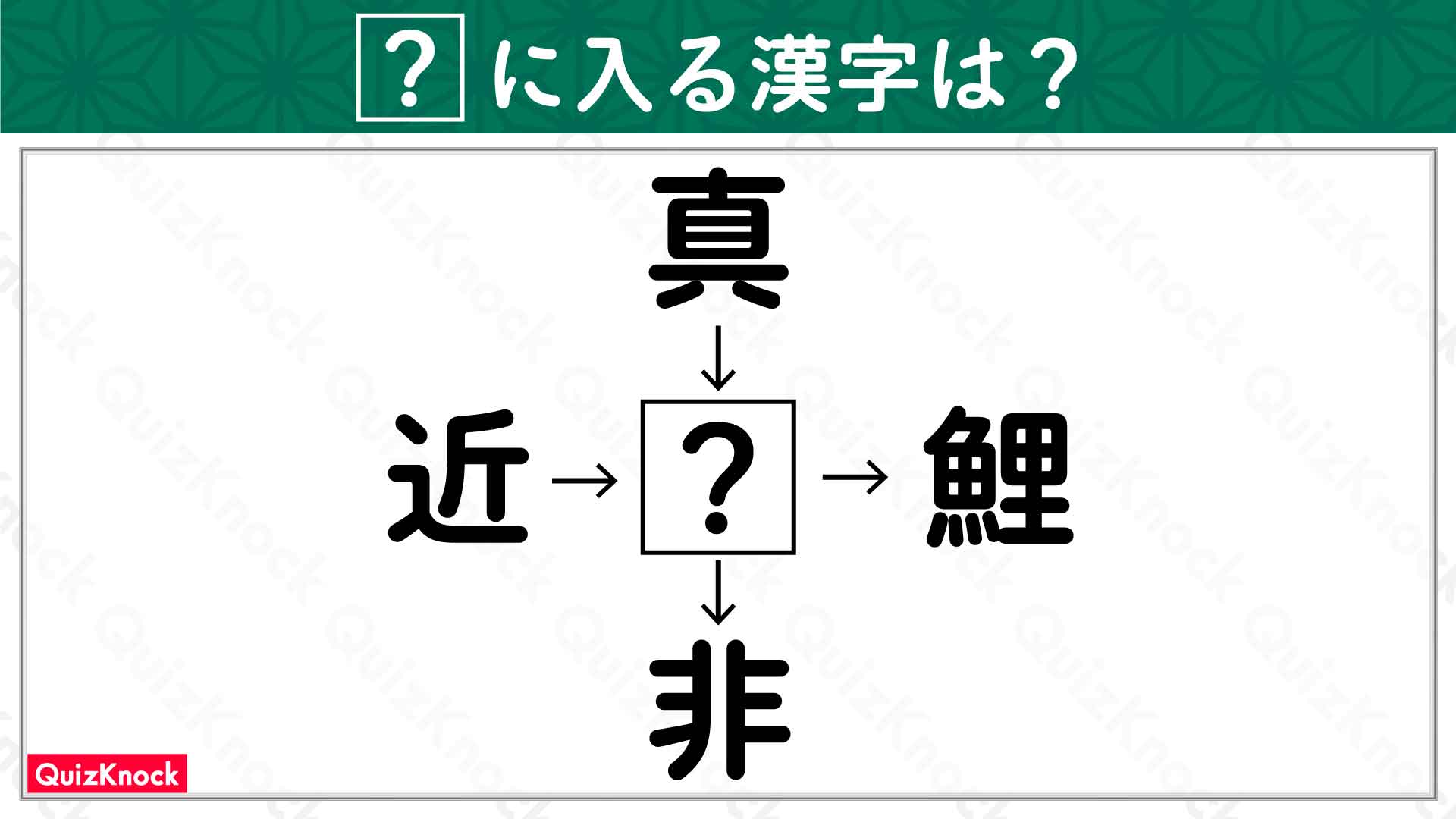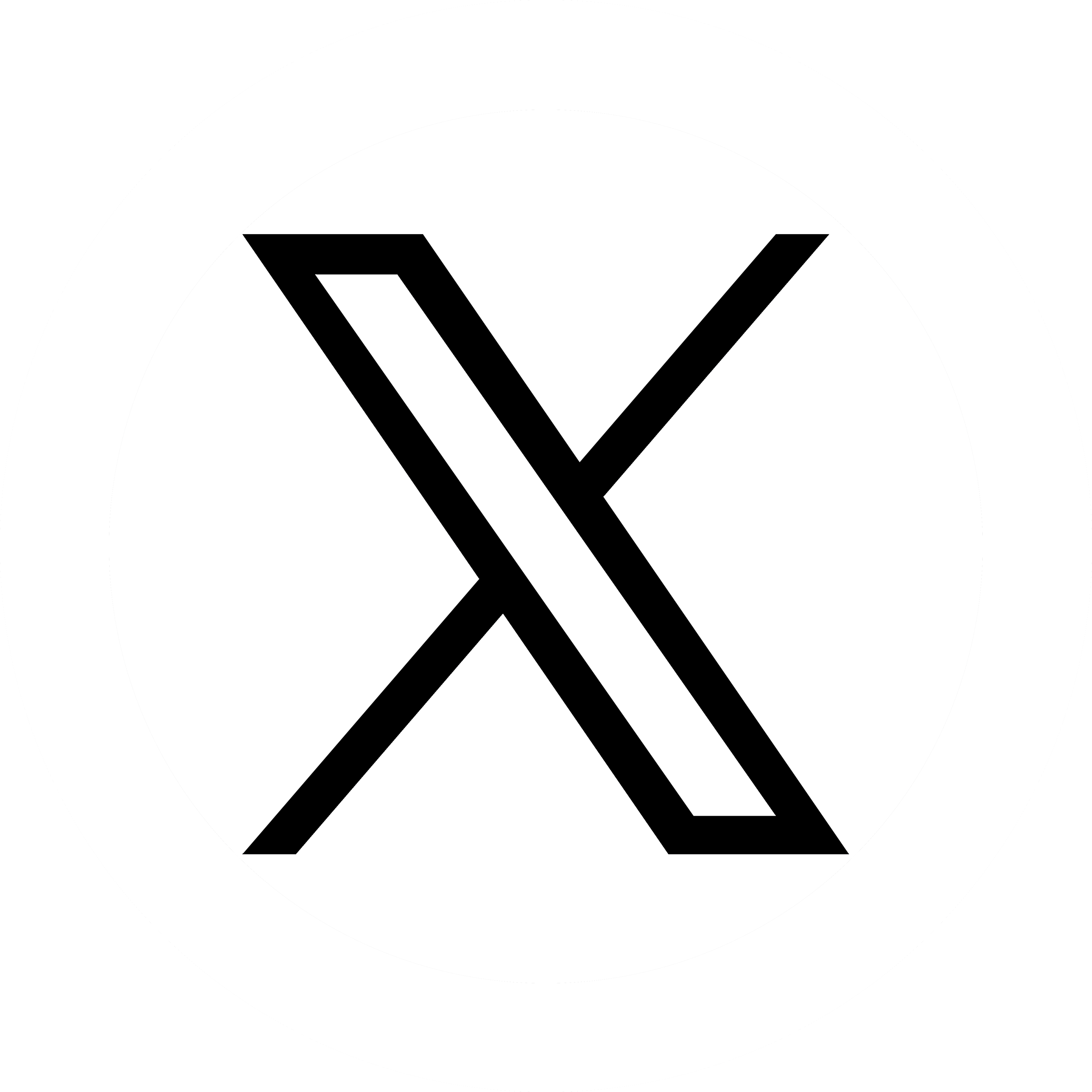クイズに出会って、クイズに青春を捧げた。
2009年には「高校生クイズ」でベスト4。2010年には伊沢・大場と優勝旗を手にした。
大学に進学したとき、僕はクイズをやめた。
それから紆余曲折あって、いまはクイズと人生の区別がつかなくなった人たちのすぐそばで働いている。
そんな僕に、伊沢拓司から「クイズのある暮らし」というテーマで記事を書いてくれないかと依頼があった。
わざわざ僕に依頼してくるのだから、クイズ大会に出たり、友達とフリバ※をしたりする生活について書いてほしいわけではないだろう。かつて彼と過ごした高校時代のように、がむしゃらで危なっかしい密度のクイズは、いまの僕の生活のどこにも見当たらない。
※フリバ:「フリーバッティング」の略。早押しクイズを繰り返すクイズの練習方法のひとつ。
 ▲高校時代の筆者(右)
▲高校時代の筆者(右)
僕がクイズをやめた理由はいろいろある。もちろん、クイズが嫌いになったわけではない。どちらかといえば、高校時代にひたすらクイズに打ち込んだことで変化した僕の身体が、別のことをやりたいと感じるようになったのだ。
屁理屈のようだが、クイズではないことをやっている僕のなかに、クイズが息づいている。今回は、その変化について書くことで「クイズのある暮らし」というお題に応えようと思う。
田村 正資(たむら・ただし)
1992年生まれ、東京都出身。開成高校3年生のとき、「第30回高校生クイズ」(日本テレビ系)で優勝。当時のチームメイトである伊沢拓司は2年後輩にあたる。東京大学に進学し、大学院では哲学の研究で博士号を取得。現在は株式会社batonで新規事業などを手掛ける。
クイズを通して知る、海の広さ
もう3年前のことになるが、文芸誌『ユリイカ』で「クイズの世界」という特集が組まれた。さまざまなバックグラウンドを持つ人たちが「クイズ」というお題で面白い文章を書いている(僭越ながら、僕も寄稿している)。
そのなかで、テレビのクイズ番組で長年活躍されている俳優の宮崎美子さんがこんなことを書いていた。
「勉強をするなかで、人間の文明の歴史というのは、有形無形すべてのものに名前をつけてきた歴史なんだということがわかりました。そして、そうした研究を続けている研究者の凄さを知りました。なんだか知という海の波打ち際で貝殻を一つ拾ったように思います。」
『ユリイカ』2020年7月号(青土社) 67ページ
知に圧倒される経験をしたひとの純粋な感動を表した言葉だと思った。僕にも、これと似たような経験がある。クイズ研究部に入って、はじめてクイズの問題集を紐解いたとき、目眩を覚えた。
砂時計のくびれた部分は「オリフィス」、ゴルフボールのちいさなくぼみは「ディンプル」、新潮文庫についているしおり紐は「スピン」……。いちどは見たことがある些細なものに、いちいち名前がついている。「こんなの、覚え始めたらキリがないじゃないか! まったく人類ってやつは……」などと思っていた。

とはいえ、クイズをやっていくうちにわかってきたのは、とにかくなんでもかんでも出題されるわけではないということ。そして、出題されそうなものを見極めるためには、自分でクイズを作ってみるのが一番いい、ということだ。
「クイズ」というコミュニケーション
ものすごく単純に言ってしまえば、クイズというのは「これ、なに?」という問いかけから始まる出題者と解答者のコミュニケーションだ。
楽しいコミュニケーションにしようと思ったら、それ相応の工夫が必要になる。「昨日の僕の夕飯はなに?」もクイズといえばクイズだけれど、昨日の僕の夕飯に興味があるひとは世の中にはほとんどいないだろう。
けれど、「日本で初めてラーメンを食べたひとはだれ?」と聞かれたら、昨日のぼくの夕飯よりも興味を持つひとは増えるはずだ。こういう問題だったら、正解できたら嬉しいし、正解できなくても「へぇー! そうだったんだ」という驚きがある。ちなみに、ラーメンを初めて食べた人物としてよく名前を挙げられるのは水戸光圀(水戸黄門)だが、これも諸説あるらしい。
つまり、楽しいクイズを出題しようと思ったら、意外だったり面白かったりする事実を見つけてくる「いい目の付け所」が必要なわけだ。

ふだんから「これはなんだろう?」というアンテナを張りめぐらせて、面白そうなものを記録するクセをつけておくと、クイズとして出題したくなる題材がなんとなくわかってくる。いままでまったく意識していなかった世界の細部に目を向けて、面白そうなものを見つけ出そうとする姿勢が、そのままクイズを楽しんで強くなることにつながっていく。
だから、自分でクイズを作って、誰かに出題してみることをオススメする。クイズの真髄は、答えることよりも出題することにあると言っても過言ではないと思っている。
……という具合に、僕はクイズをエンジョイするコツをつかみはじめていた。クイズのおかげで、身の回りの世界がいろんな情報を隠し持っていて、自分の切り口次第でいろんな顔を見せてくれることがわかり始めていた。
ところが、ある時期から僕はもっといろんなことが気になり始めてしまった。「これなんだろう?」よりもさらに「どうしてこうなっているんだろう?」という疑問の答えを考えることのほうが、楽しくなってしまったのである。
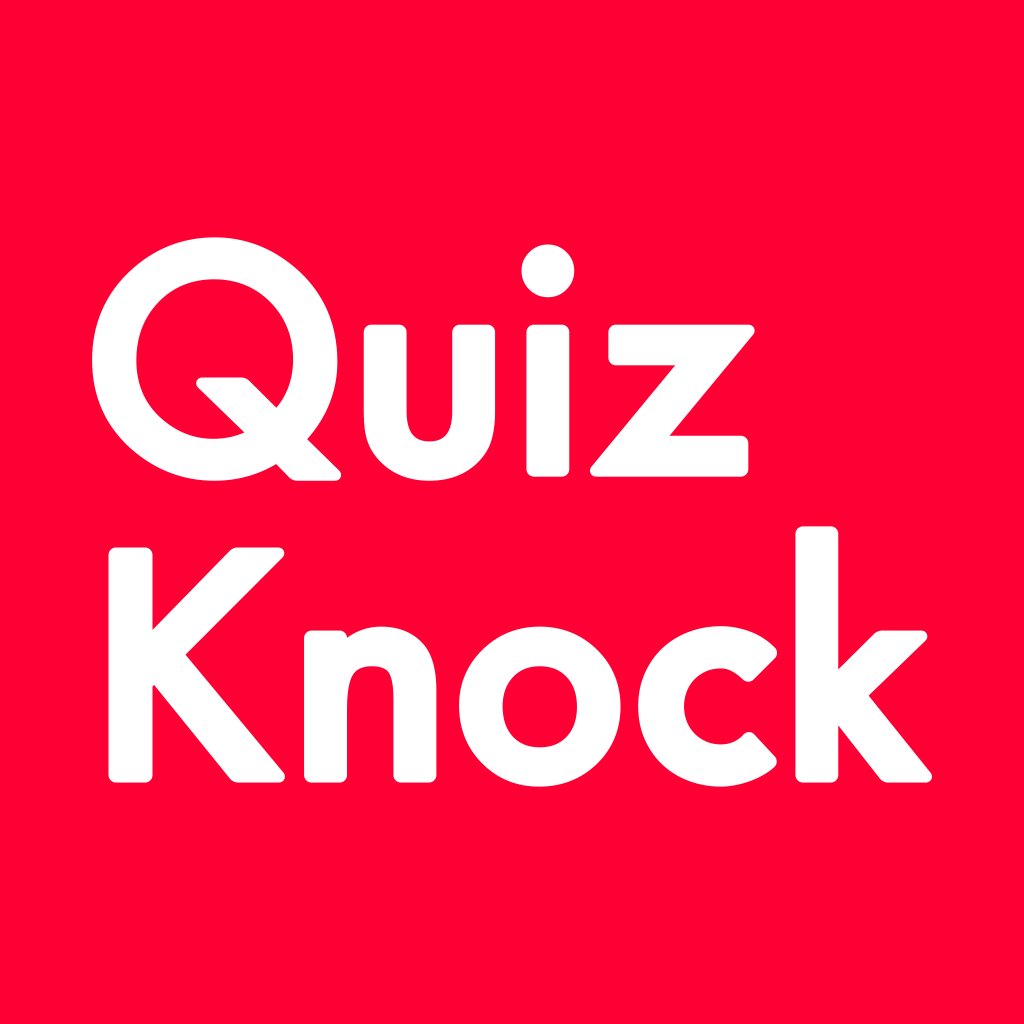



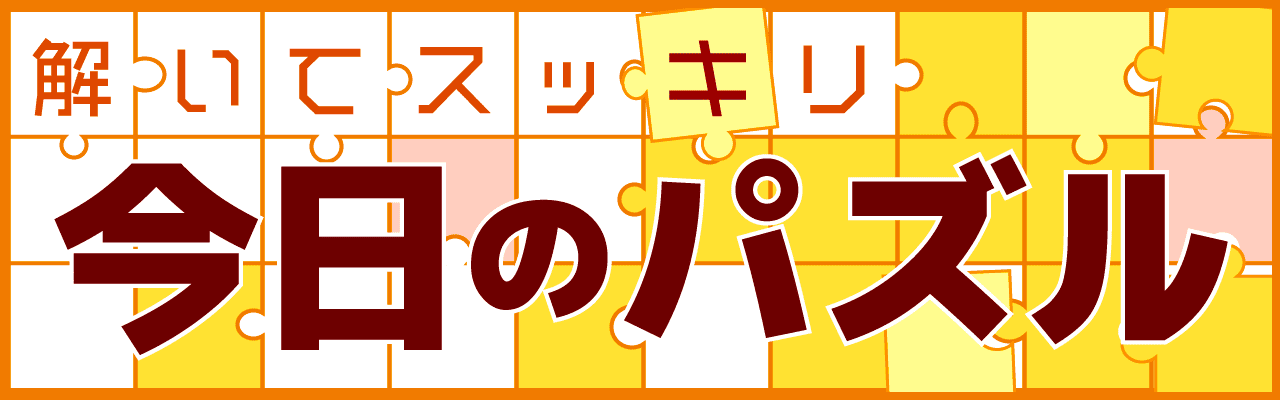
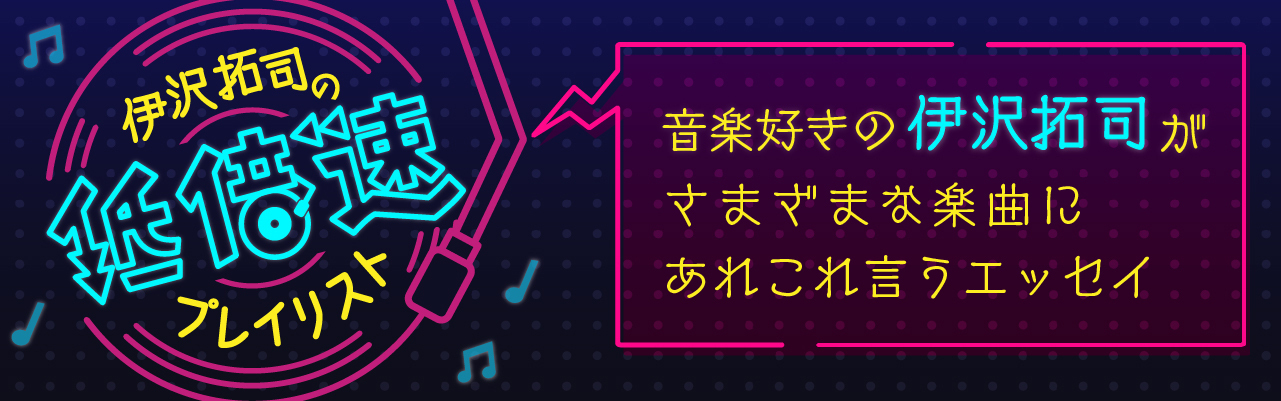

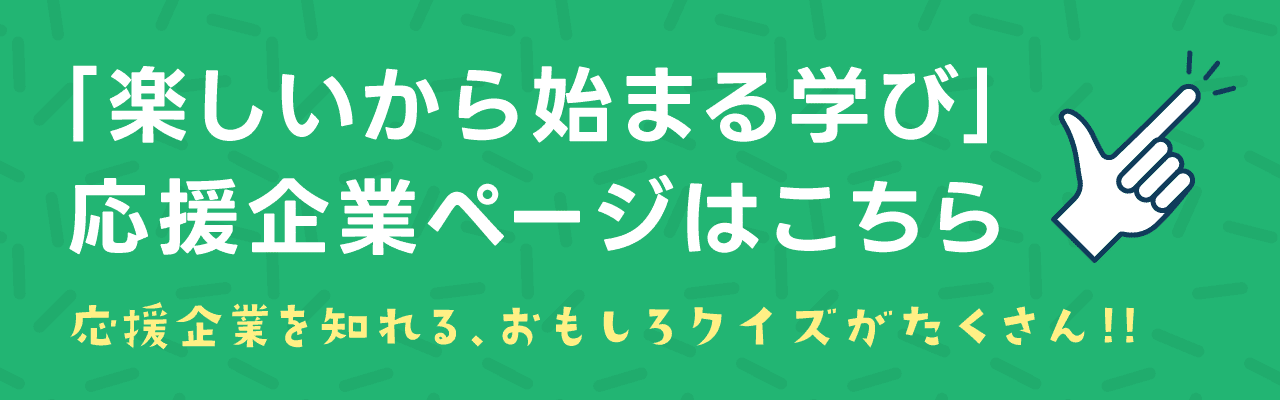

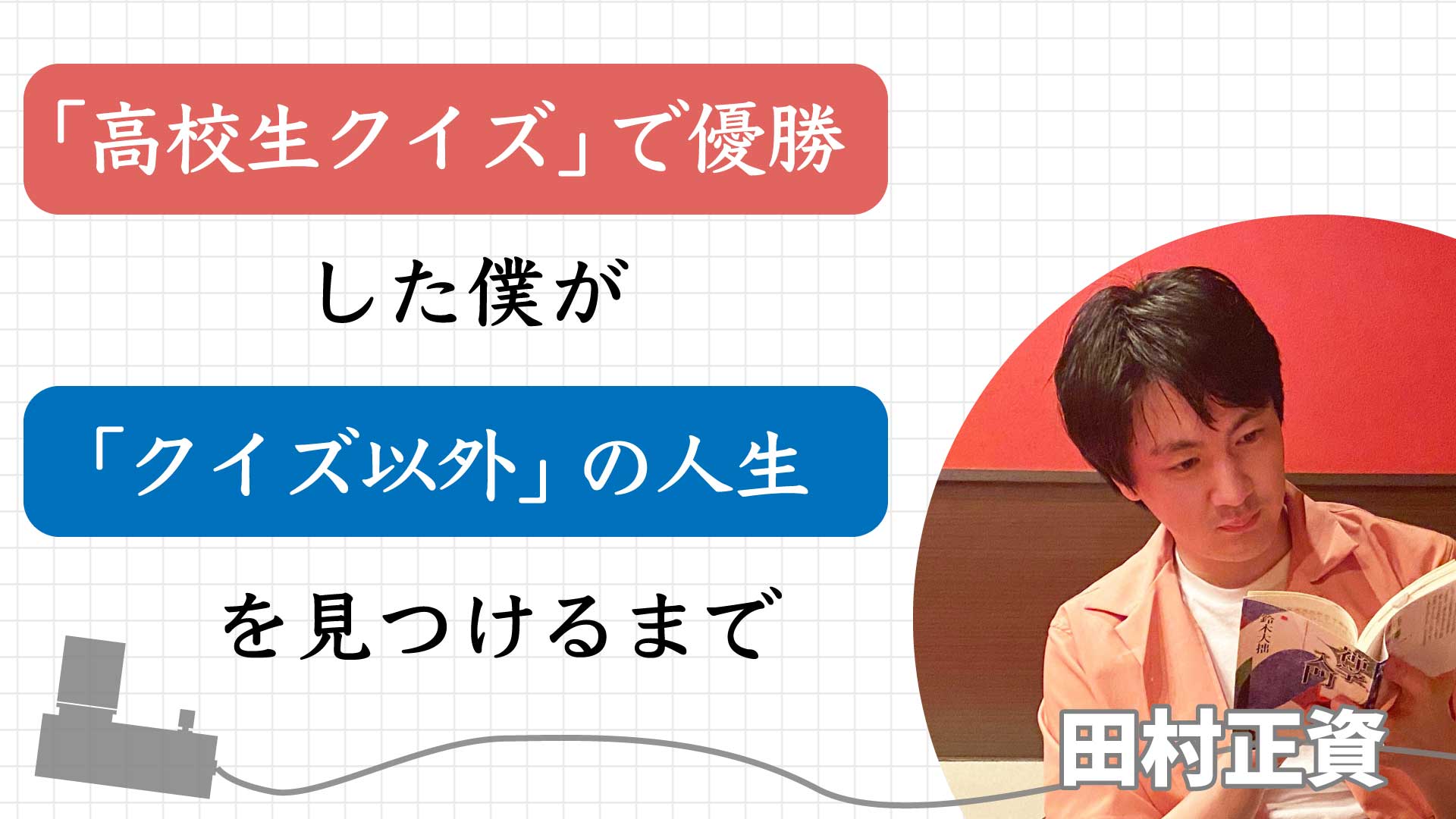

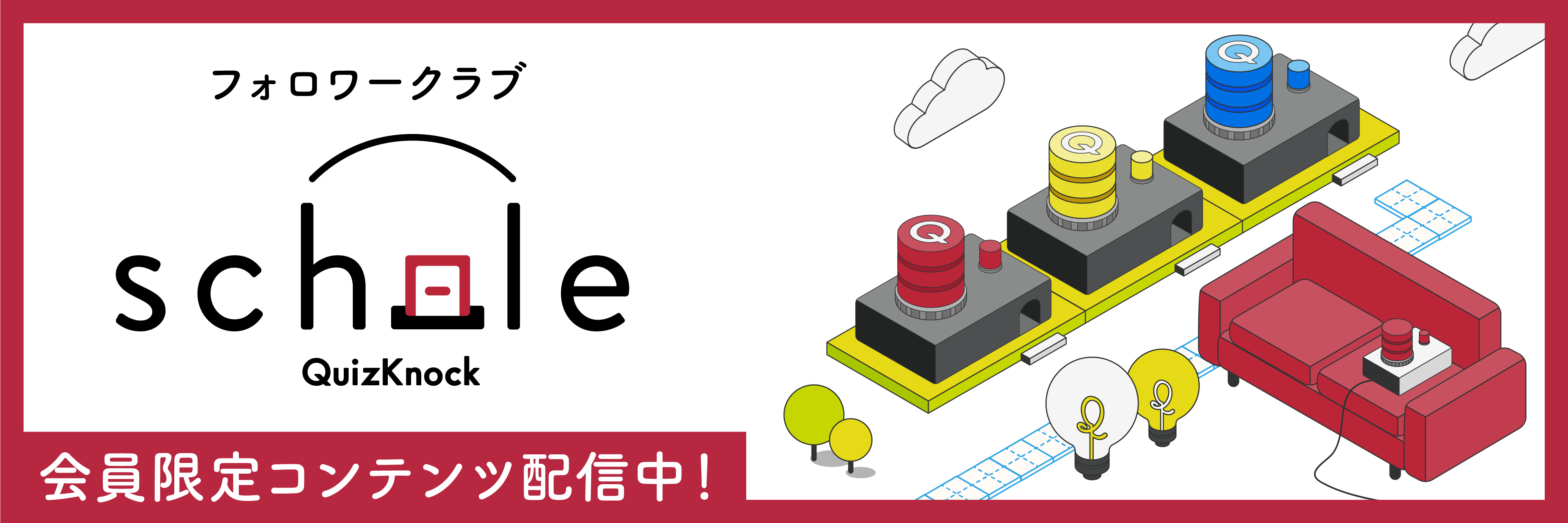









.jpg)