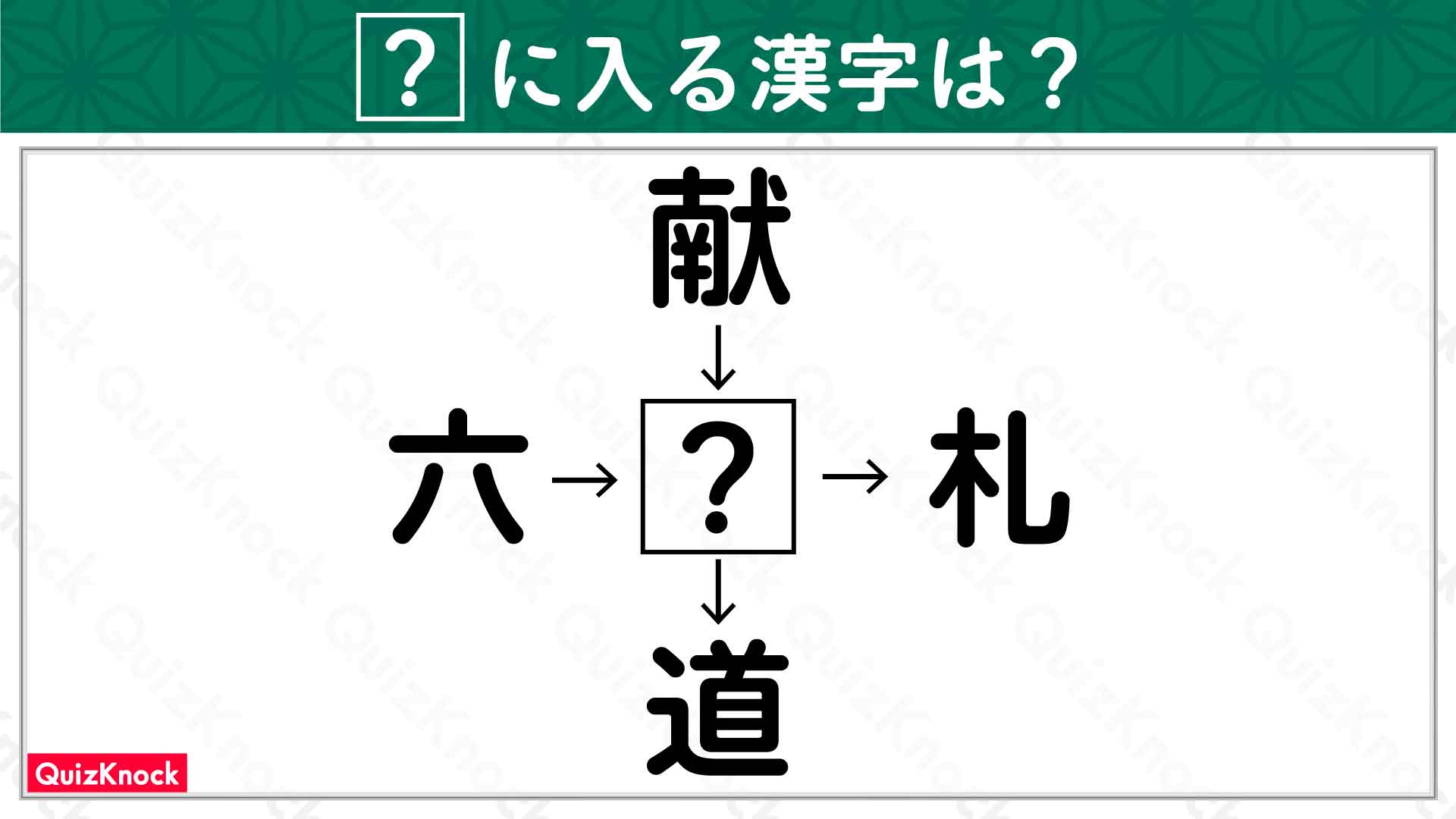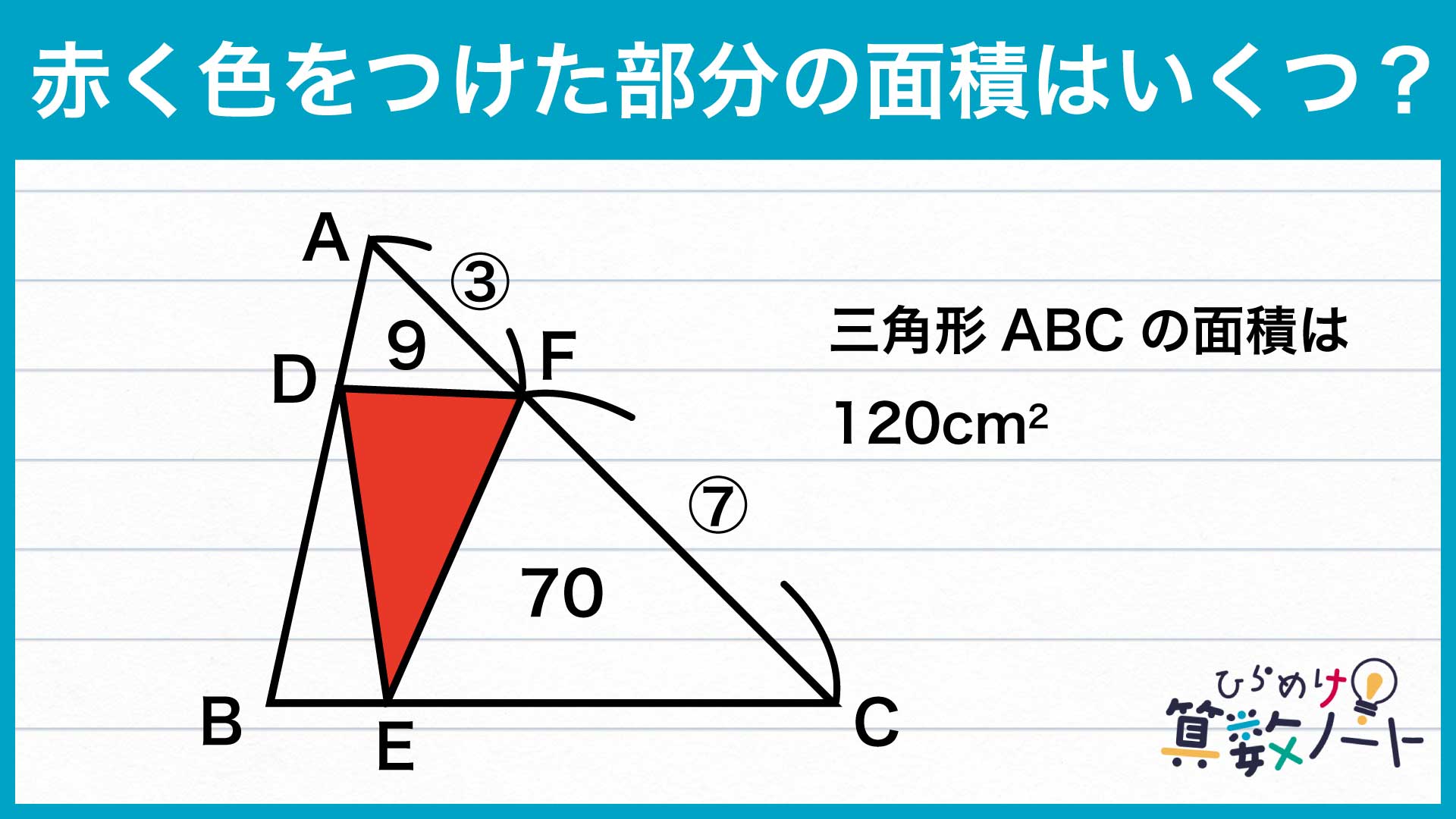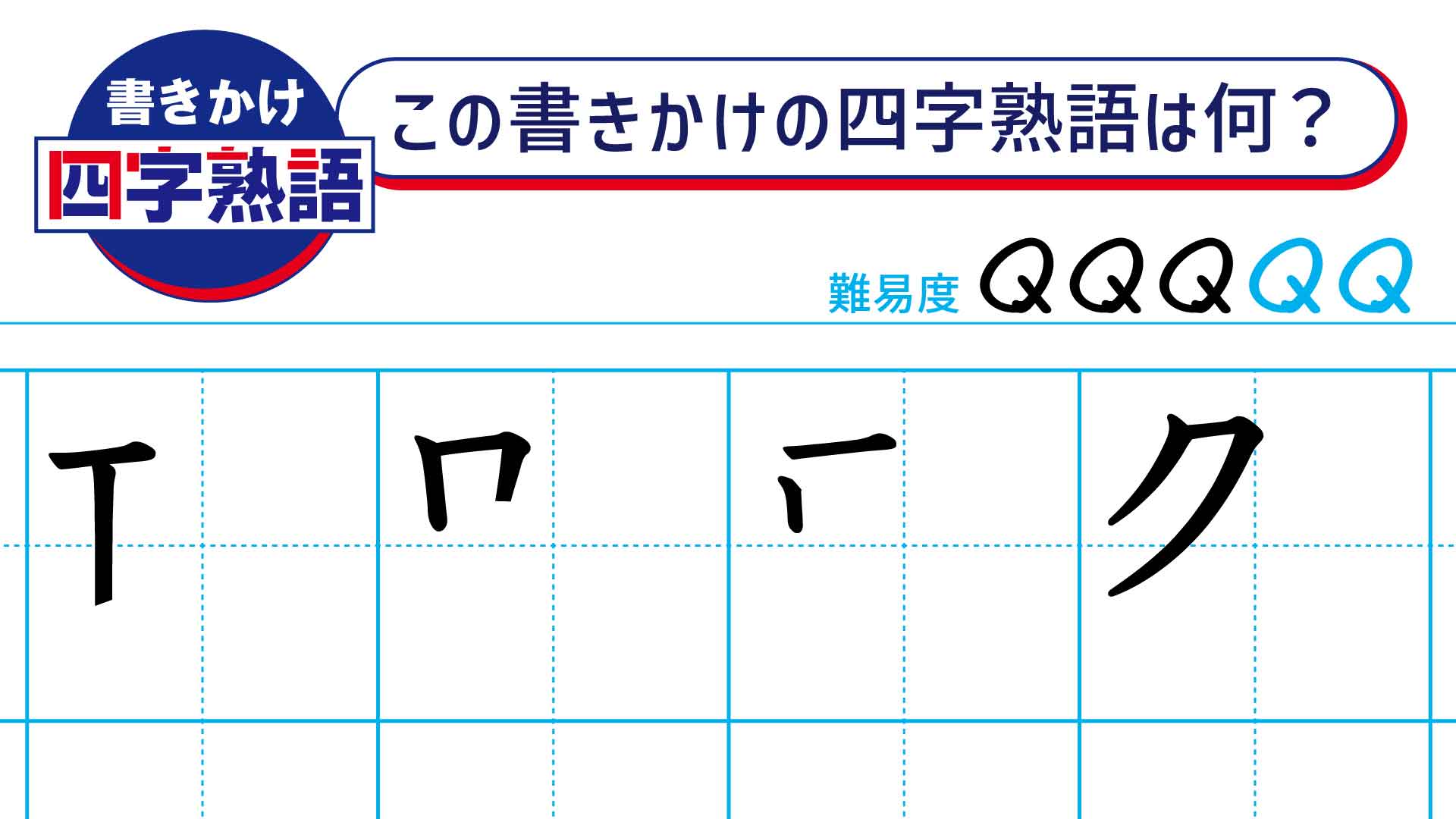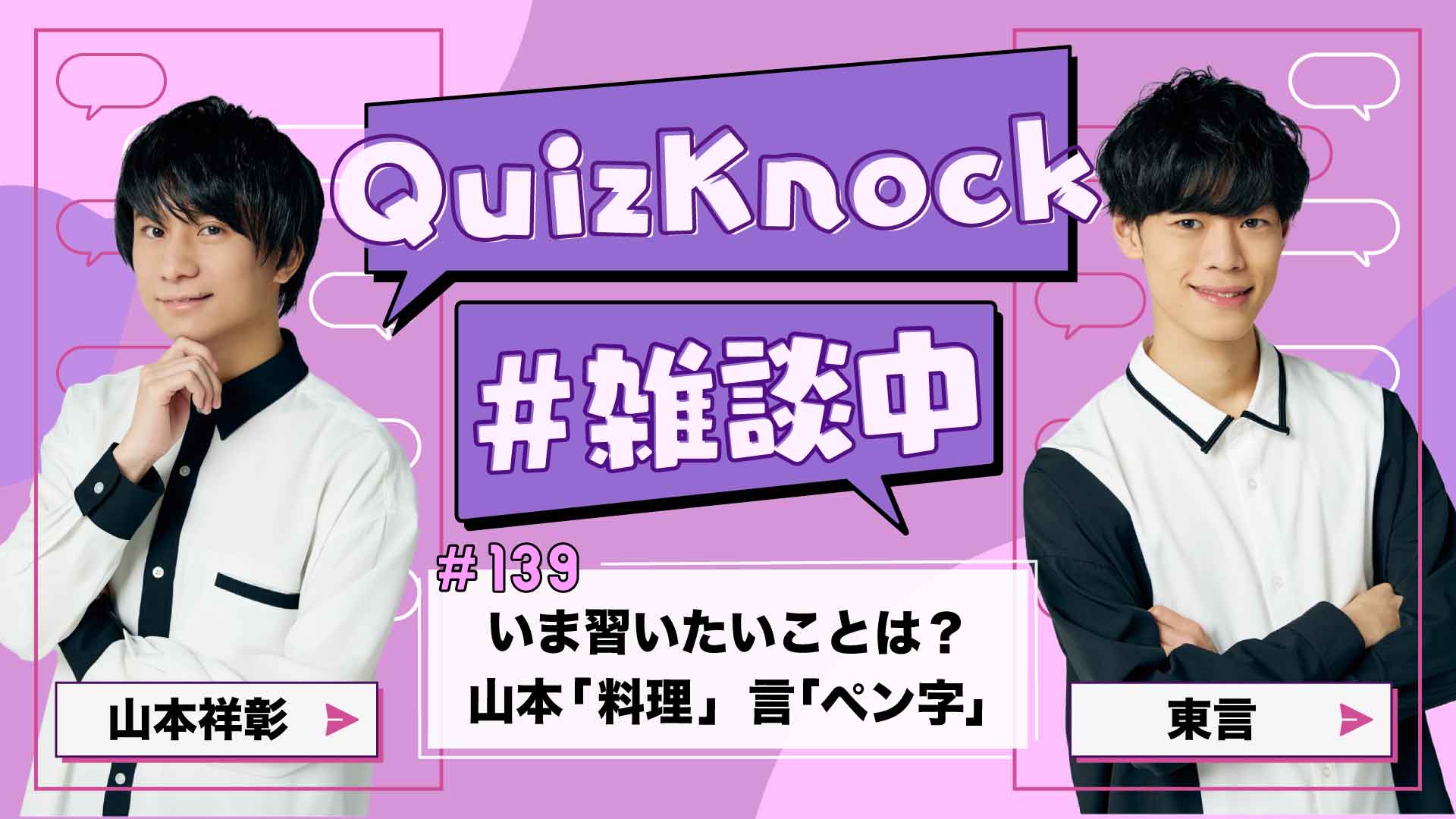こんにちは。村上です。
みなさんは子どもの頃、転んでけがをしたとき、誰かに痛いところをさすりながら、こう言ってもらった経験はありませんか?
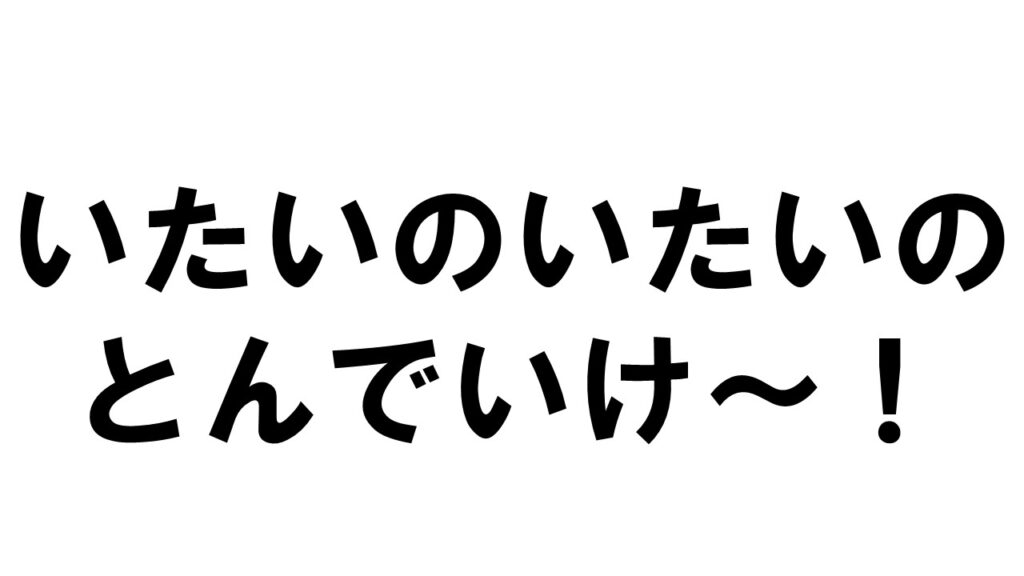
実は、あの言葉と、「痛いところをさすってその痛みをどこかに投げる」ような動作……本当に痛みを和らげる効果があるのです。
もちろん、根本的に痛みがなくなるものではありませんが、和らげる程度の効果が期待できる根拠はしっかりとあります。今回は「痛いの痛いの飛んでいけ」の科学的な効果について探っていきましょう。
言葉の思い込みによる効果
まずは、言葉そのものの力です。「痛いの痛いの飛んでいけ」とおまじないのように言われると、なぜか本当に痛みが軽くなったように感じることがあります。
これはプラセボ効果(プラシーボ効果)と呼ばれる現象です。一般的には薬学の分野の言葉で、「プラセボ」とは何の効果ももたない「

「痛いのが飛んでいく」との思い込みによる期待から、脳内でエンドルフィンなどの鎮痛物質が分泌されて痛みが軽減したり、ドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質が放出されて痛みの感覚が緩和したりするというメカニズムです。
「痛いの痛いの飛んでいけ」も、このプラセボ効果の一種であると考えられています。 “病は気から” というのは、まさにこの現象を逆手にとった言葉なのです!
さすることによる効果
また、けがをした部分に手をあてて “さする” ことにも大きな効果があります。大人でも体をぶつけてしまったとき、「イテテ……」と自然と痛いところをさすってしまいますよね。
これはゲートコントロール理論という考え方でよく説明されます。刺激を伝える神経には、痛覚を伝える細い神経線維(神経繊維)と、触覚による圧力を伝える太い神経線維があります。複数の刺激が発生すると、感覚を脳に伝える経路の門番である脊髄が、太い神経からの信号を優先的に受け取り、細い神経からの信号に対しては門を閉ざすというのが、ゲートコントロール理論による痛みのメカニズムの説明です。

痛いところを手でさすると、脳は細い神経で伝わる痛覚より、太い神経で伝わる圧触覚の刺激を感知するため、痛みが和らぐと考えられています。 “さする” という行為も「痛いの痛いの飛んでいけ」において理にかなっていると言えますね!
科学のおまじない
最初に述べた通り、「痛いの痛いの飛んでいけ」で実際にけがが治るわけではありません。それでも、言葉による思い込みの心理的効果と、さすって痛みの信号を遮断する身体的効果、この2つの力が合わさって生まれる “科学的なおまじない” によって痛みを和らげる理屈はあるのです。
だからこそ、あの優しいおまじないが今でもよくかけられているのかもしれませんね。
【あわせて読みたい】









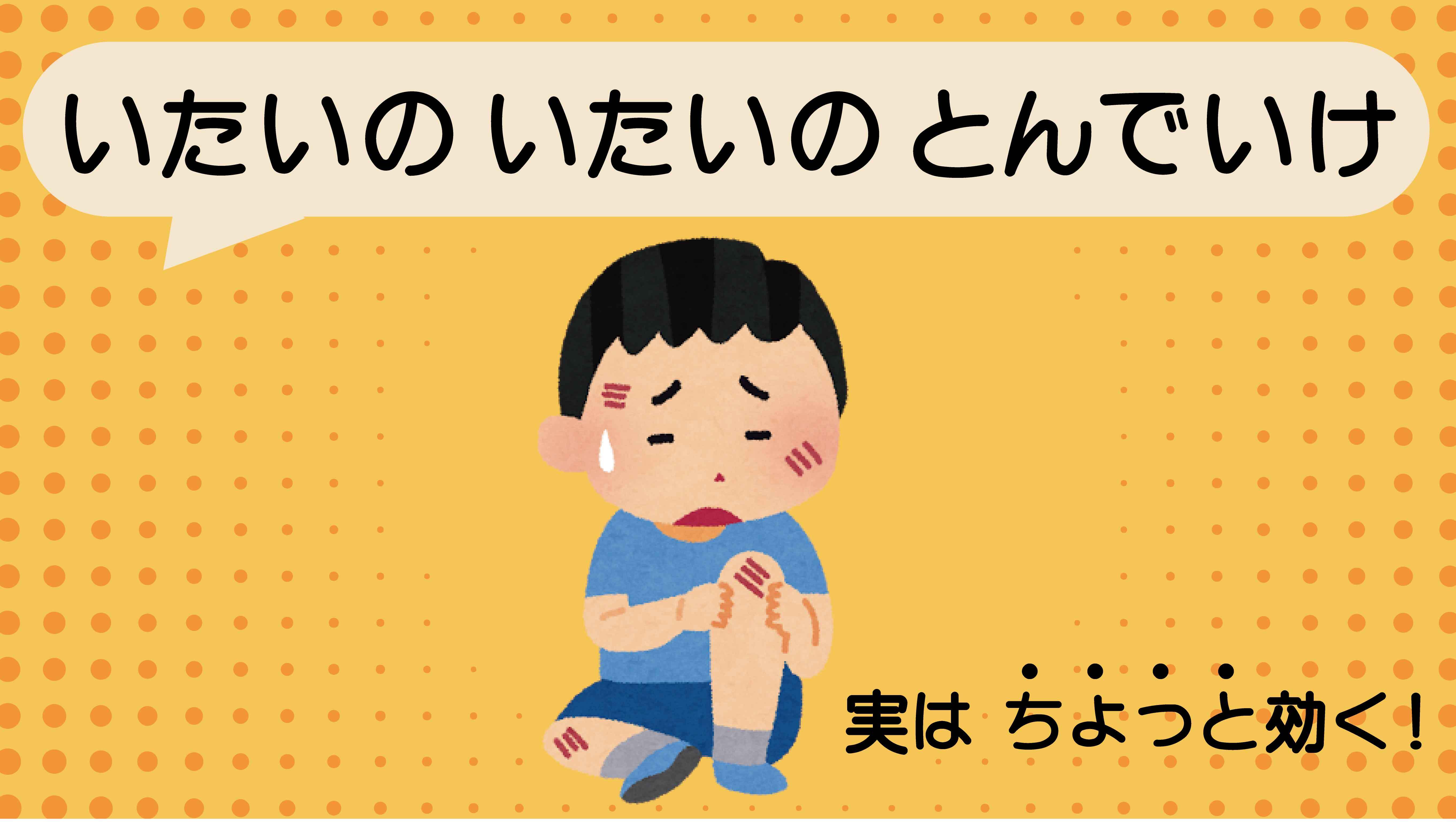

.jpg)
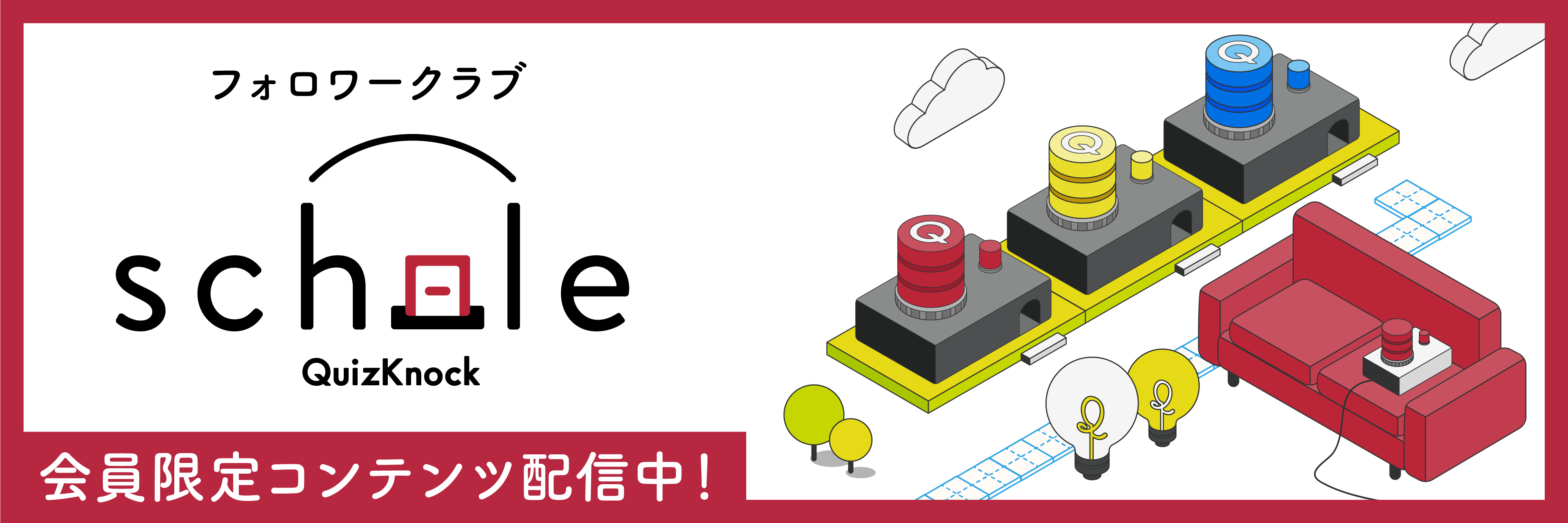



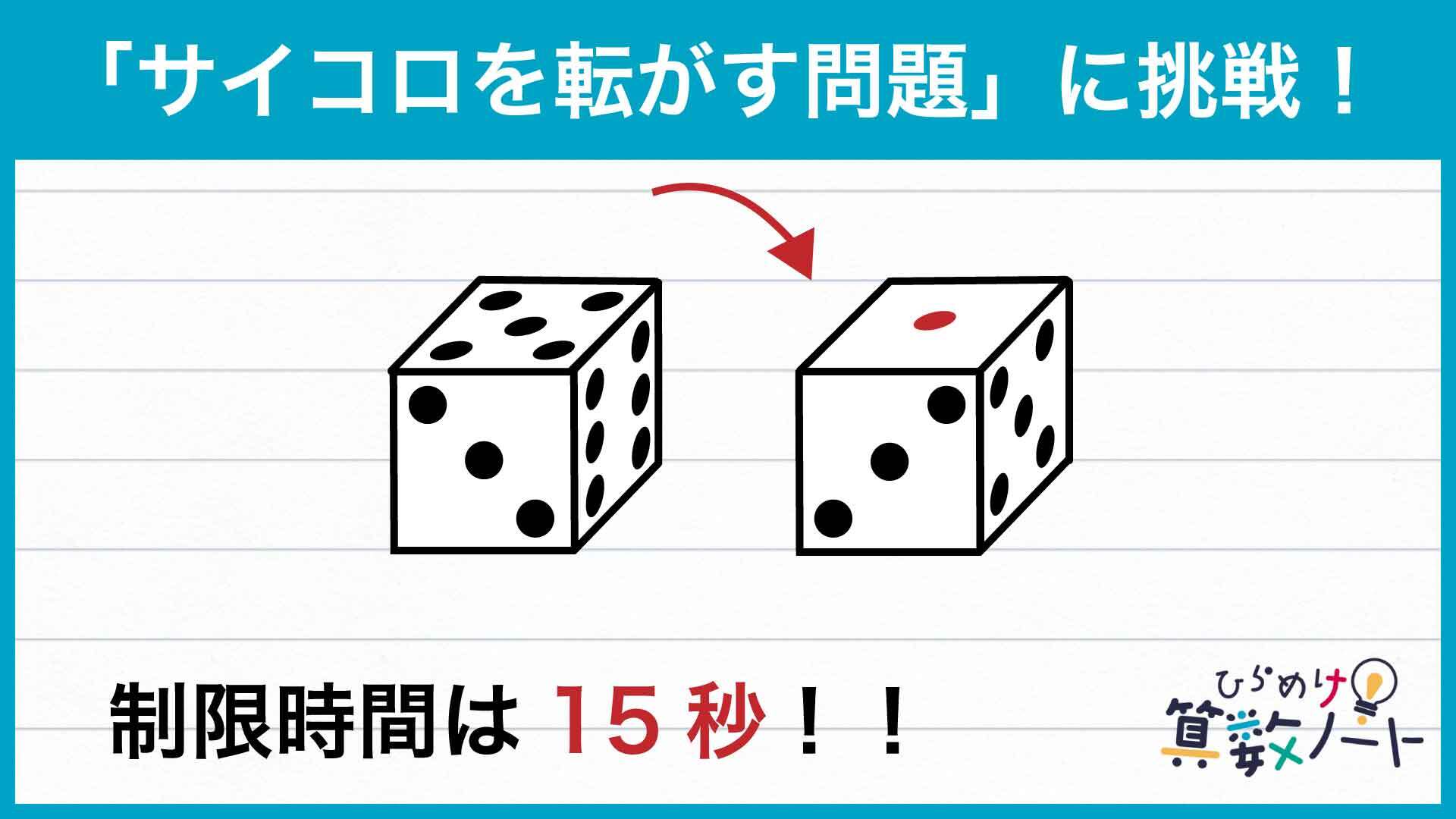

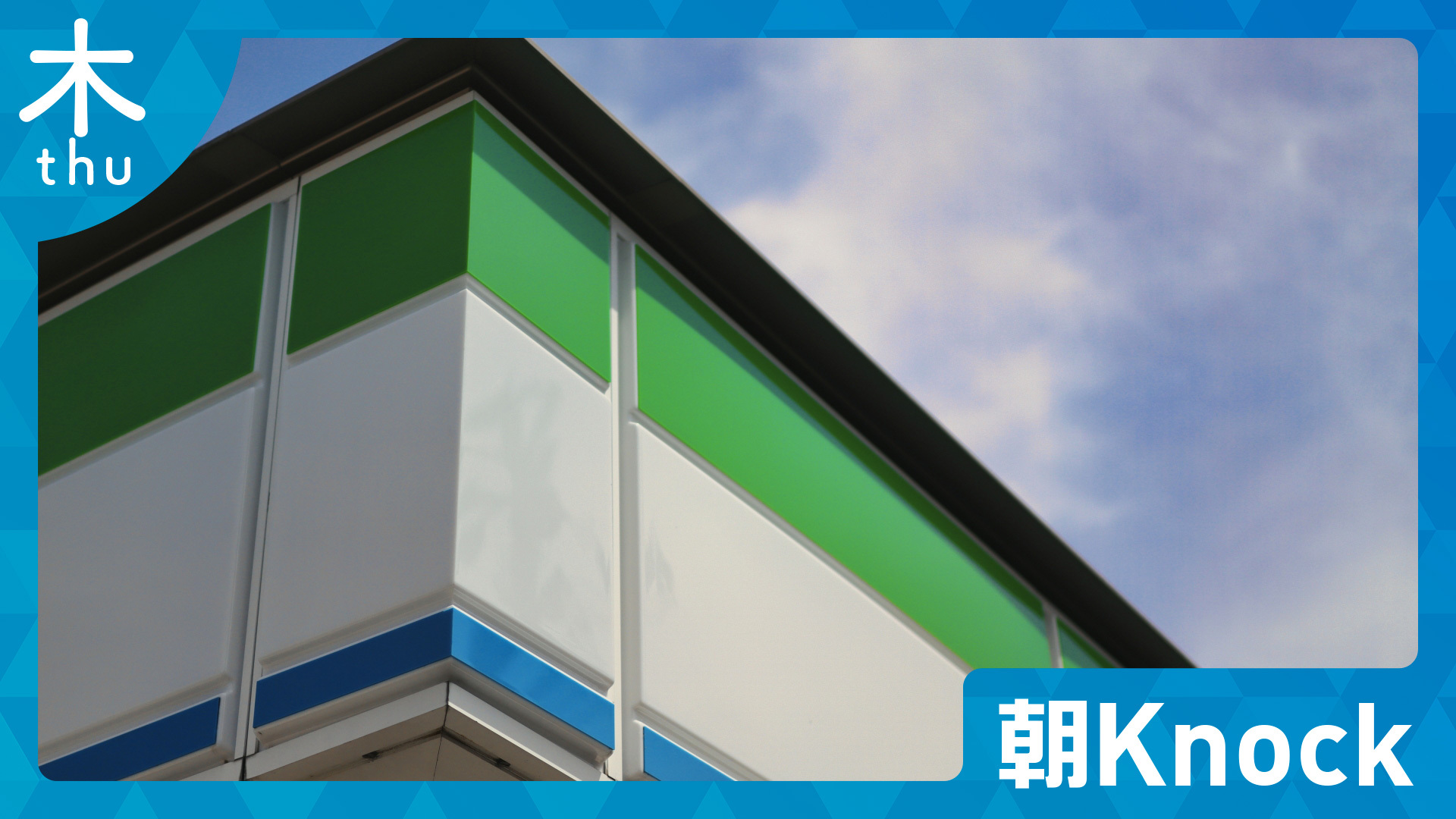


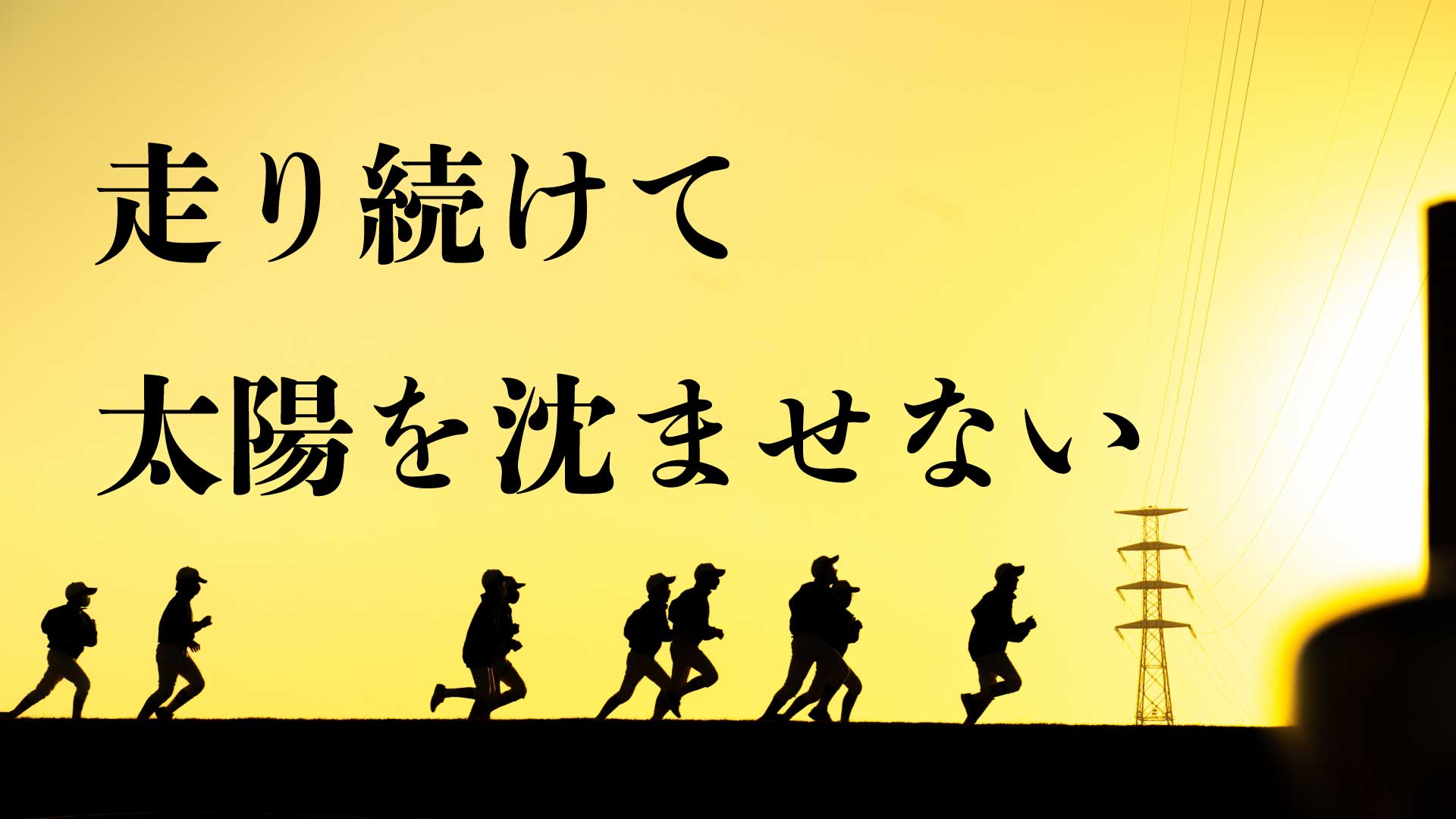
.jpg)