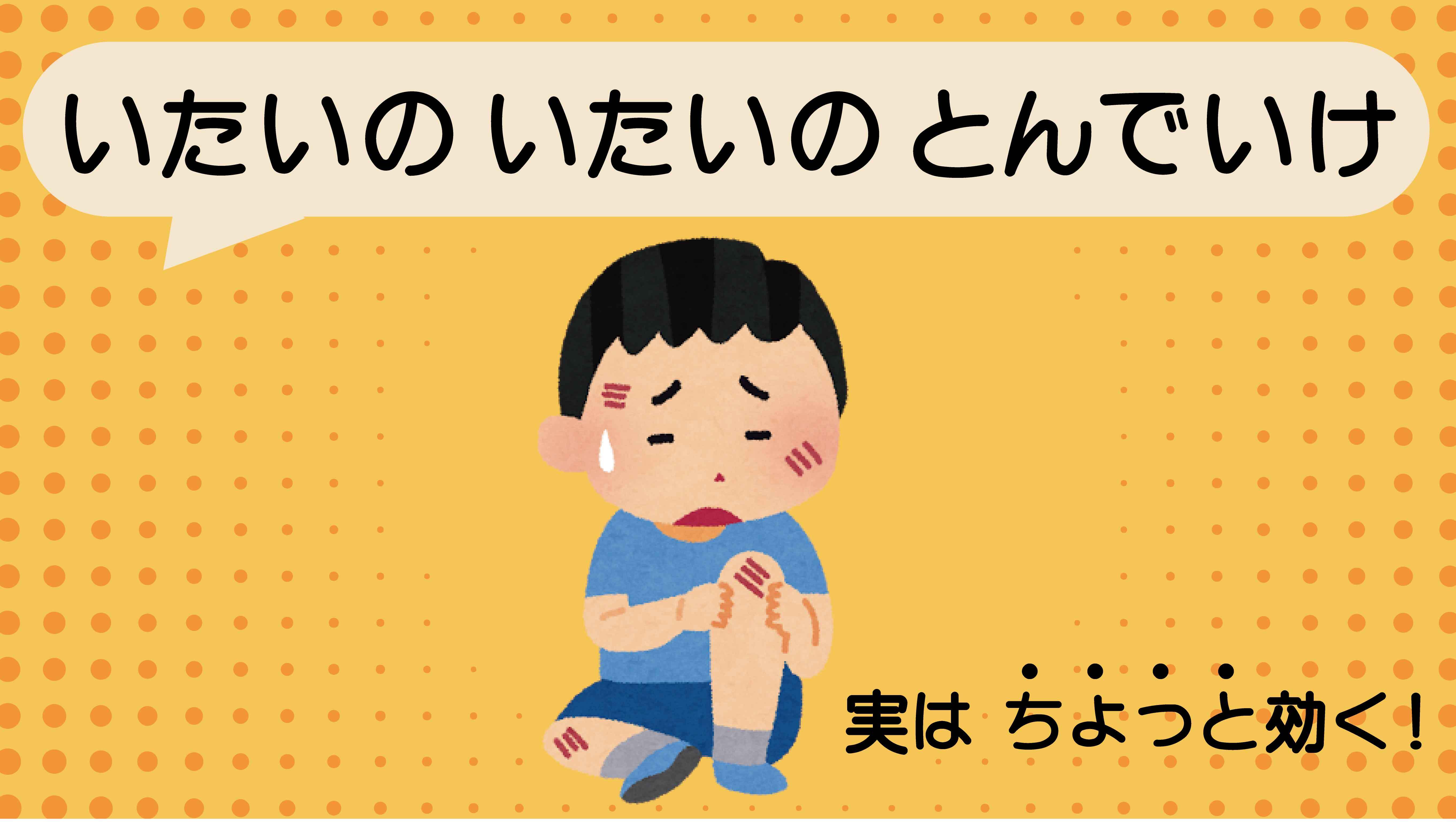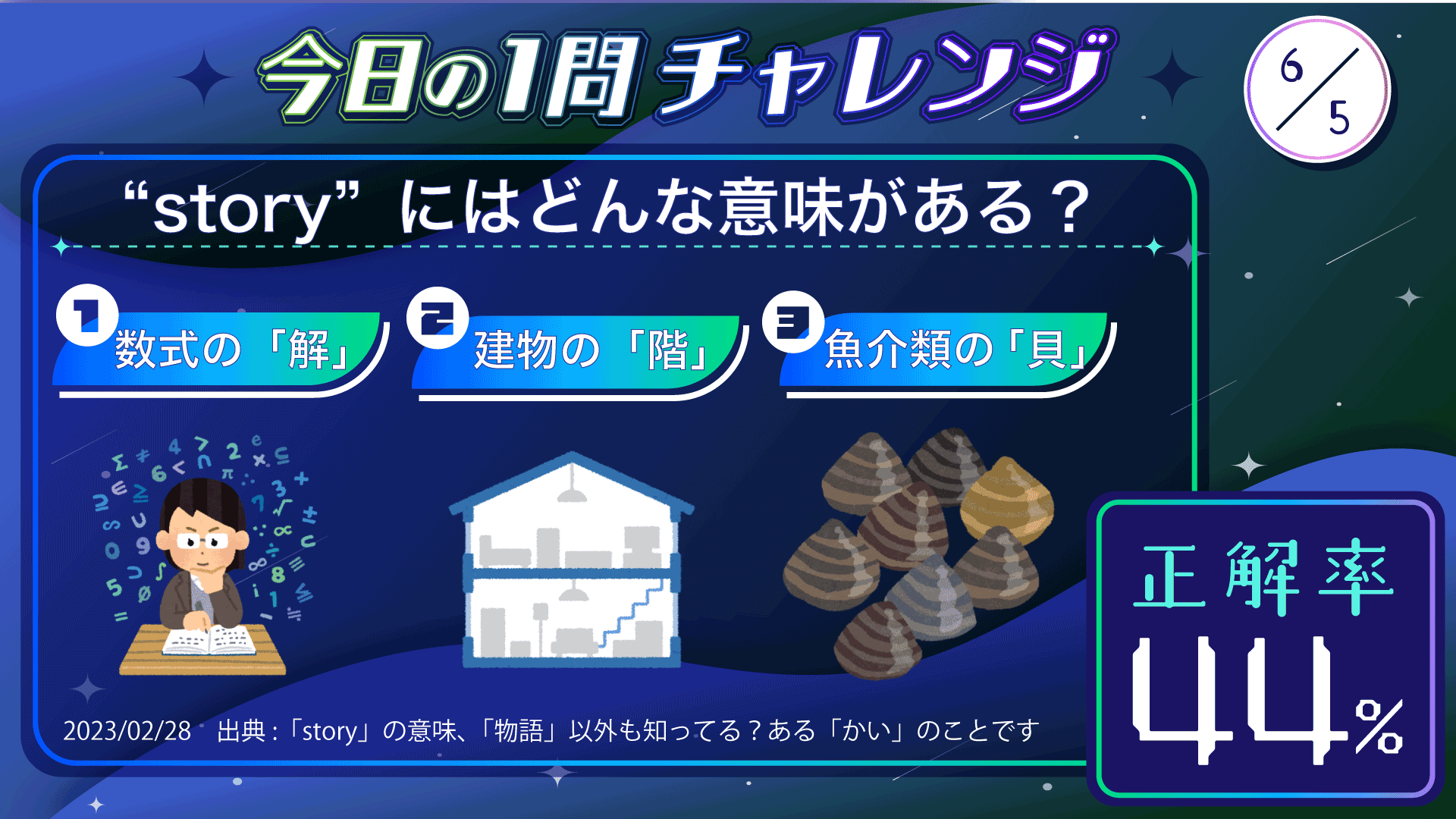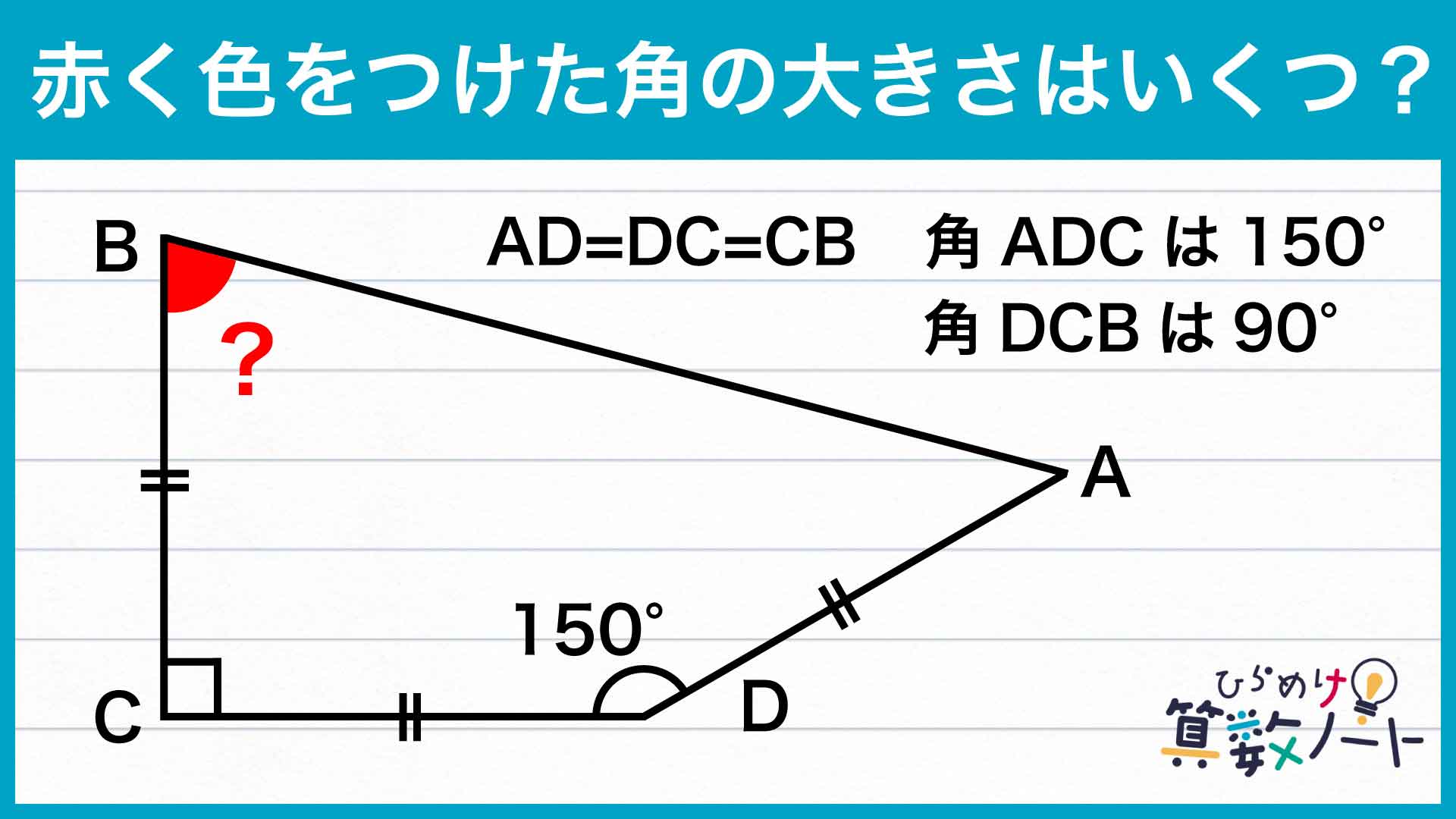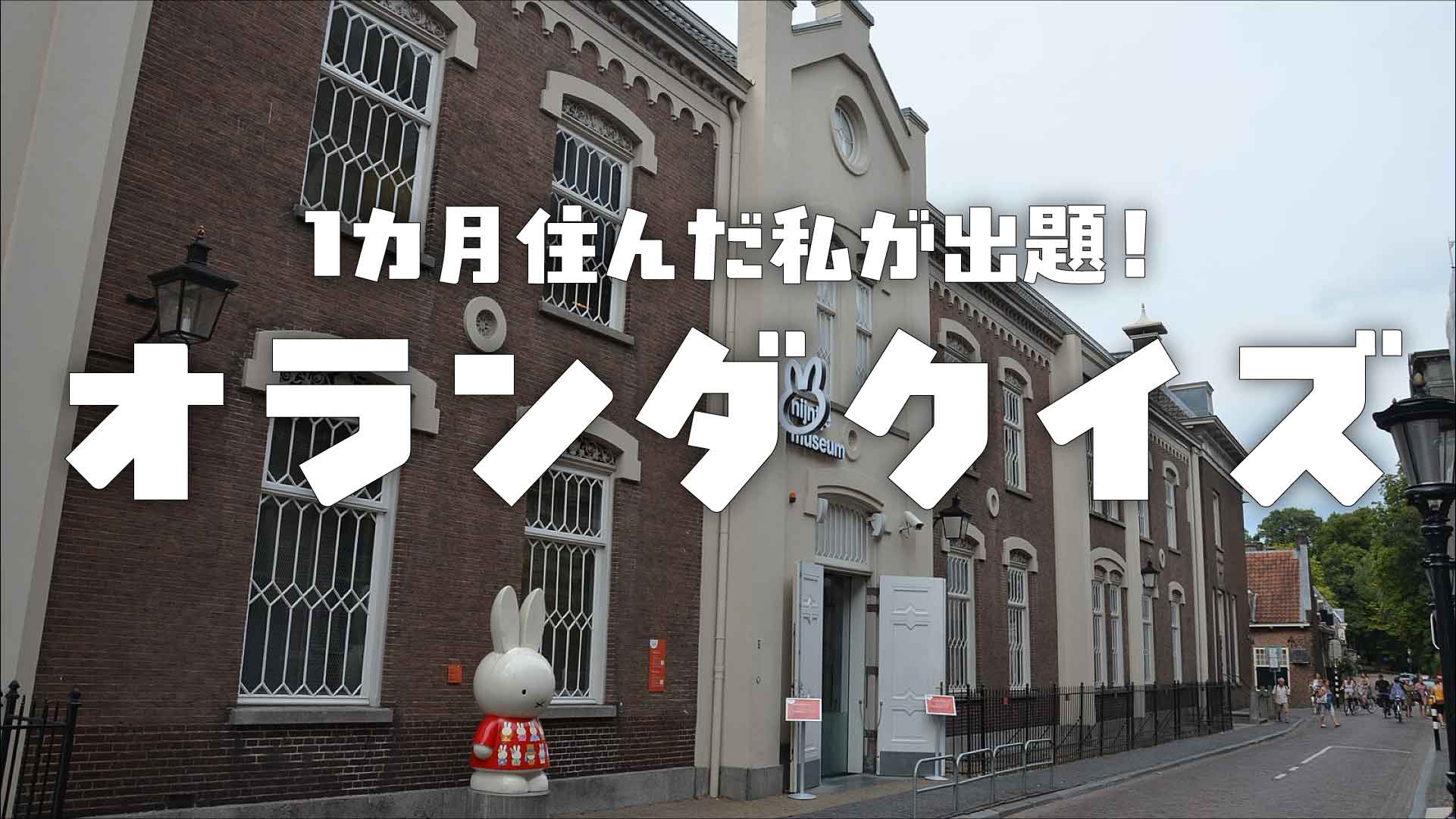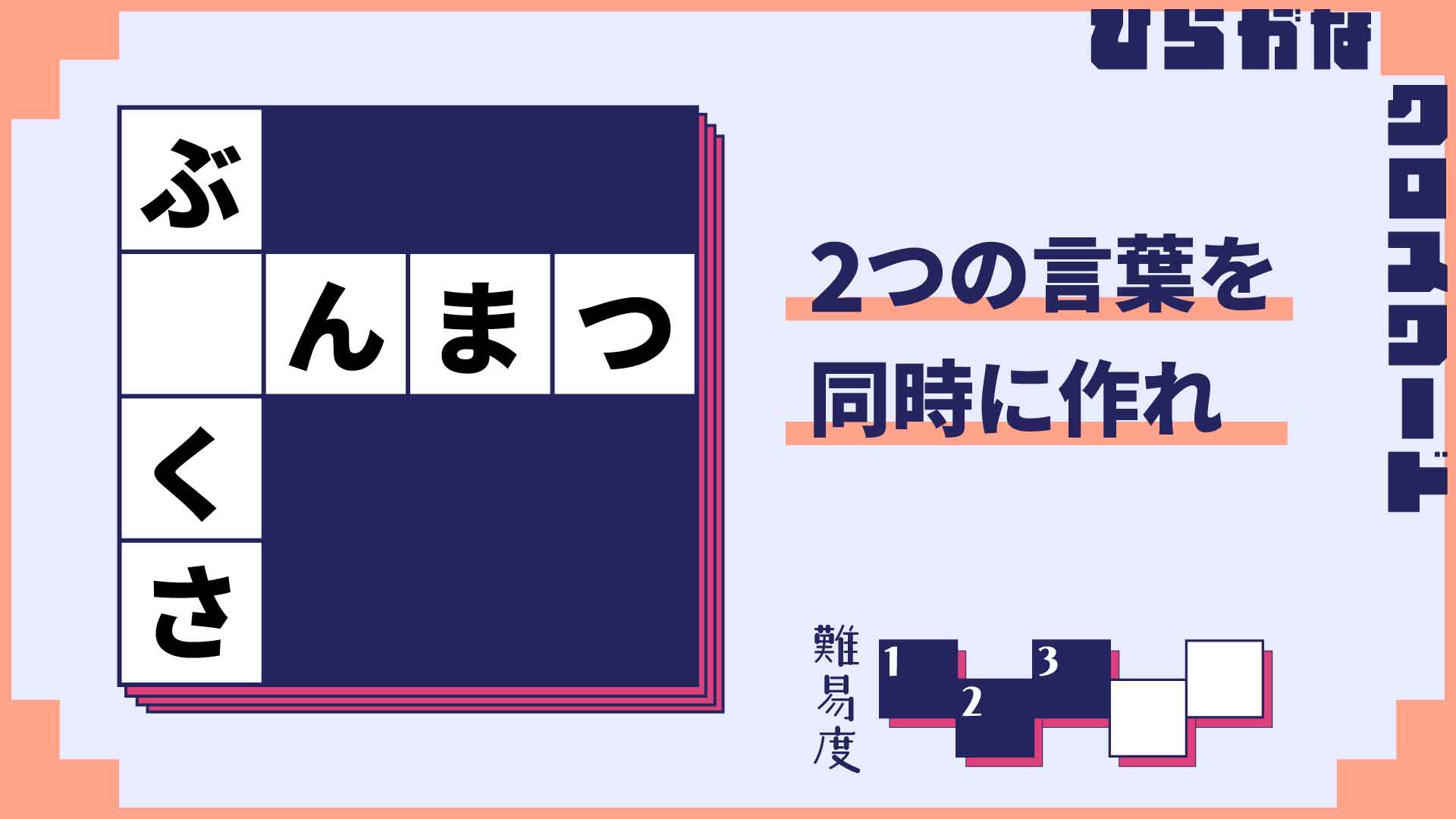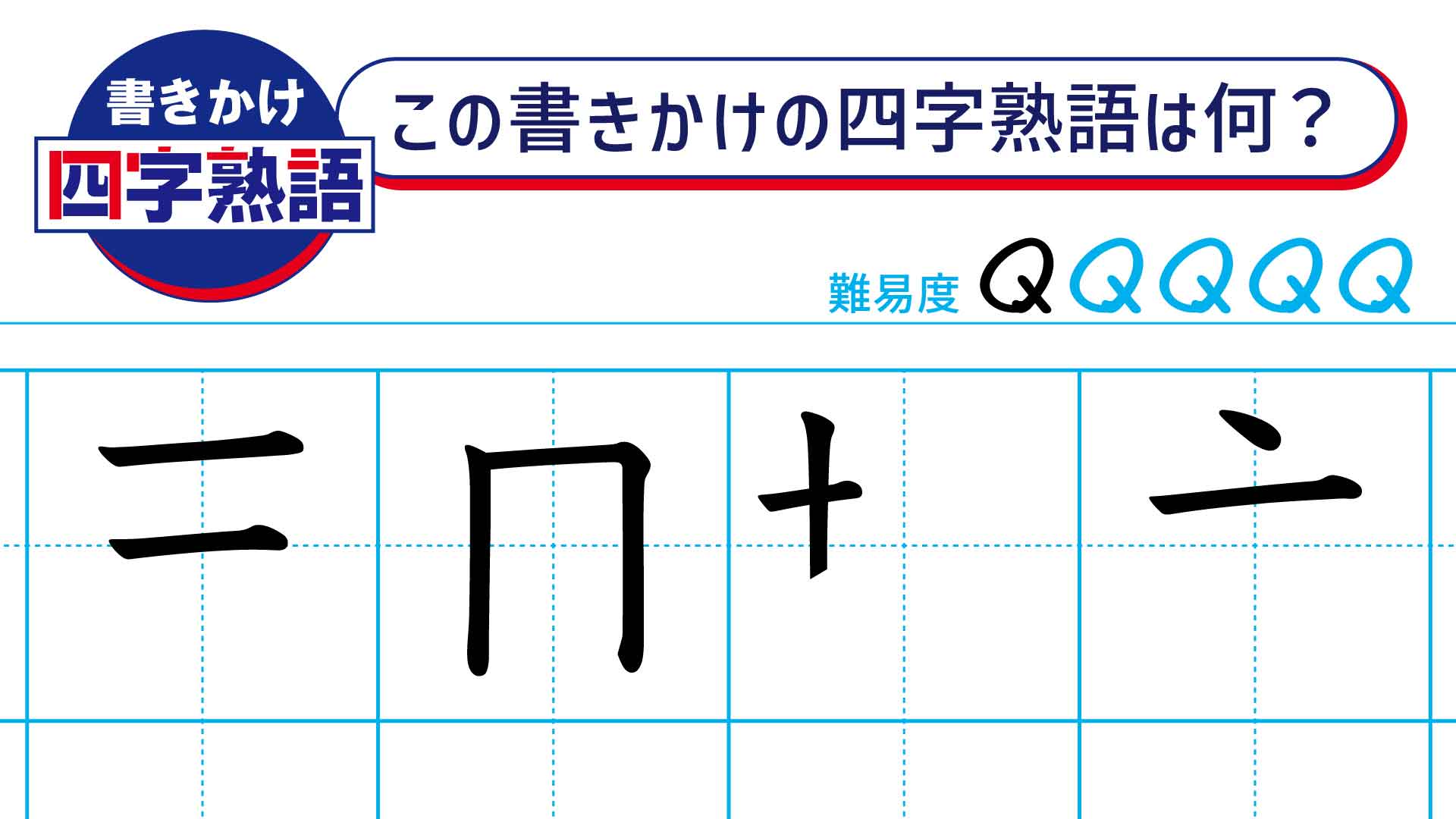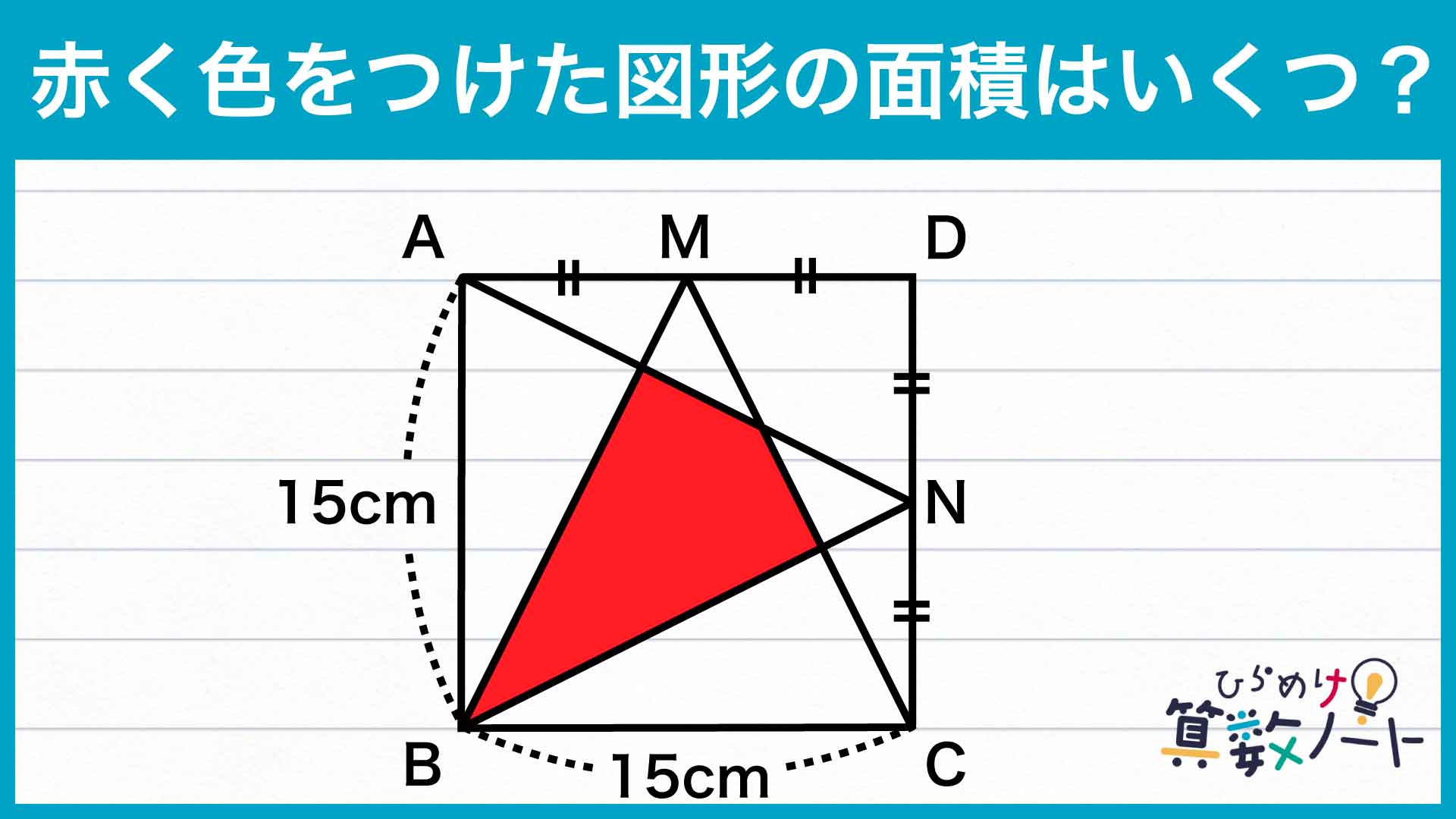ポイント1:津波の被害を受けた建物の内部に入れちゃう
東日本大震災の大きな特徴は巨大な津波。ただ、たとえば「10mの津波」と言われても、私はどのくらいの高さまで波が来てどんな被害を残したのか正直ピンと来ませんでした。
そんなときに一目で理解できたのが、津波被害を受けた建物(震災遺構)を直接見たときでした。東日本大震災遺構の被災地では、震災遺構が数多く残されており、津波がどこまで到達したのか、どのくらいの威力で建物を破壊したのかを一目で見ることができます。

特に衝撃を受けたのが、外から見るだけではなく、中に入って見学できる施設を見たときのことです。コンクリートの建物がこんなにはがれてしまうのか、教室の中に木や車など様々な瓦礫が流されてきたのか。想像を超える津波の威力を感じることができます。

仮設住宅の暮らしも体験できる
被災後、避難所生活のあとに生活を再建するまでに入ることも多い「仮設住宅」。テレビなどで見たことがあっても、実際どんな感じなのかイメージがつかないものです。

宮城県石巻市の震災遺構門脇小学校では、実際に使われていた仮設住宅を体育館の中に移転して保存しており、仮設住宅での生活を体験することができます。実際に中に入ってみると、壁が思ったよりも薄かったり、結露の跡が見えたりして、仮設住宅での生活の大変さがうかがえます。

私が震災遺構を訪れるときの感覚は、歴史が好きな方が寺社やお城などを巡るのと近い気がしています。過去にその地で起きた出来事やそれがうかがえる何らかの記録を、人々が価値を見出してそのまま残し、時を経て私たちが訪れる構図は、共通点も多いと思うのです。
日本の災害遺構の45件のうち25件は、東日本大震災関連です(西尾、2021)。みなさんも東北に訪れた際には、ぜひ震災遺構を訪れてみてもらいたいです。ちなみに、いくつかの例外はありますが、震災遺構は発災後比較的遅めに報道記事が出て、「その建物で亡くなった人がいない」などポジティブなストーリーを有するものが保存される傾向にあります(佐藤・今村、2016)。
ポイント2:三陸のおいしい海産物を楽しめる
東北被災地に来たなら、おいしいものを食べたい! そう考える人も多いかと思います。
ちょっと意外かもしれませんが、私たちの研究グループが実施した東北被災地への訪問者1,175名のアンケートの結果、東北訪問時に期待していた人数が一番多いのは、「被災地の名産物を食べること」でした(渡邉ら、2021)。震災遺構の見学よりも多くの人が、おいしいものを食べることを期待していたんです。

東北被災地といえば、世界三大漁場のひとつである三陸漁場。そこでとれるおいしい海産物を楽しむことは外せません。せっかくの旅行、おいしいご飯食べたいですよね。
「海とともに生きる」を選んだ東北
もちろん、「食」からも被災地に関連してたくさんのことを学べるんです。例えば、岩手県山田町では「復興まち歩き つまみ食いツアー」というものがあり、商店街の語り部さんの案内のもと、食べて学ぶツアーが開かれています。

津波は大きな被害を生じさせましたが、海は私たちに「恵み」をくれるものでもあります。みなさんも現地でおいしい海産物を食べれば、その恵みの一部を実感できるのではと思います。

ポイント3:「語り部」のすばらしさ
私が思う東北の震災伝承の最大の魅力は、やっぱり「語り部」だと思います。東日本大震災の被災地では、これまでの被災地と比べて人による口頭の伝承が非常に盛んだといわれています。
来訪者の防災への行動変容を引き起こす力がある
語り部さんの話には、「直接の語り」が持つ力があります。
私たちの研究グループが実施した調査においては、被災地で語り部など被災者の話を聞いたことは、備えへの行動変容と有意に関連していることがわかりました(渡邉ら、2024)。小中学生を対象にしたオンライン語り部が家族の話し合いなどを促進していること(佐藤ら、2023)や、本人による直接の語りが長期的な記憶の定着度合いの高さと関係すること(佐藤ら、2019)などがわかっています。
東北には、様々な年代・立場・地域の語り部さんがいらっしゃるので、あなたにマッチした語り部さんとも出会えるはずです。語り部さんから繰り出される、想像もつかなかった話との出会いも醍醐味のひとつです。
紹介したい方はたくさんいらっしゃいますが、今回は特に、若い語り部さんたちの一部を紹介します。
被災した当時の中学生と当時の避難を一緒に疑似体験できる
岩手県釜石市にあるいのちをつなぐ未来館では、当時の中学生が避難したルートを、本人たちと一緒に歩くことで津波避難を疑似体験できるプログラムが実施されています。

「津波避難」とは「速やかに海の近くから離れてできるだけ高いところに逃げる」こと。原則はただそれだけです。なんだかシンプルで簡単に思えるのですが、実際は避難開始時、避難行動中、避難場所到着後などに様々な葛藤や迷いがあったりするもので、実際に歩くことで語り部さんの体験を身をもって味わうことができます。
説明ポイント間のすき間時間で語り部さんと話しやすいのもうれしいポイントです。
今の中高生による語り部・ガイド
東日本大震災発災時はまだ小さな子ども、なかには生まれていなかった今の中高生も震災の語り部やガイドを行っています。
気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館では、震災の記憶がある世代は「震災を直接知る最後の世代」としての覚悟を持った話を、震災を知らない世代は「震災を直接は知らない視点」を生かした話を、来訪者に近い立場で話してくれます。
私は、彼らを見ているととても不思議な気持ちになるんです。とっても真剣に伝えてくれるんですが、なんだか楽しそうで生き生きしているんですよね。実際に、語り部をしている先輩を見てかっこいいと思ったから語り部をしているという学生もいます。


ほかにも、迅速な意思決定が求められた災害発生時を学ぶことでリーダーシップや起業防災を学ぶプログラム、ARやVRを用いたプログラム、震災前の街並みを再現した立体模型、民間施設だからこその失敗の教訓を伝える施設……と、みなさんに被災地で見てもらいたいものは書ききれないほどたくさんあります。が、本日はここらへんで終えたいと思います。
気軽に被災地・伝承施設に行っていい
被災地に行っていいのかな……。私もそう思っていました。
今なら自信をもって言えます。気軽に来てください。
私たちの調査では、「観光や仕事など震災学習以外の目的で訪問した人の9割が伝承館を訪問している」ことがわかりました(渡邉ら、2021)。つまり、震災学習をメインで東北に訪れなくても、「東北被災地に行ったからには震災のところも見てみようか」という方が多いことを示していると考えています。被災地には、「ついで」で行っていいんです。
震災を思い出すこと、向き合うことは時に非常に莫大なエネルギーを必要とします。被災を経験していない私ですら、耐えられないような痛みを負うことがあります。震災との距離感は人それぞれで、無理にその距離を縮めることが良いとは思いません。
でも、少しでも行ってみたいと思う気持ちをお持ちならば、ためらう必要はありません。おいしいごはんを食べに来たり、美しい自然を見に来て、ついでに伝承施設に行ってみる、語り部さんの話を聞いてみるくらいのスタンスでもいいんじゃないでしょうか。日本三景・松島の近くにも、JRの駅を遺構として保存している東松島市震災遺構・伝承館という伝承施設があります。
この記事は、「被災地」だから書いたのではありません。帰ってきたくなる私の大好きな「まち」を、大好きな「人」を、大好きな取り組みである「震災伝承」を知ってもらいたくて書きました。東北でお待ちしています。
【あわせて読みたい】












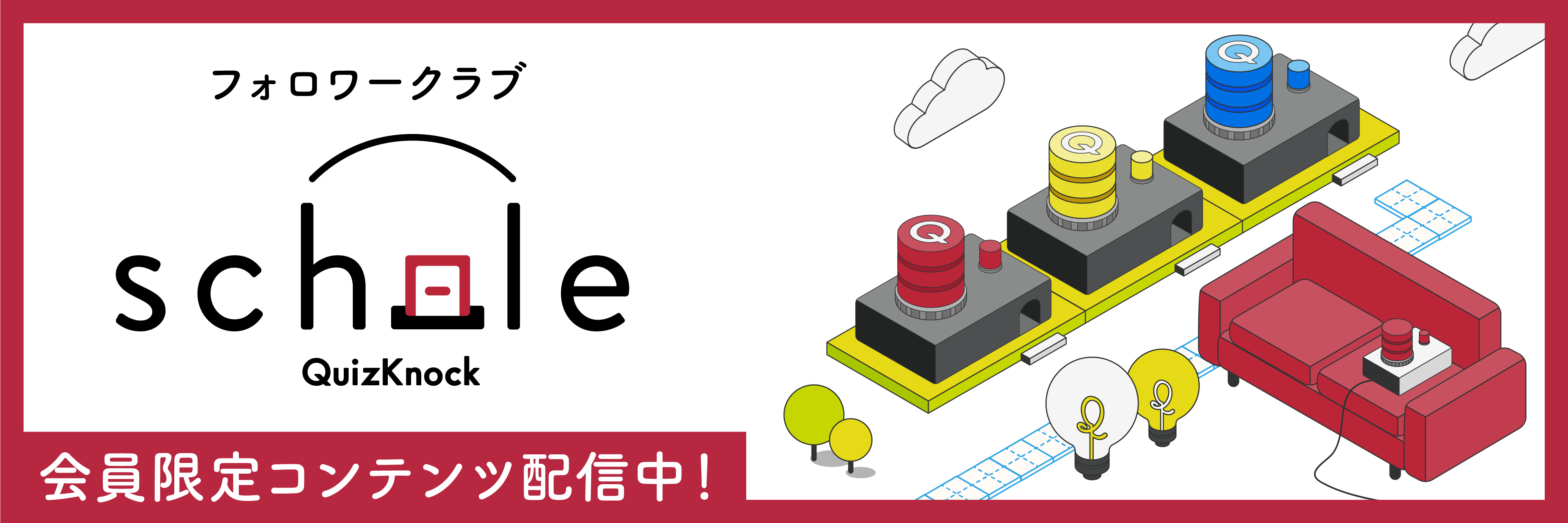

-1-1024x683-1.jpg)