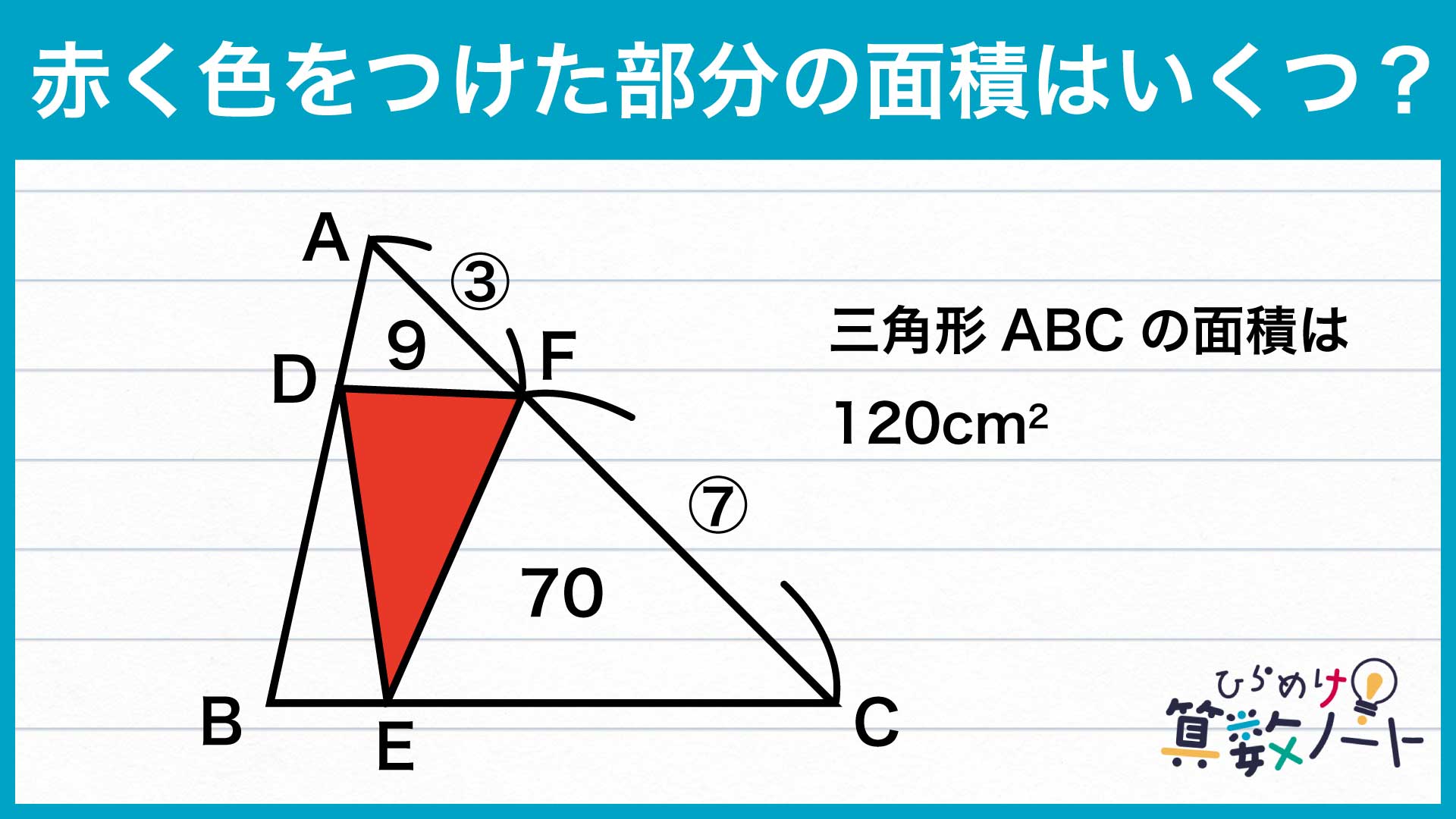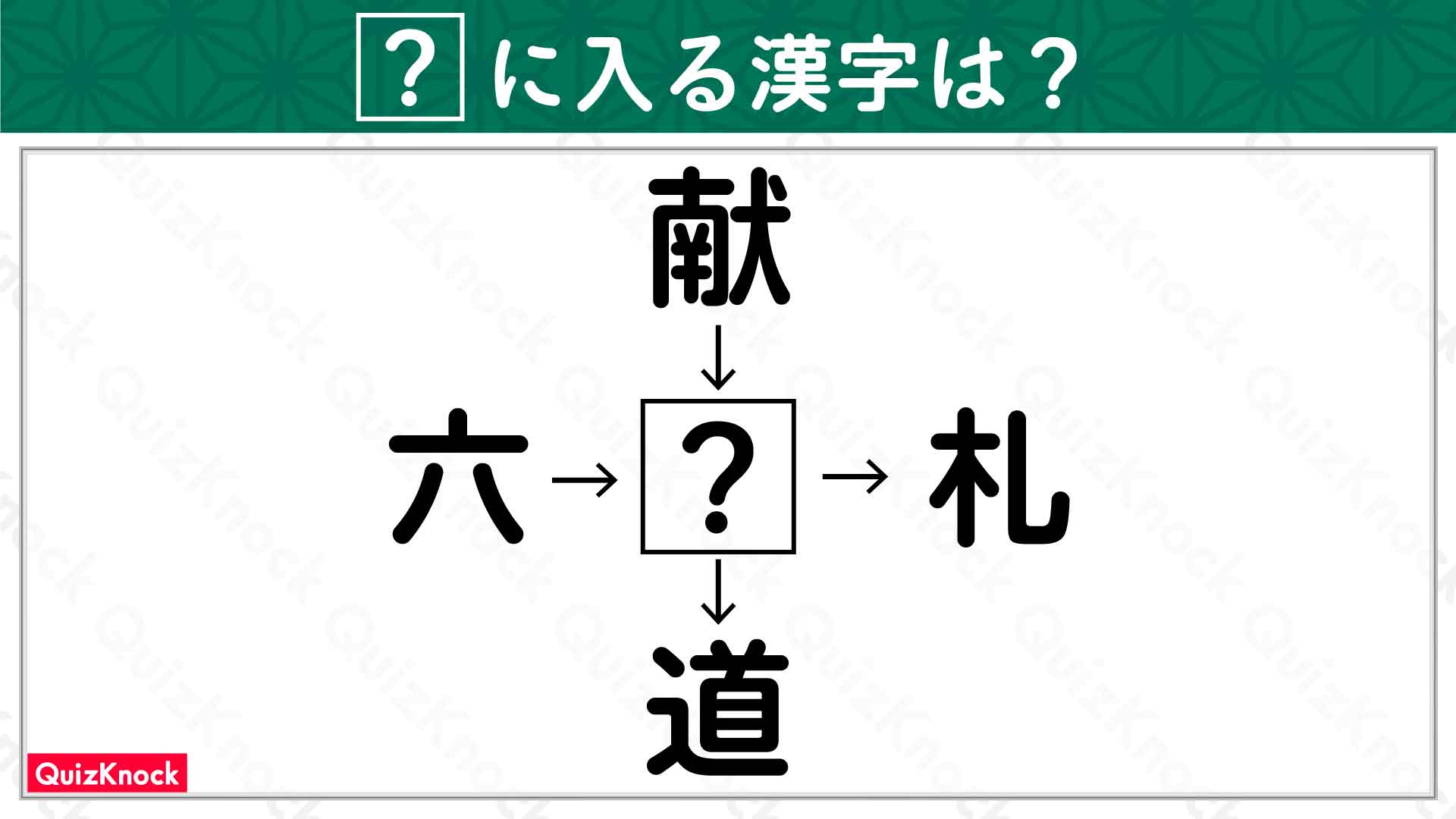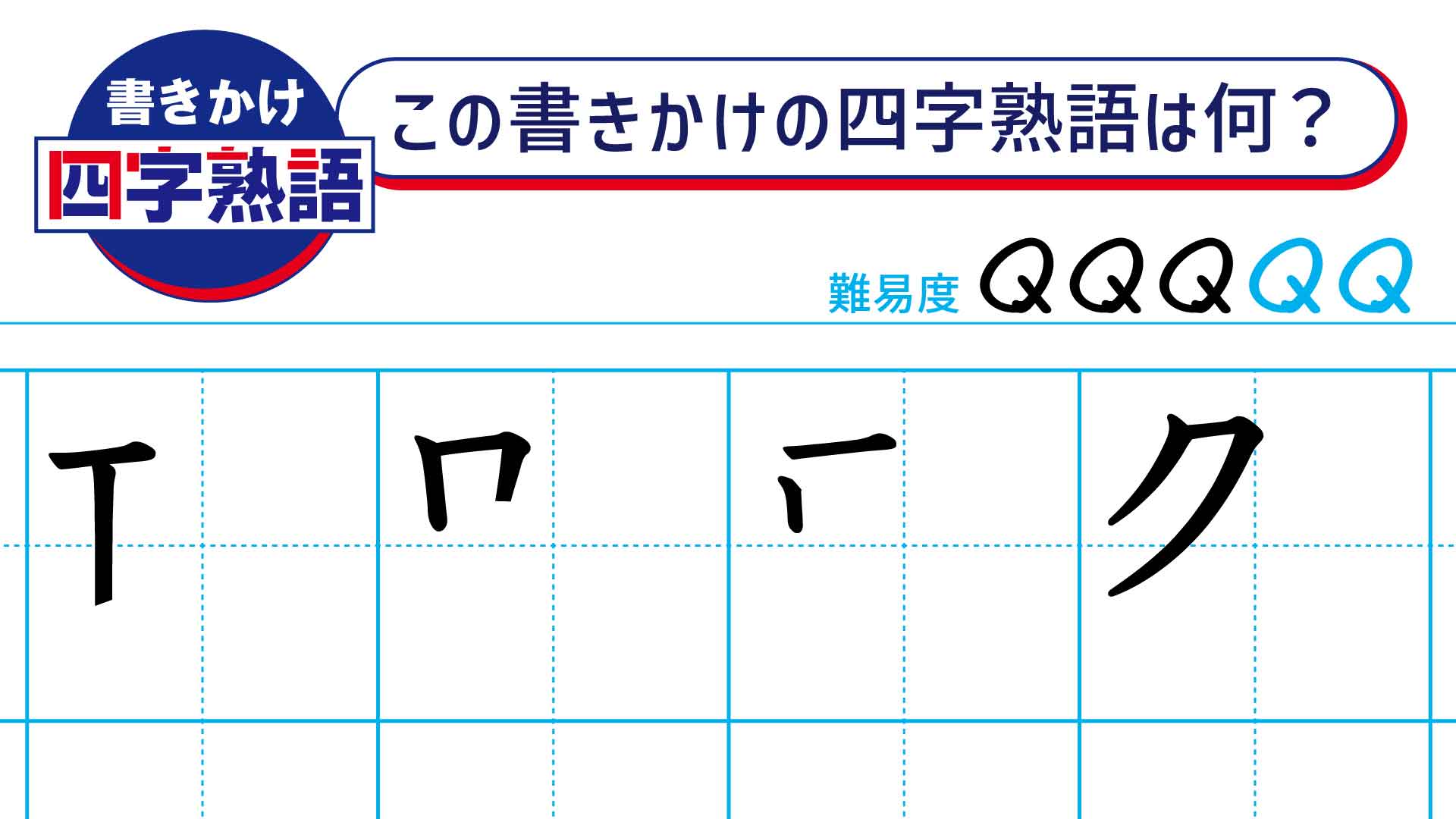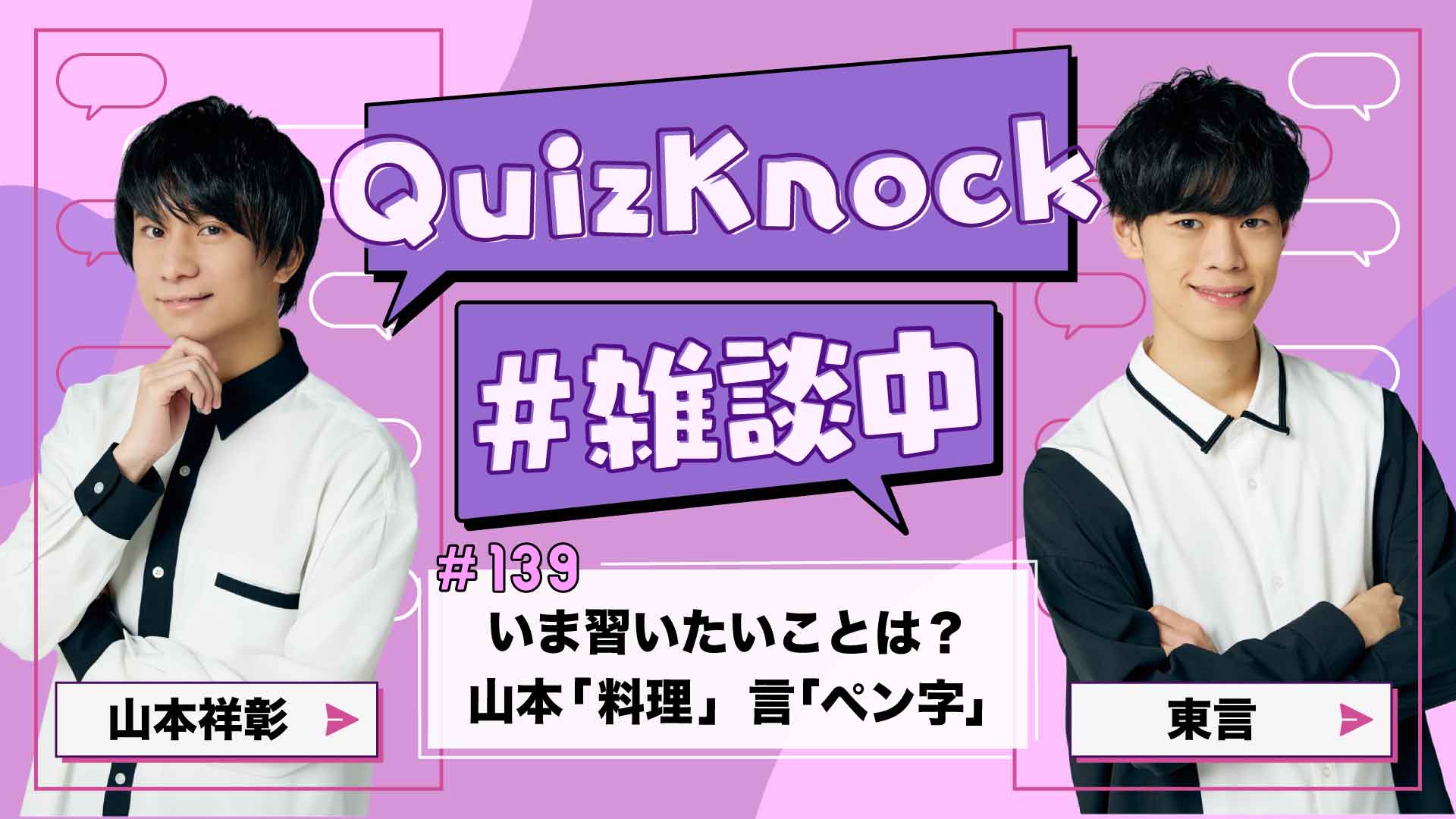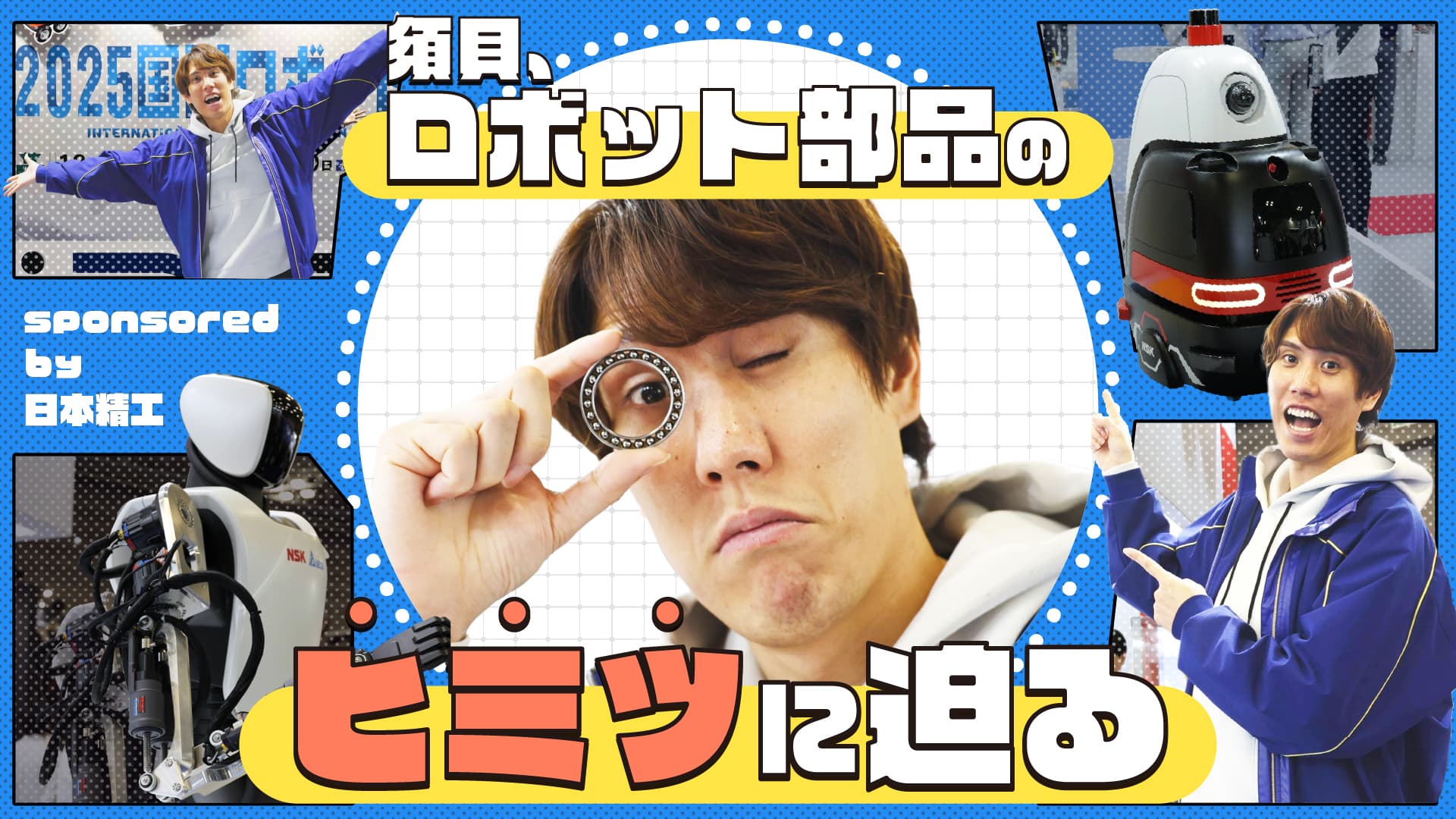みなさんは、時間を忘れるほどハマってしまったものってありますか?
私はあります。どっぷりハマっちゃいました。ハマりすぎて、大学・大学院で6年間そのテーマで研究を行い、先日博士号を取得しました。
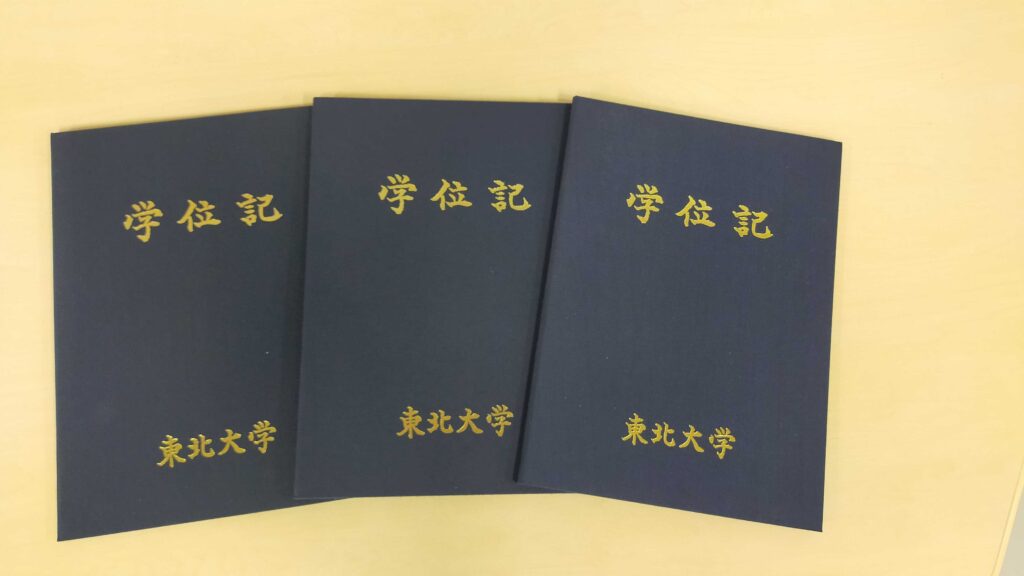
私がハマったものは、ずばり「震災伝承施設」。震災の経験や教訓を伝えるための展示施設や遺構などのことです。広島にある原爆ドームや平和資料館の「震災版」というとわかりやすいかもしれません。

「被災したものに“ハマる”だなんて、不謹慎じゃない?」そう思われるかもしれませんね。無理もありません。
でも、もうちょっとお付き合いください。私は、東北大学に進学して9年間被災地に通うようになってから、震災伝承は「未来の日常を守るためのとっても素敵な取り組み」であることを学んできました。
私は、東北の主要69施設すべてと、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、熊本地震の被災地、さらにはハワイにて、国内外さまざまな震災伝承施設を巡りに巡ってきました。今日は、その実体験と研究成果をもとに、今日は東北の震災伝承の魅力を語らせてください。
震災伝承施設とは
2011年3月11日に東日本大震災が発生して以降、過去の災害の経験や教訓を伝えていく震災伝承の重要性が強く認識されるようになりました。
それをふまえ、東北の各市町村や民間団体は震災伝承施設を数多く整備してきました。現在、青森県から福島県まで、主要なものだけで69もの震災伝承施設が登録されています。

一口に「震災伝承施設」といっても、建物に入って震災が残した爪痕をそのまま見られるような遺構のほか、津波が到達した地点に置かれた碑、災害に負けず立ち続けるポプラの木に至るまで、その種類は様々です。
被災地では復興に伴い、震災の被害を受けた建物が解体され、新しい建物が作られてきています。震災伝承施設は、発災から時間が経過して町の骨格や地面の高さが変わった現在でも、当時の様子を知ることができる貴重な存在なのです。
なぜ「震災伝承」にハマったのか
「震災伝承」にどうして私がハマったのか。そもそも私は震災当時は埼玉県に住む中学2年生で、東北で被災を経験したわけではありません。私の身の回りでは、毎年3月になるとテレビで震災のニュースが増えるものの、それ以外の期間はごくごく普通の日常がありました。そんな日常に若干のもどかしさを感じながらも、私は「震災が起きたことは知っているけど、その中身については実は全然何も知らない」状態のまま過ごしてきました。
「仙台に行くからには、震災も知っておきたい。でも……。」
そんななか、東日本大震災の発災5年のタイミングで、私は仙台の大学に進学することとなりました。
あれほどの大きな地震、津波、原発事故があった場所が今どうなっているのか。まだ自分にできることはあるのだろうか。
東北に行くからには、被災地に行ってみたい気持ちが生まれてきました。でも同時に、「そんな軽い気持ちで被災地に行ってもいいのか」という葛藤もありました。5年が経った今、被災地がどんな状態かもわかりません。被災地に対して何も知らない・何もできない自分が行ったところで、力になれることは何もなく、ただ被災者の皆さんに迷惑をかけるだけなんじゃないかとも思っておりました。
訪問して初めて知った「震災」への衝撃
そんなときに、大学主催のボランティアツアーの案内が届きました。私は、思い切ってそのツアーに参加してみることにしました。

参加して良かったと、心から思えたツアーでした。たった2日間ではあったけど、現地で見聞きすることが何から何まで衝撃だったのを今でも覚えています。
私が訪れたその地域は、約7人に1人が亡くなってしまった地域でした。私自身、東日本大震災によっておよそ2万人の方が犠牲になったことは知っていました。それでも、「知り合いの誰かしらは亡くしてしまった」という人が多くいる町があること、自分たちの住んできた町が丸ごと壊されてしまったこと、その町はまだ一面茶色の景色が広がっていること……そんな、この地に来なければ知ることができない、想像すらできないことが現実に起こったことに衝撃を受けました。

人々の温かさと伝えたい思いの熱さに感化
そのボランティアツアーでは、仮設住宅を訪問し、住民の方と交流をする行程がありました。率直に言うと、その時の私は「被災者」と呼ばれる人々と会うことに緊張していました。
さっき自分が見聞きした震災の話は、実際に起きたことのほんの一部なはず。それを自分の身で経験されている方々に、自分が会ってしまって良いものなのか。

その心配は、良い意味で裏切られました。とっても楽しかったのです。なぜか仮設住宅のおばあちゃんたちに逆におもてなしをされてしまい、お茶っこ(お茶会)をして終わりました。
このとき私は、自分が「被災者」に対して「みんな震災で悲しみに暮れている人たち」のようなイメージを勝手に抱いていたことに気づかされました。当たり前だけれども、「被災者」と一括りに呼ばれる人たちは、決して特別な存在ではなく、十人十色それぞれの人生があって、生活をされています。
このボランティアツアーをきっかけに、私のなかで、被災地やそこに縁のある人々への認識が大きく変わりました。「被災者」ではなく「〇〇さん」、「被災地」ではなく「〇〇さんたちの住んでいる場所」という解像度で被災地を見ることができるようになりました。
ときおり、涙を流したり、辛い表情をしながらも私たちに経験を教えてくださる方々がいます。震災伝承の活動に精力的に取り組まれる方々もいます。なぜそこまでして語ってくださるのかを尋ねたところ、「二度と私たちと同じ思いをしてほしくない」という想いがあることを教えてくださいました。
「震災を知りたい」のループに
さらに、少しずつ震災について理解を深めていくうちに、同じ震災でも地域ごとにも事情は全然異なることがわかってきました。震災発生前の地域の様子、発災当時の避難のこと、救助のこと、避難所のこと、仮設住宅のこと、生活再建のこと、まちの復興のことなど、あらゆることが場所によって違います。
不思議なもので、震災について少し知るともっともっと知りたくなっていきました。気が付いたら私は、そんな「知りたい」「被災地に行ってみたい」のループにはまっていったのです。

災害の恐怖を希望に変える震災伝承に共感
私が、震災伝承にハマったのは、被災地で想像を超える「震災」を目の当たりにして衝撃を受けたから、そして、真剣で熱い想いを持つ温かな方々の「熱」が伝わってきたからです。埼玉にいたときの自分は、こんな現実があること、こんな方々がいることを全く知りませんでした。
災害自体は日常を壊すとても悲しいものだけれど、震災伝承は未来の日常を守るための取り組みである。震災伝承は、亡くなった人・生き残った人・これからの世代の人、それぞれへの「思いやり」なんだ。東北に住んで被災地に通っていく中で、東北をはじめとする語り部さんたち・伝承にかかわるみなさんからそう学んできました。
彼らはみな、真剣だけど温かい雰囲気で思いやりをもって私たちを迎え入れてくれます。そんな「熱さ」や「温かさ」にふれて、私はどんどん引き込まれてしまい、すっかりファンになってしまったんだと思います。不思議なことに、「また来ますね!」と自然と言ってしまう魅力があったんです。
この方々のためになりたい、だからその一助となりたくて震災伝承の研究を始めました。
「推しポイント」語らせてください
ここからは、東北被災地でどんなことが体験できるのか、研究成果と訪問した実体験も交えて、おすすめ体験を語らせてください。
次ページ:東北ならではのポイントを紹介します!













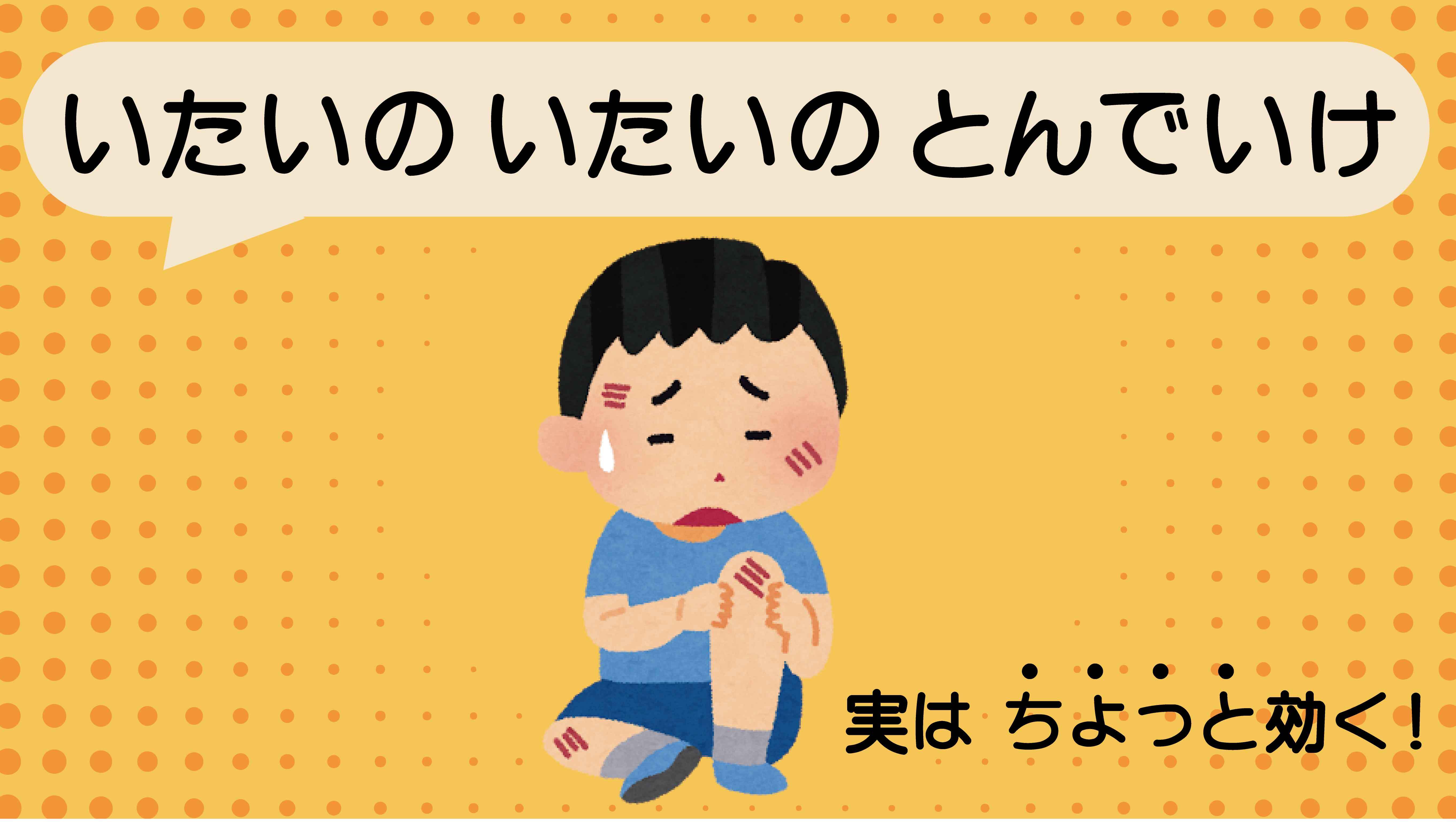
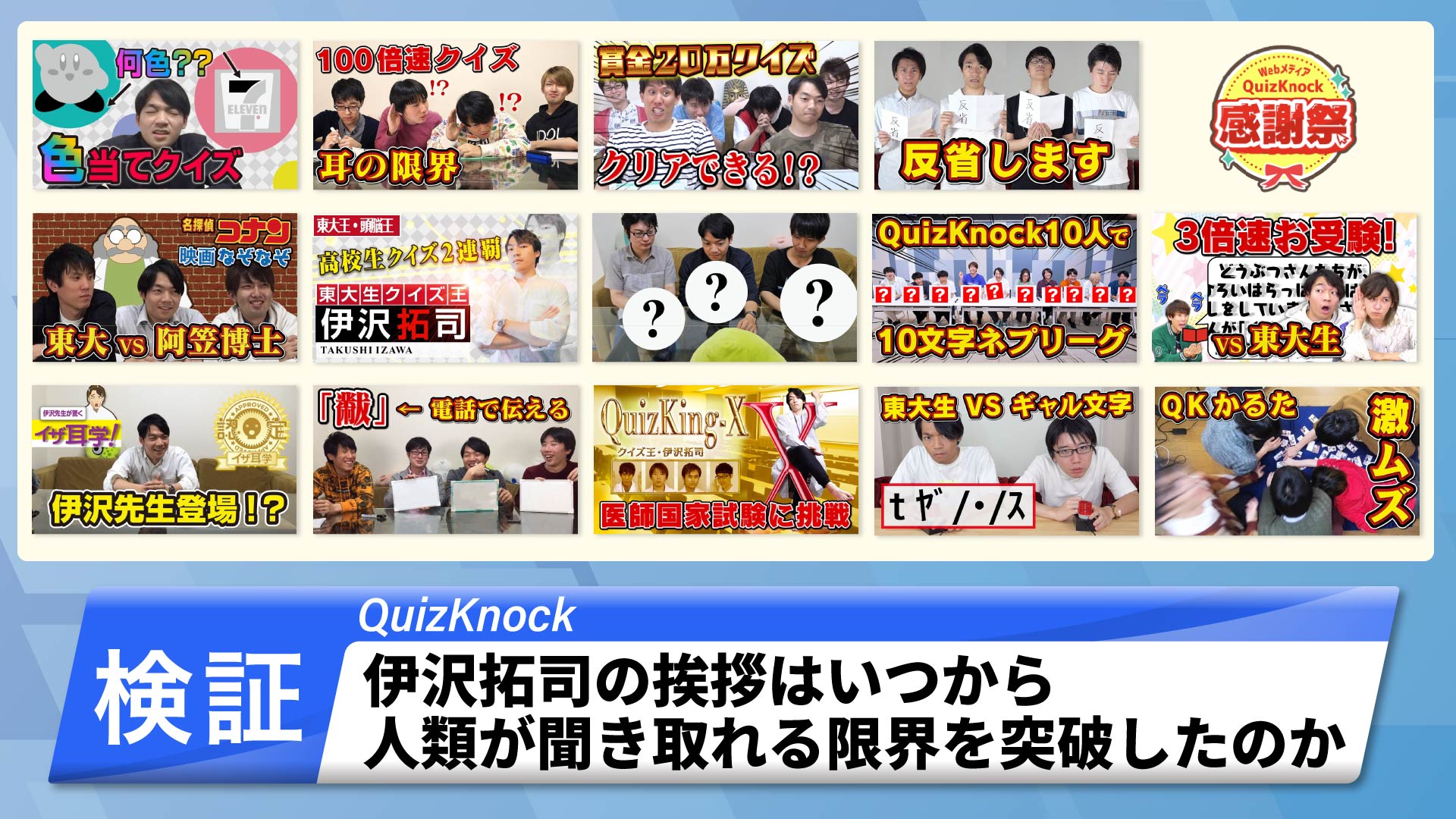
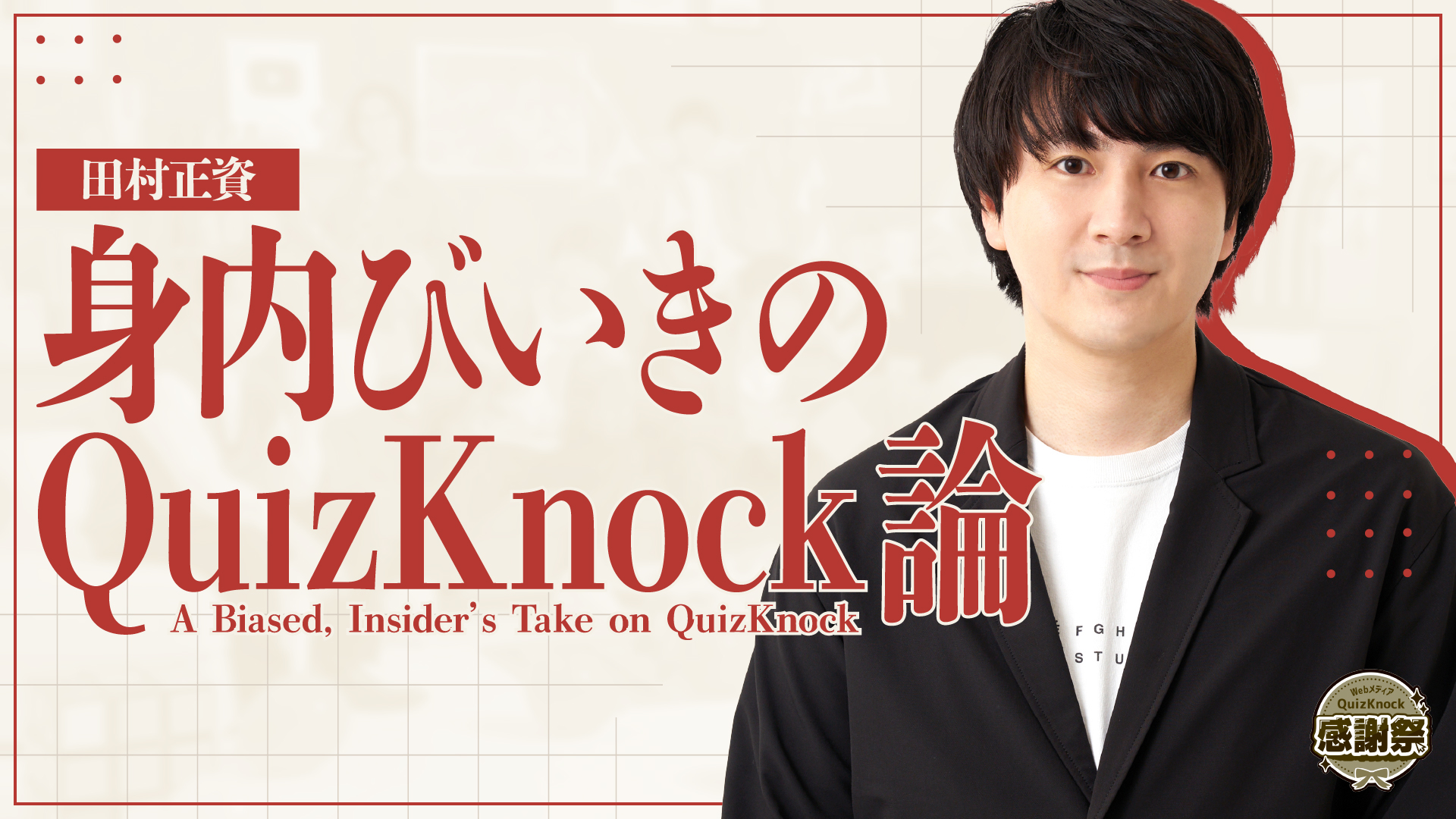



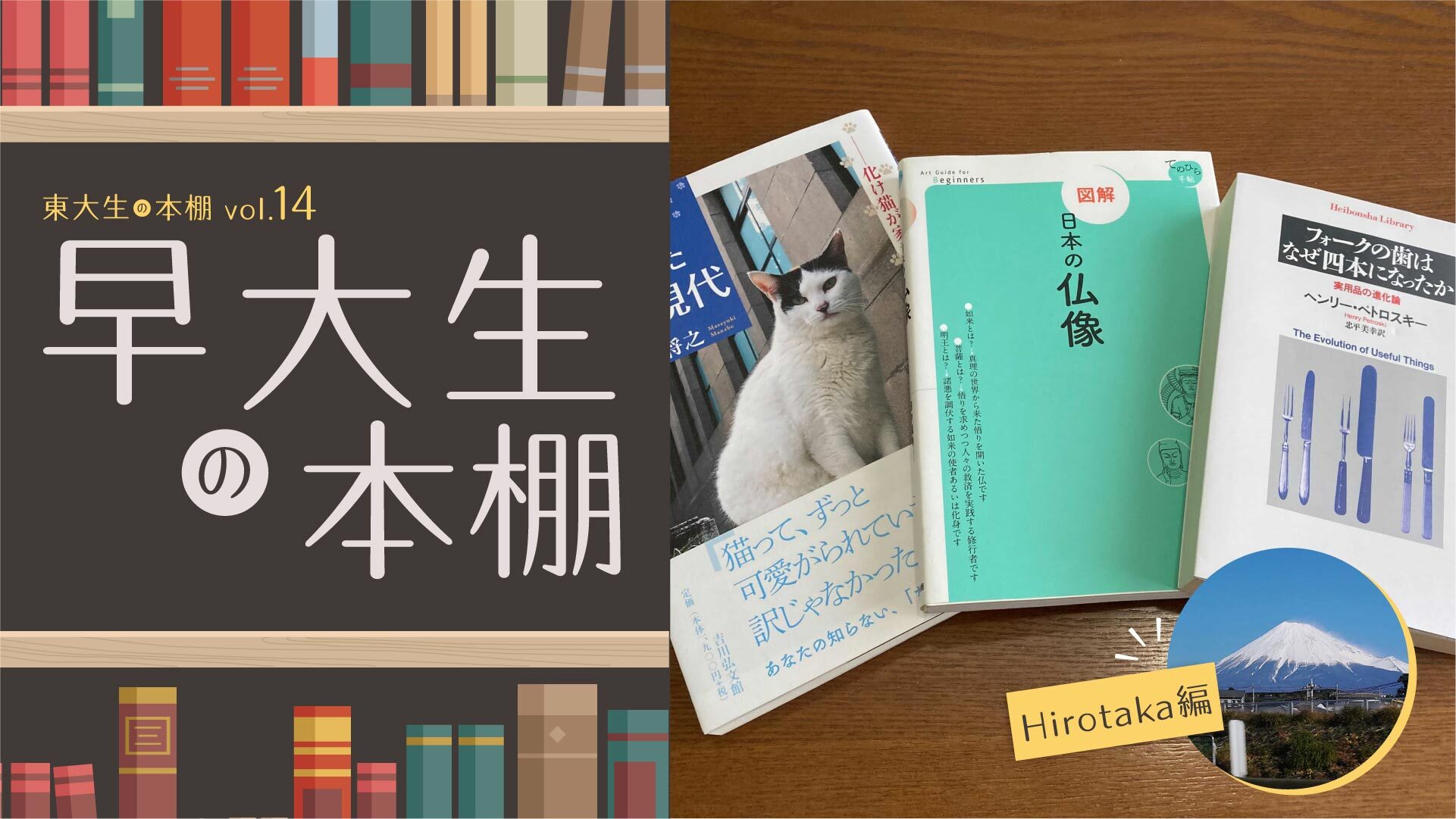
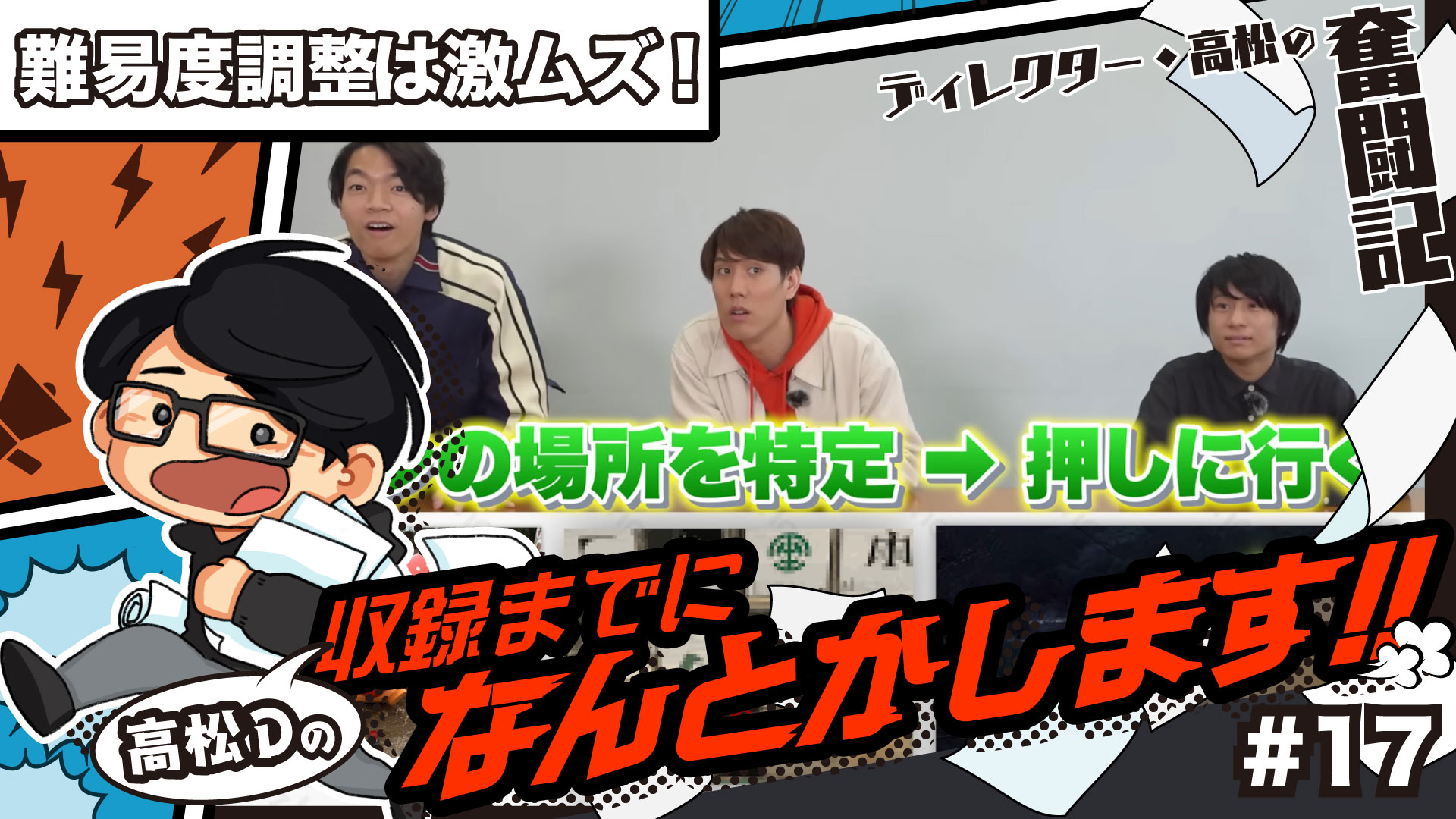
.jpg)