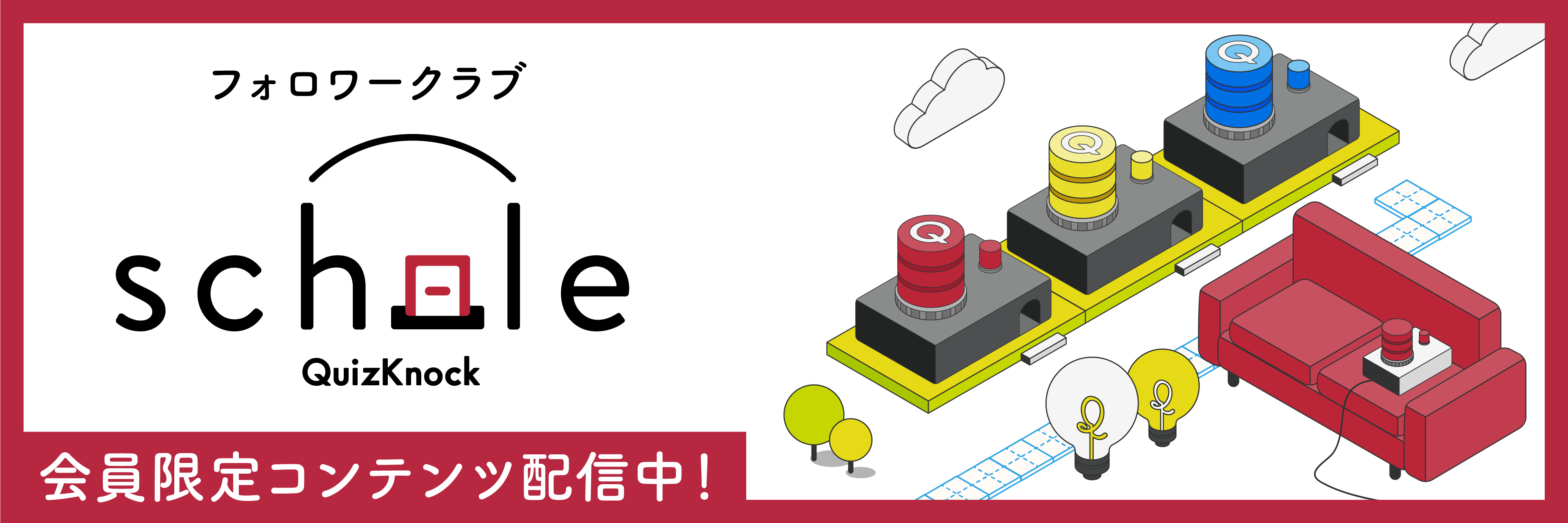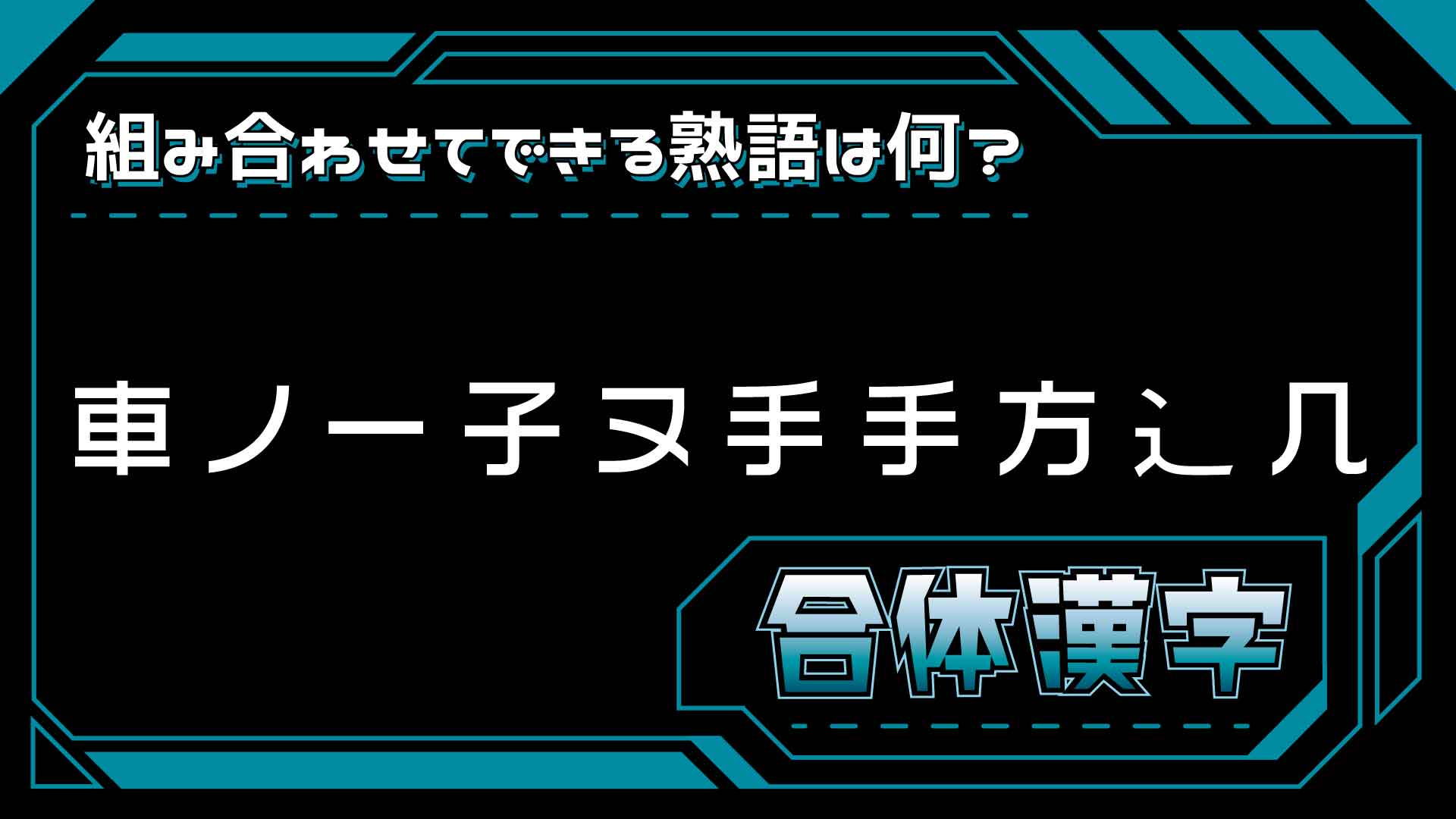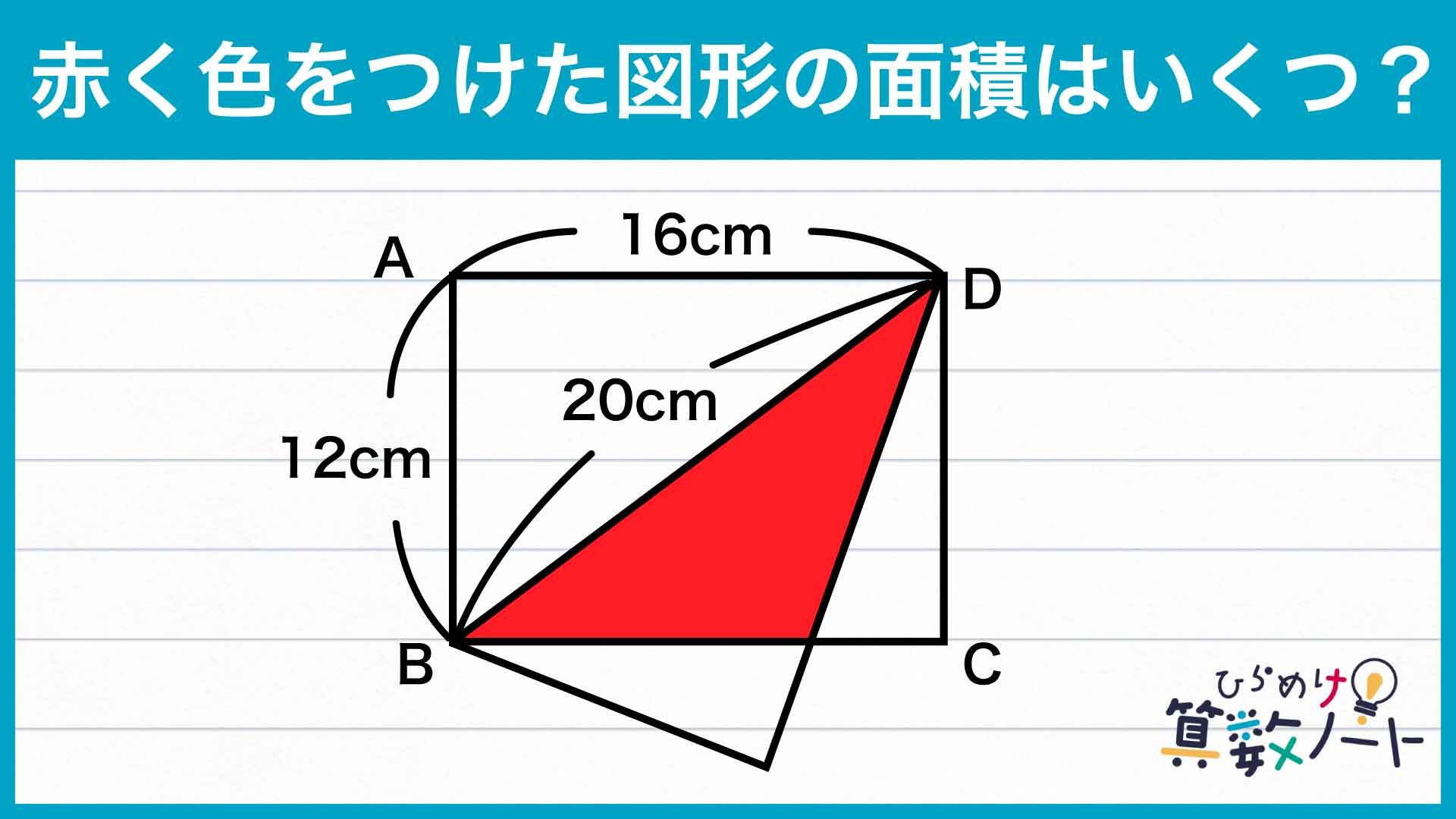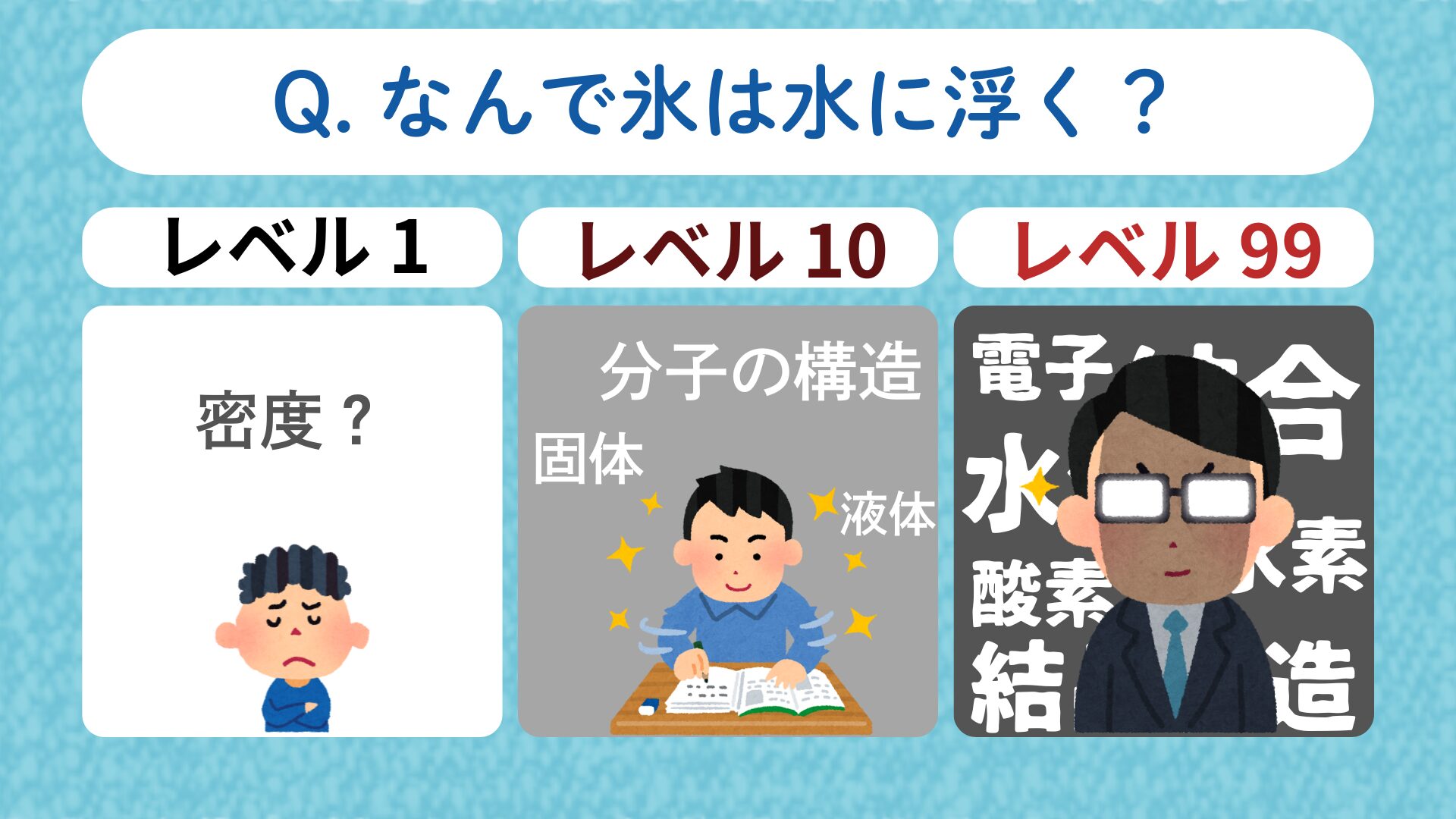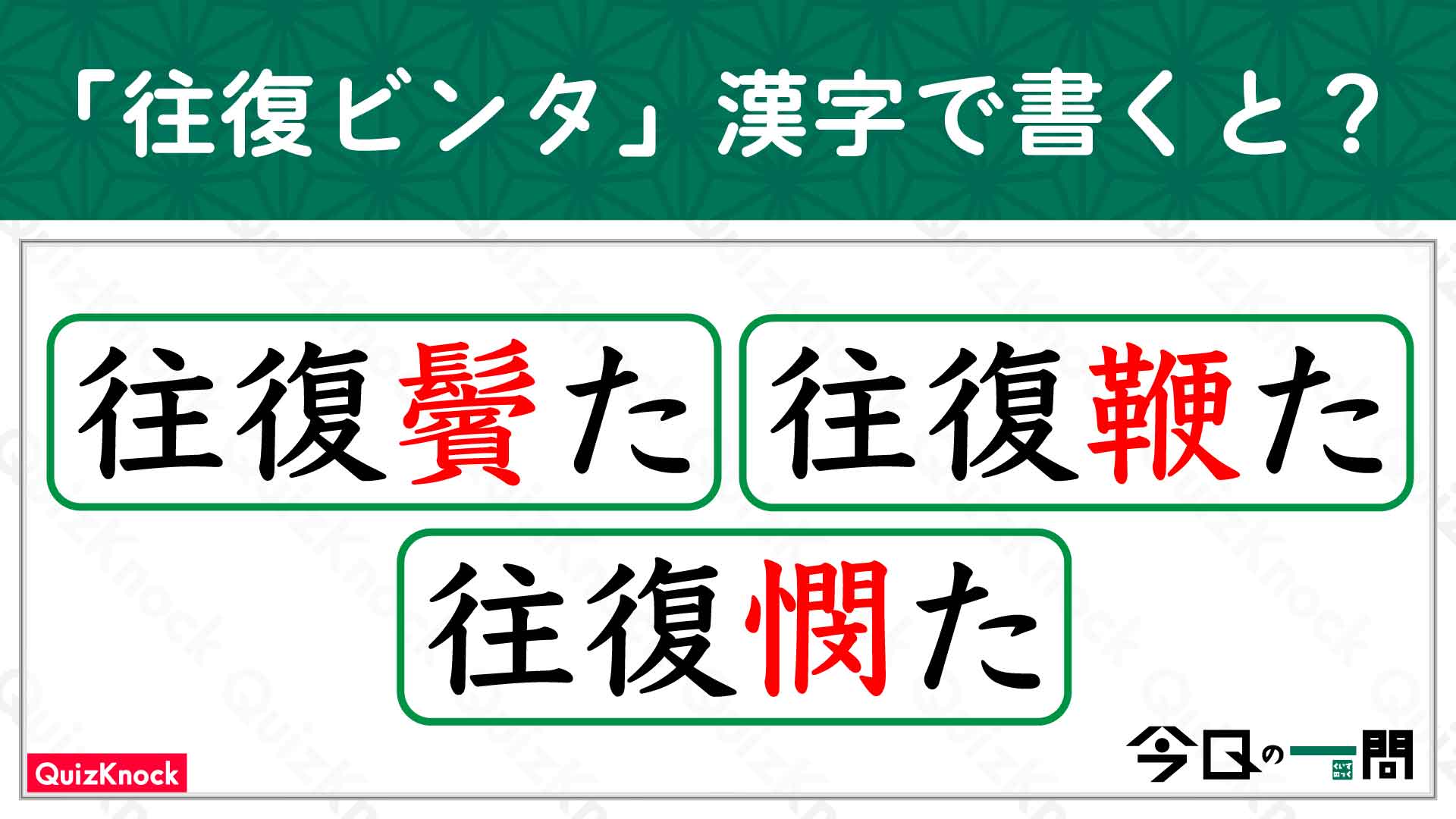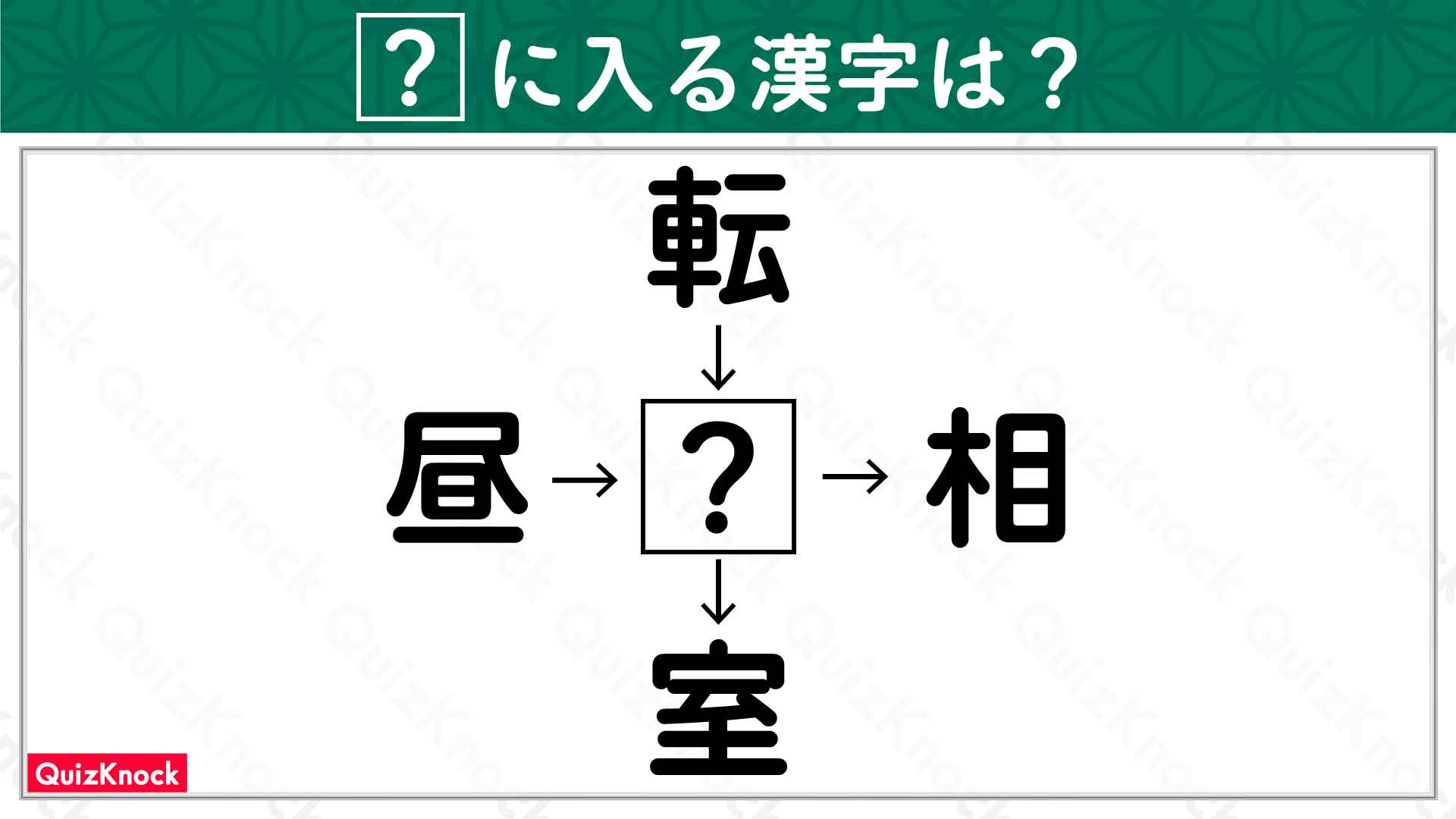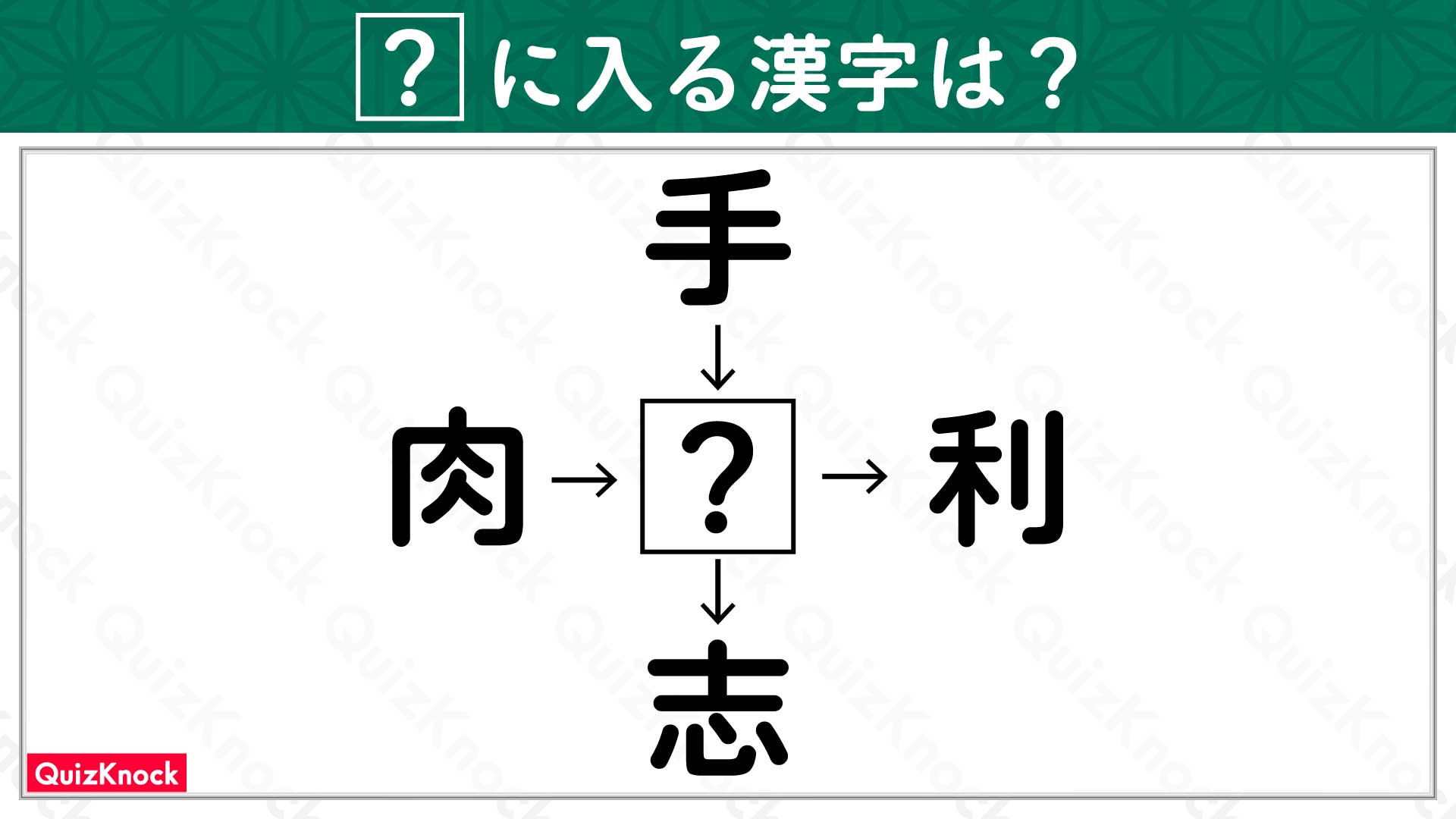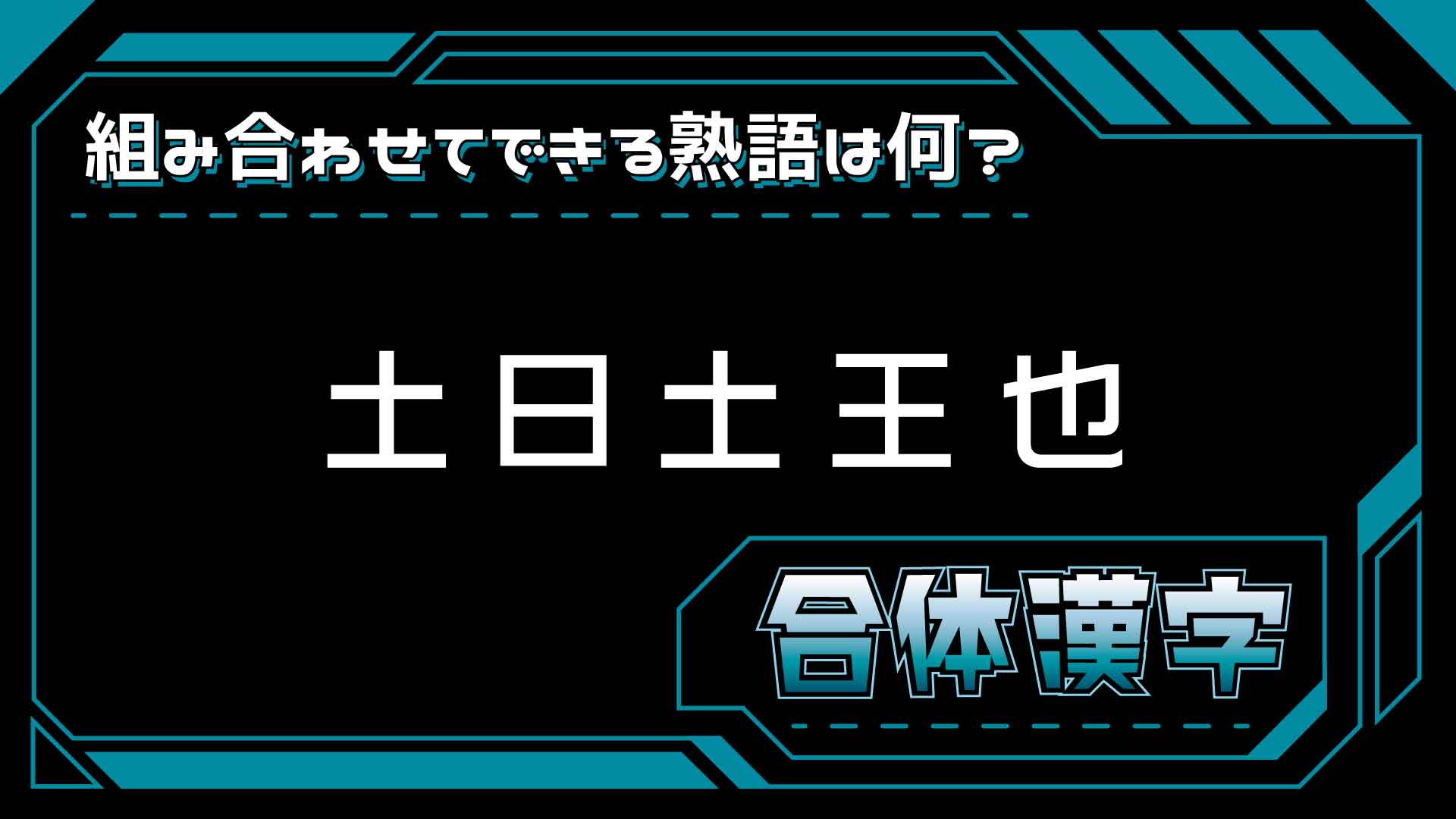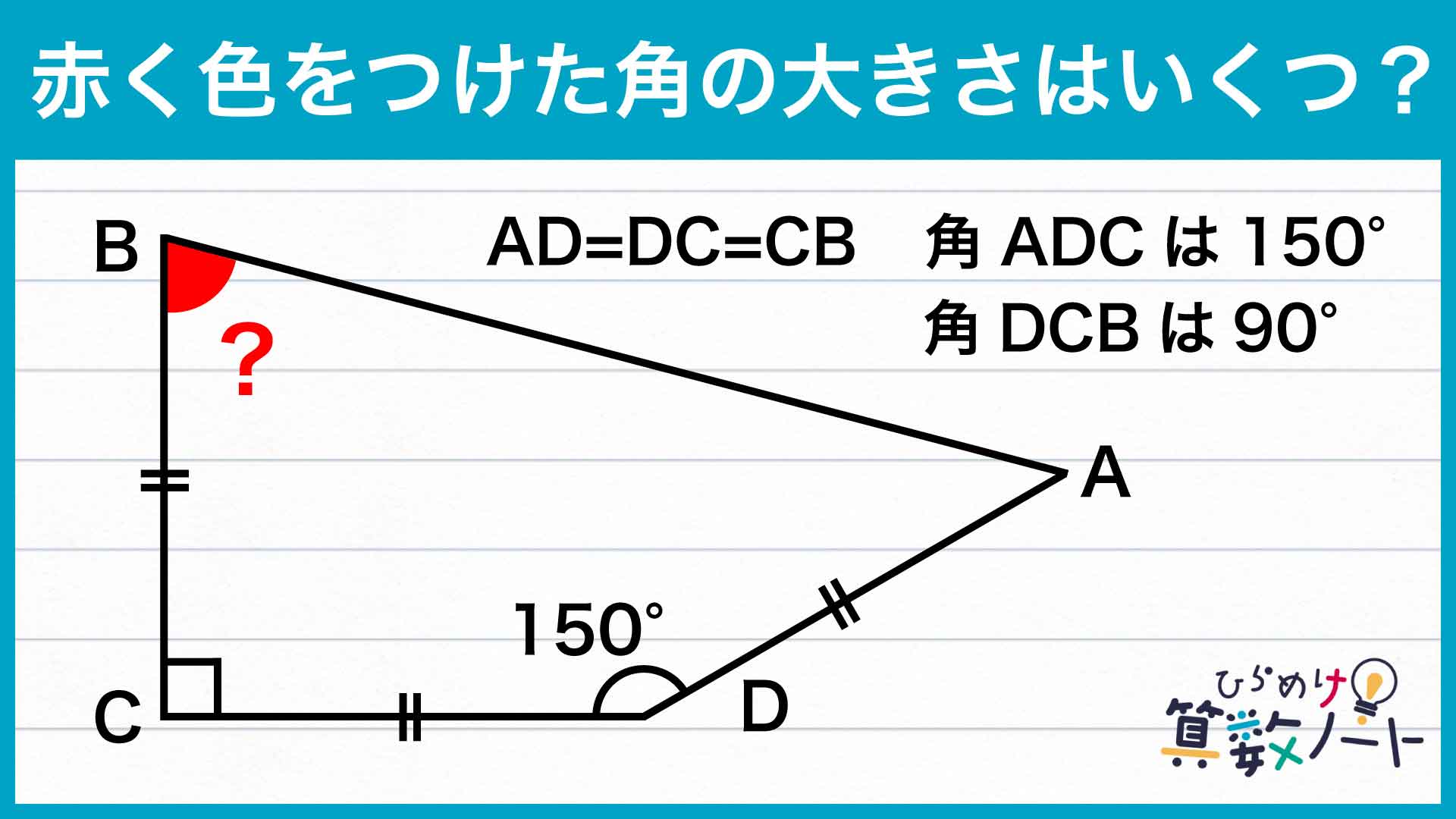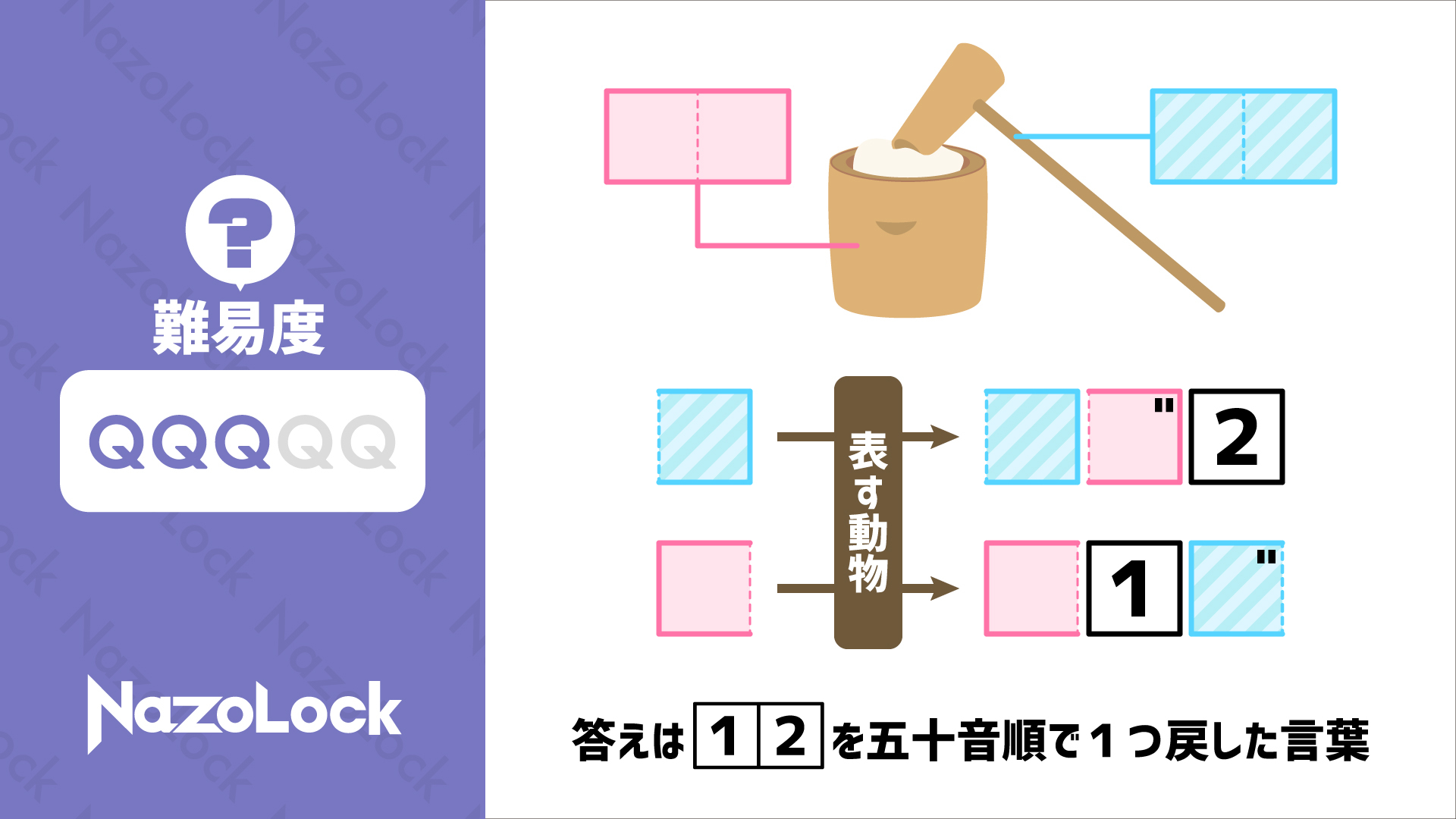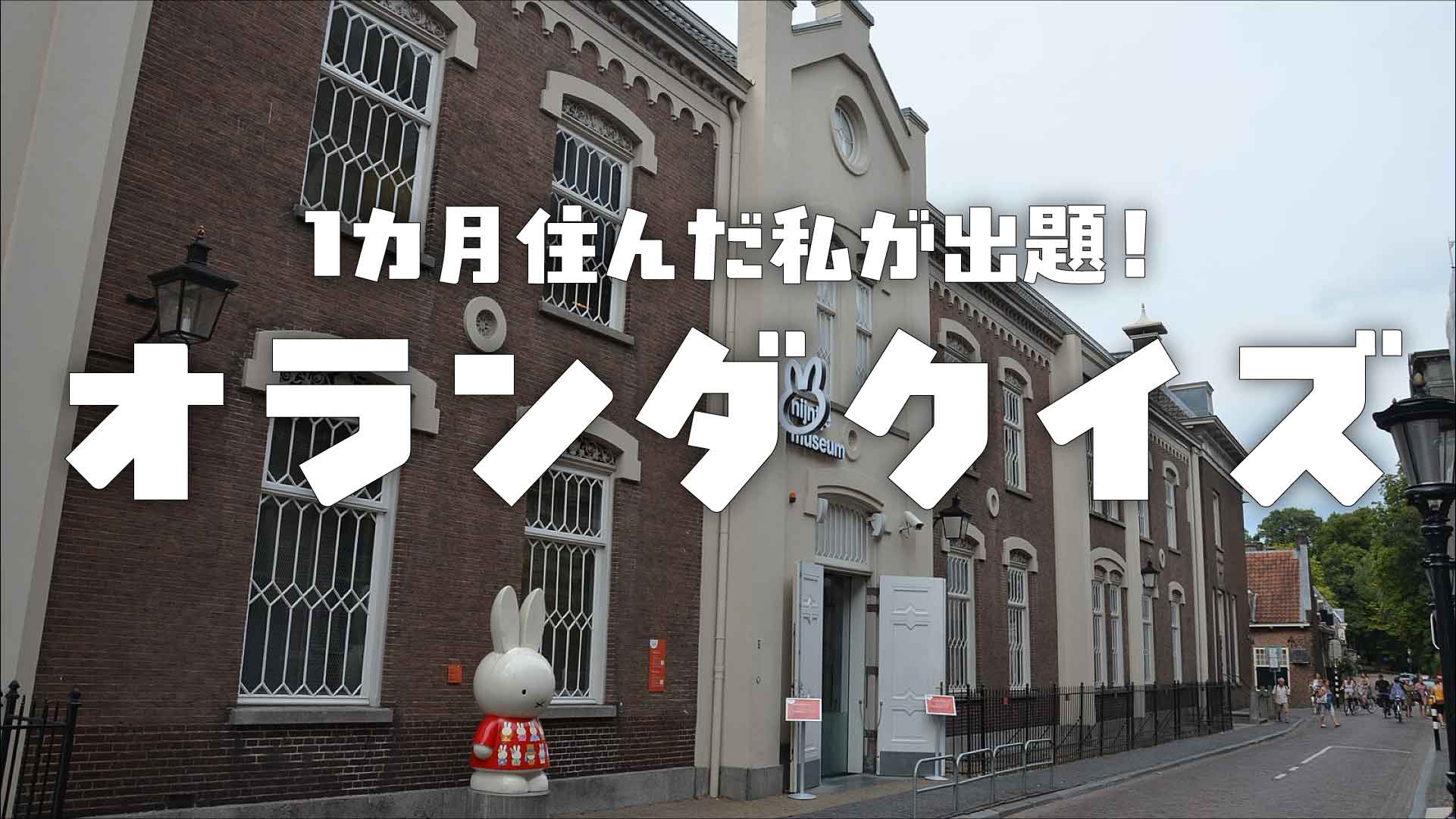はじめまして! 新人ライターの熊倉です。
風が急に肌寒くなってきた今日この頃。街のケヤキの葉もすっかり色づいています。
さて、この時季ならではの楽しみといえば……?

そう、どんぐりです。
小学生のころ、よくどんぐりの殻でどんぐり笛をつくって遊んだものです。どんぐりゴマなんてのもありますね。懐かしい思い出です。
今回は、知っているようで知らないどんぐりの魅力についてご紹介します。
そもそも、「どんぐり」って何?
一口に「どんぐり」といっても、その種類はさまざまです。一般的には、ナラ、カシ、シイなどのブナ科樹木の果実(堅果)のことを、総称して「どんぐり」といいます。
広義にはクリの実もどんぐりに含まれますが、今回クリは除外して扱います。

どんぐりをよく見てみましょう。どんぐりの実にかぶさっている「どんぐりの帽子」のようなものは、「殻斗」といいます。これは、花を支えていた総苞片という葉のような器官が集まって変化したものです。殻斗の反対側を見てみると、先が3つに分かれた小さな突起がありますね。これは、めしべの先端部が変化したものです。
実の殻を割った中身は、栄養をため込んだ2枚一組の子葉が大部分を占め、そこから小さな胚軸(のちに茎になる部分)がちょこんと突き出ています。季節などの条件がそろうと殻を突き破って胚軸が伸びていき、子葉の反対側が根となって芽生えが育っていくわけです。
どんなどんぐりがある?
ここでは、都市部でもよく見かける代表的な5種のどんぐりをご紹介します。
コナラ

クヌギ

シラカシ

スダジイ

マテバシイ

じつは食べられるどんぐり
縄文時代の人々は、どんぐりをすりつぶして焼き、クッキーのようにして食べていたといわれています。
ただ、多くのどんぐりには渋味があり、面倒な灰汁抜きの工程を経ないと食べられません。
しかし、マテバシイ、スダジイなどのどんぐりは渋味が少なく、灰汁抜きせずにそのまま食べることができます。
マテバシイを食べてみる
縄文人も食べていたどんぐりの味、気になりますね。私、熊倉、実際に食べてみることにしました。
今回は、手に入れやすく、大きくて食べ応えのありそうなマテバシイを食べてみます。次ページで紹介する食べ方は、私自身がひと月どんぐりを食べ続けて、編み出した調理法です。個人的にはおいしい食べ方だと思っていますが、個人視点の範囲内であることはご了承ください。
次ページ:はたしてどんな味?









-1-1024x683-1.jpg)