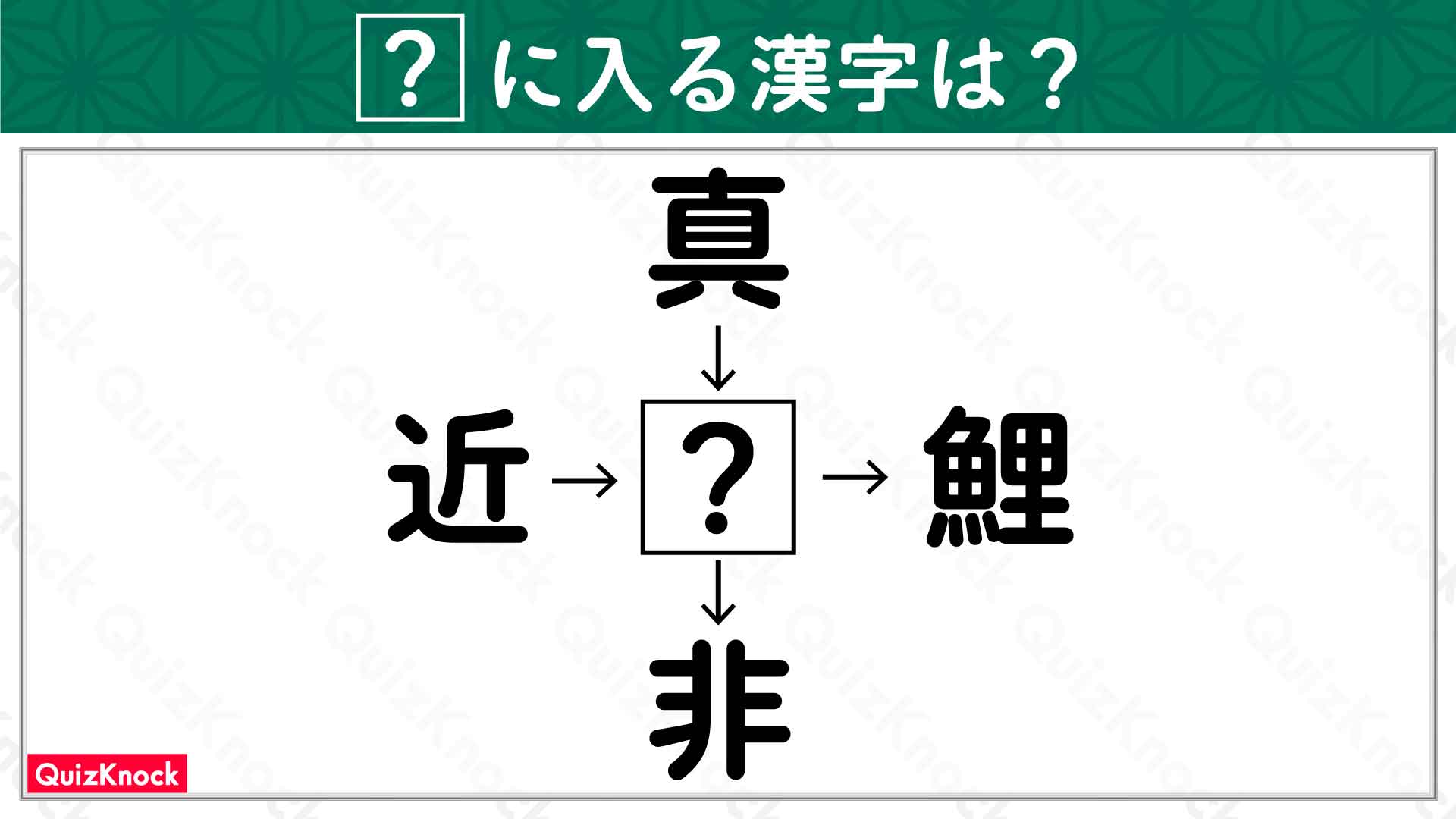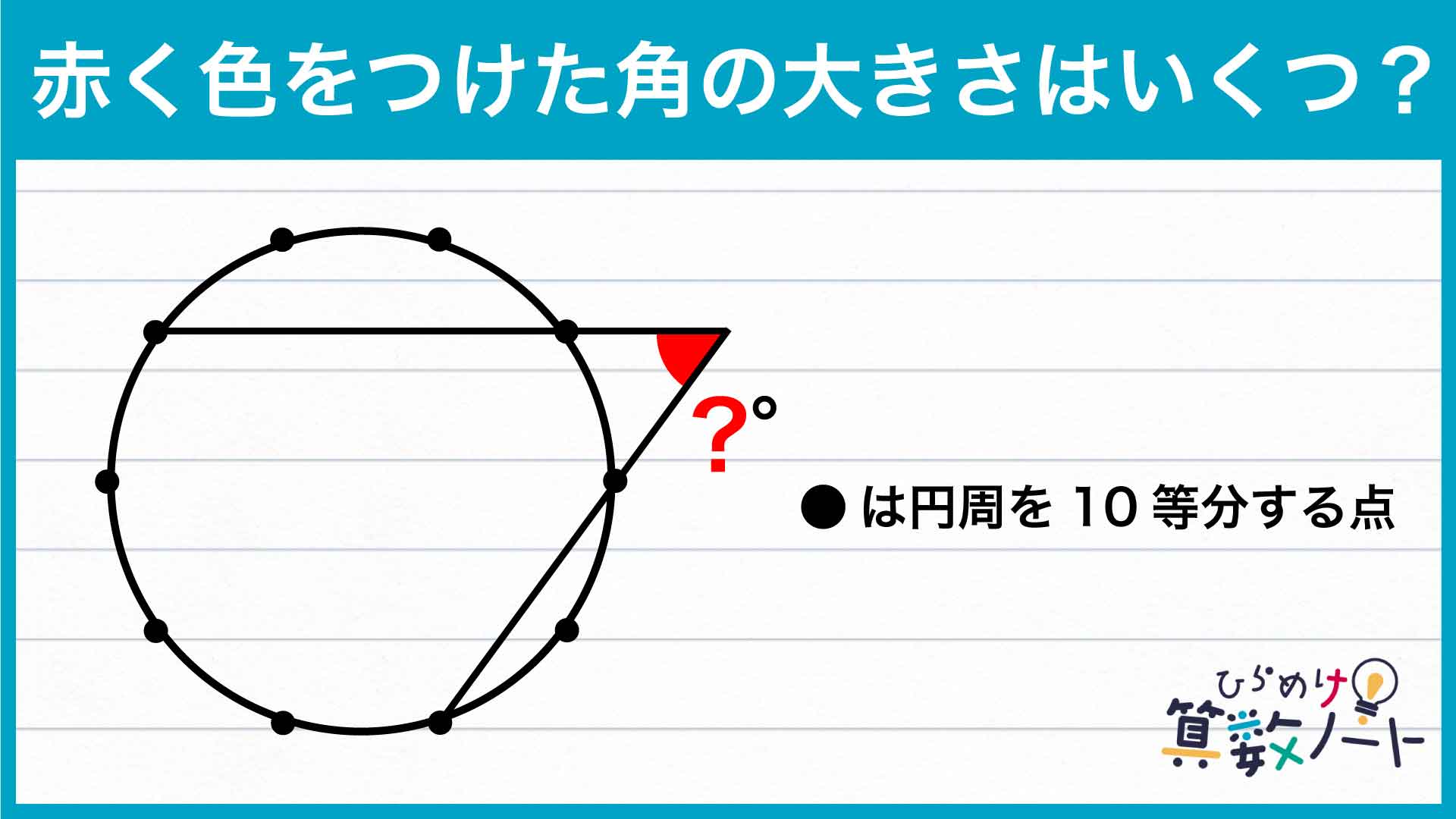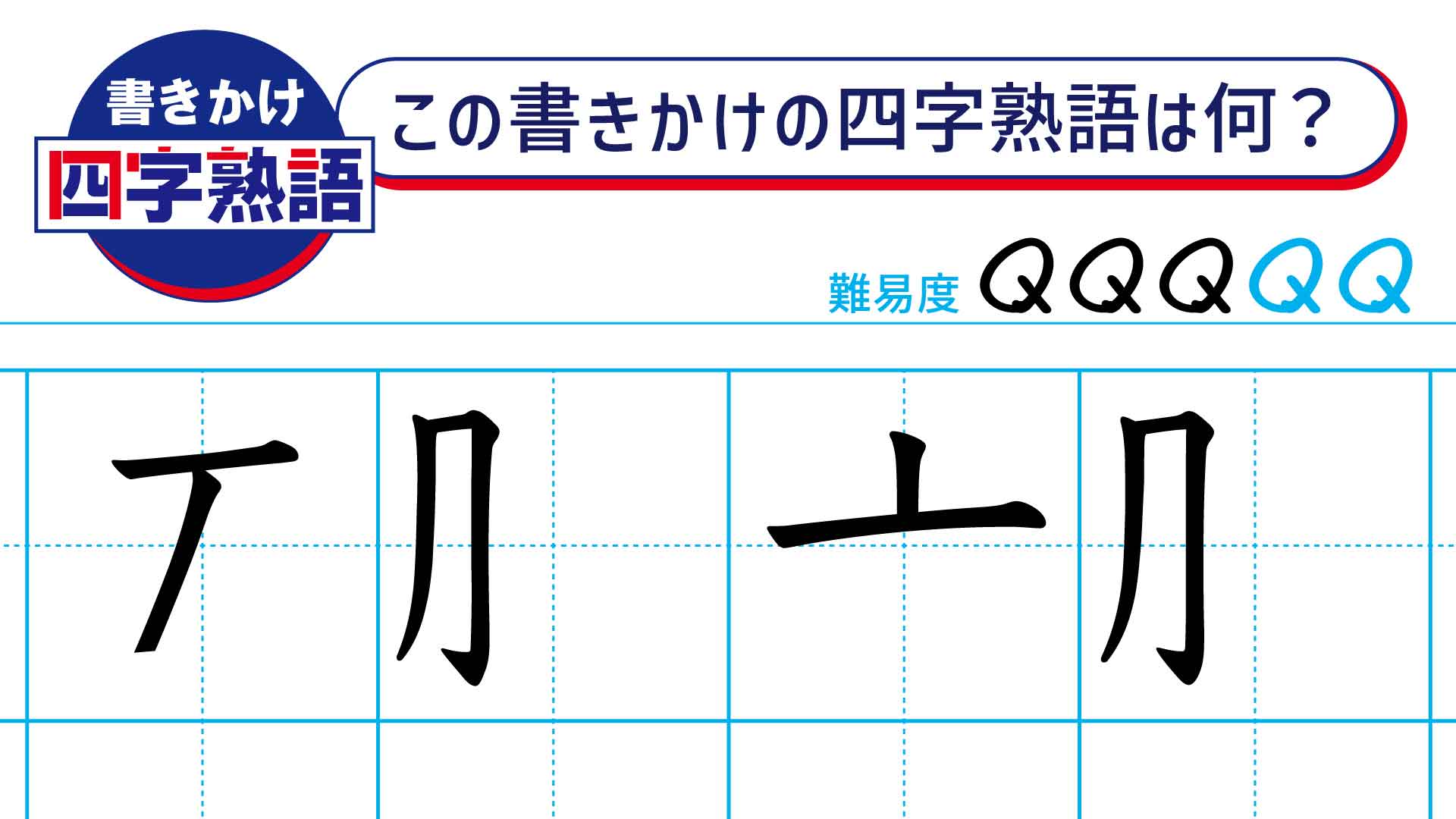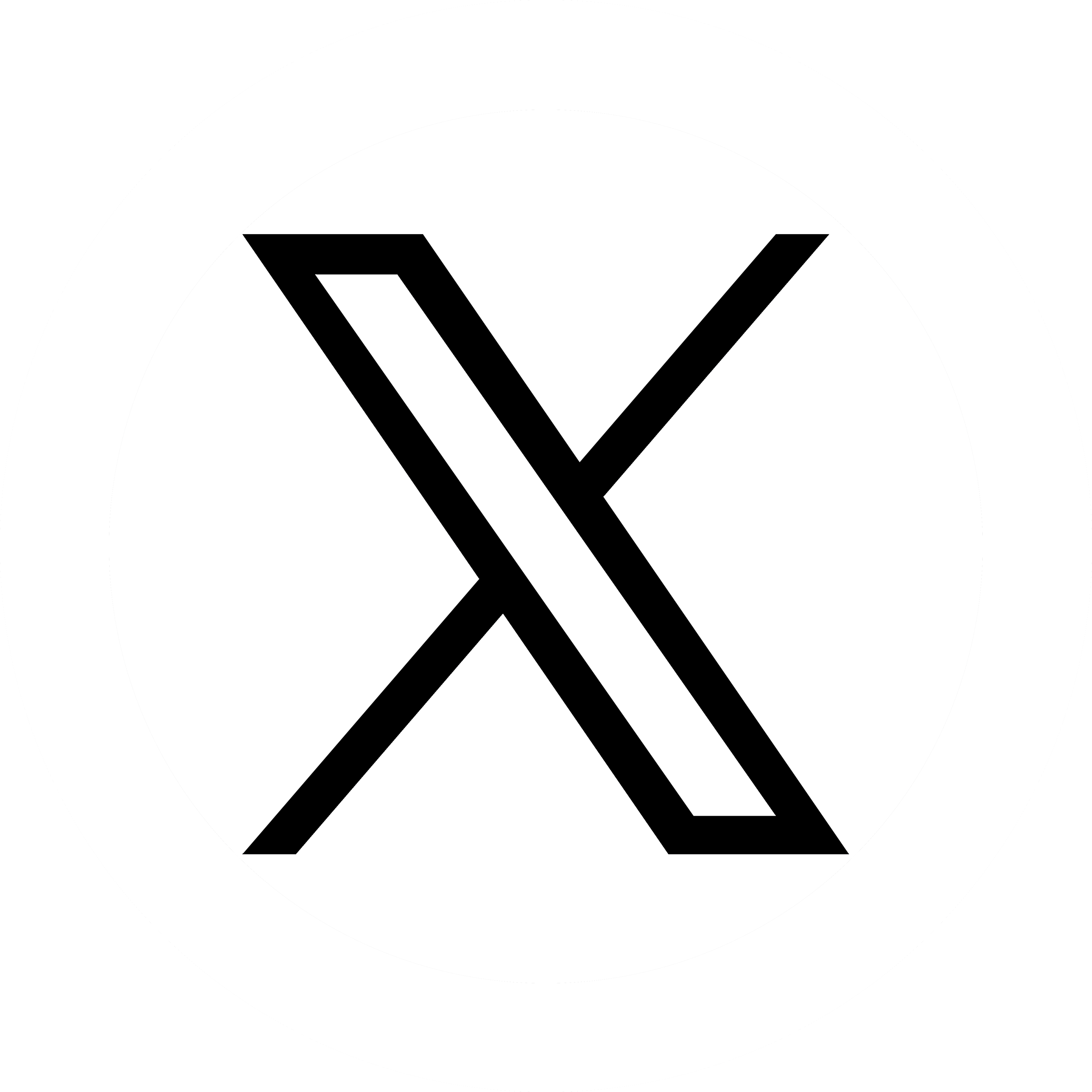あるクイズプレーヤーの話
私の友人に、山上大喜というクイズプレーヤーがいる。彼は骨の髄にまでクイズが染み込んでいるんじゃないかと思うようなクイズ好きで、私なんかでは頭の上がらないようなプレーヤーの一人だ。
彼との会話の中、以前に言っていた言葉で妙に頭に残っているものがある。それはある大会を指して(半ば嘲笑的に)放っていた一言だった。
「〇〇とかいう大会は、それに出るような問題を全て覚えてしまえば勝てるんだからしょうがないよな——」
当人にとっては本当に大したことのない一言だったと思う。長年積み重ねられたクイズ文脈で問題傾向が固められた、人によっては敬遠されるかもしれないそんな大会を笑っての一言だった。でもそれは、私にとっては救いにすらなりうる一言でもあった。
そうだ、クイズは、クイズなんだと。人生なんて関係ない、クイズのためのクイズをすれば、その場における全てを覚えれば勝てる場がある。そのクイズが悪であるとは私は到底思えなかった。なら、人生にこだわっていた私ってなんなんだろうと、素直にそう思えてしまった。
それに、山上は笑っていた。彼は、素晴らしいクイズを語るときも、しょうもないクイズを語るときも、どちらも同じくらい楽しいことみたいに、等しく笑う。
クイズってそんなものなんだ。今になってようやく、彼の笑顔の理由がわかった気がする。
頼むよ、クイズ
自分はQuizKnockという今の環境で、クイズに関わっていることをときに後ろめたく思うことがある。
動画やテレビ番組で聴衆を前に鮮やかな正解を積み、華々しく活躍するようなメンバー以上に、クイズという競技や文化に真摯に向かい合い考えることをやめない人たちがここにはたくさんいる。
そんな中で、クイズに関わる企画の制作や作問を行っていると、どうにも自分がこんなことをしていていいのかという思いに囚われてしまう。つい「クイズプレイヤーにはできない自分だけの強み」を見つけようと、逃げたくなることもある。クイズができなくとも、自分には他のものがあるじゃないかと。でも、クイズの場で戦う以上、クイズによってしか得られないものがほとんどだ。野球場でサッカーの自慢をしたってなんになる? 虚しいだけのことだ。
私がこの仕事を、クイズに関わることを続ける以上、救われなかったこれまでの人生の部分のことを度々考えることになるのだと思う。でも、私はそれ以上にクイズが好きだ。クイズをしている人たちが、どうしようもなくカッコよくて大好きだ。クイズの中で正解を積み上げ何かを得られてこそ、「人生が肯定される」クイズの素晴らしさも、いつかきっと素直に受け取れる日が来るんじゃないかと、そう信じていたい。
先日、実家の本棚を片付けていて、最後まで解き切ることもなく積んでいた多くのクイズの問題集が見つかった。「この本ではベタ問を中心に掲載し——」と書かれた問題集をパラパラとめくり、その多くを覚えていない自分に笑ってしまった。私、まだ何もやっていないじゃない。
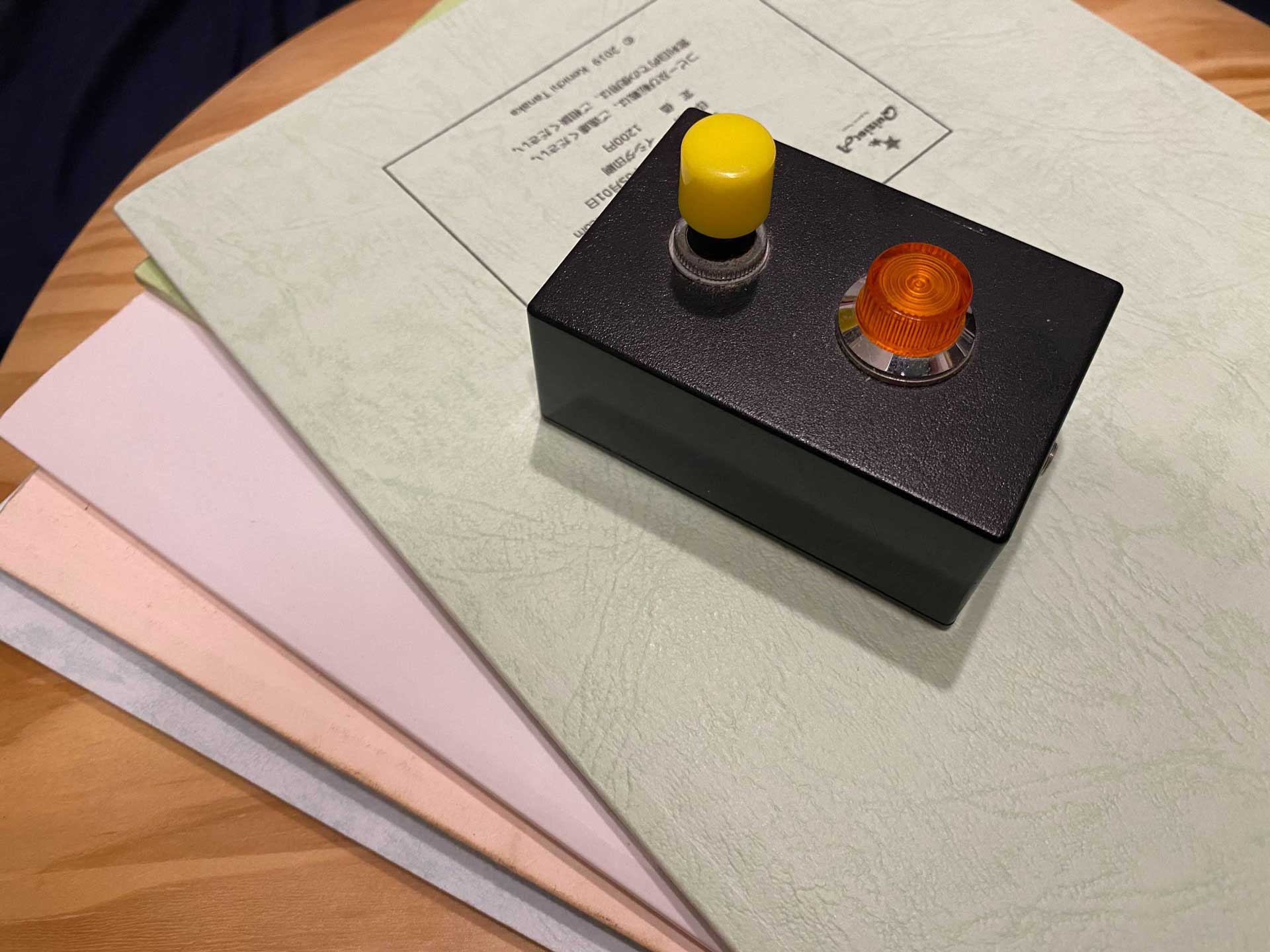
クイズプレーヤーは強い。私がたとえ必死に勉強をしようとしても、彼らはそれ以上に勉強し、クイズをし続ける。救われようなんてそんな下心もなく、ただクイズのためにボタンを押す。正直、追いつこうだなんてとても思わない。勝とうとも、なんなら思わない。ただ私の、自分のためにもっとクイズがしたい。もしかすると、次の正解こそが私の人生を救ってくれるかもしれない、なんて余計なことを考えながら。
【あわせて読みたい】
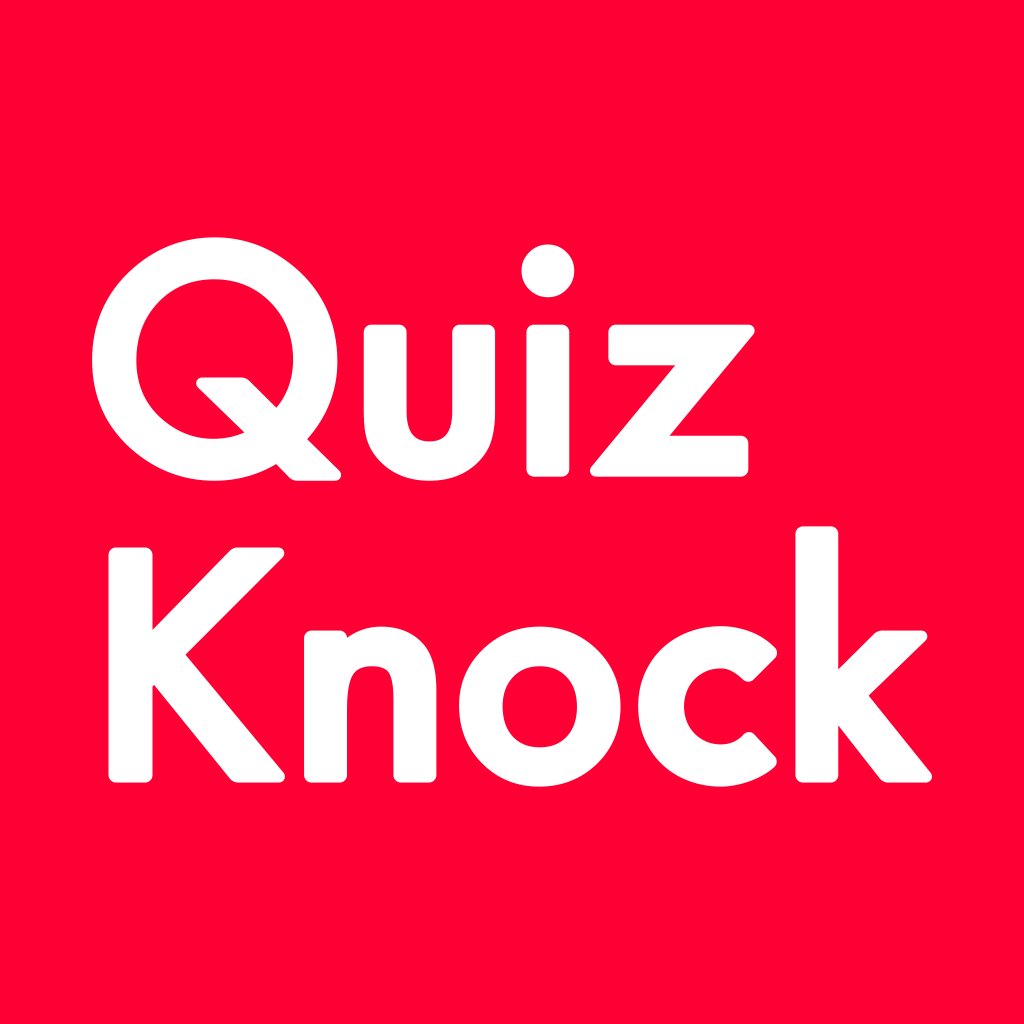



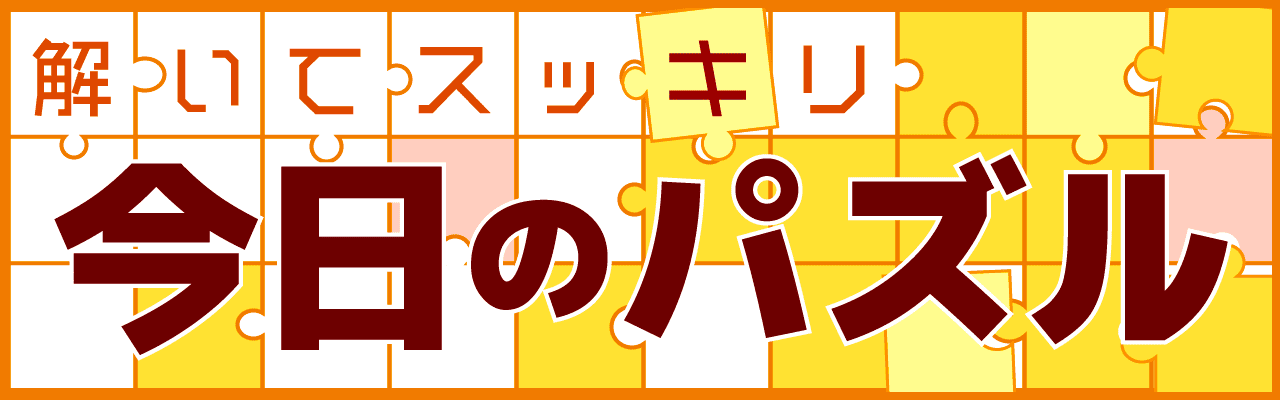
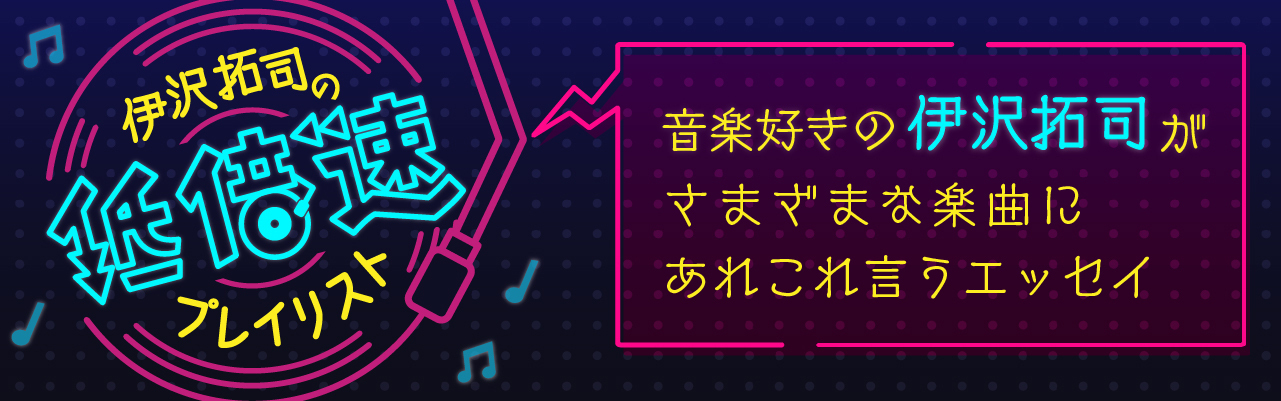

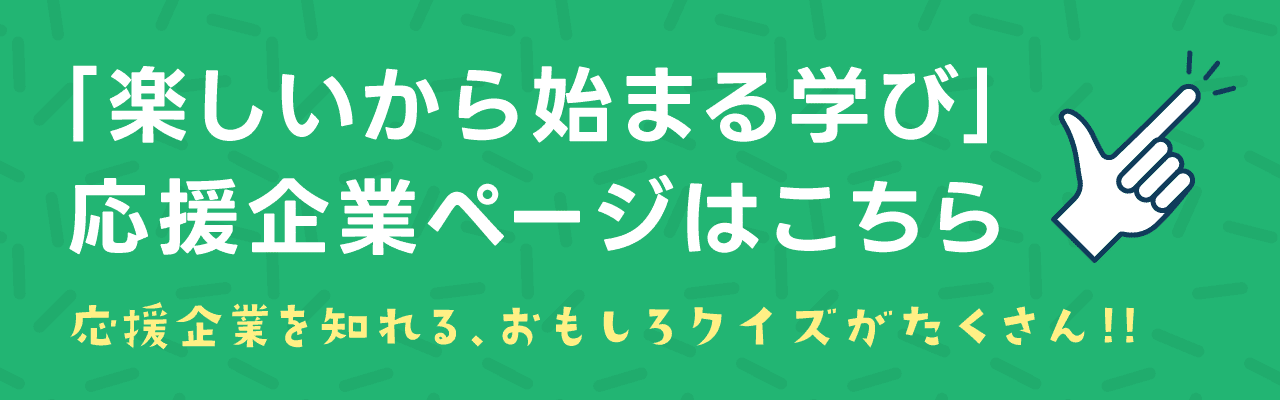



.jpg)
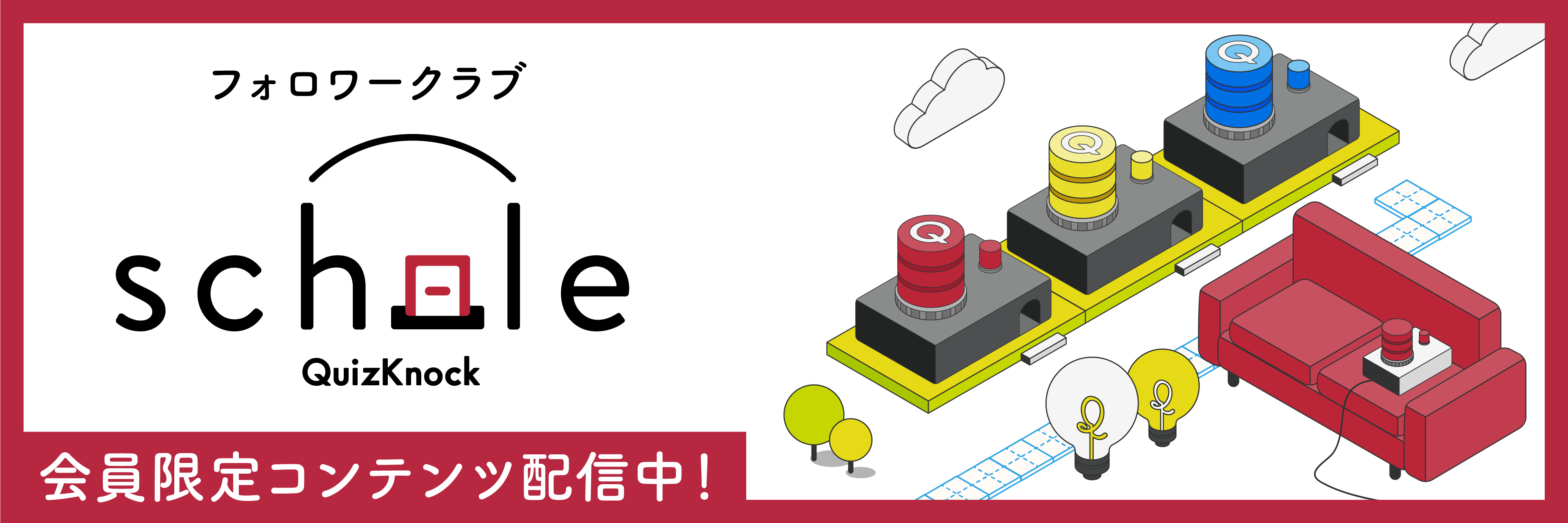







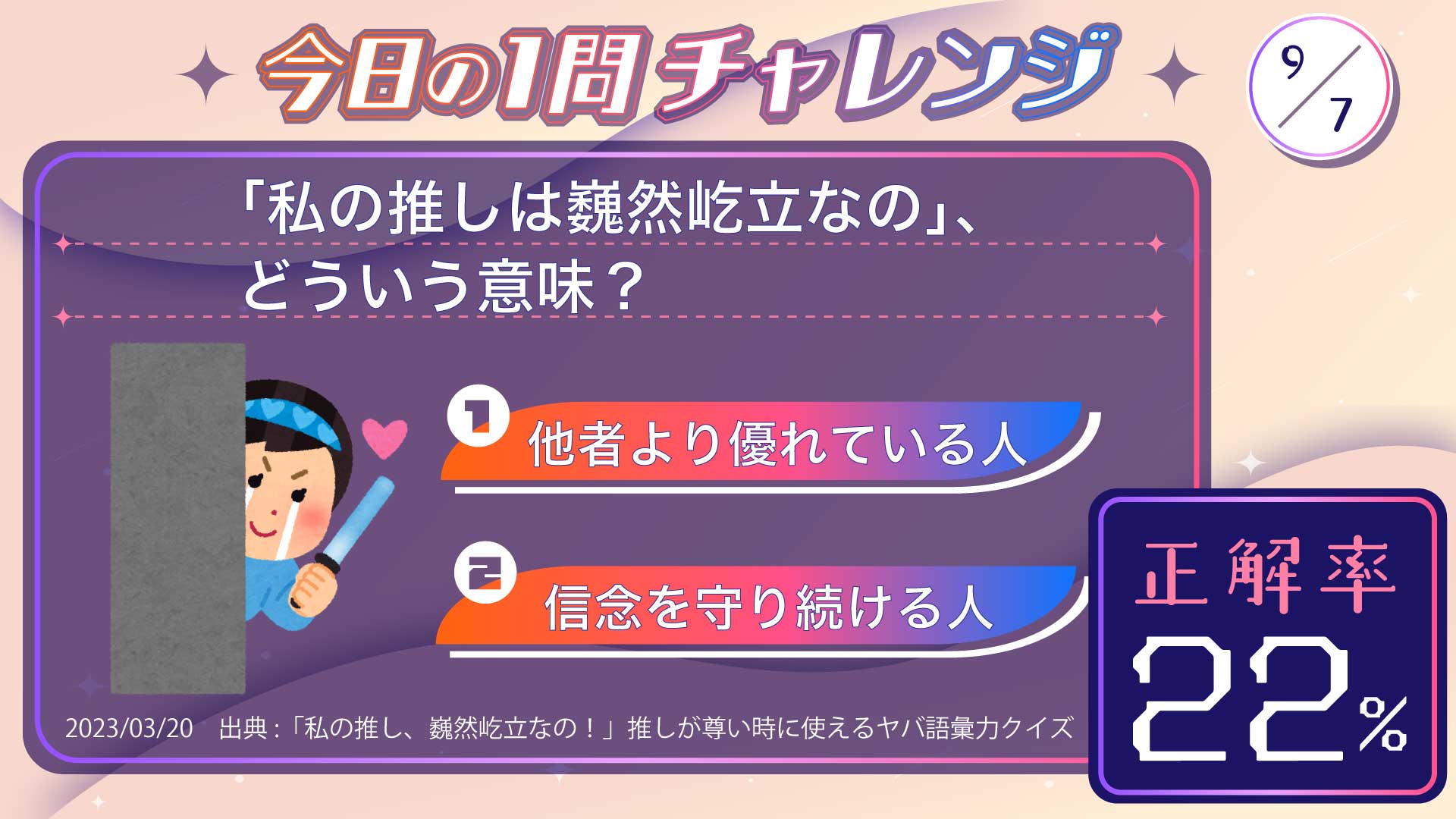

.jpg)