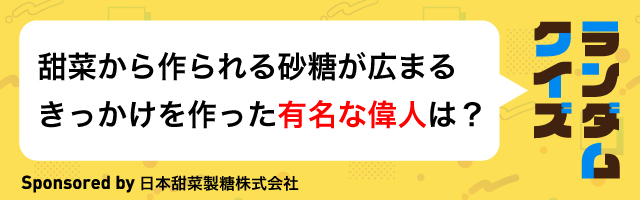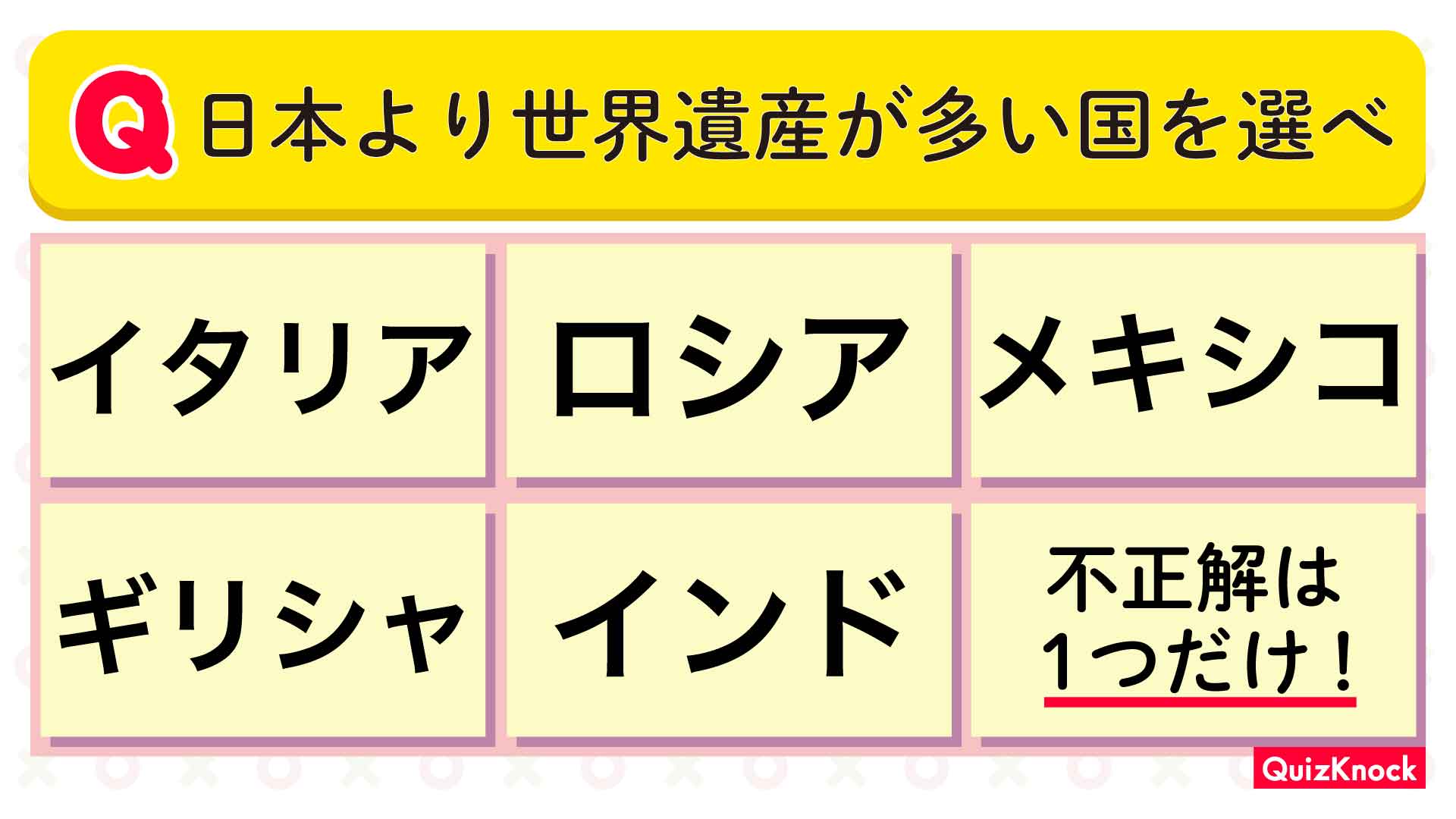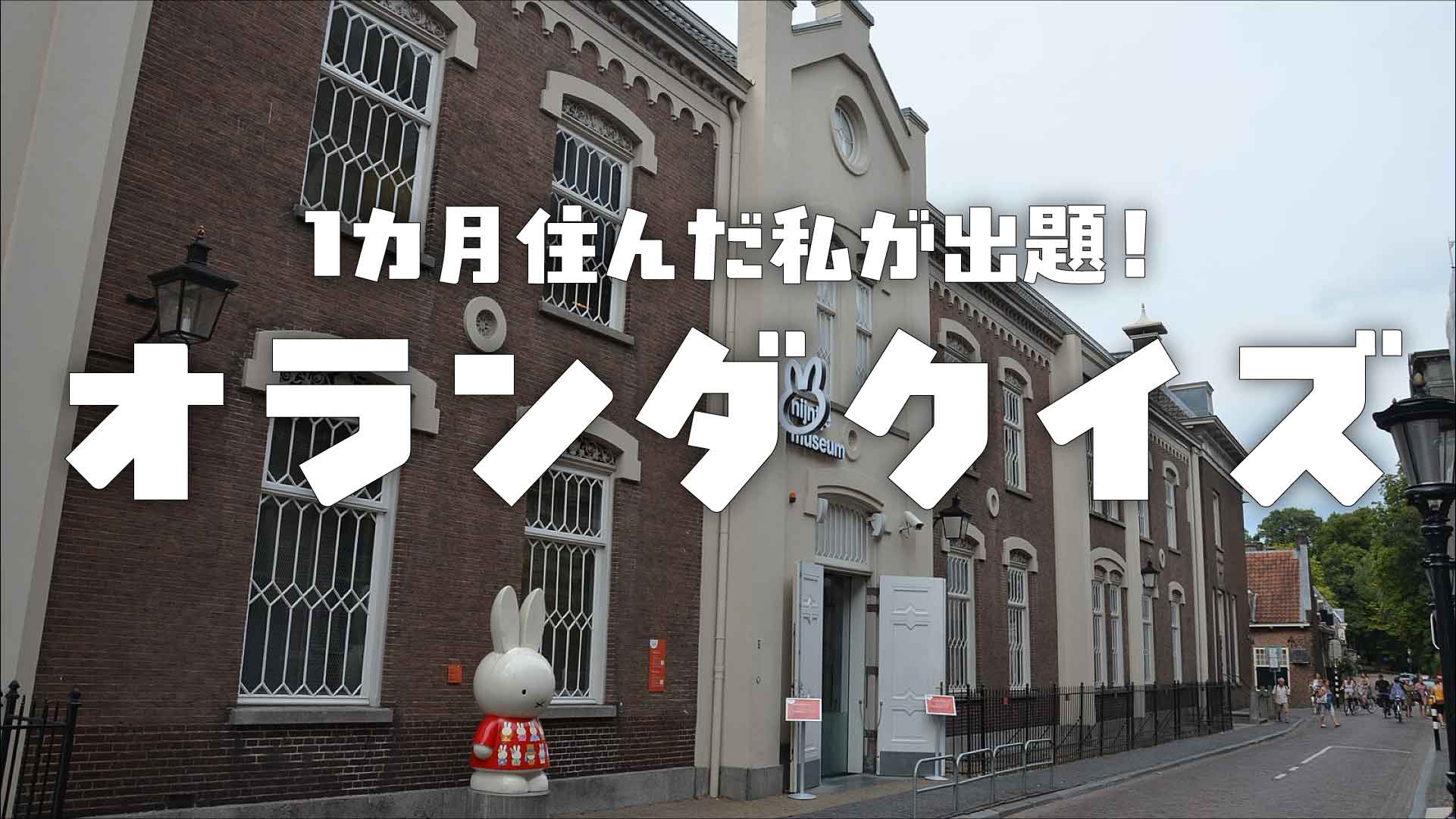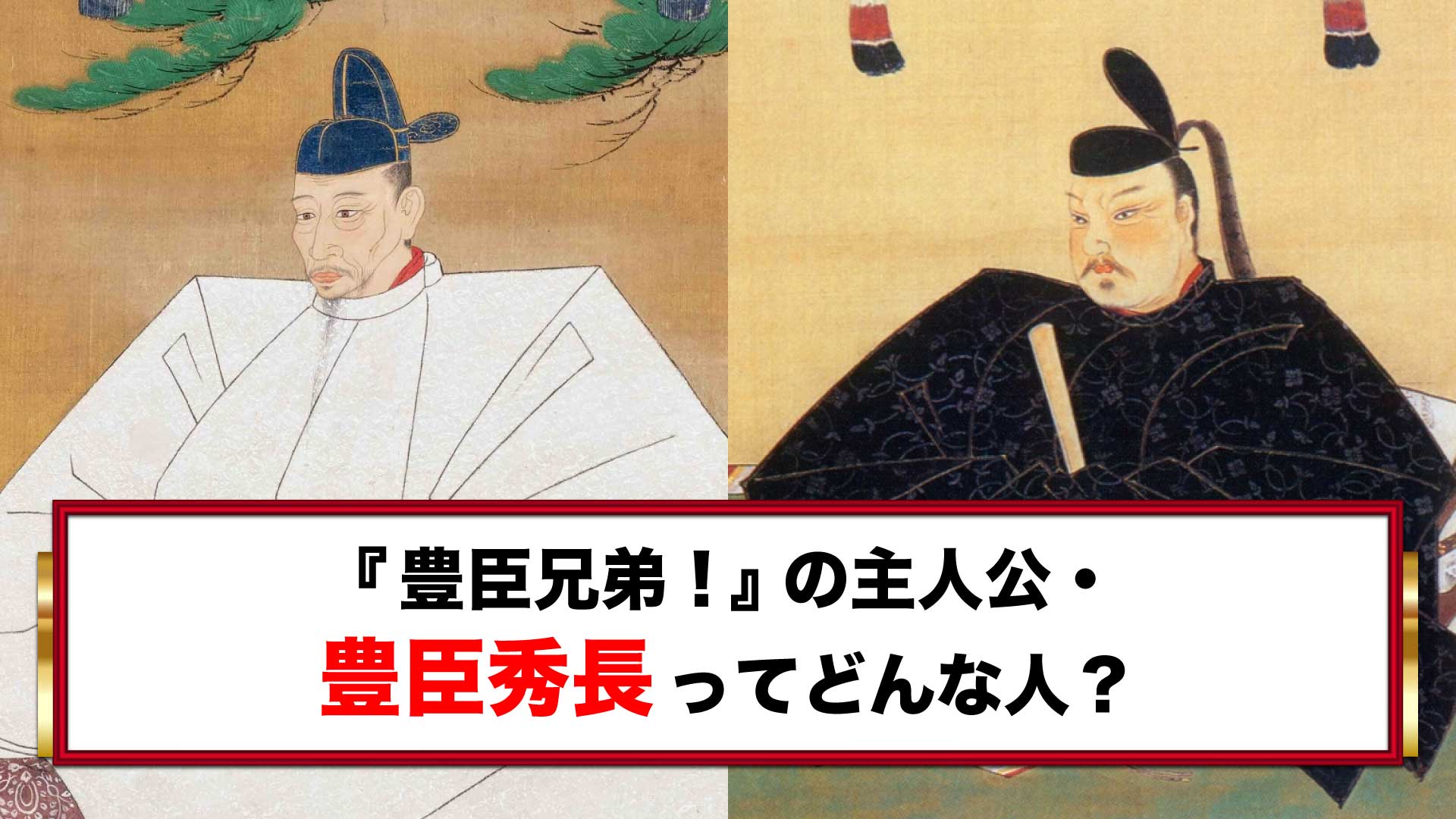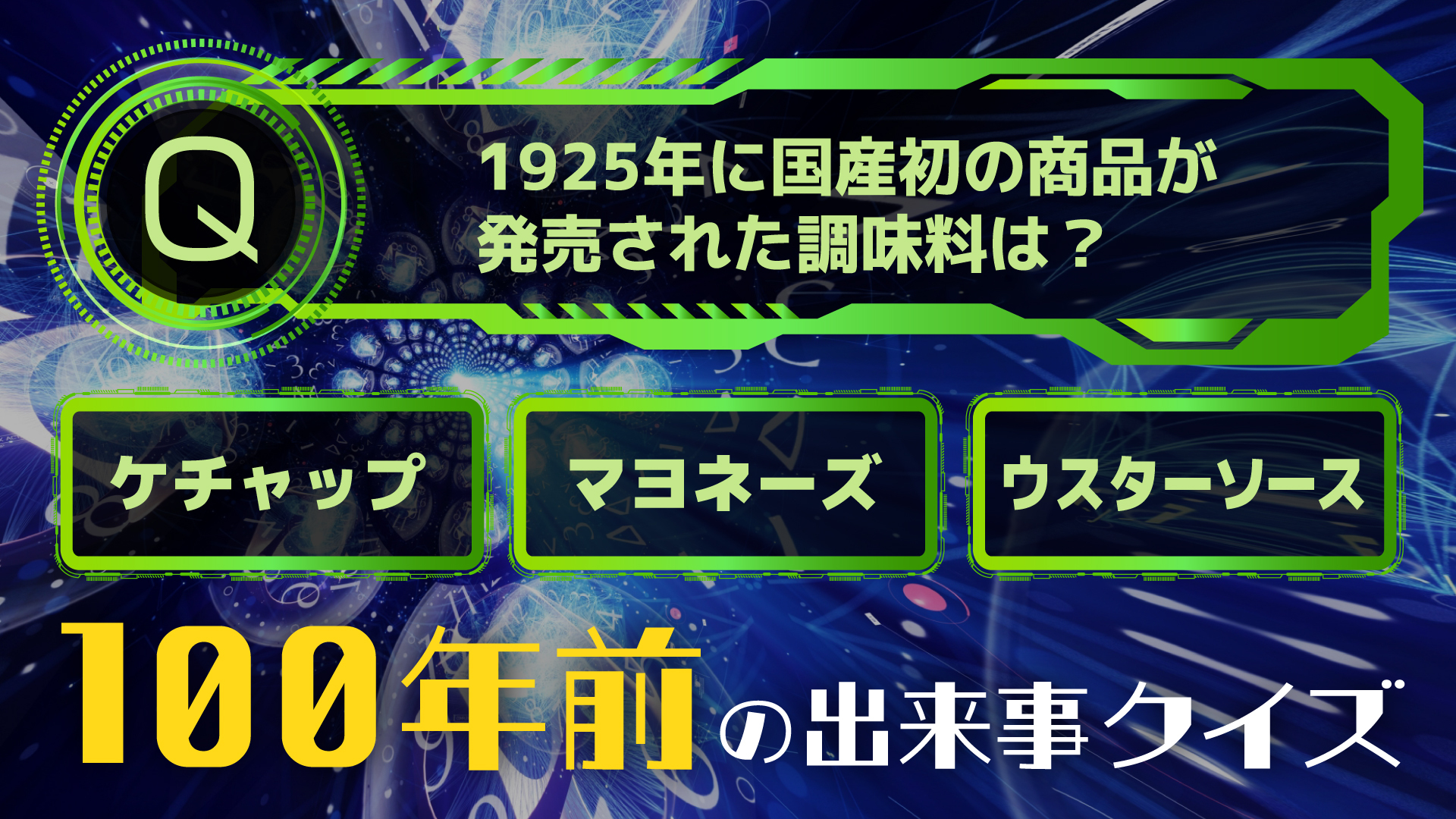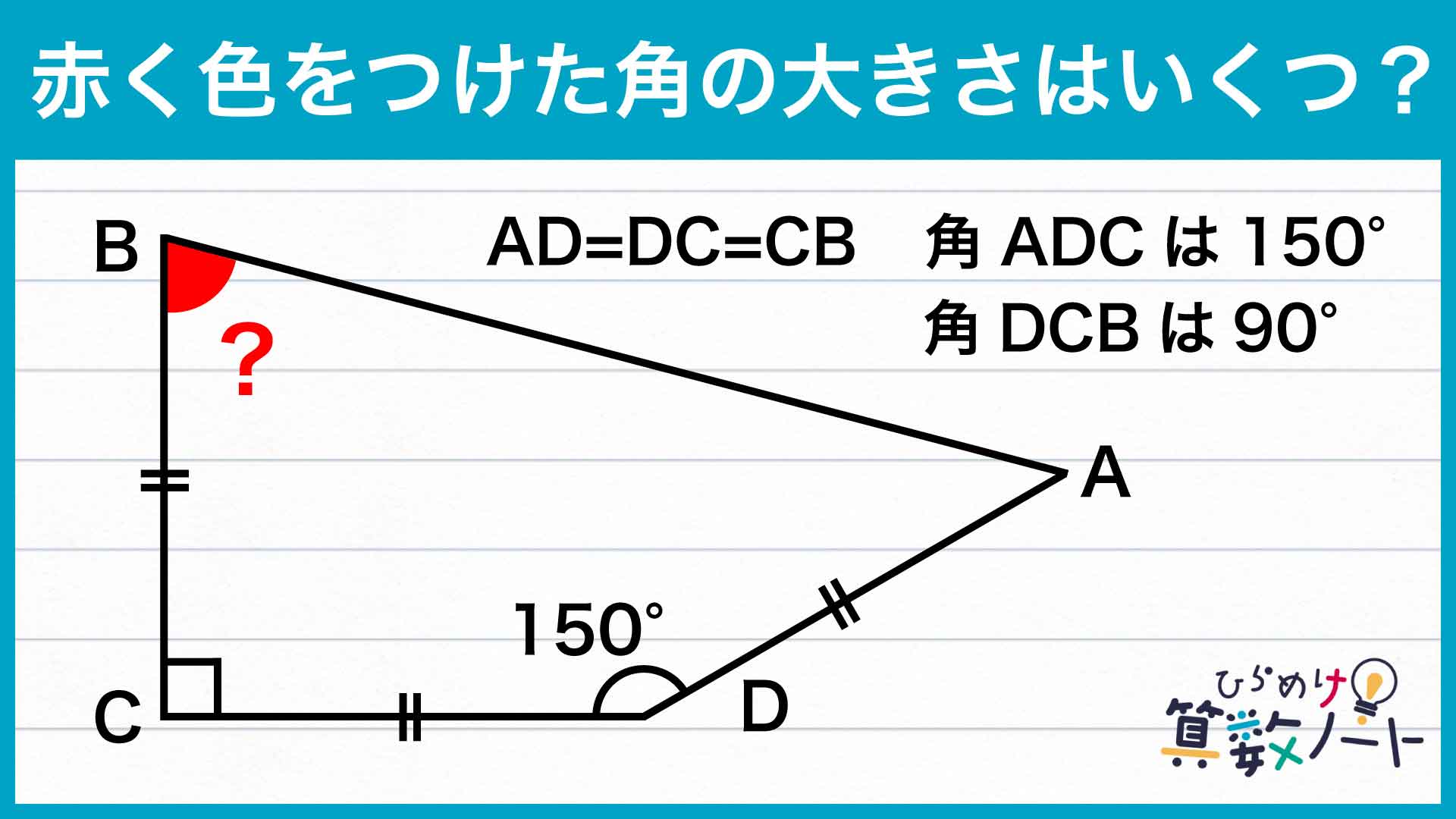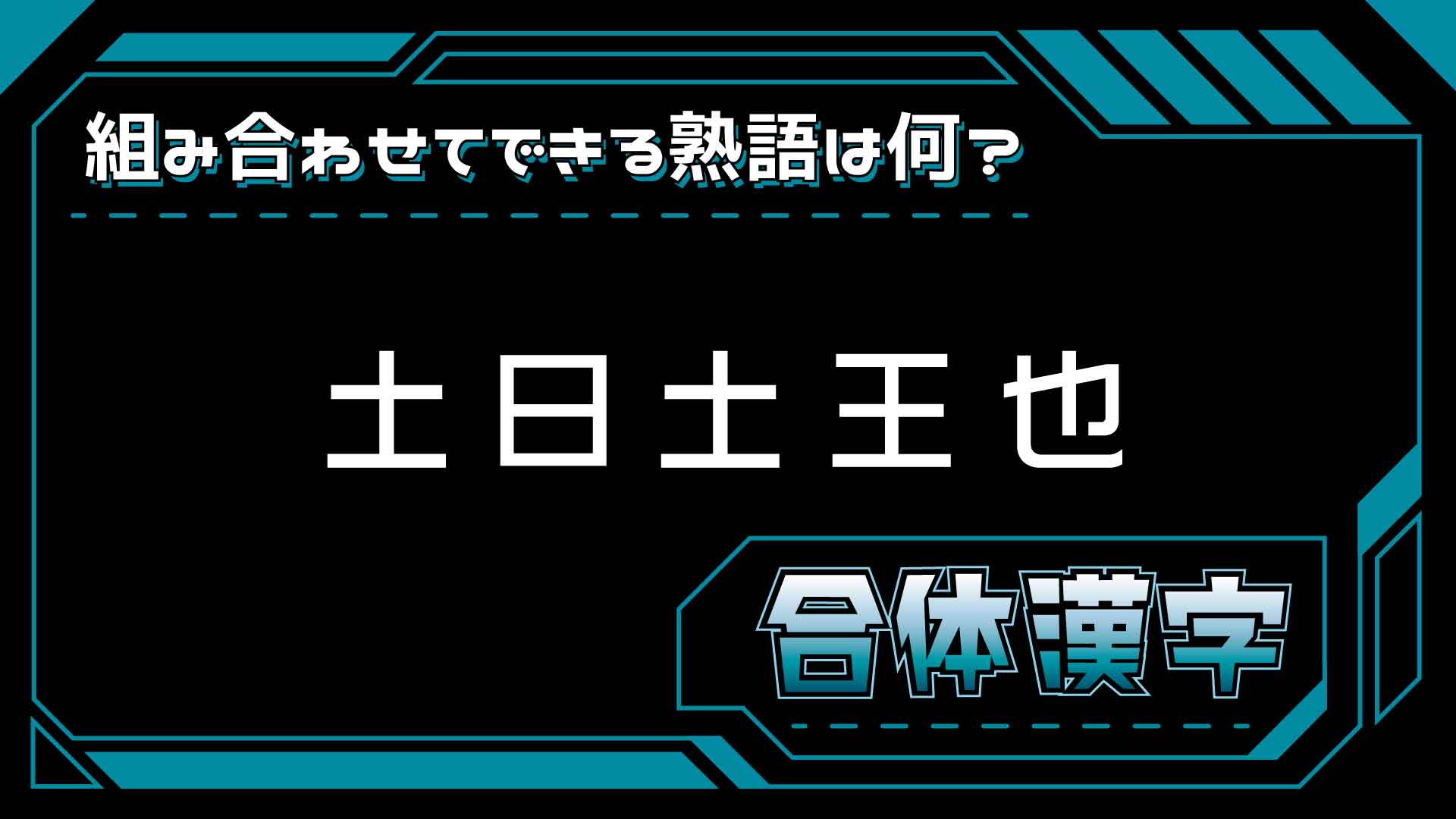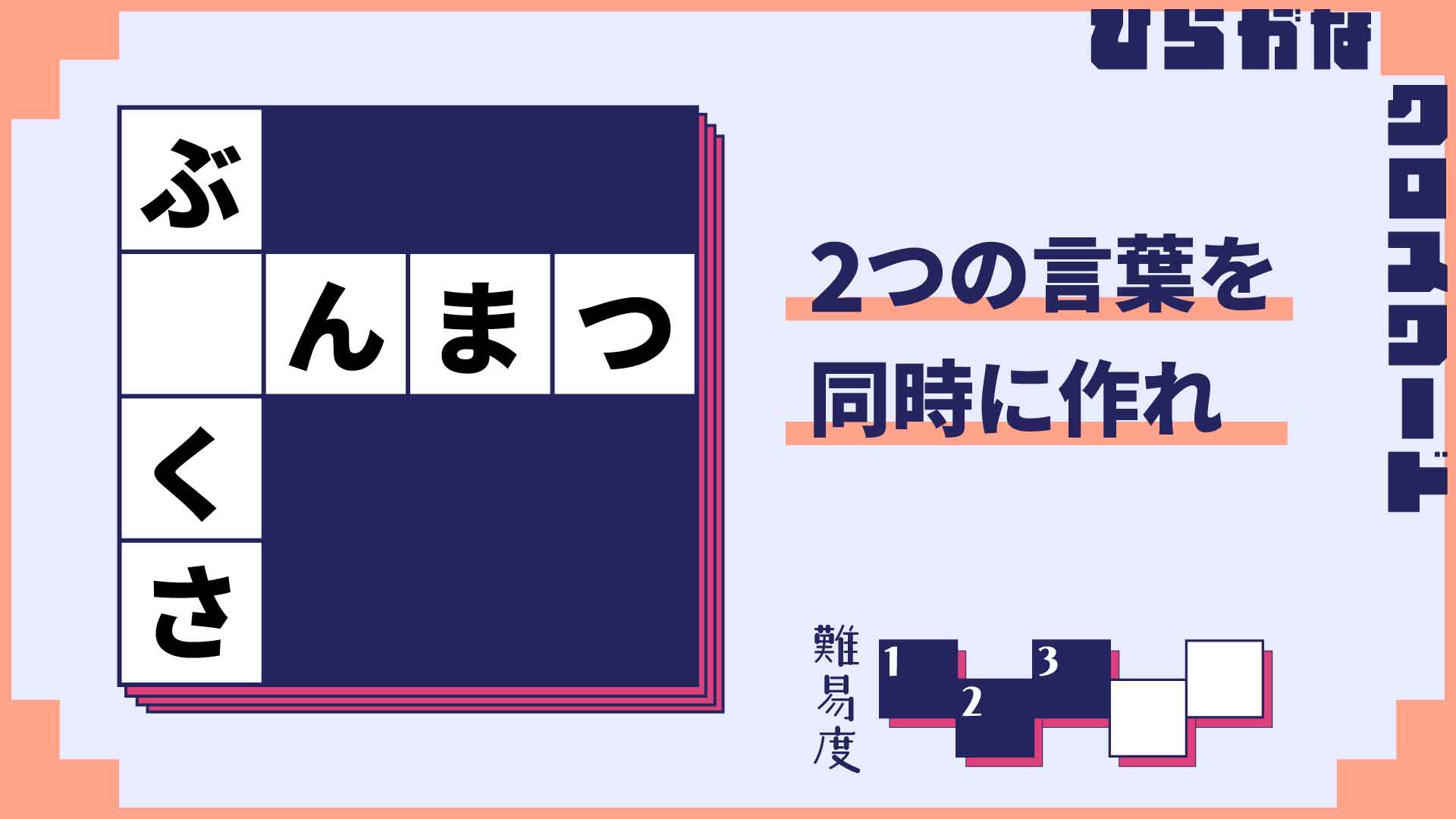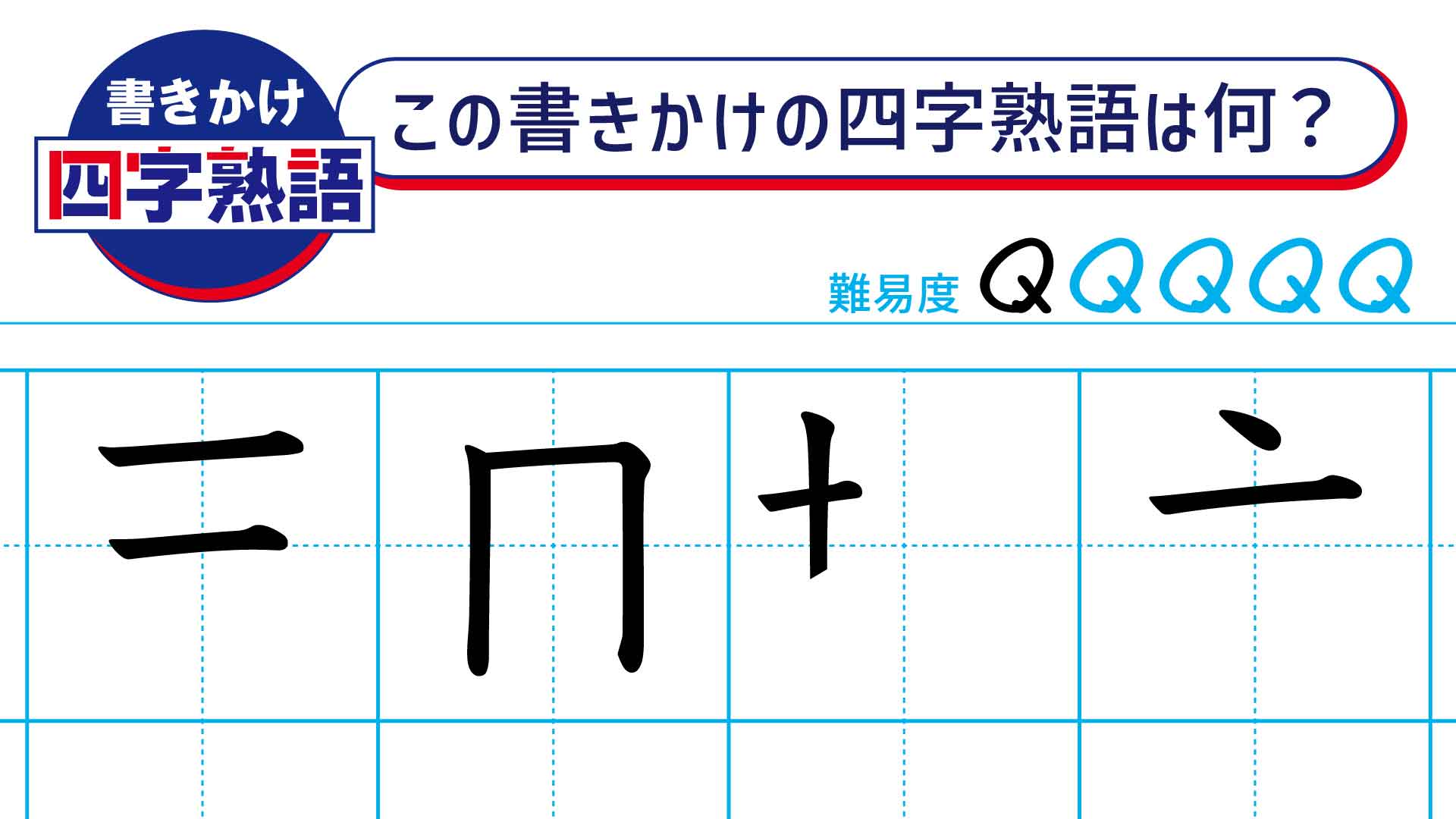フィリピンは「下請け」に甘んじている国
フィリピンはなぜ「のびしろの国」に留まっているのか。大きな要因のひとつは、長年政治が機能不全に陥っている点にあると見ていいだろう。
シンガポールの経済発展を主導した初代首相、リー・クアンユーも以下のように述べている。
豊富な天然資源、英語に堪能な教育水準の高い国民、アジアの中心という立地……フィリピンは国家が望むあらゆるものを備えているが、政治こそがこの国の進歩を遅らせている。(筆者訳)
アメリカにならって民主主義を取り入れたはいいものの、これがなんとも中途半端に終わってしまった。選挙は行われるものの、政治・経済を動かすのは一部の有力な一族、いわゆる財閥に限定されてしまったのだ。ここに「少数の富裕層」対「大多数の庶民」という構造ができ上がり、汚職と経済格差に満ちた社会が築かれる。

問題に拍車をかけたのが、フェルディナンド・マルコス元大統領による長期独裁だ。1965年から20年以上にわたって権力を握り、反体制派の弾圧や大規模な財政難で混乱を招いた。マルコス政権は1986年の革命で打倒されたものの、フィリピンが韓国やシンガポールのような経済発展の波に乗れなかったのは、マルコス時代の停滞によるところが大きい。

結果として、現在のフィリピン経済は次の2つが主要な外貨・雇用の柱となっている。1つは「OFW(Overseas Filipino Worker)」と呼ばれる出稼ぎ労働者からの送金だ。国内に十分な雇用がないので、多くの人々が家族と離れて海外で働き、故郷への仕送りで何とか家族を養っている。
もう1つは、高い英語力を活かしたBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)産業。コールセンター業務などは代表的なもので、欧米の企業に問い合わせの電話をかけると、フィリピンなまりの英語が聞こえてくることも珍しくない。聞こえはよいが、つまるところアメリカなどの「下請け国家」に甘んじているという見方もできる。
フィリピンは「眠りから覚める(かもしれない)国」
苦境にあえぐフィリピンだが、その未来は決して暗いばかりではない。むしろ相当なポテンシャルを秘めた国、というのが筆者の考えだ。
最大の強みは、年齢の中央値が約25歳という圧倒的に若い人口構成である。その多くが英語能力に長け、国際社会で活躍する素地ができている、というのは再三述べた通り。働き口を求めて世界中へ移住したフィリピン人のコミュニティも、他国にはない「人」の資産と言える。

ここからはさらに私見になるが、フィリピンの見栄・外見を重視する文化も発展に一役買うのではないかと考える。とかく外面を気にする国民性ゆえ、仮に外向けのパフォーマンス力と政治の手腕を兼ね備えた強力なリーダーが現れたら、国がひとつにまとまる公算が大きい。まずい政治と、「下請け国家」の現状から脱却する推進力だって生まれる可能性もある。
アジアとラテン、欧米が交差する文化の独自性もやはり魅力的だ。近年韓国のカルチャーが世界を席巻したように、フィリピンもオンリーワンのブランドを世界に発信できる潜在力を持っている。我々があと30ほど年を重ねる頃には、K-POPよろしく数億人がフィリピン文化に熱狂する世界が訪れている……かもしれないのだ。

ぐんぐんと発展していくのか、このまま「ポテンシャルの国」に留まり続けるのか。今度スーパーでフィリピン産のバナナを見かけたら、そのバナナが育った国の行く末にも思いを馳せてみてはだろうか。
【おまけ】
先日、筆者が住むシンガポールの美術館に足を運んだところ、こんな絵が展示されていた。フィリピンのフアン・ルナという画家が描いた《España y Filipinas(スペインとフィリピン)》という作品だそうだ。

画面左=赤い服の女性はスペイン、支えてもらっている青い服の女性はフィリピンの象徴になっていて、「スペインがフィリピンを包み込むように啓蒙した」ことを表しているんだとか。フィリピンの画家、つまり支配された側の人物がこの絵を描いたというのがまた興味深い。画家にとってスペインは憎たらしい支配者ではなく、文化を授けてくれる「庇護者」という意識が大きかったのかもしれない。
【こちらもおすすめ】
【あわせて読みたい】
【画像出典(画像を一部加工しています】
アドボ:Joy D. Ganaden CC-BY-SA-4.0
フィエスタ:Michol Sanchez CC-BY-SA-4.0
マニラ:Mike Gonzalez CC-BY-SA-3.0