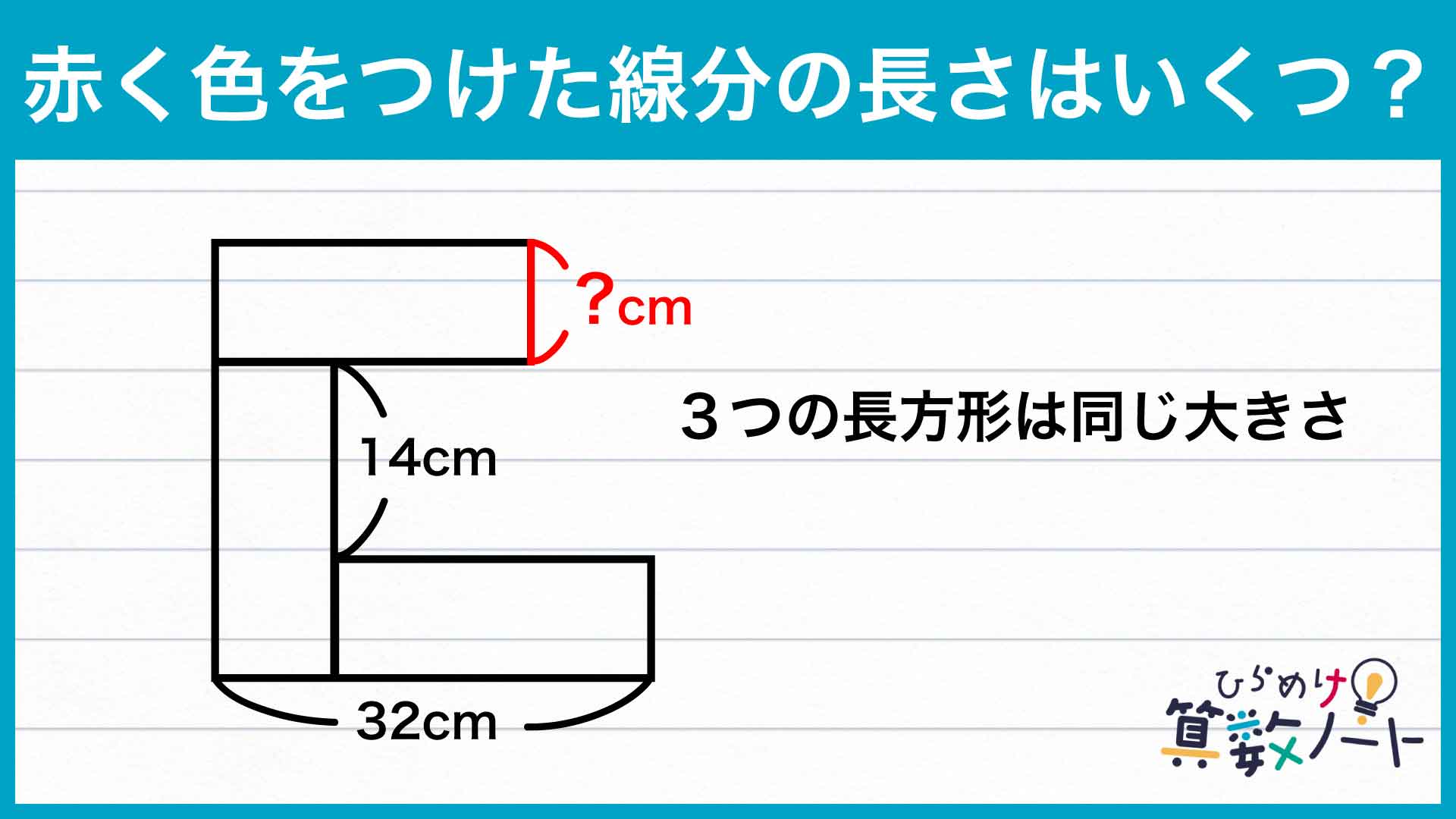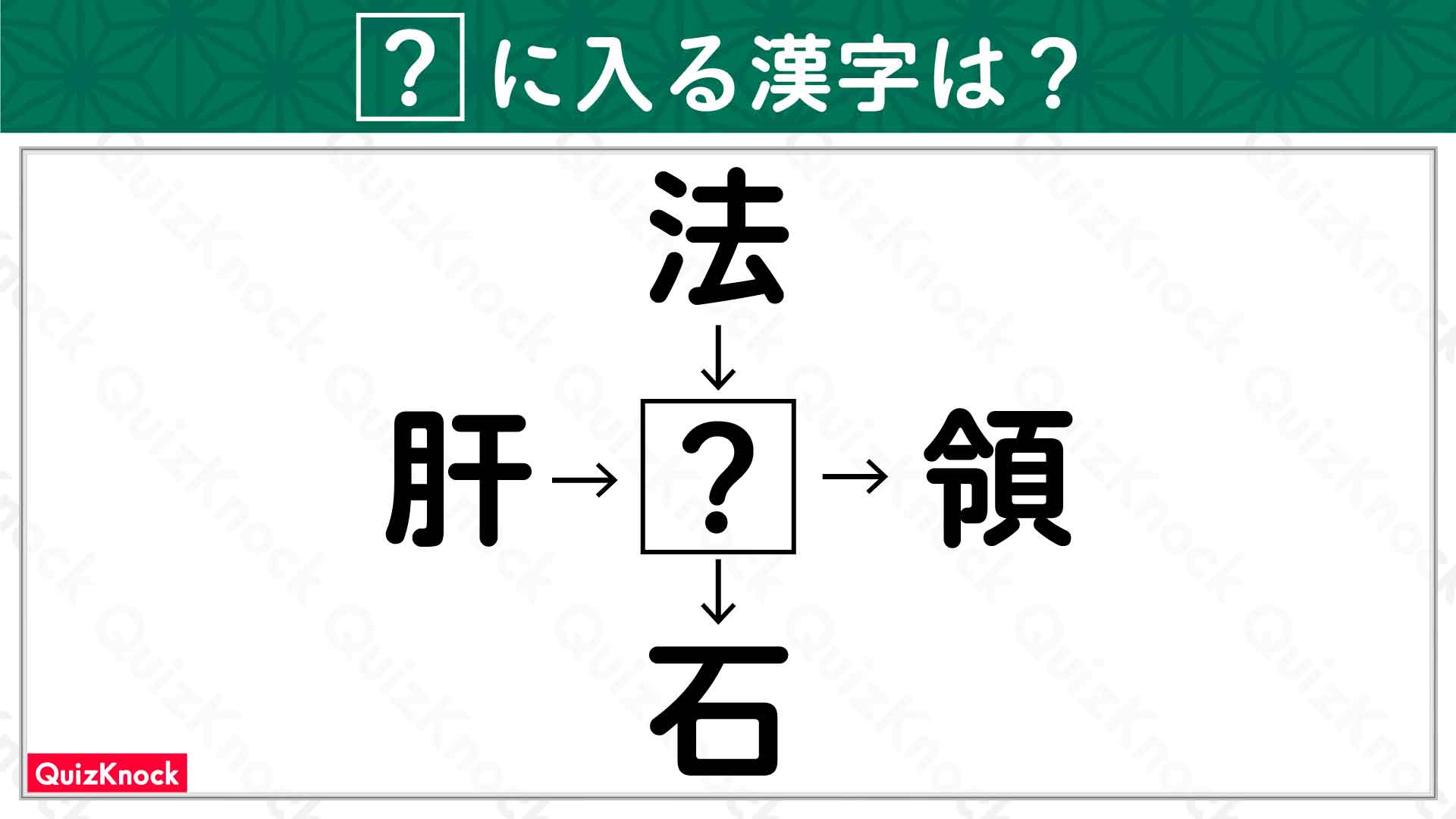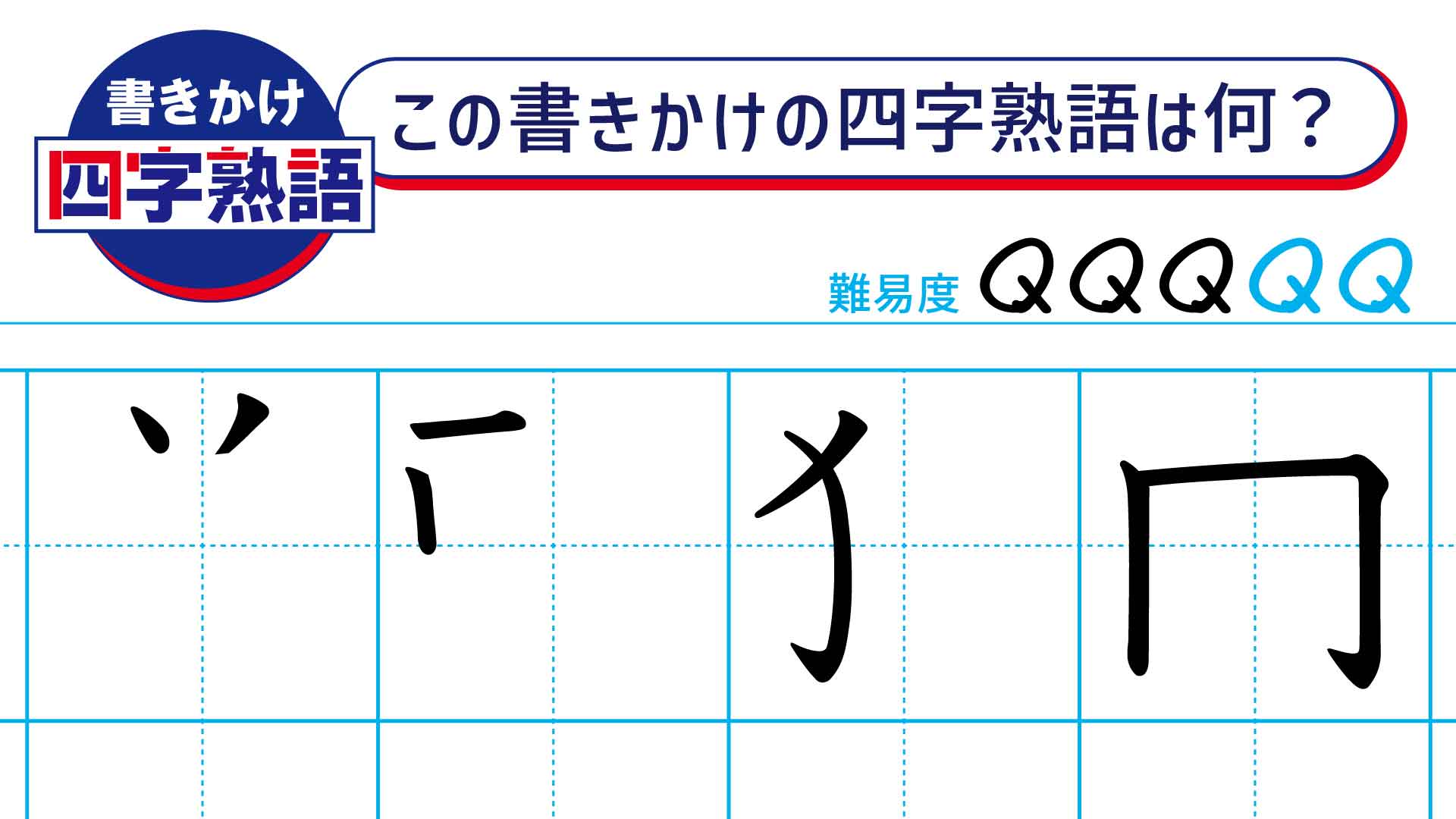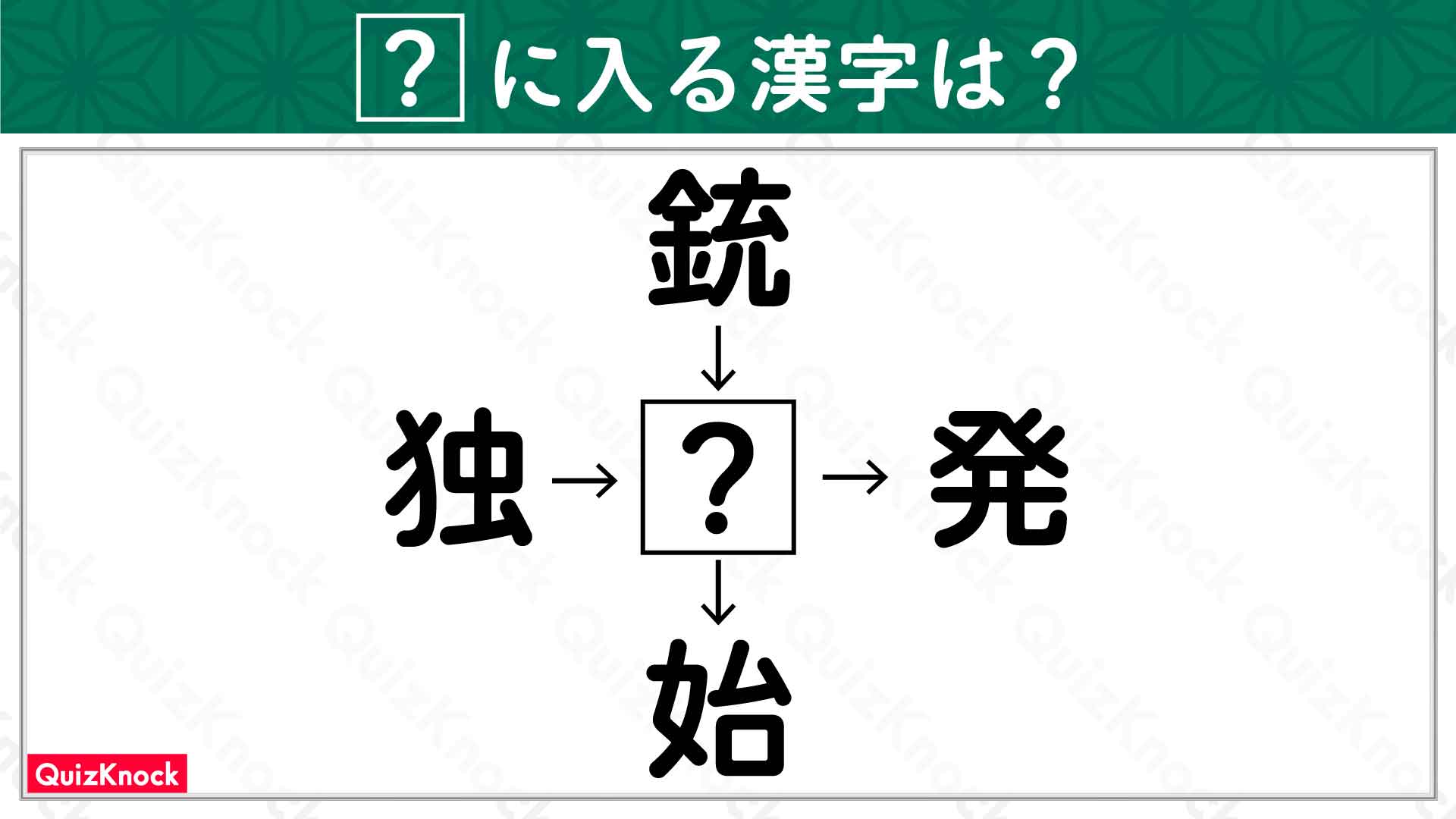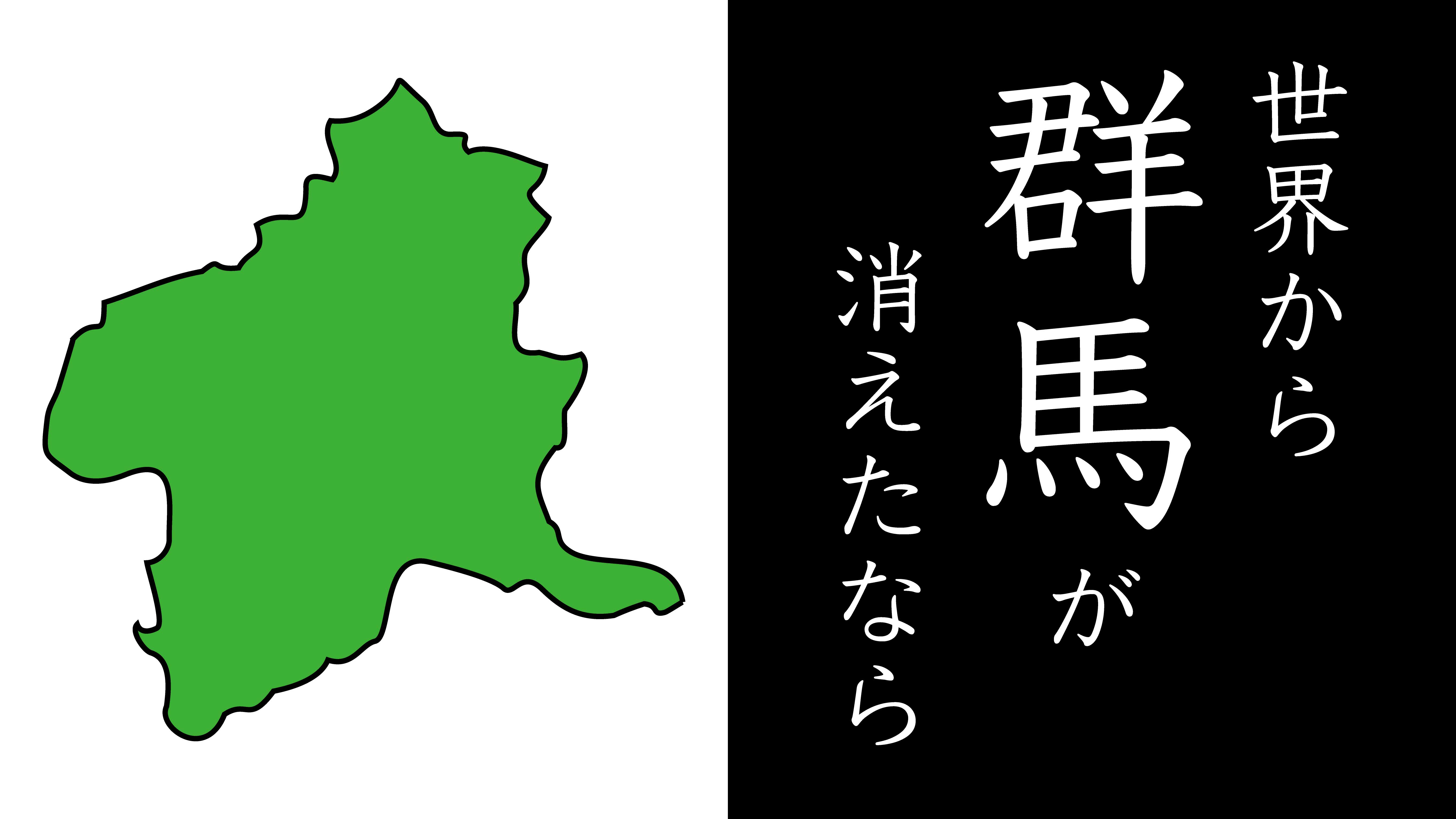河村です。どうも。
僕は「東京大学クイズ研究会」というサークルに所属しています。
 東大クイズ研(TQC)のロゴ。
東大クイズ研(TQC)のロゴ。このサークルではクイズをします(それはそう)。
ここで使うクイズ、決して無から湧き出てくるわけではありません。自力で作る必要があります。
そうして生まれた自作のクイズを持ち寄り、互いに出題しあう、というシステムでサークルは回っています (ちなみに、テレビ番組のクイズは、主にクイズ作家という専門職・プロの方が作っています)。
今回お話するのはこのクイズを作る行為、「作問」についてです。
QuizKnock見てる人なら、クイズ、ひいては作問に興味ありますよね。あってほしいな。頼むあってくれ。
さて。17文字から成る俳句は、ご存知の通りとんでもなく奥が深いです。
クイズの問題文に文字数の縛りはありませんが、例えば80文字としましょうか。この80文字の中での言葉の選び方も、俳句に負けず劣らず、とんでもなく奥が深いのです。
 僕の友人はよく「80文字に宇宙を詰める」と表現する。
僕の友人はよく「80文字に宇宙を詰める」と表現する。クイズの問題文なんて伝わればテキトーでいい、という意見もありますでしょう。
しかしそれは、「米の上に魚が載ってれば寿司になるだろ」と同じくらいの暴論なのです。職人が握る寿司と素人が作る寿司が違うように、プロの綴るクイズと素人の作るクイズの味わいは異なります。
 職人の握る寿司は素晴らしい。
職人の握る寿司は素晴らしい。おそらくまだ実感が沸かないこの事実、つまりクイズ問題文の奥深さを、実例をもって説明したいと思います。作問道の第一歩は、その歩みの先に無限の道が広がっていることを知ることですから。
今回は、弊研究会が著した『東大まるごとクイズ』から、僕が書いたコラムを全文掲載します。
これは単純に宣伝の目的もあるのですが、数日をかけ、丹精込めて書いたこのコラムを超える文章を、今の僕が短時間でサックリとは書けないという部分が大きいのです。
あと単純にすごく頑張って書いた文章なのでもっと広く読んでほしいのですよ。
小難しい理屈をこねた子鬼のような文章なのですが、僕がここで主張したいことは簡単、「僕はこんなに沢山考えてクイズを作ってるんだぞ」ということです。
文章のもともとの趣旨は「ウィキペディアを使って作問しよう!」。それではお読みください。長いけど読んでください。がんばって。
次ページ:僕のフルパワーコラムを読んでほしい。(1/2)。











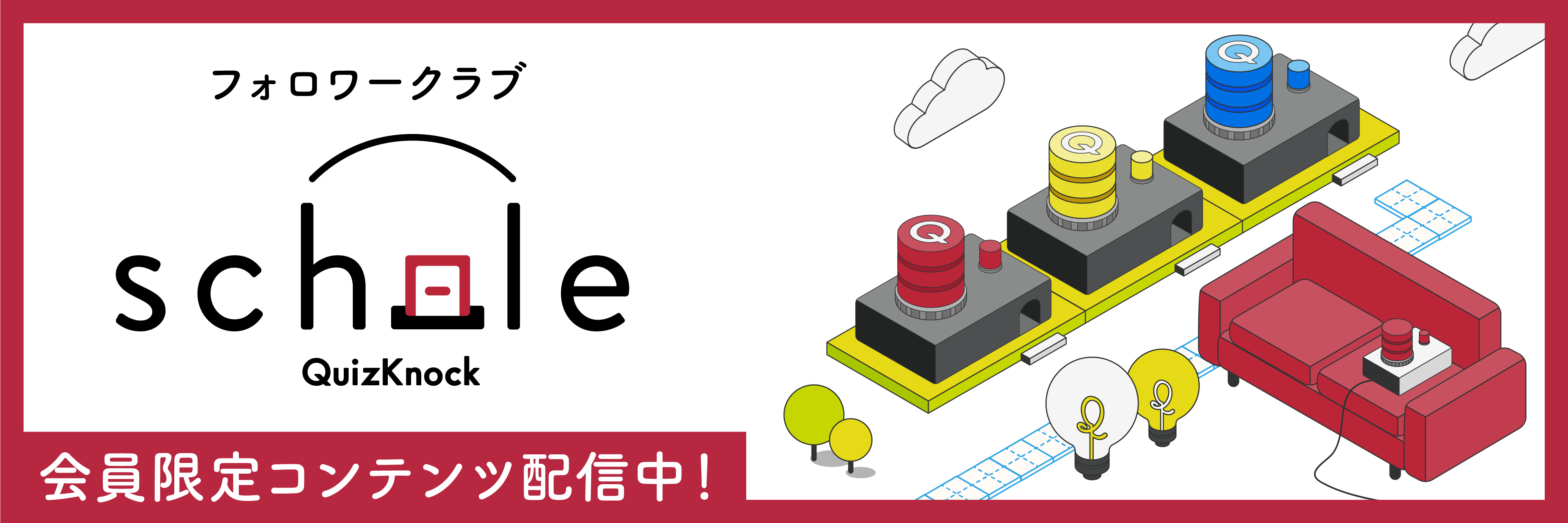


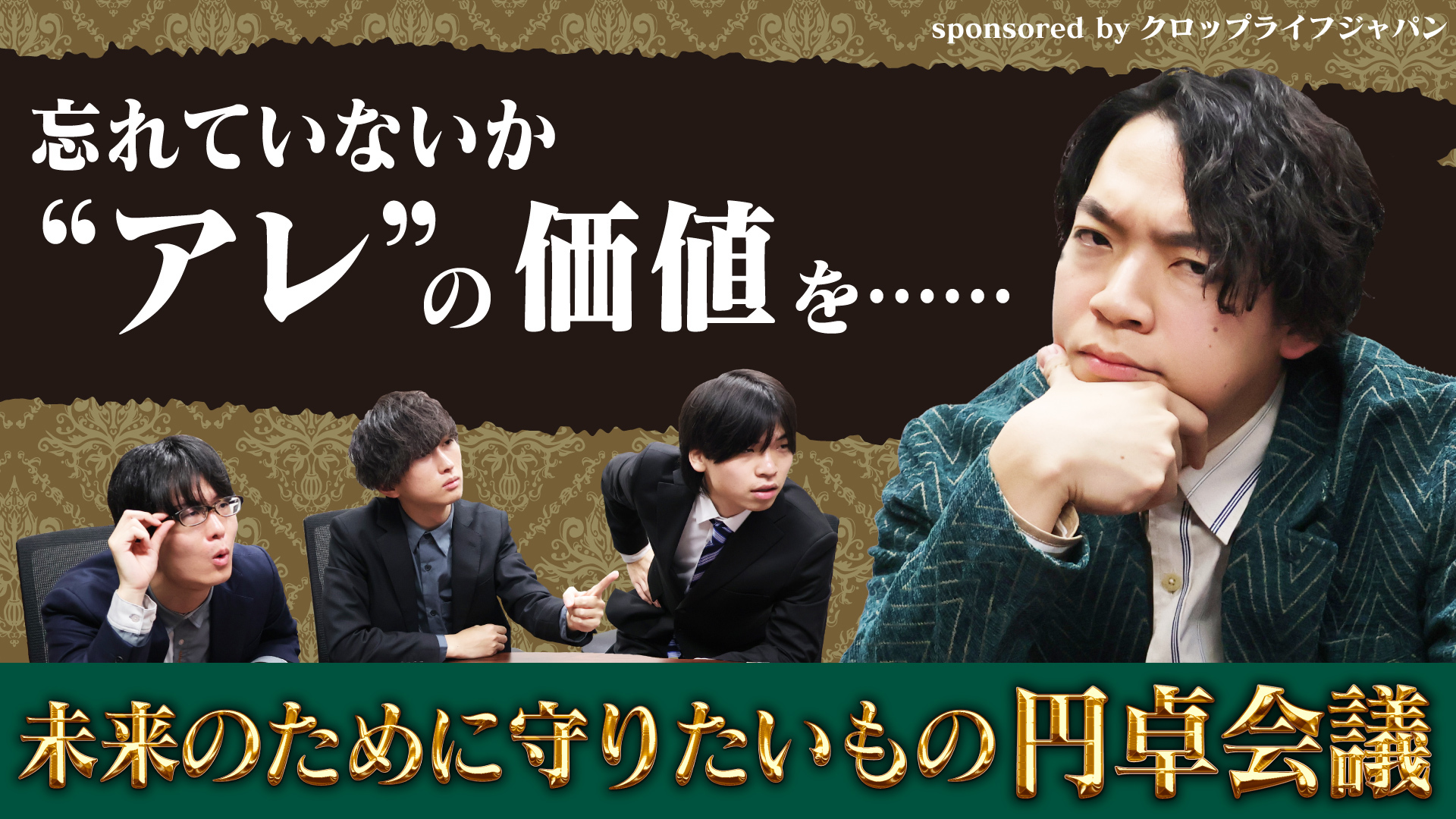
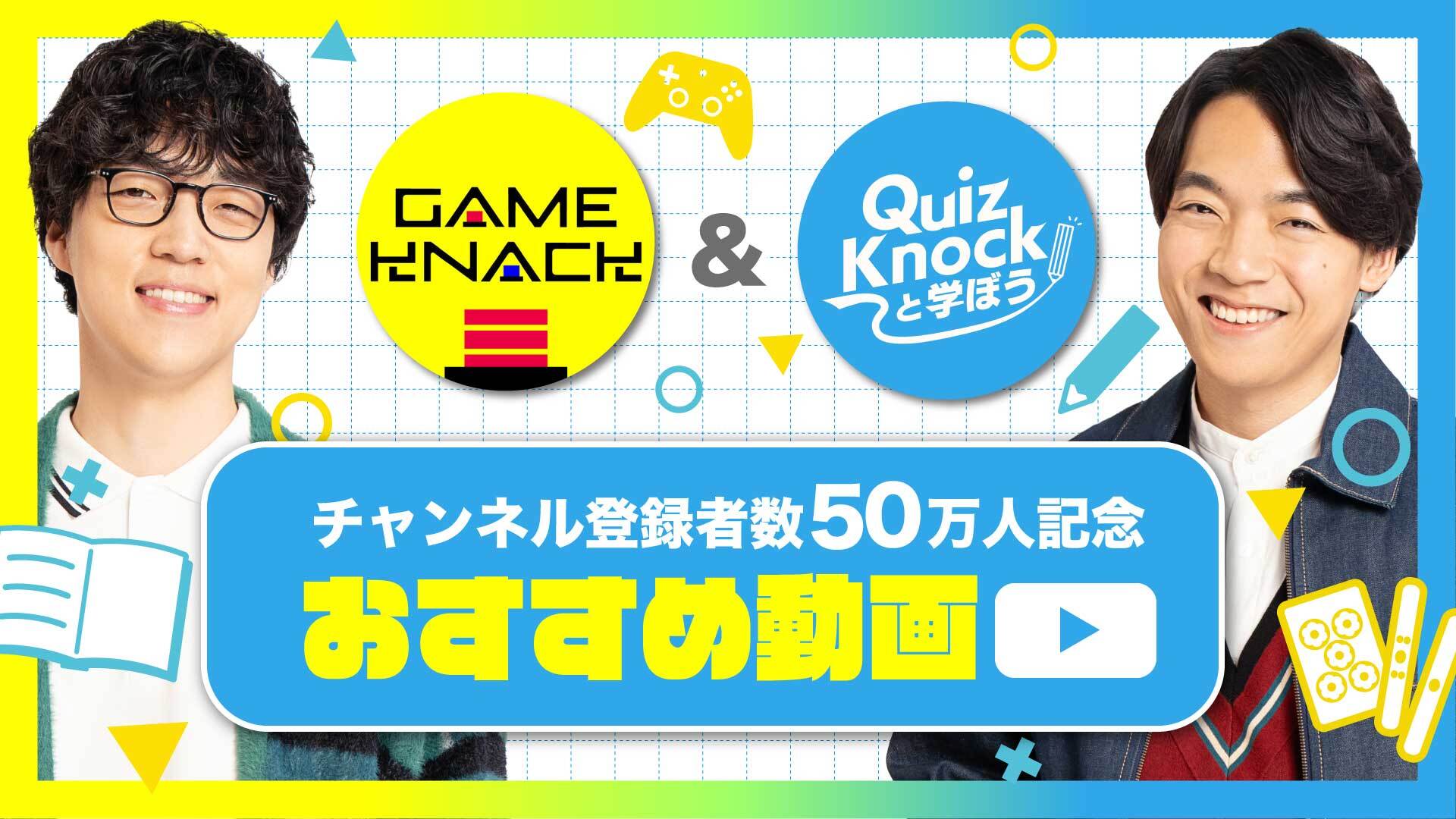
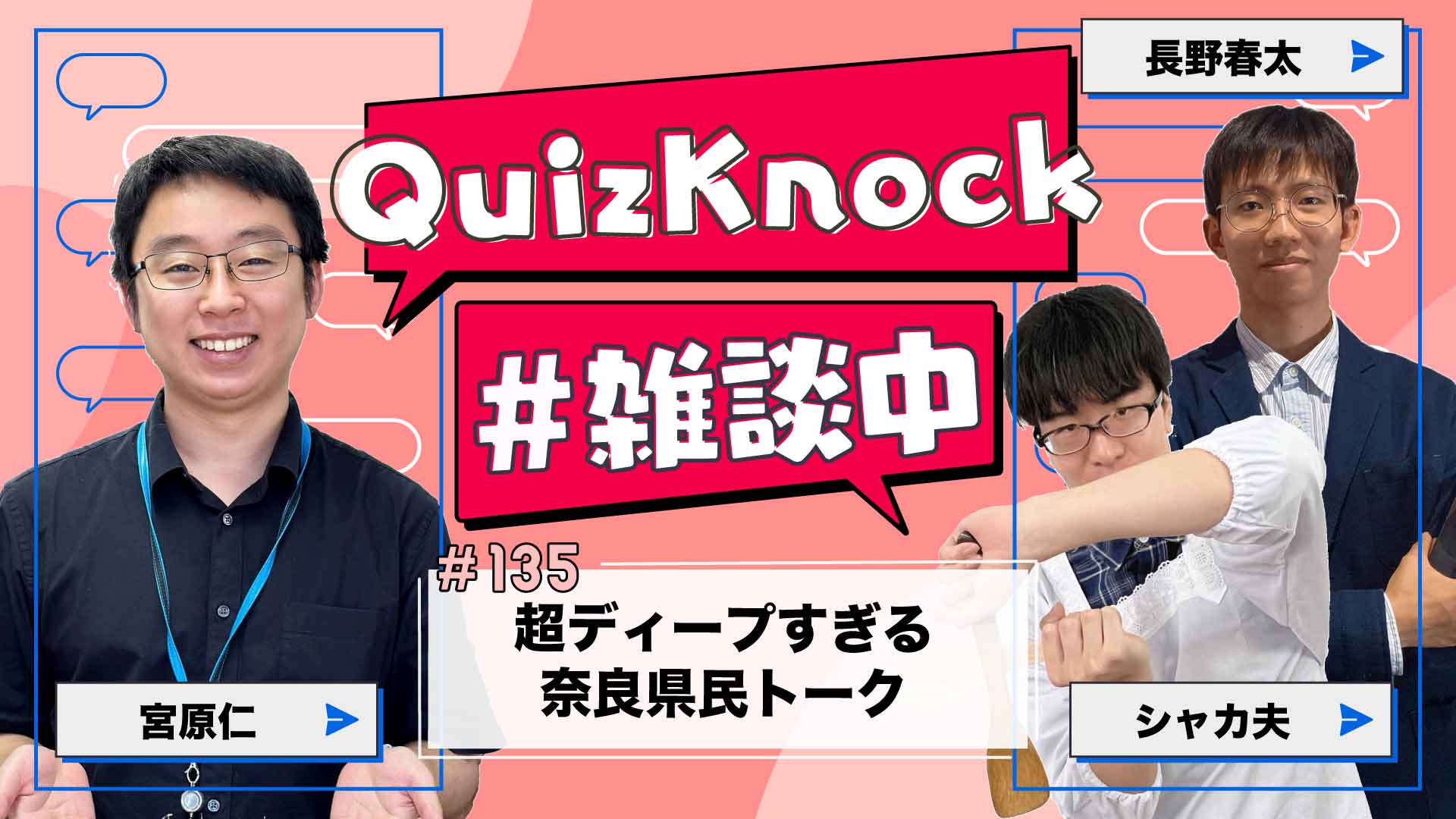

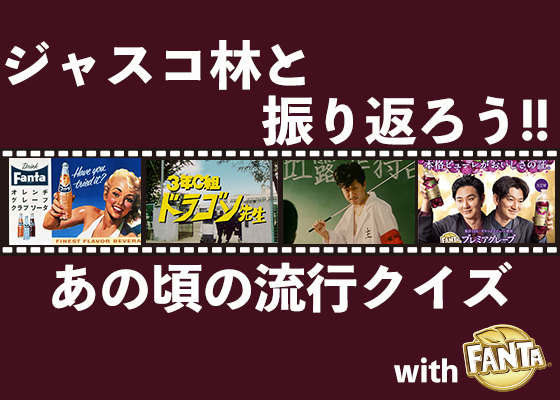


.jpg)