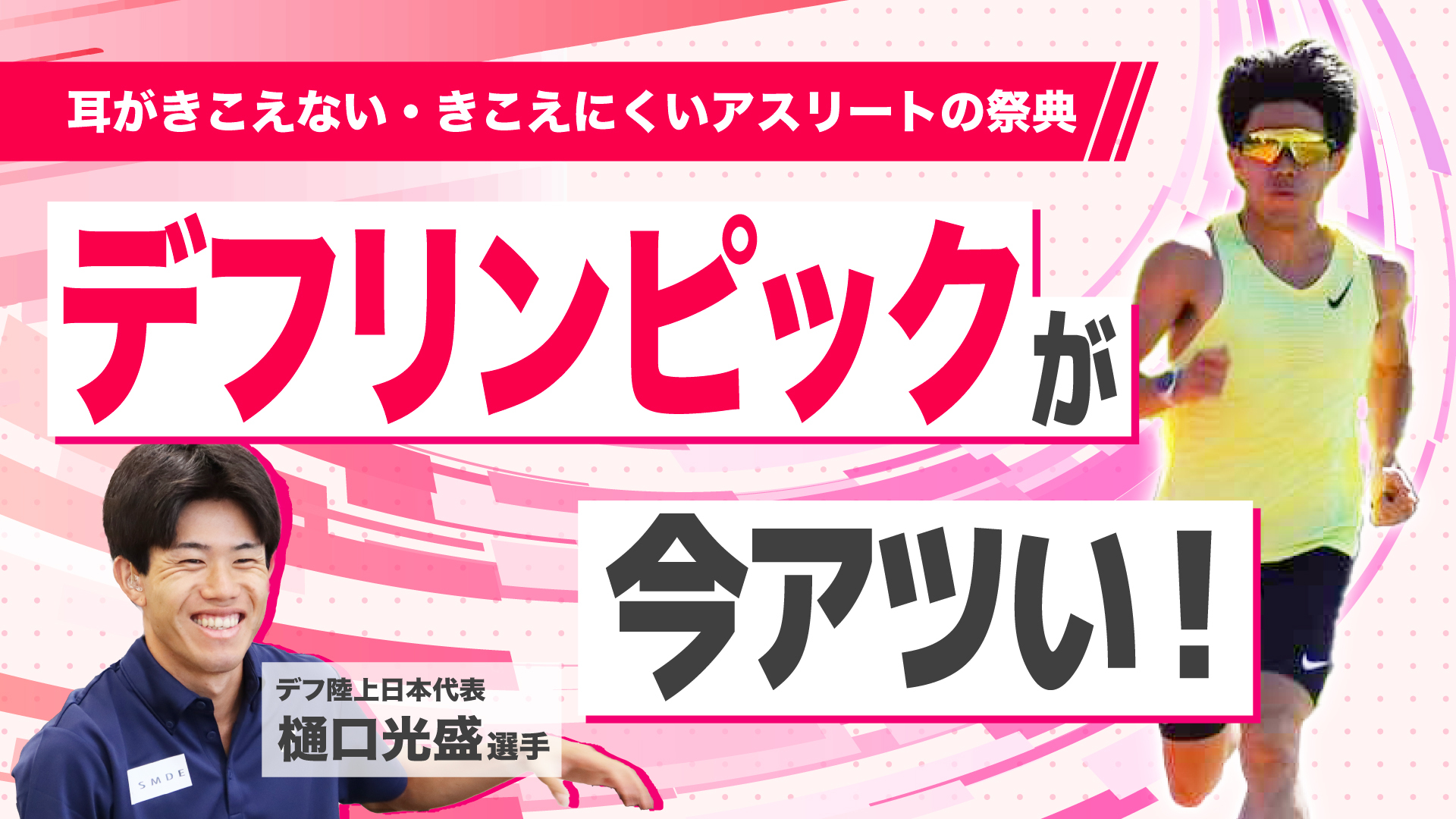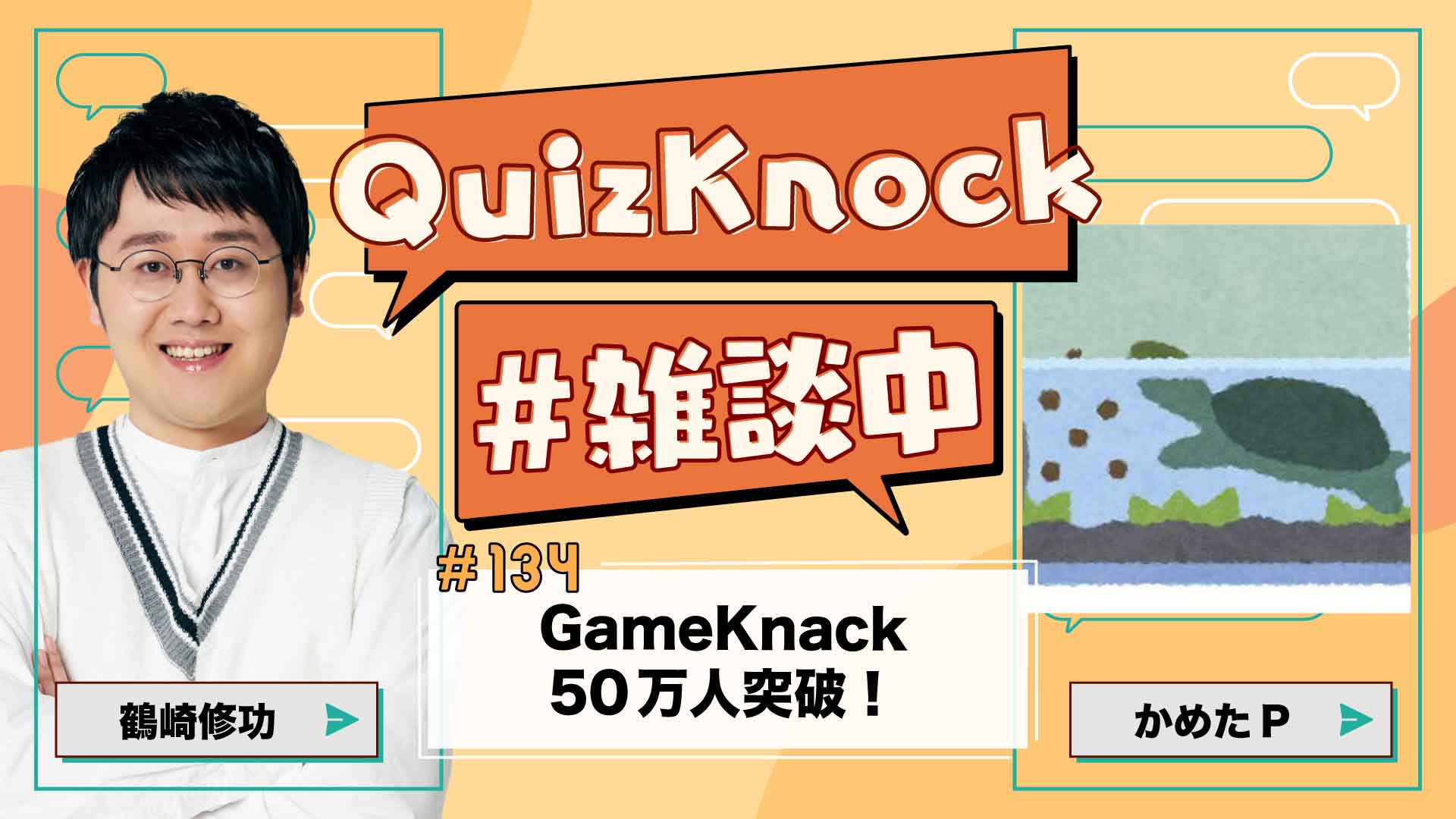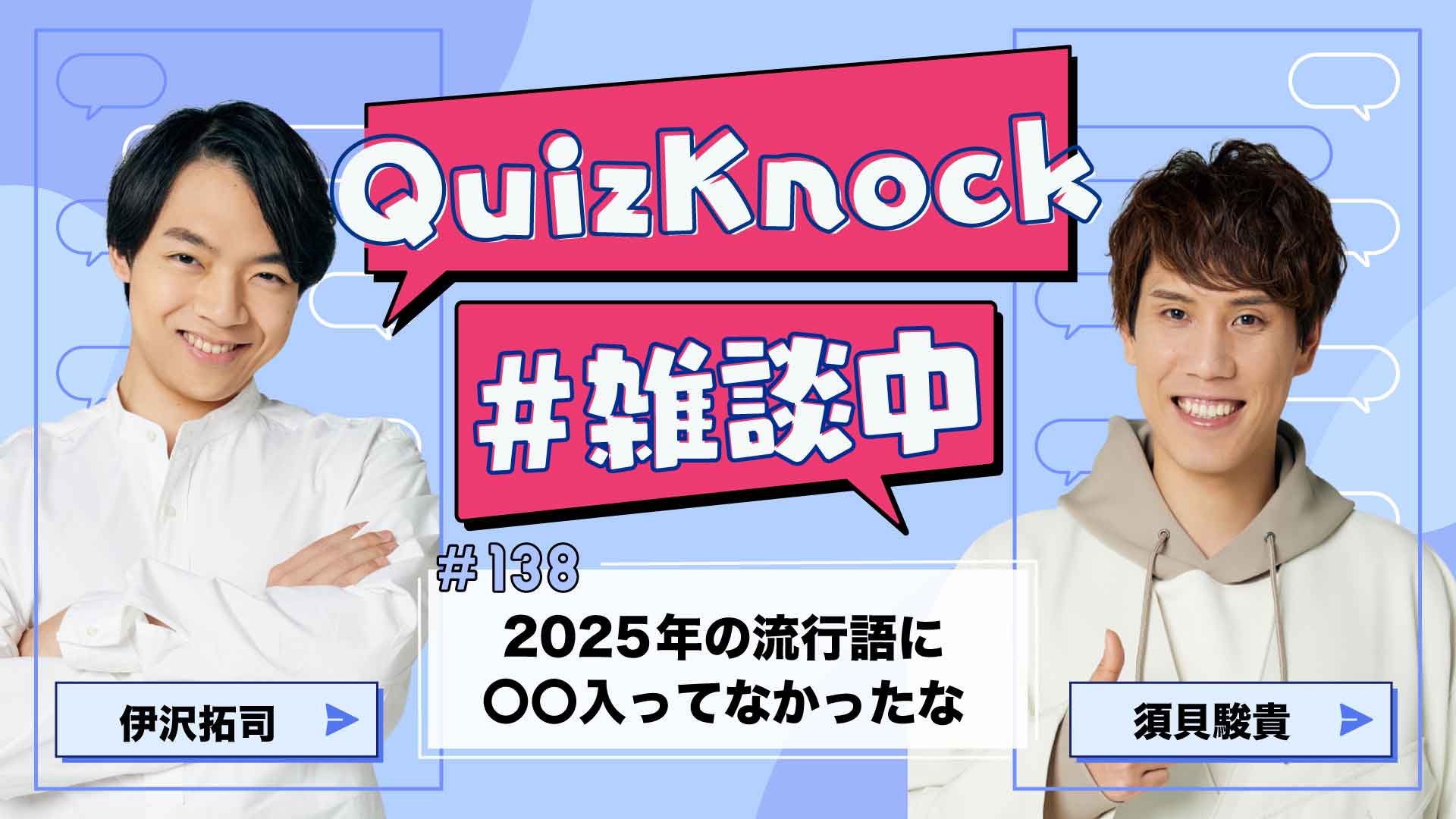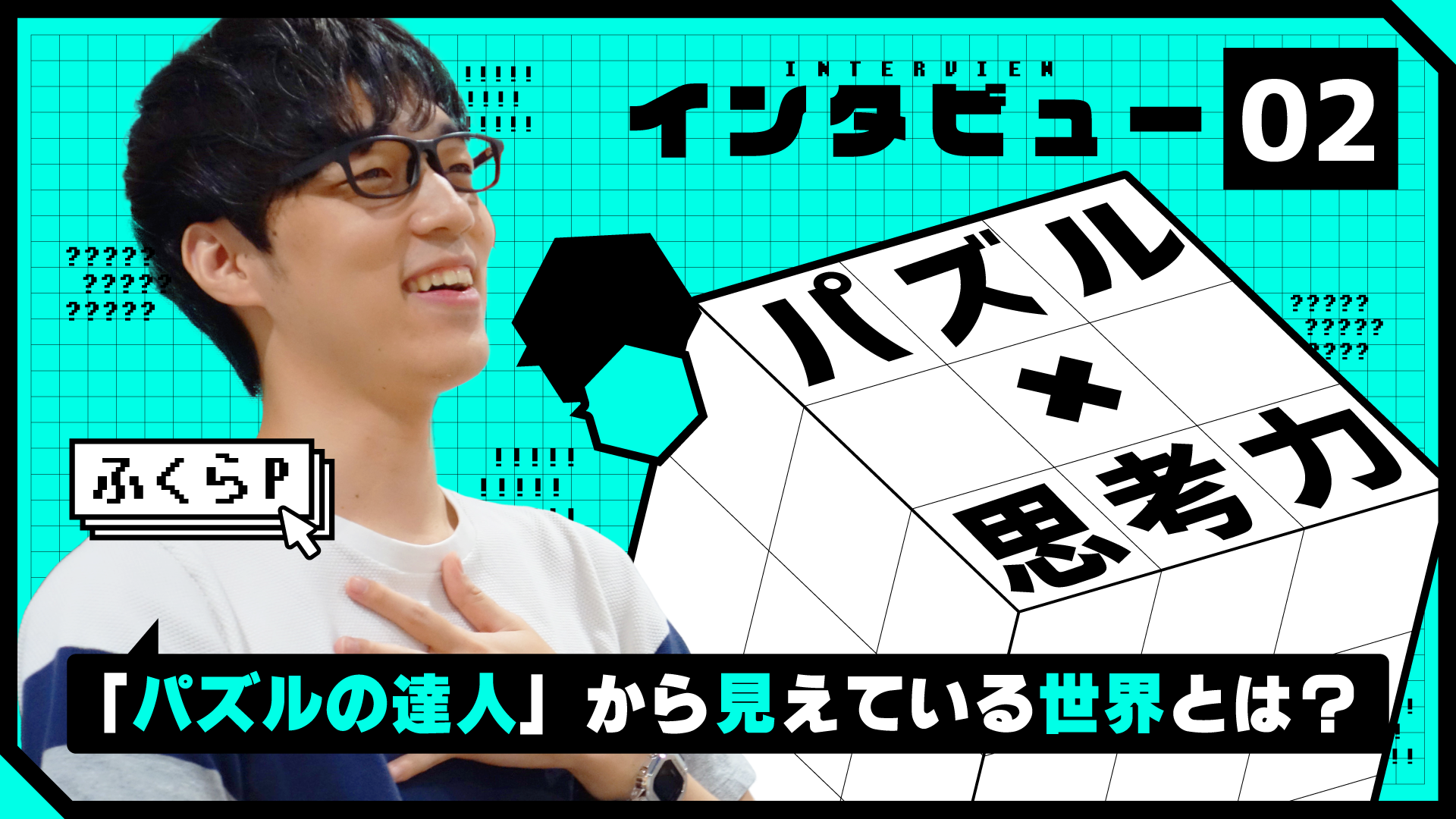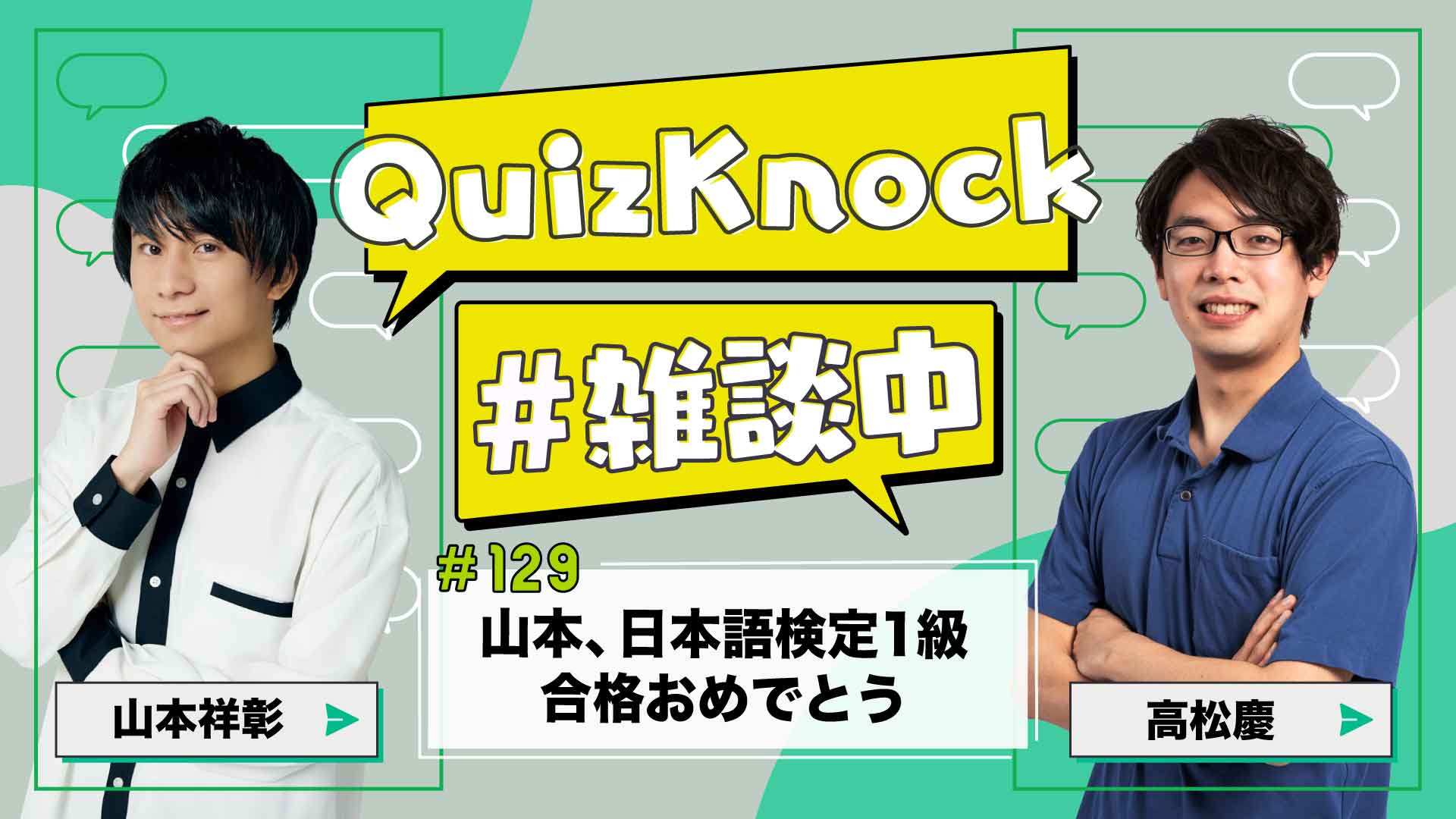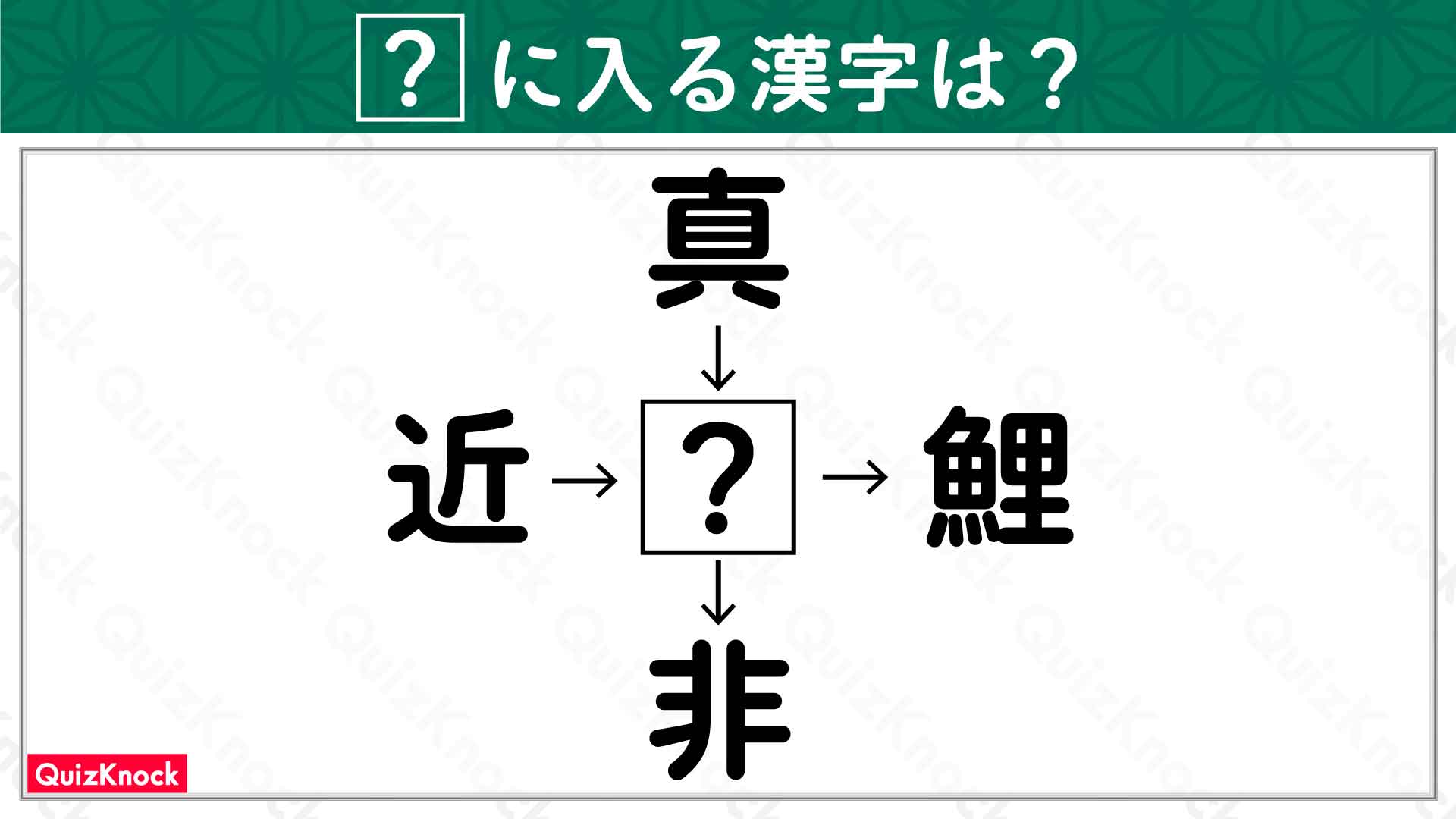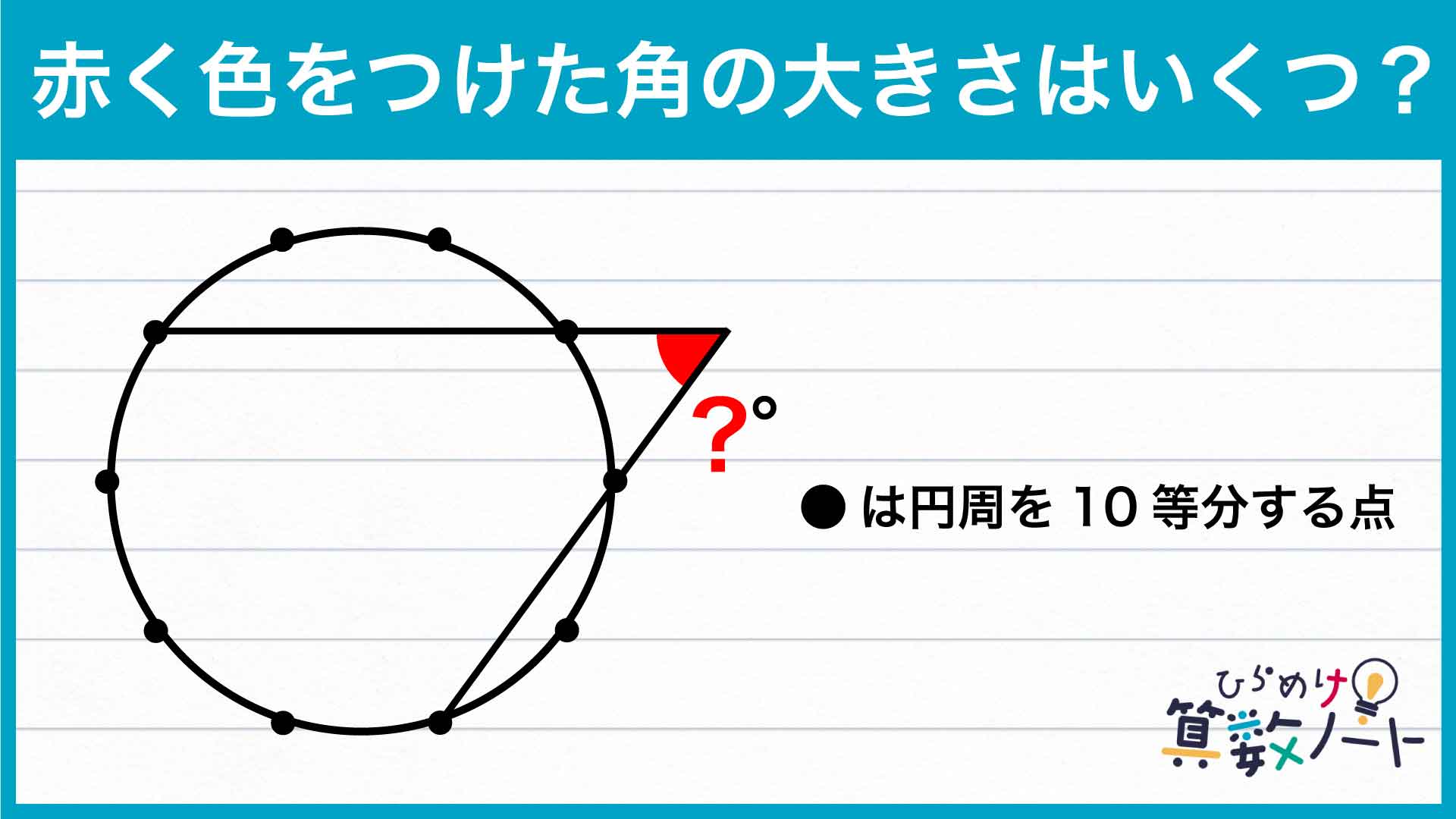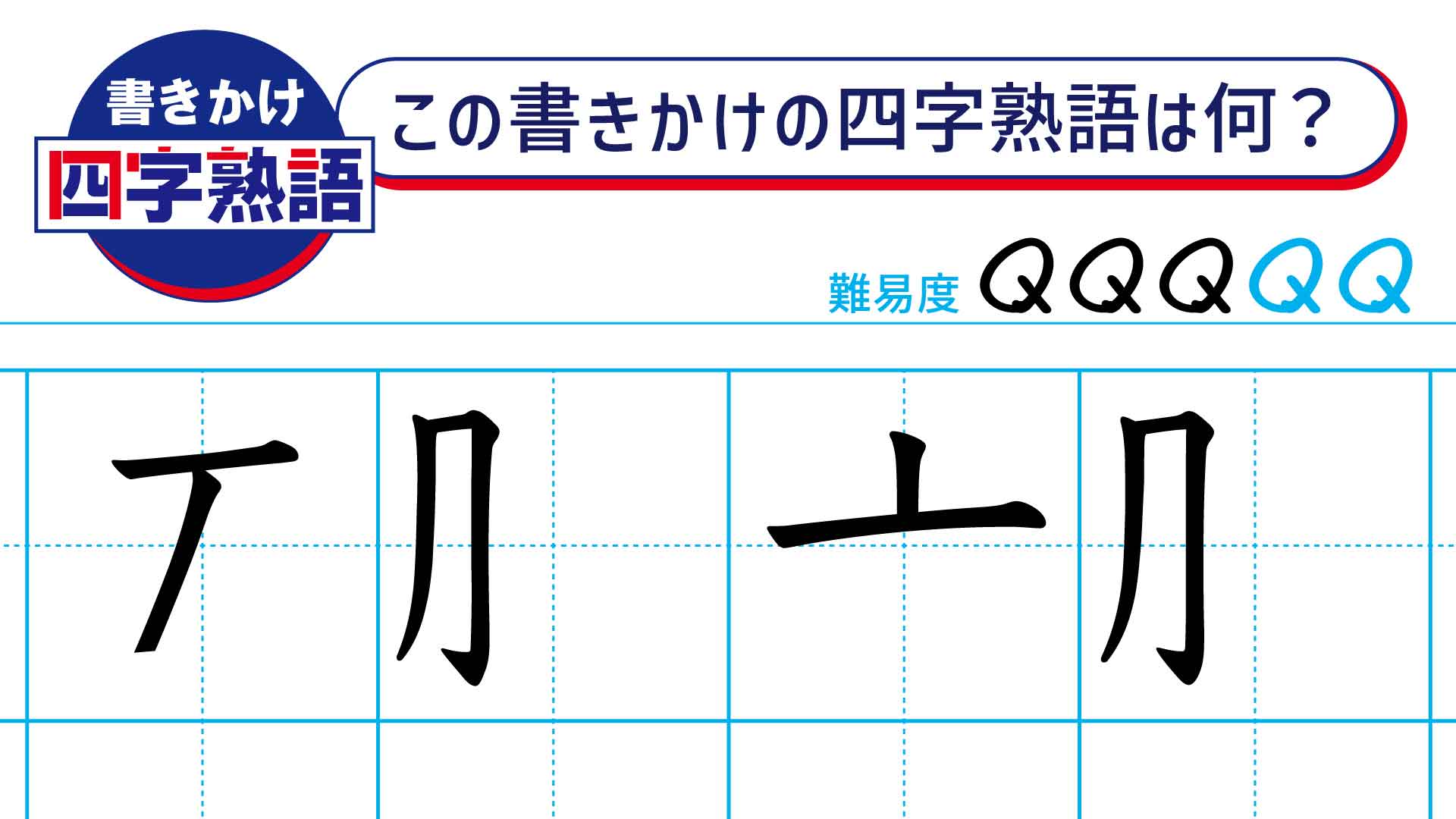肌で感じた現地の空気
昨年から参加されている方々は実際現地に行ったということですが、行く前と行った後で考えが変わったことなどはありましたか?
まず、アフリカに行けたという事自体が凄かったんですけど、一番感じたのは「幸せの尺度の違い」ですね。
ウガンダの難民の人たちは、ウガンダ政府がわらやレンガの家を提供していたりと、他の地域にある難民キャンプと比較すると環境が整っています。ウガンダ政府の難民支援政策はとても良くて、移動の自由があったり仕事ができたり配給があったり。当たり前のように思えても、ほかの難民キャンプではどれも制限されていることです。
知らなかった……。
ただ、難民じゃない人も難民とほぼ同じ水準で生活しているんです。なので、そもそも全体の生活水準が低いと。
そういう貧しい状況なんですが、直接そういった現地の人たちと話してみると、とってもフレンドリーで、いつも楽しそうで。泊まっていたホテルの横の道路も昼夜問わず音楽流しっぱなしだったりとか、とても陽気な部分も見えました。
そういうときに、日本の通勤電車なんかを考えると、ウガンダの人のほうが、より自分の生活を持っているような気もしましたね。幸せの転換というか、こういうのもいいなと。
我々が日本にいてイメージする難民キャンプというものとは、少し違いそうですね。
とはいえ「陽気」の一言でくくってしまうこともできません。例えば、家族と離れて難民となった人は精神的な不安を抱えていますし、そういう個々人のストーリーというのは、日本にいてはわからない深刻さがあります。
もちろん僕たちも4日しかキャンプに滞在できなかったので限界はありましたが、気温40度の空気の中に身を置いて一緒に考えているうちに、本や映像でわかった気になる部分が、より自分ごとになっていくように思えました。
そういえば、みなさんの活動のモットーである「自分ごと」というキーワードについてお聞きしてませんでしたね。
「自分ごと」というのは、現地に行った上で思いついたK-Dのコンセプトで。現地の人と同じ空気を吸って、同じものを見た上で、みんなでたどり着いたコンセプトです。
僕たちはなにより「人」に感動したんですよね。正直、現地に行ったら拒絶されるんじゃないかというイメージが強かったけど、どこにいってもダンスや歌で歓迎してくれて。活動の一環として、CFS(チャイルド・フレンドリー・スペース)という、難民キャンプの中で女性や子供が過ごせるようにした場所があってそこを回っていたんですが、どこへ行っても喜んでくれました。街中にいてもガンガン話しかけられて、握手したりするんです。そういう感動が、「自分ごと」につながっていきましたね。
なるほど、心の壁がなくなったことで自分ごとに転換していったんですね!

発信者としての強みと葛藤
そうした現地体験を経て日本に戻られて。今度は受け手から発信者になるわけですが、「自分が発信者である」ということのメリットやデメリットなどは感じましたか?
活動を通して、高校生であることというのはストロングポイントではありました。やはりメリットとして、同世代に伝えていく上で、年が近い僕たちがアクションしているというのは、大人から教え込まれるより響くのかなと思っています。
あくまで僕たちは難民ではない、当事者ではないというのは壁になります。まだ僕たちが知らないことがたくさんあって、伝えていく上でもっと勉強しなきゃいけないというか。仕方ないこととも言えるけれど、もどかしいし、難民自身ではない僕たちが伝える、ということに責任を感じてやらないといけないと思っています。
伝える主体が「現地にも行っている自分である」ということは、自分が思ったことを伝えやすい点でメリットだと考えています。
ただやっぱり、5人で渡航したら5人が全く違うことを考えているんですよね。それをいざ取りまとめる段になって、K-Dとしてどれを伝え、どれを削るかというところで、折り合いをつけるのは難しかったです。
今まではニュースとかを見ていて「事実の半分しか伝えていないんだろ……」と思っていたんですが、自分が発信側にまわってはじめて、伝えることの難しさを感じました。
あとは、講演会などをやっていく上で、細々とした準備が多いというのはつらいポイントですね。
僕はその点、そういうマネージメントとかは楽しいと思えるタイプなので、そこもやっていきたいですね。
デメリットなんかも挙げていただいた中でいじわるなことを聞くようですが、難民支援や情報発信自体は、分野としては過去にも存在していたものだと思います。「自分たちのオリジナリティはここだ!」という部分はありますか?
やはりNGOに比べると規模などで劣る部分はあると思います。ただ、現地に行って実際の現場を見てきたという部分は僕たちの強みです。学生団体としても熱量には自信がありますね。それこそ毎朝授業前に食堂に集まって準備して、放課後もスポンサー回りを繰り返してきましたから。僕たちの世代で全員のモチベ―ションが高い、というのはチームとして強いと思っています。

なかなかそれは実現しづらいことですね。最初からみんなやる気満々?
最初からというよりは、K-Dの活動を通してやるべきことが多すぎたので、それをひとつひとつやり遂げる中で、どんどんと全員の熱量が高まっていったという感じです。
その点で言うと、高2世代はまだ現地に行ってない、というのがあって。立場としてはK-Dを動かす側なのに、現場を見ていないのでそこはニューカマーと変わらない。悩みどころですけど、今は増えたメンバー一人ひとりと話すことを大切にしていく方向でやりたいなと思っています。
となると、今後はチームをどんな方向に持っていきたいですか?
各メンバーには能動性を求めていきたいですね。今のところ、能動性については維持できていると思います。開成以外のメンバーで集まる機会もできていますし、外からの刺激を開成に、開成からの刺激を外に、みたいなことを目指しています。
チームの雰囲気は、高1の僕から見ても意欲的ですね。先輩がやってきたところを超えられるように、というモチベーションがあります。あとは継続ですね。
チームとしてのオリジナリティについても、しっかりと考えているんですね。具体的な手法としては、どのような伝え方を選んで差を出そうと思っていますか?
僕たちの手法のひとつとして、現地の映像を伝えるVR体験は、リアルを伝える上で大事にしています。ただ現地の体験を伝える、というのではなく、実際の空気感を伝える上でもっと工夫をしたくて。「自分ごと」に感じてもらうということですね。
どうしても映像とかは切り取り方というか、「伝えたいように伝えてしまう」ところがあると思います。なので、僕たちはフィルターを取り外して、なるべくそのままを体感してほしいと考えてコンテンツを作っています。VRはまさに360度、自分の意のままに感じられるリアルですね。
VR以外に、ドキュメンタリー作成もしています。BGMもかけず、インタビューを淡々と流すだけにして。これも、操作せず、リアルのままを流したいというコンセプトです。押し付けず、新鮮なまま、体験だけをお届けしたいですね。
もちろん、こういう取り組みを講演会などでやっていくんですが、伝えきれなかったなと思うところもあって。どうしても、一方通行になってる部分はあるなと思います。なので今後は、より工夫をして、なるべく双方向型のイベントを目指したいです。講演の後のワークショップとかも、もう少し渡航の内容と絡められたはずで。

良い点と反省点、両方共すぐ出てきますね。巧みな分析がそもそも凄いです。












.jpg)

.jpg)