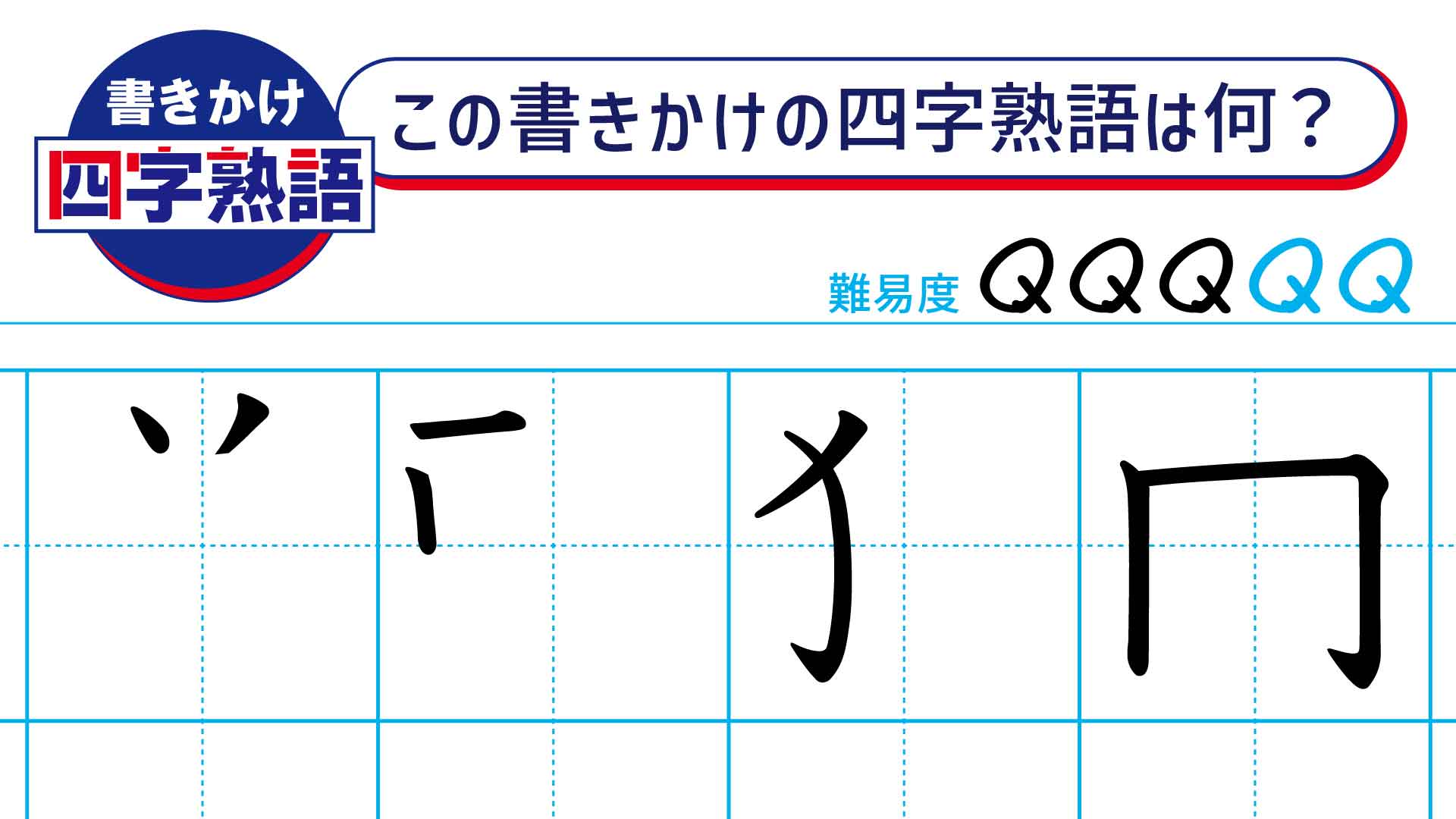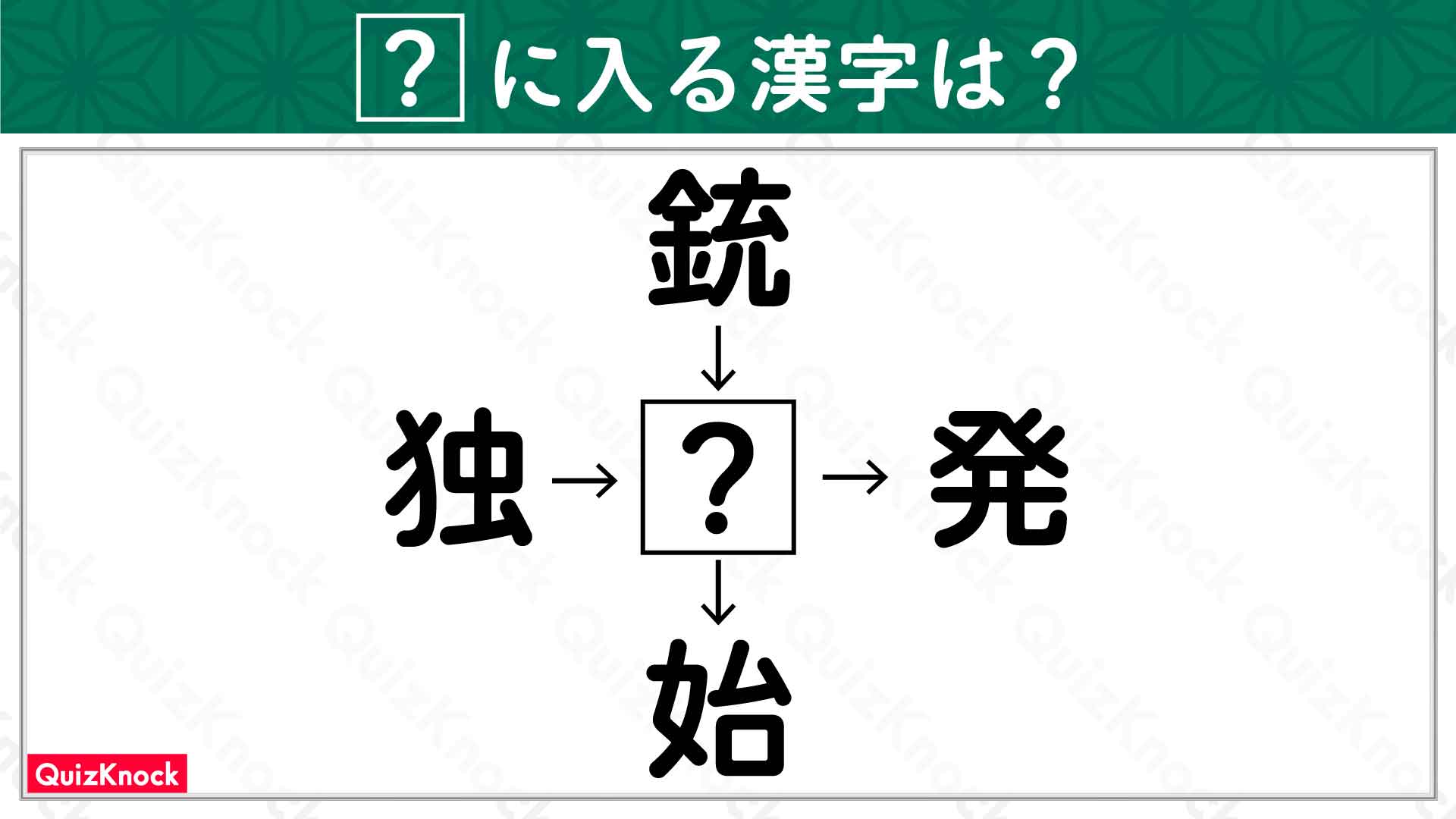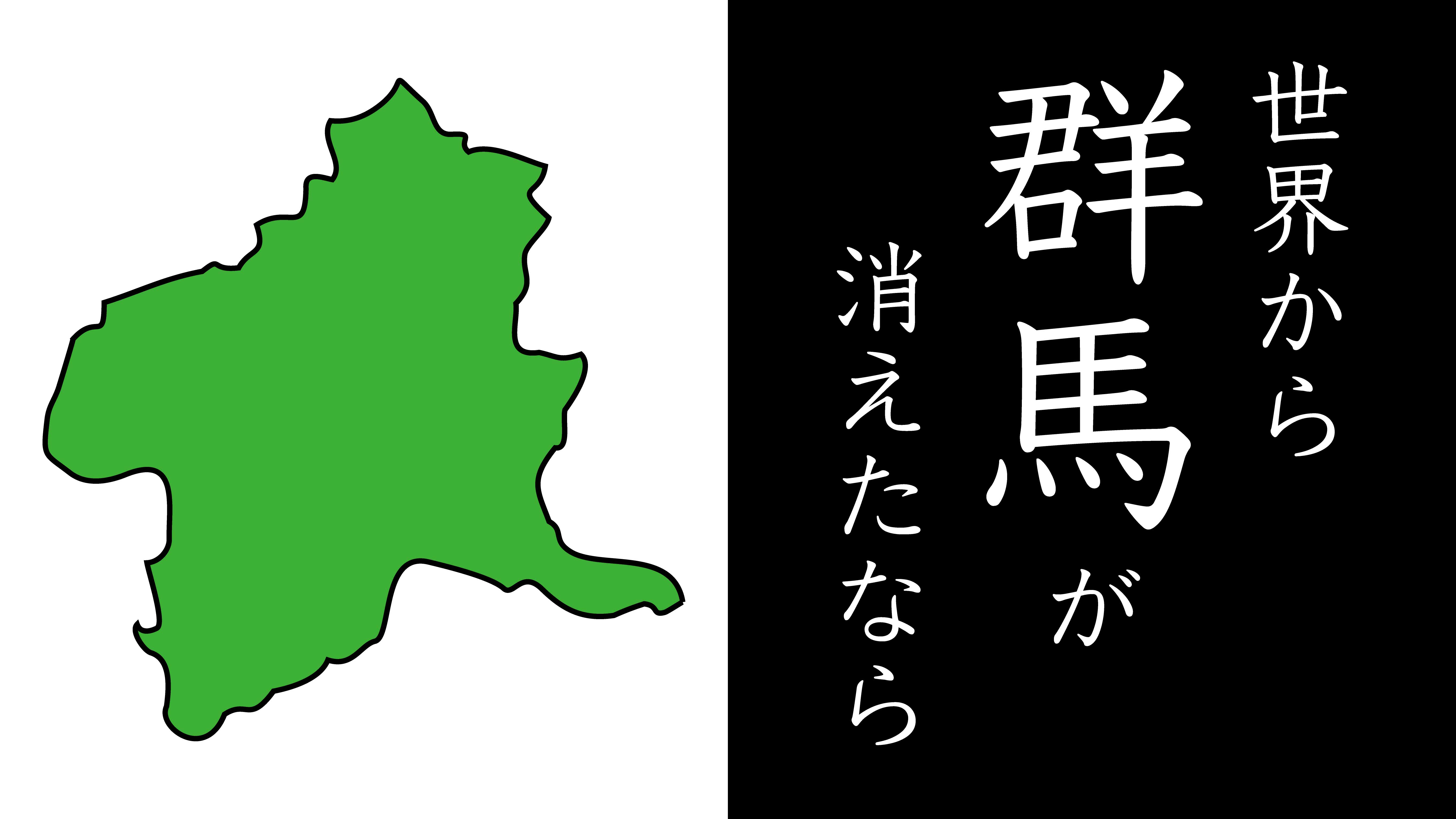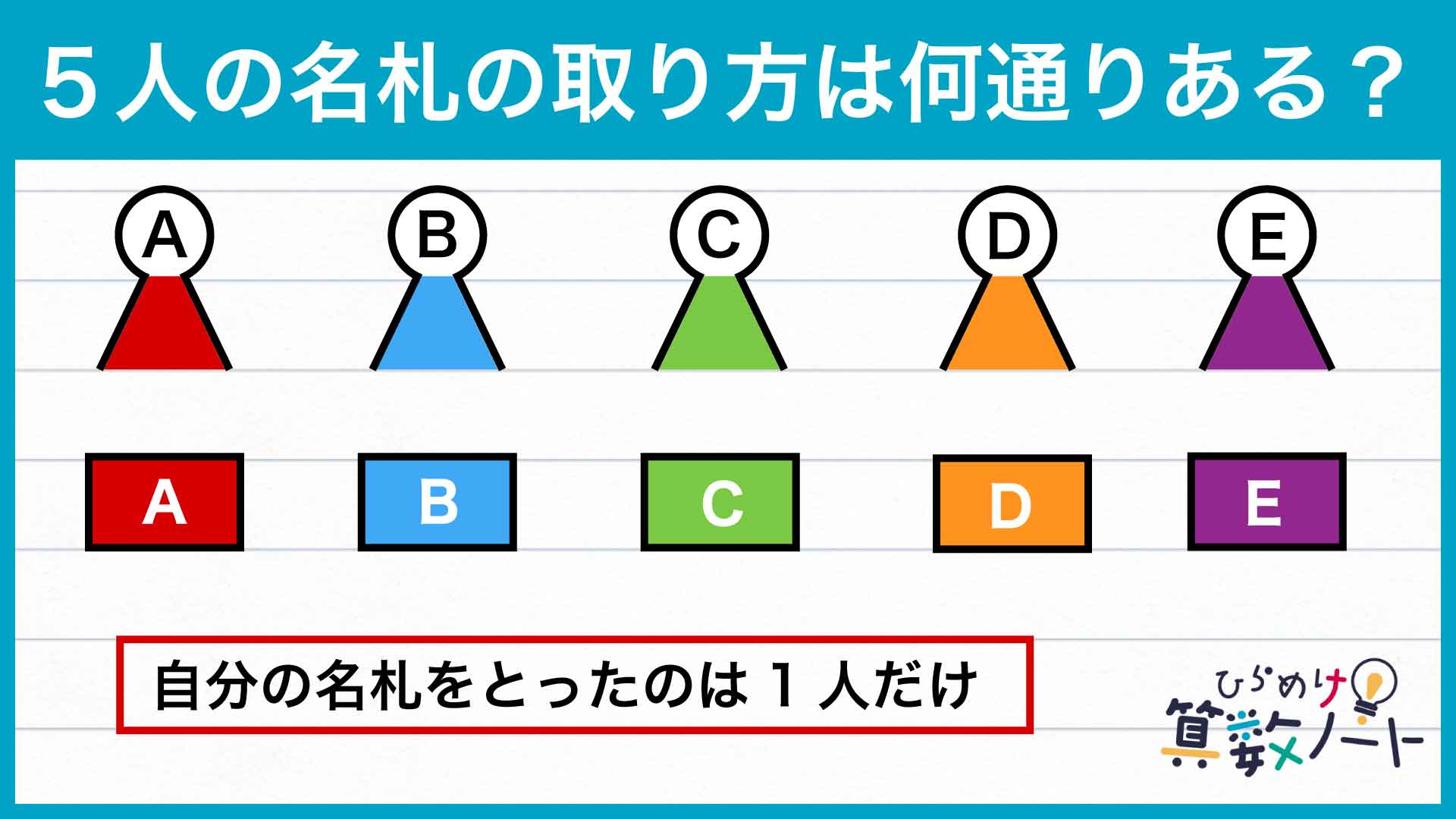問題はこちら
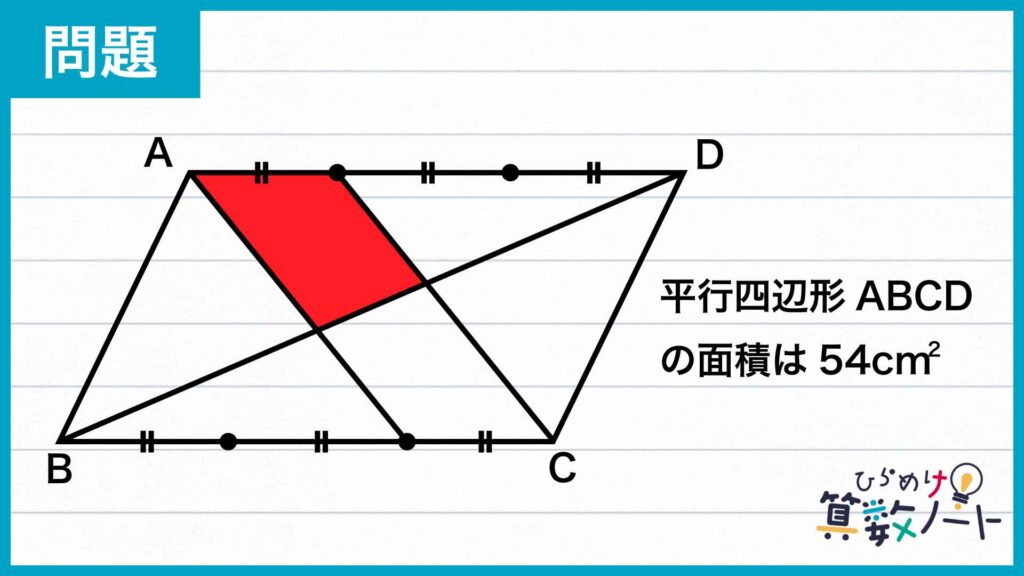
1ページ:【解答フォーム】自力で解きたい方はこちらへ!以下は問題の解説です
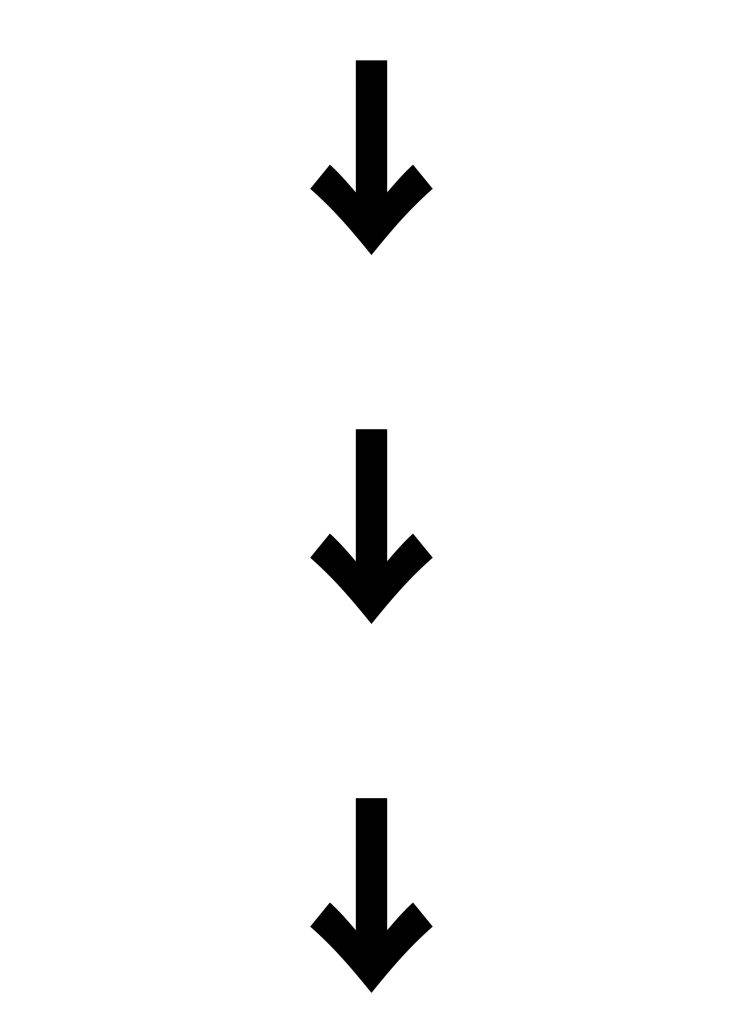
解説
それでは解説です。さまざまな解き方がありますが、ここではそのひとつを紹介します。
この問題の解き方をまとめた図がこちらです。
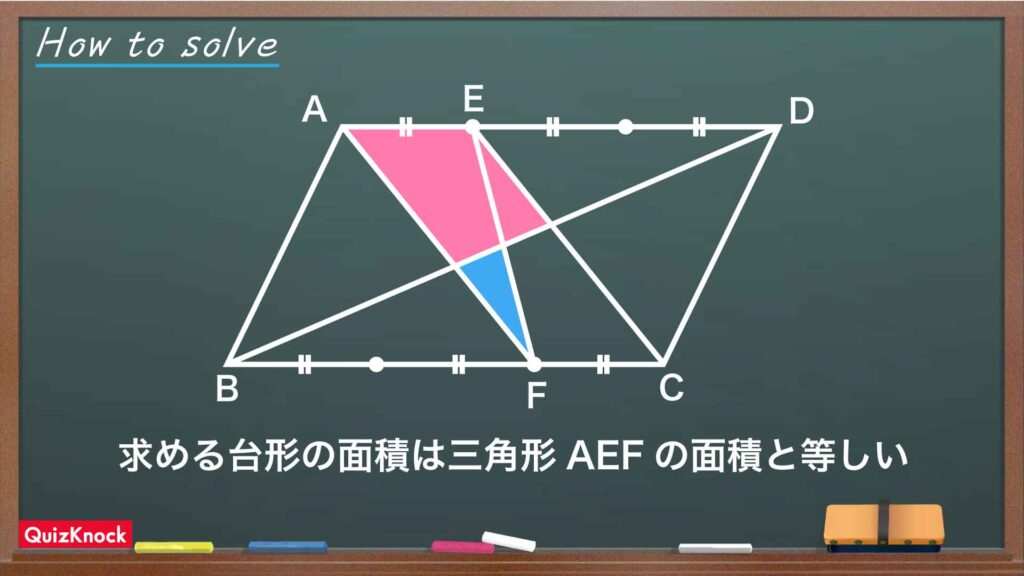
今回のポイントは「平行四辺形を使って面積を求めること」です。
このポイントをもとに、問題を攻略していきましょう!
点E、Fを置いて平行四辺形に注目する
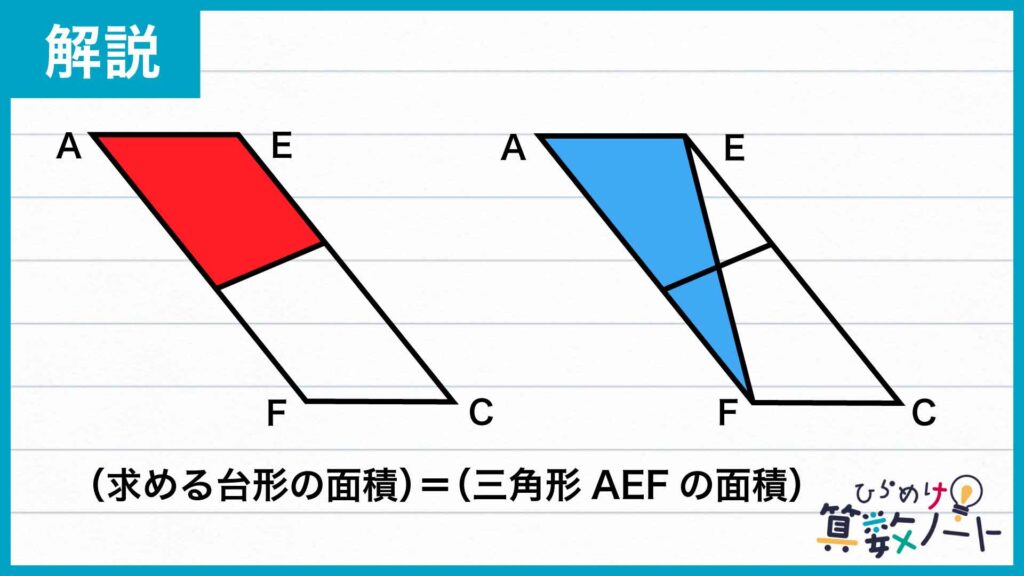
上の図のように点E、Fを配置すると、求める台形の面積は平行四辺形AFCEの面積の半分になります。また、三角形AEFに着目すると、こちらも面積は平行四辺形AFCEの面積の半分です。つまり、求めたい台形の面積は、三角形AEFの面積に等しいことがわかります。
三角形AEFの面積を求める
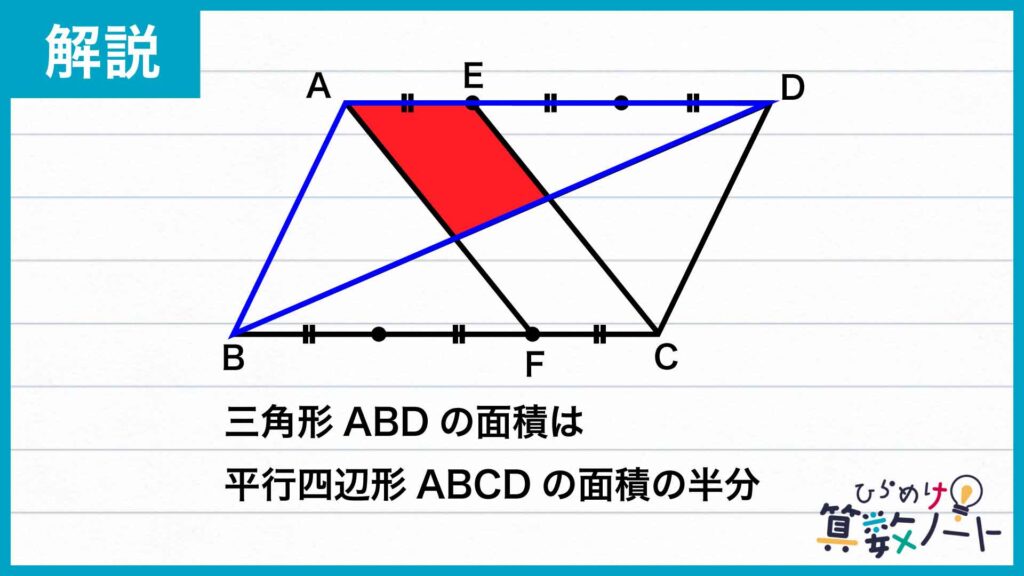
三角形AEFの面積を求めるために、三角形ABDの面積を考えてみましょう。三角形ABDは平行四辺形ABCDの半分の面積です。
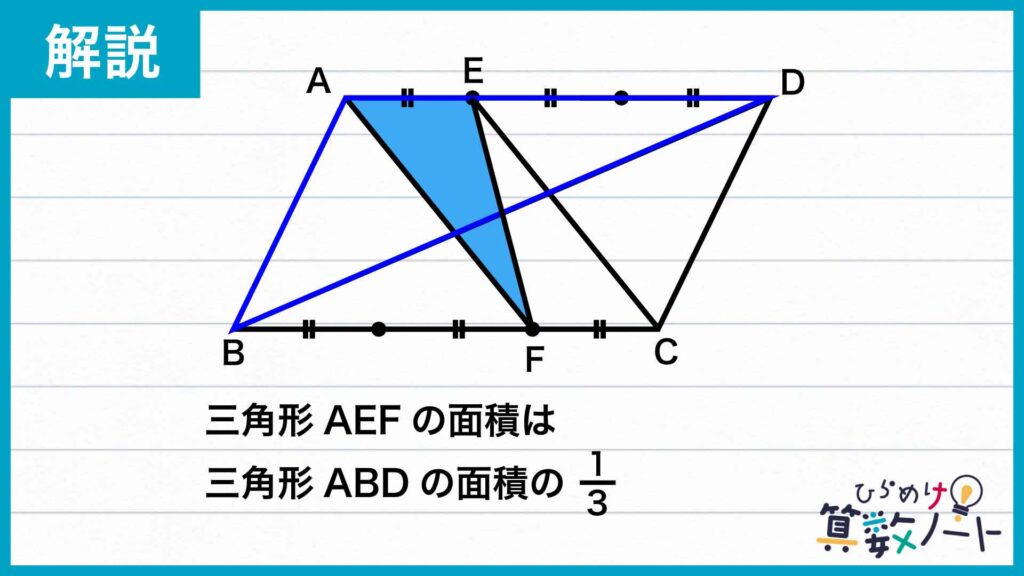
この2つの三角形は、それぞれ辺AD、辺AEを底辺としたときに高さが等しく、AEの長さはADの長さの1/3なので、三角形AEFは三角形ABDの1/3の面積になります。
したがって、(三角形AEFの面積)=54×1/2×1/3=9cm2となります。先ほど示したように、求めたい台形の面積は三角形AEFの面積と等しかったので、これが答えになります。
答え:9cm2
それではまた次の算数ノートでお会いしましょう!
「ひらめけ!算数ノート」のバックナンバーはこちらから!
【前回の算数ノートはこちら】
【あわせて読みたい】








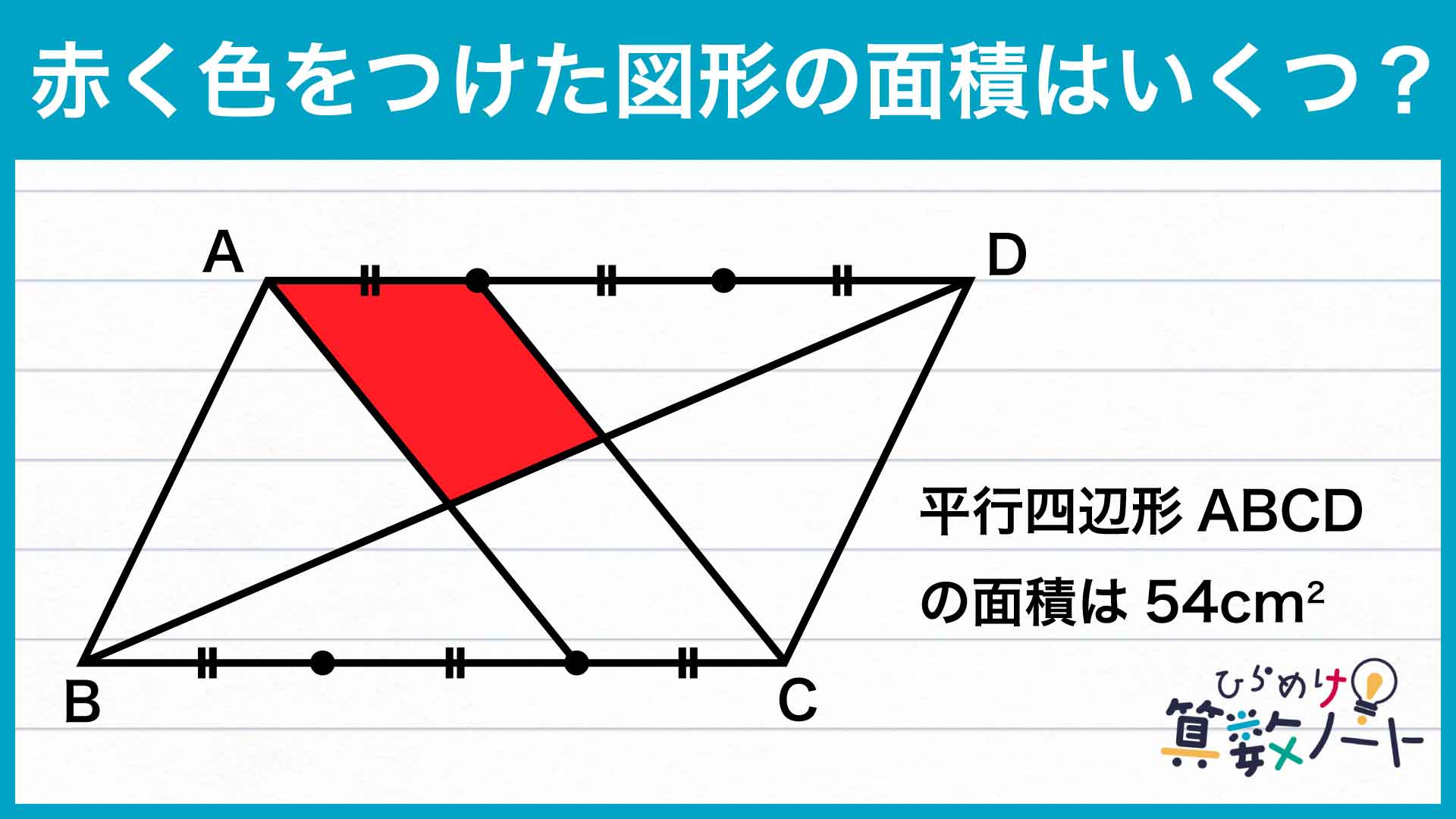

.jpg)



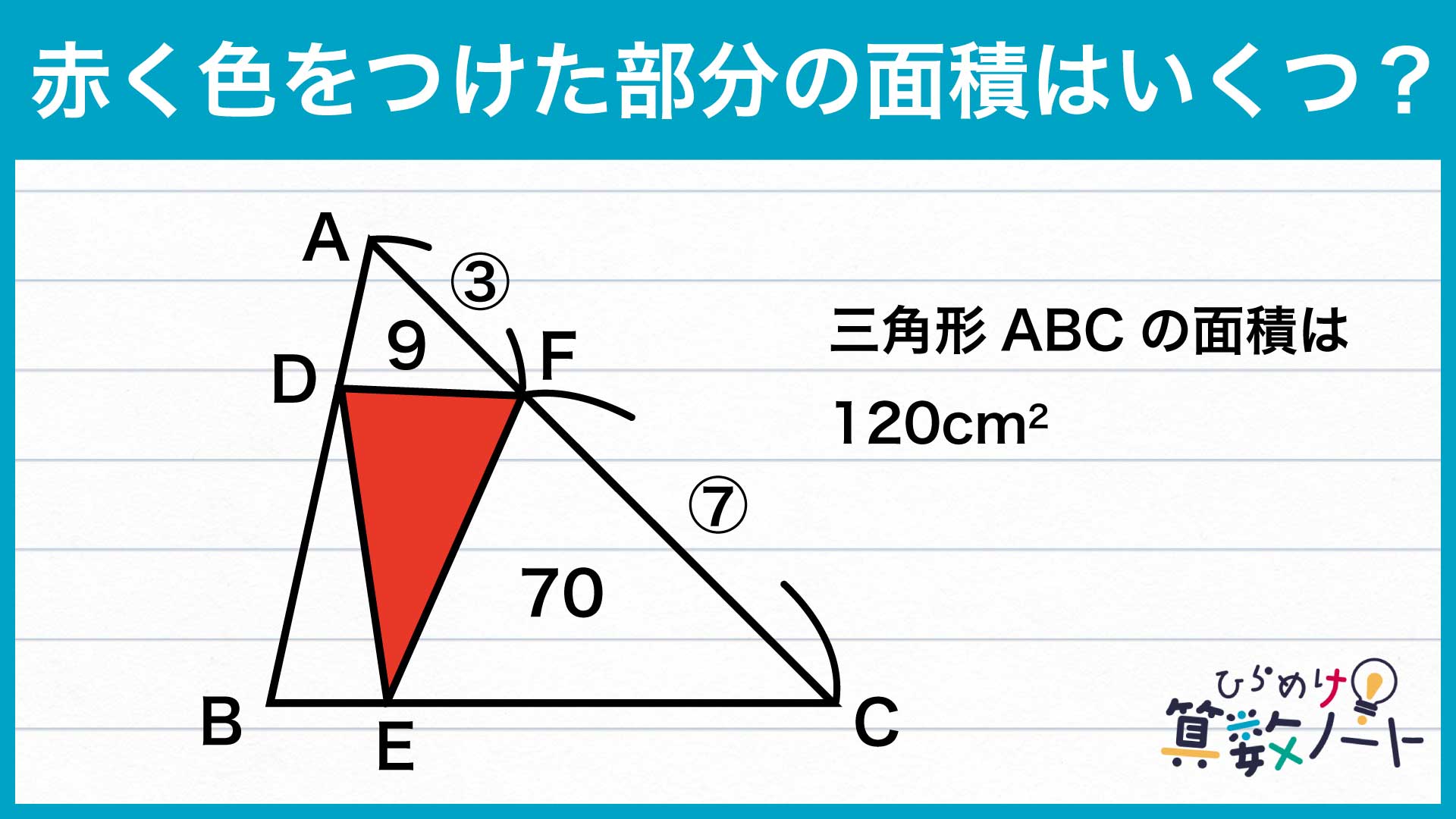
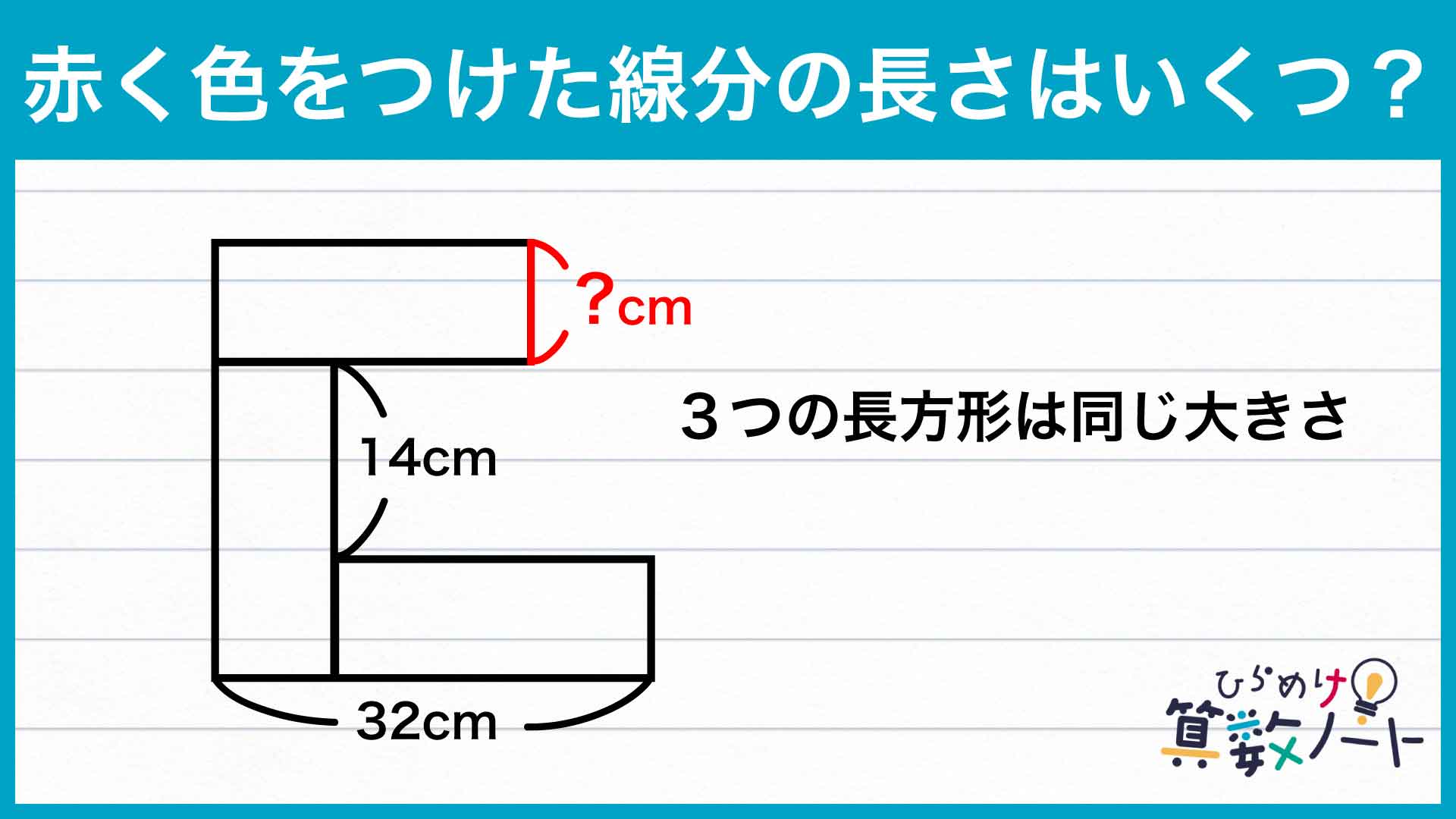
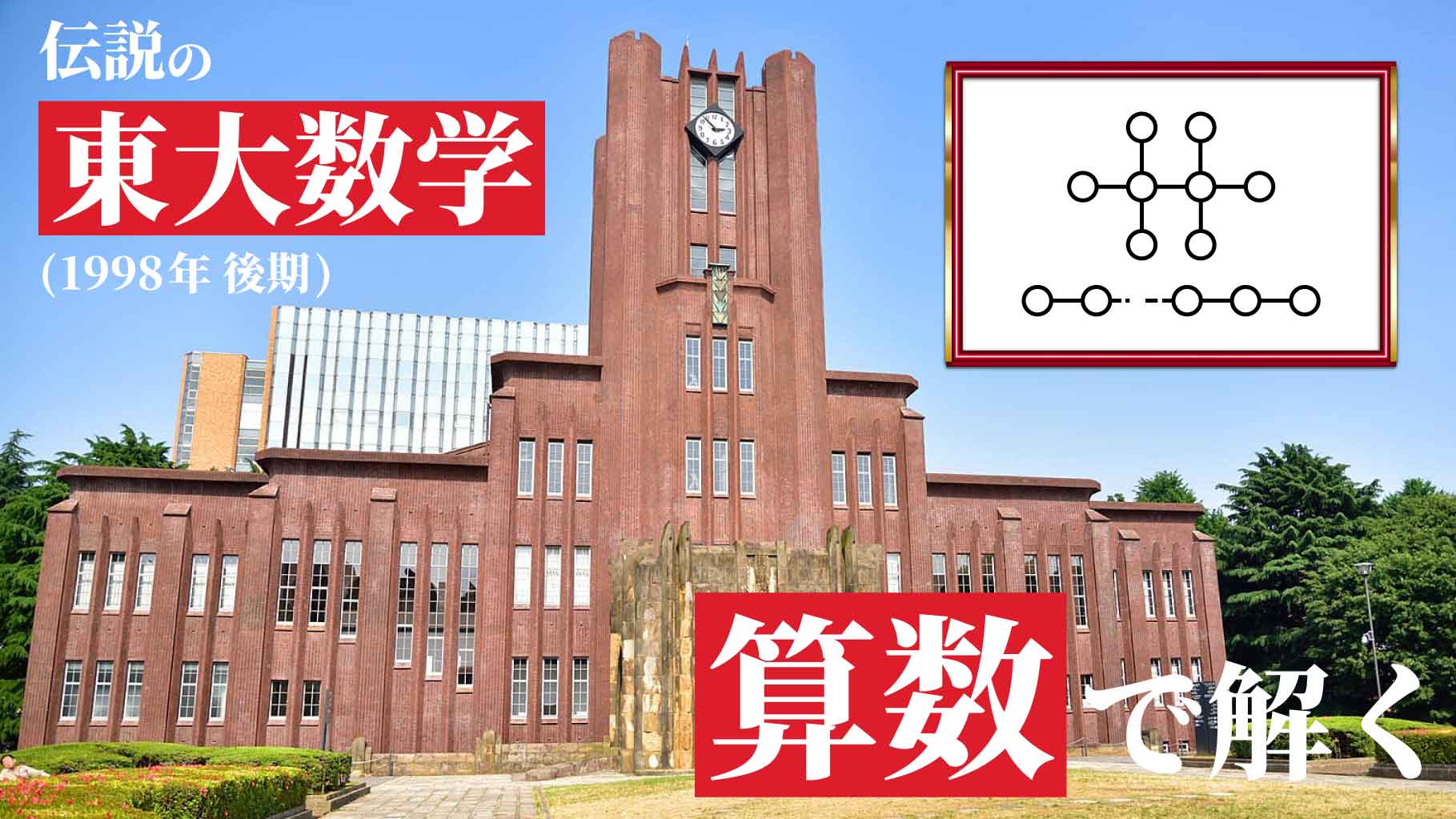

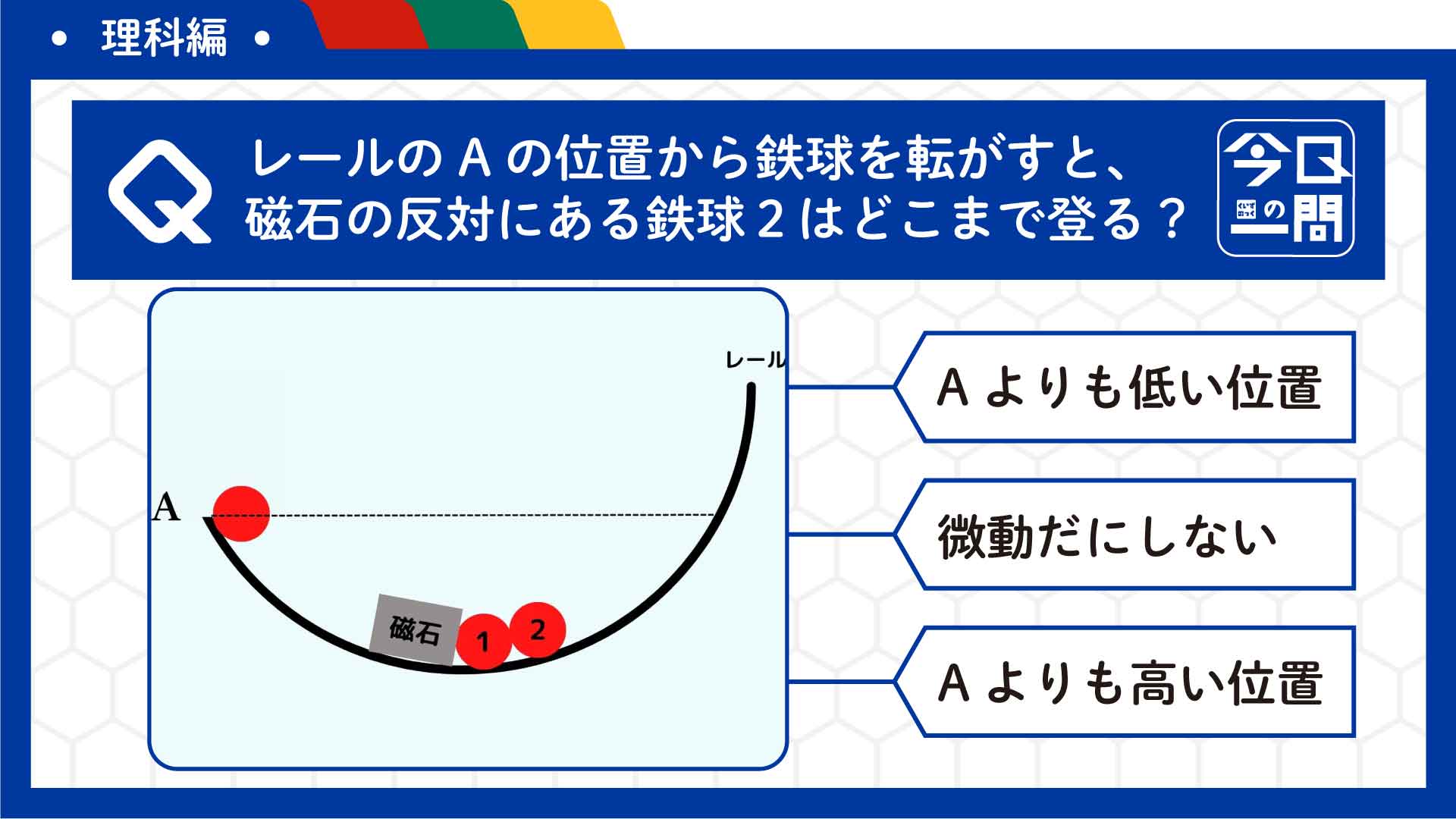


.jpg)