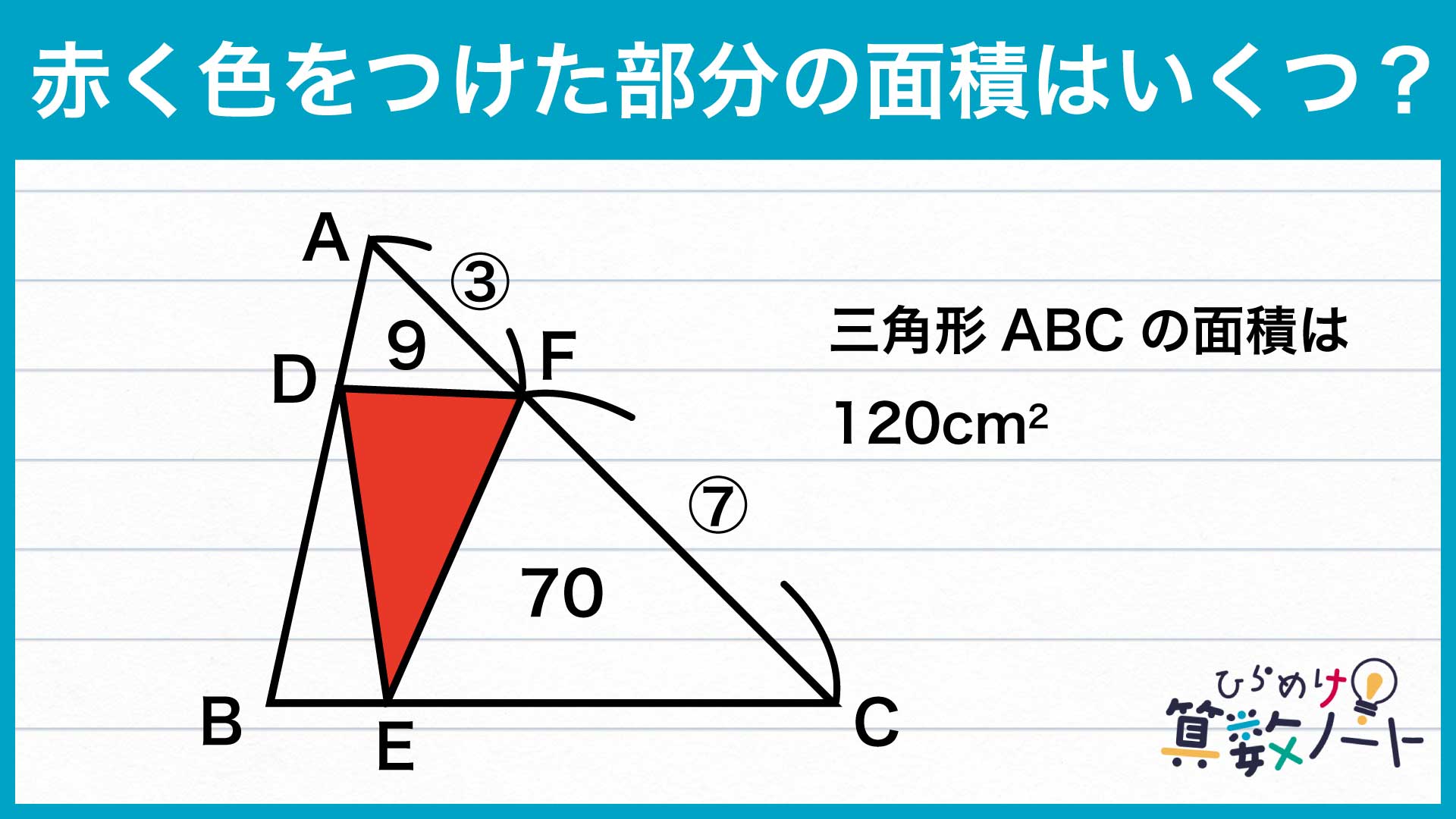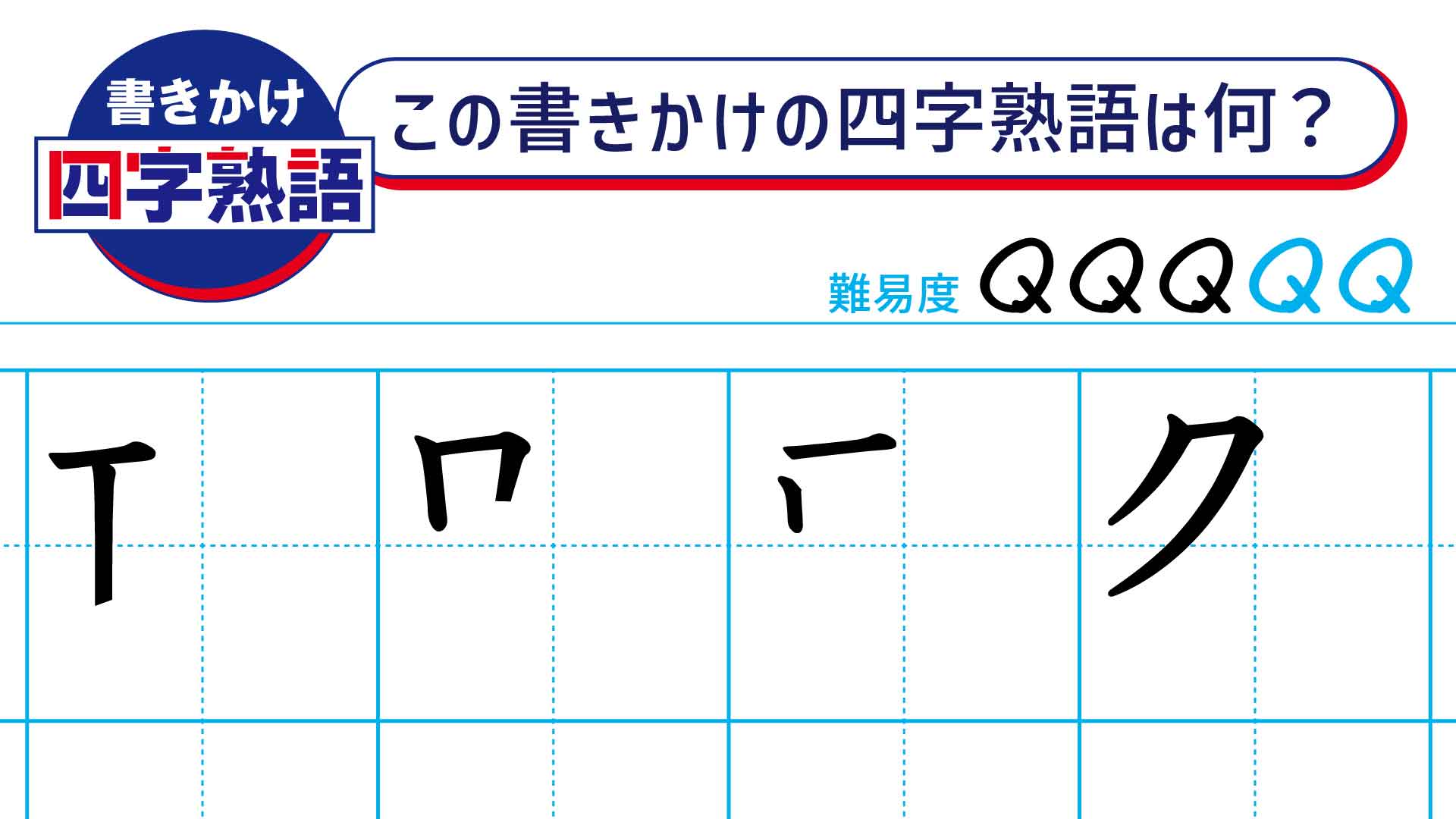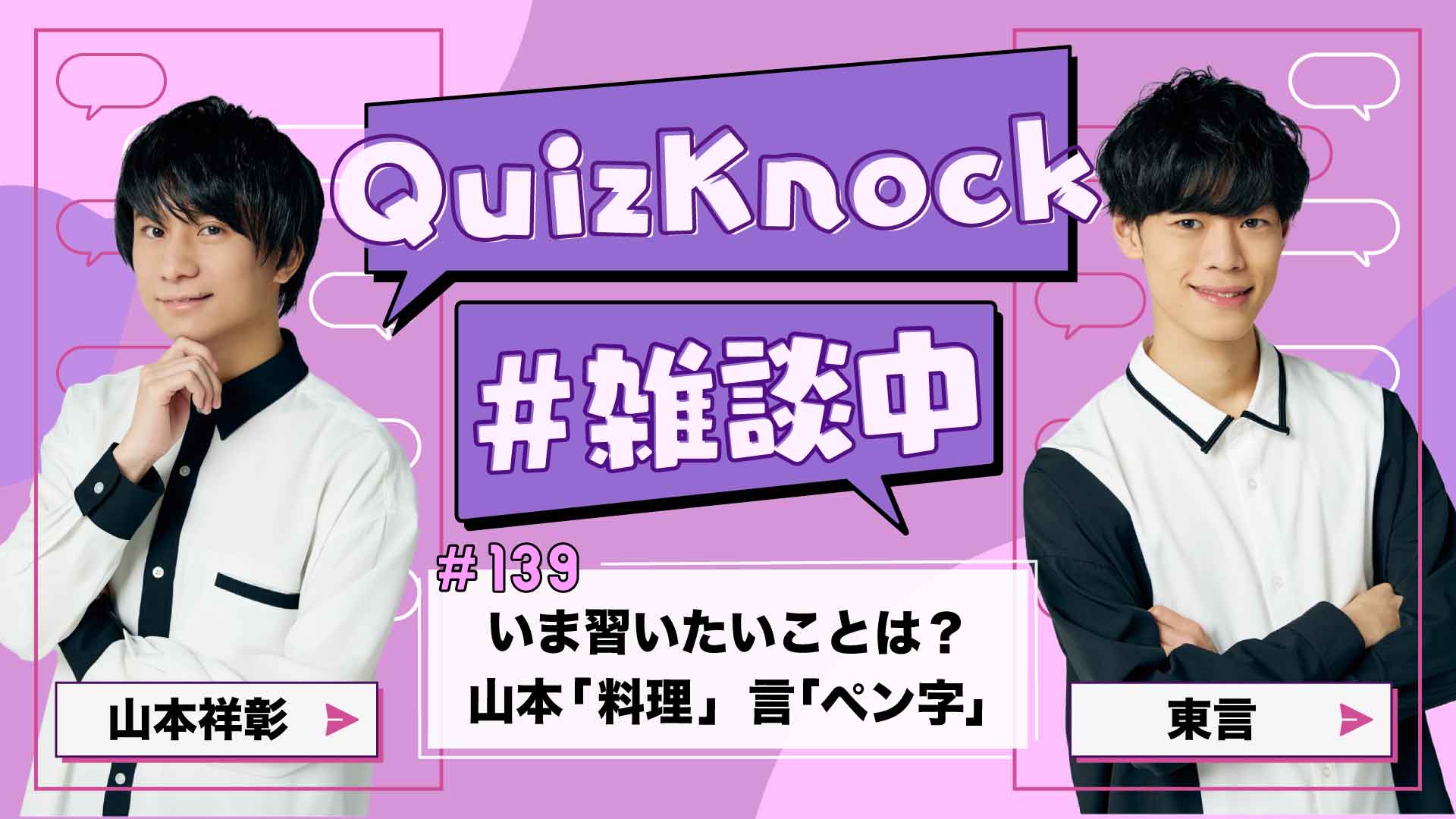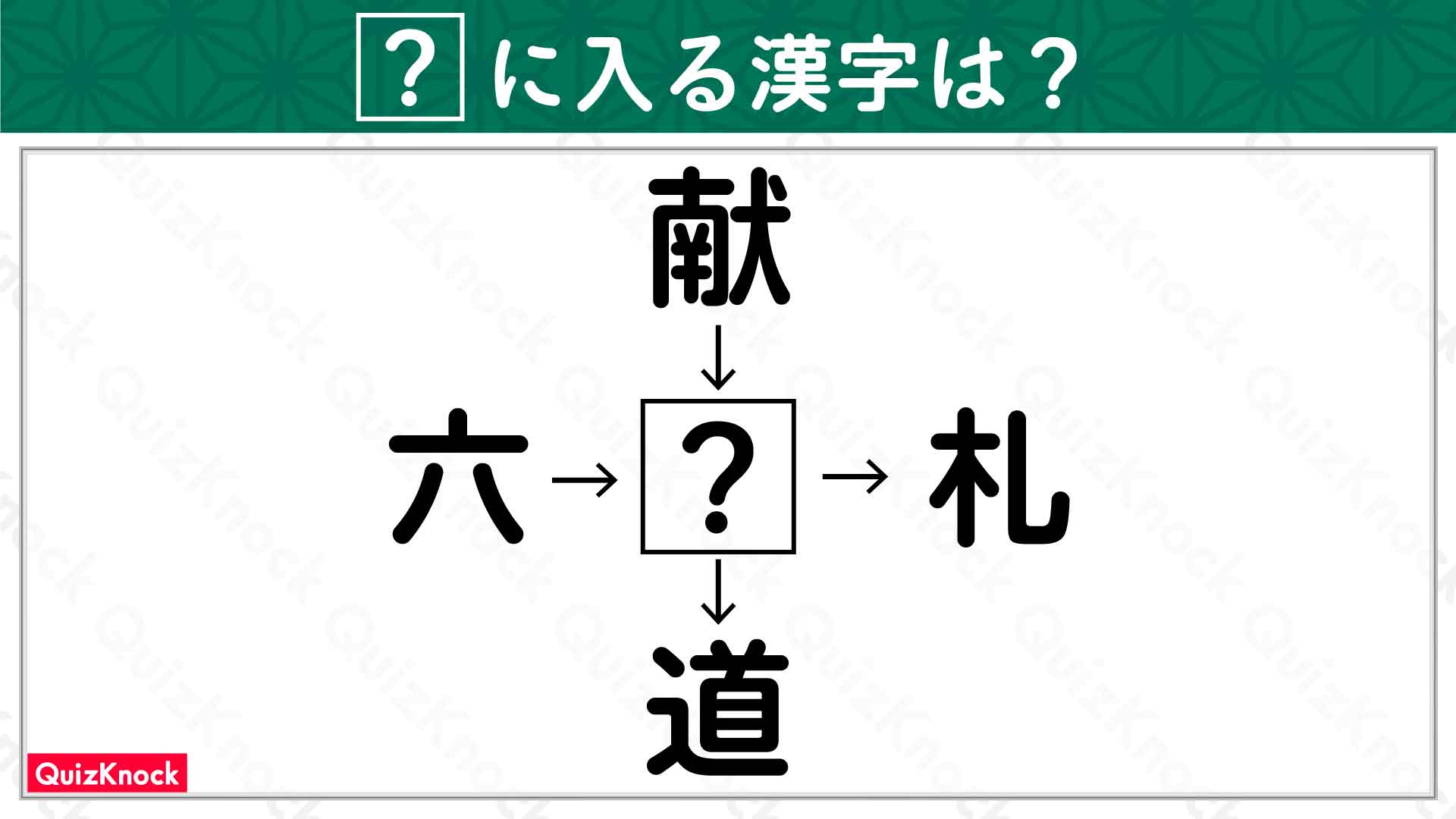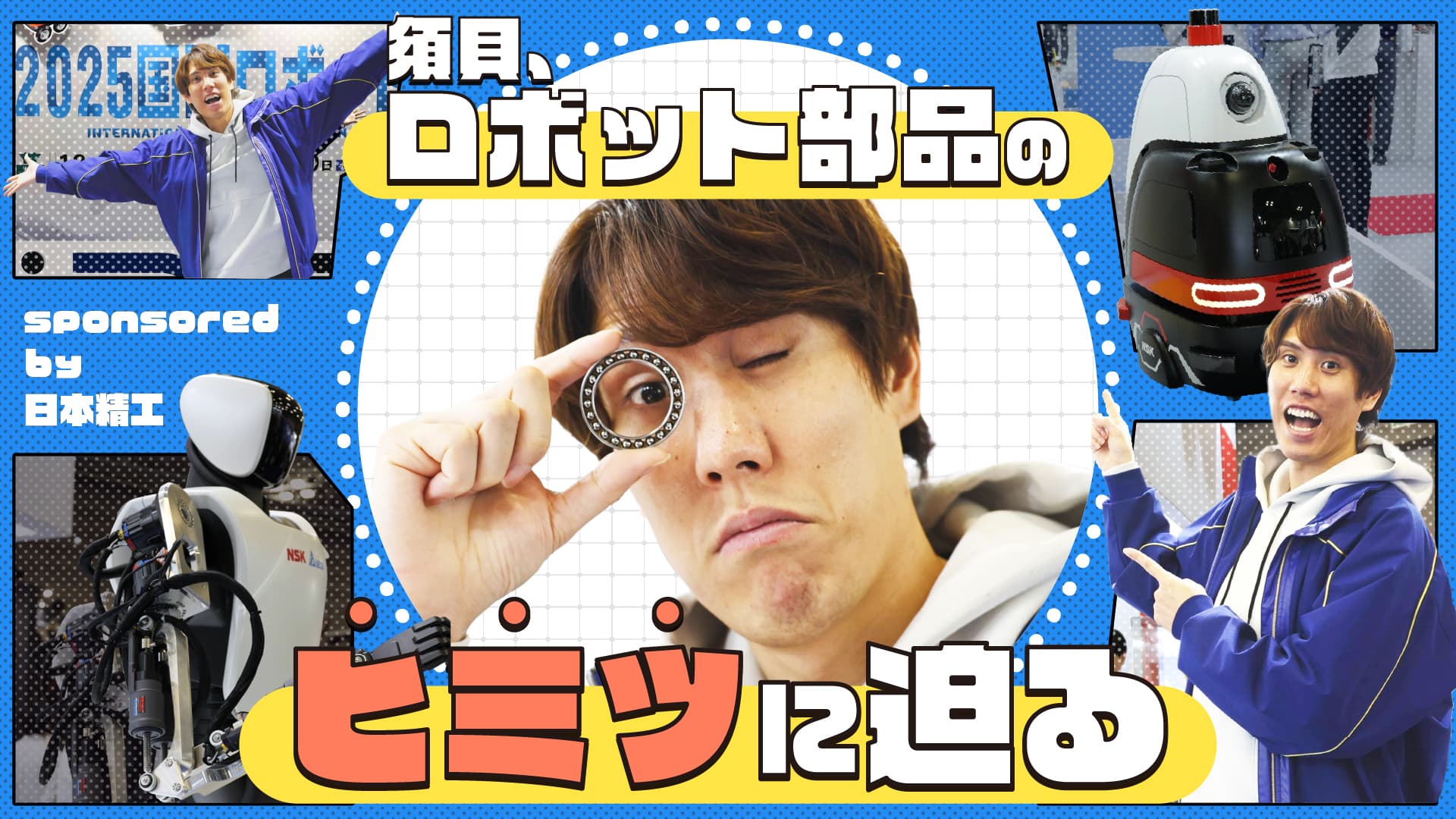問題の解説
第1問 ブイヨンとコンソメ
西洋料理に使われる「ブイヨン」と「コンソメ」。この2つの違いは主に調理過程にあります。
ブイヨンは牛肉・鶏肉に香味野菜などを加え、長時間煮込んだもの。対するコンソメは、できあがったブイヨンにさらに肉や野菜・卵白を加えて煮込み、灰汁をとったものです。
言い換えるなら、ブイヨンは「だし汁」、コンソメは「スープ」そのもの。道理で「コンソメスープ」とは言っても、「ブイヨンスープ」という言い方はあまりされないわけですね。

第2問 サイダーとソーダ
「サイダー」と「ソーダ」どちらも炭酸飲料として親しまれていますが、日本ではサイダーはソーダの一種とみなされています。
そもそも、飲料としてのソーダは「ソーダ水」を略したものです。基本形のソーダ水(プレーン・ソーダ)は水に炭酸ガスを加えて作られ、洋酒を割って飲む際などに使われます。
このソーダ水に甘味や香りをつけたものがサイダー。サイダーという言葉は、リンゴ酒を意味するフランス語の「cider(シードル)」に由来します。
ちなみに「ラムネ」は、サイダーをビー玉付きの瓶に入れたもの。こちらもソーダの仲間といえます。

なお、アメリカでは「サイダー」のような炭酸飲料を「ソーダ」と呼ぶことが多いようです。ややこしい!
第3問 そうめんとひやむぎ
「そうめん」と「ひやむぎ」の違いは、ずばり麺の太さ。
JAS(日本農林規格)では、同様の材料でできた麺のうち、乾麺の状態での長径(断面の一番長い部分)が「長径1.3mm未満」のものはそうめん、「長径1.3mm以上、1.7mm未満」のものはひやむぎと定義されています。また、長径1.7mm以上のものは「うどん」となります。

なお、上記の定義は機械による製麺に限った話。手延べ製法の場合には、直径1.7mm未満の麺を「手延べひやむぎ」「手延べそうめん」のどちらで呼んでもよいとされています。
第4問 アイスクリームとアイスミルク
「アイスクリーム」と「アイスミルク」の違いは成分にあり、乳固形分と乳脂肪分の割合で決まります。
「乳固形分」は乳製品のうち水分以外の部分が占める割合、「乳脂肪分」はその乳固形分に含まれる脂肪分の割合のこと。
「アイスクリーム」は乳固形分15.0%以上・乳脂肪分8.0%以上、一方の「アイスミルク」は乳固形分が10.0%以上・乳脂肪分が3.0%以上のものと決まっています。アイスミルクの成分は一般的な牛乳とほぼ同じ……といえば、おおよそのイメージがつかめるでしょうか。
第5問 ビスケットとクッキー
「ビスケット」と「クッキー」は本来同じものを指し、明確な違いはありません。
ただし、「糖分や脂肪分が多く含まれており、手作り風の外観をもつもの」を「クッキー」と呼んでもよく、両者は区別して使われる傾向があります。
この決まりができた1971年当時は「クッキーのほうがビスケットより高級品」という認識が広まっており、消費者の誤解を防ぐために基準が設けられたといわれています。

海外でも「クッキー・ビスケット」をめぐる事情はさまざま。たとえば、アメリカでは類似の製品をすべて「クッキー」と呼び、「ビスケット」は主に菓子パンのようなものを指す言葉とされています。
第6問 軟水と硬水
軟水と硬水の違いは、金属成分の含有量です。
カルシウム・マグネシウムの含有量から「硬度」という数値が求められ、硬度が高いものは「硬水」、低いものは「軟水」となります。WHO(世界保健機関)の分類では、硬度が1リットルあたり120mg以上で「硬水」とされています。
軟水は昆布だしを取るときなどに向いているとされ、地域によって若干差はあるものの、日本の水道水は概ね軟水です。一方西洋では硬水がよく飲まれており、水の違いが食文化の違いにもつながっているといえるかもしれません。
第7問 ニラレバ炒めとレバニラ炒め
「ニラレバ炒め」と「レバニラ炒め」は同じものを指し、明確な違いはありません。

実際、お店によって表記はバラバラで、餃子の王将や日高屋では「ニラレバ炒め」、大阪王将では「レバニラ炒め」が提供されています。
第8問 和牛と国産牛
「和牛」となる牛肉は、日本固有の4つの品種の牛、もしくは4品種の交配種の牛の肉だけです。
その4品種とは、黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種。このうち黒毛和種が和牛全体の9割を占め、「黒毛和牛」として広く知られています。余談ですが、日本の黒毛和牛の母牛の99.9%は、
一方、「国産牛」は品種にかかわらず、肥育期間のうち、最も長く過ごした国が日本である牛を指します。
第9問 大判焼きと今川焼き
「大判焼き」と「今川焼き」は同じものを指し、明確な違いはありません。
この「小麦粉の生地にあんこなどの具を入れて焼いた円筒形の菓子」は、全国各地でさまざまな呼び方をされています。
広島県では「二重焼き」、兵庫県では「御座候」、九州では「回転焼き」、北海道では「おやき」……と呼ぶ人が多いようですが、同じ地域で人によって変わることもしばしば。

ちなみに「今川焼き」という名称は、江戸時代に神田の今川橋でこの菓子が売り出されたことが由来とされています。
【あわせて読みたい】











.jpg)



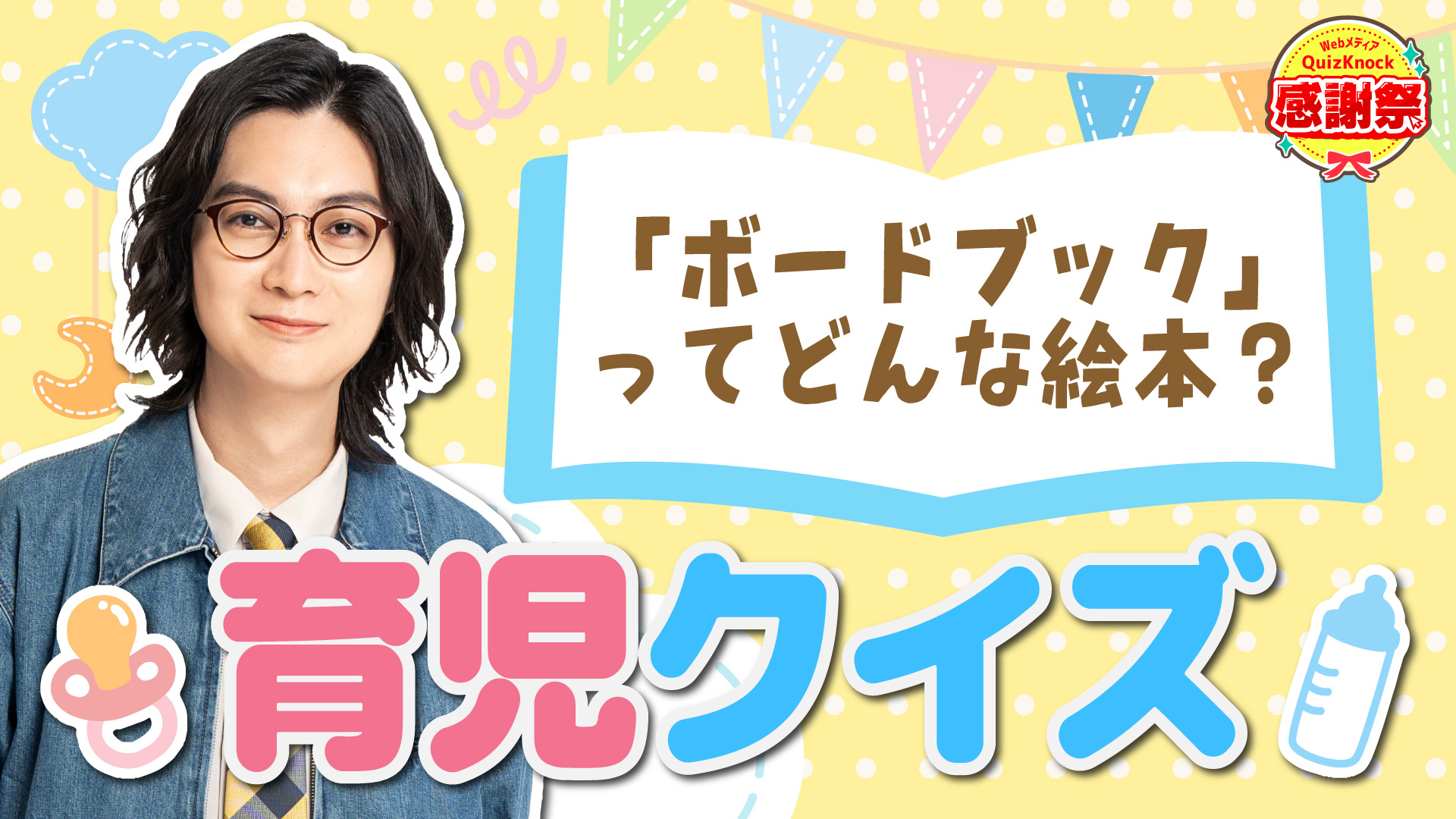
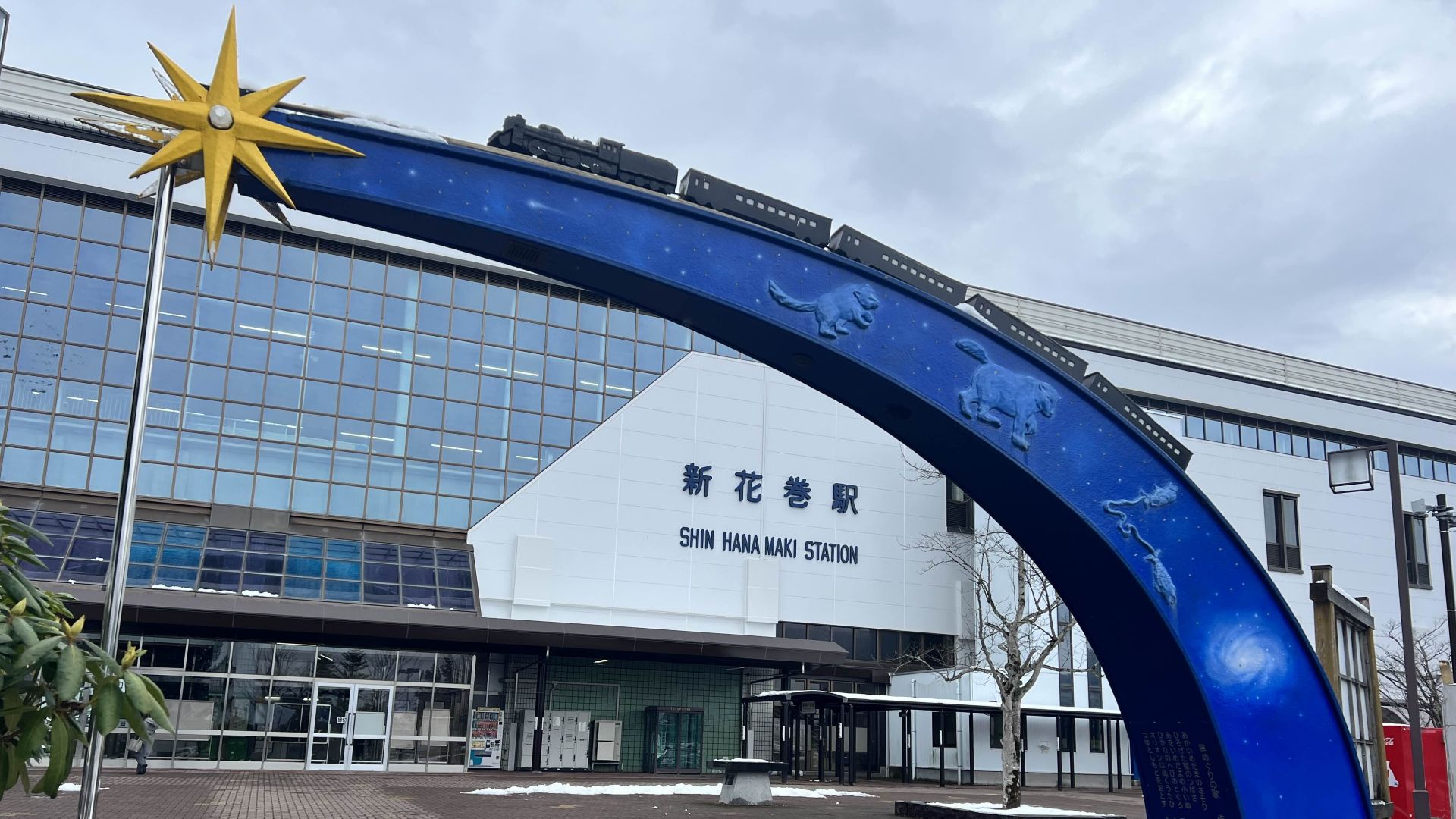
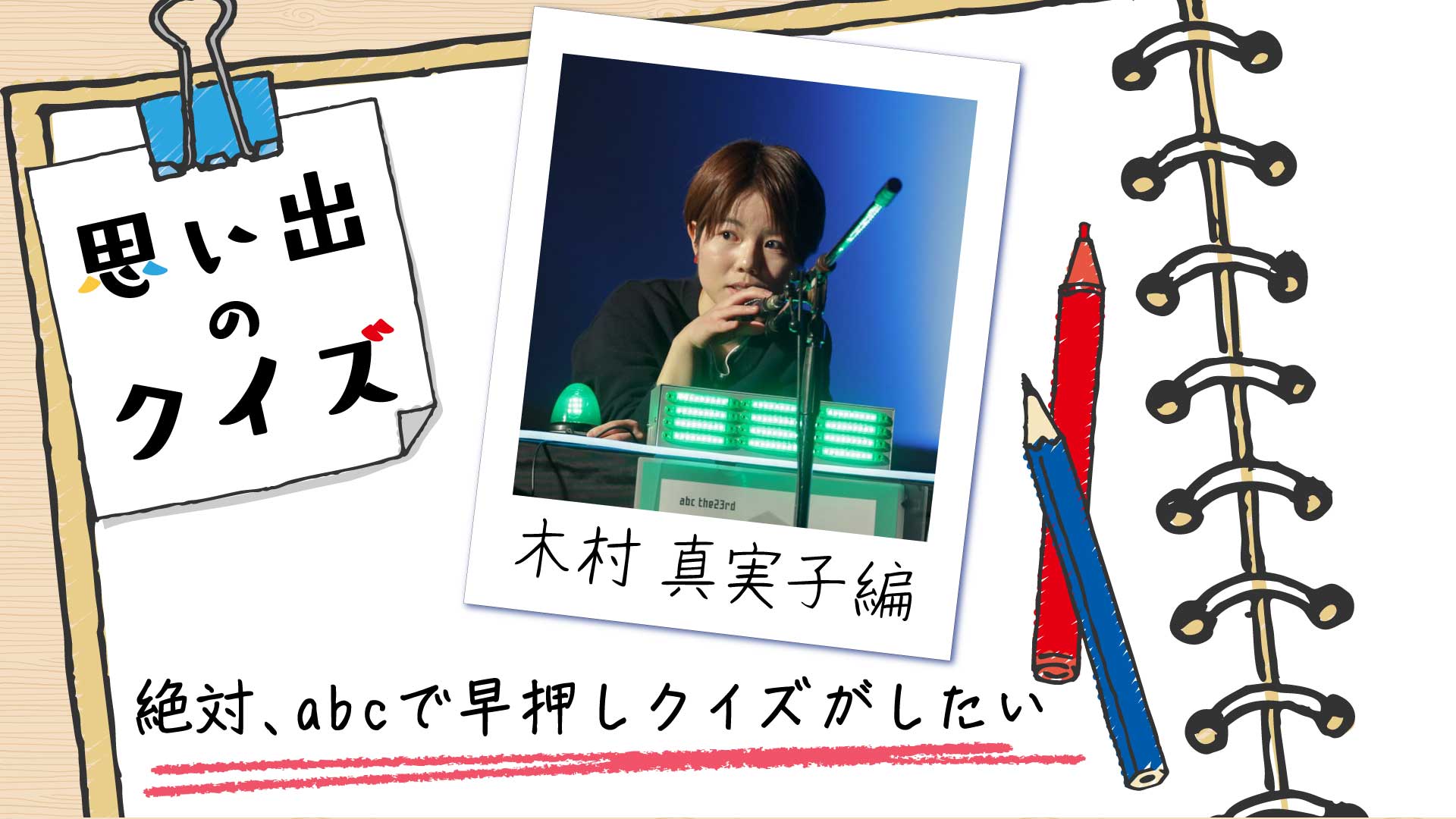




.jpg)