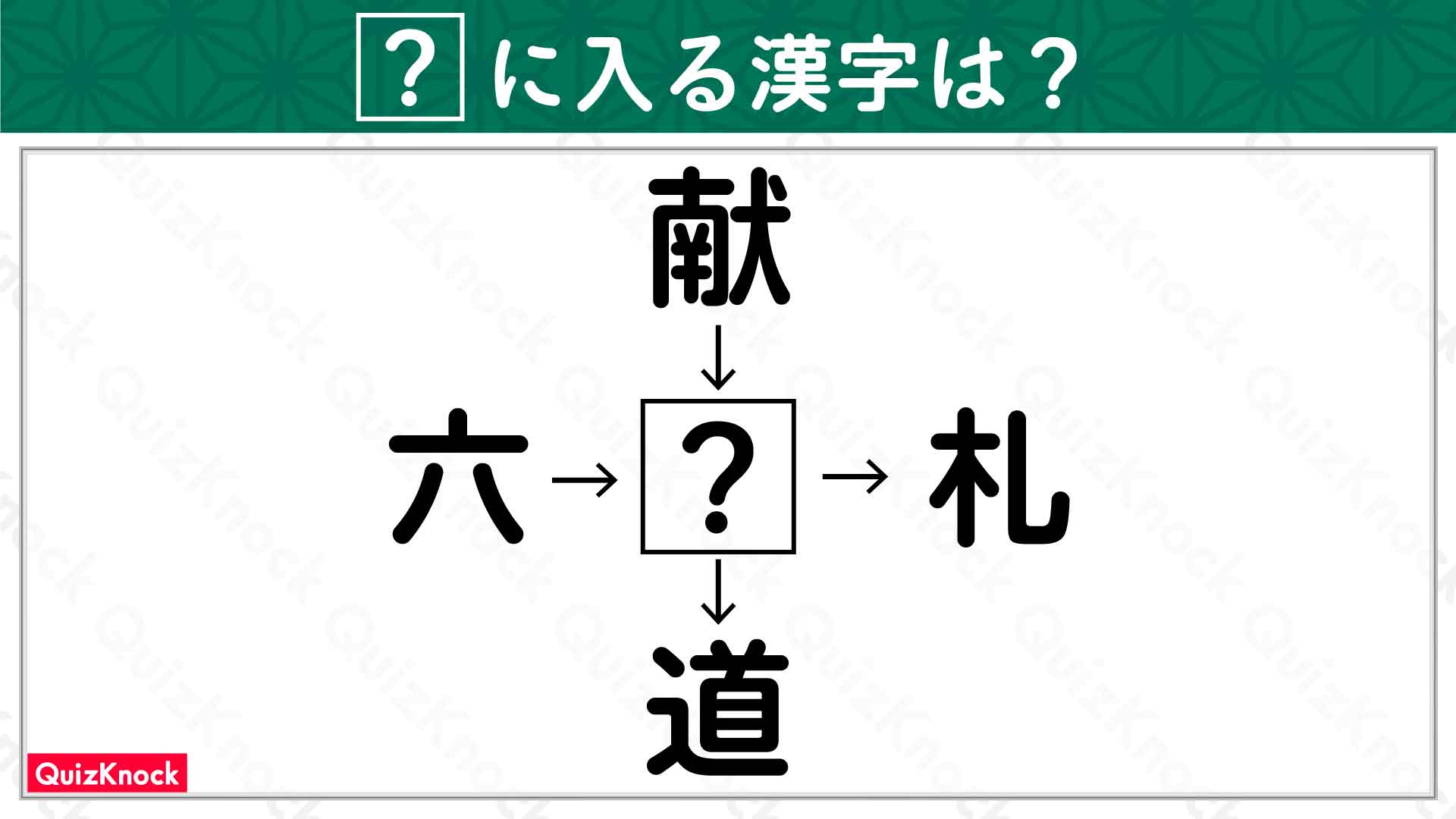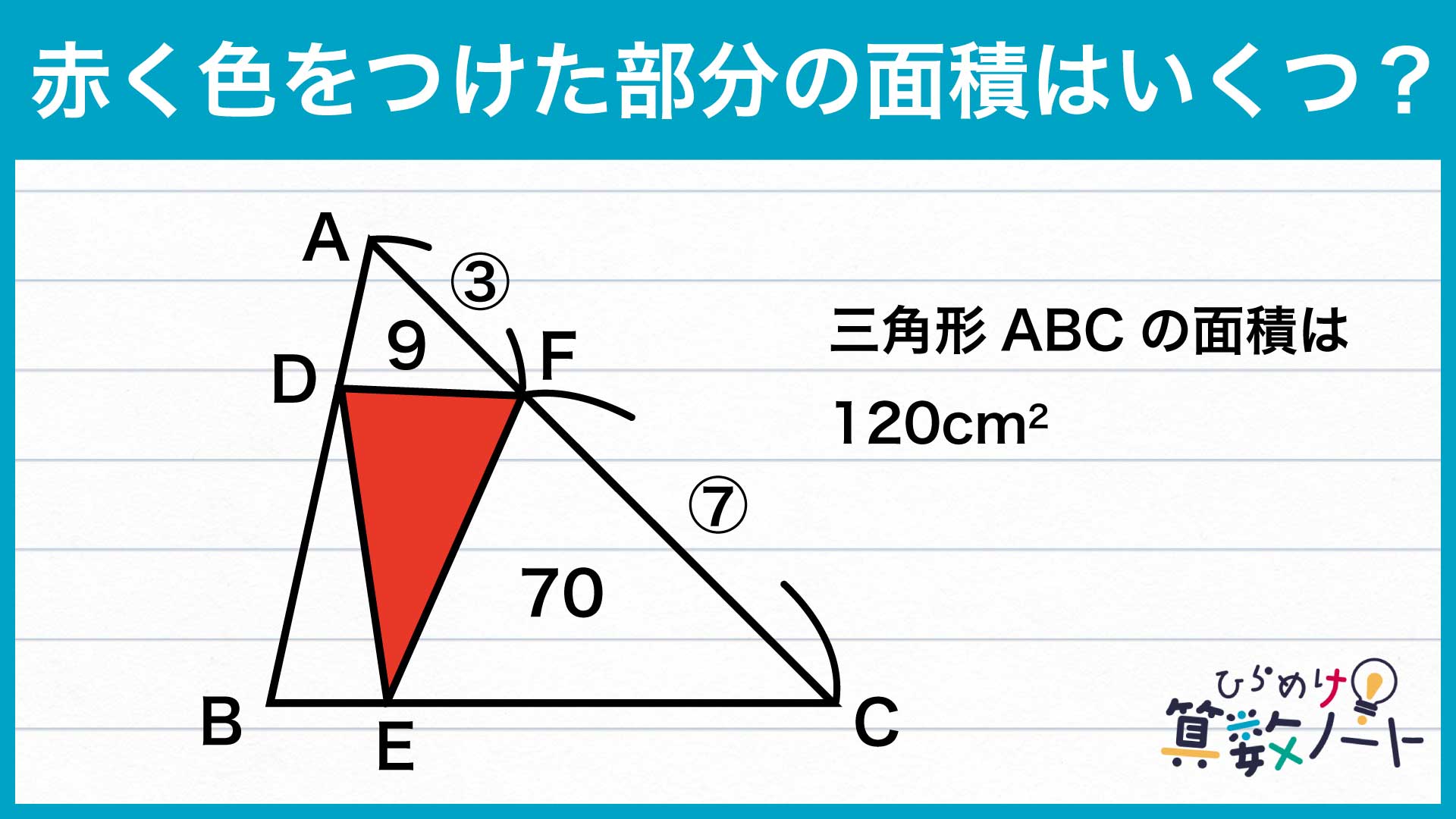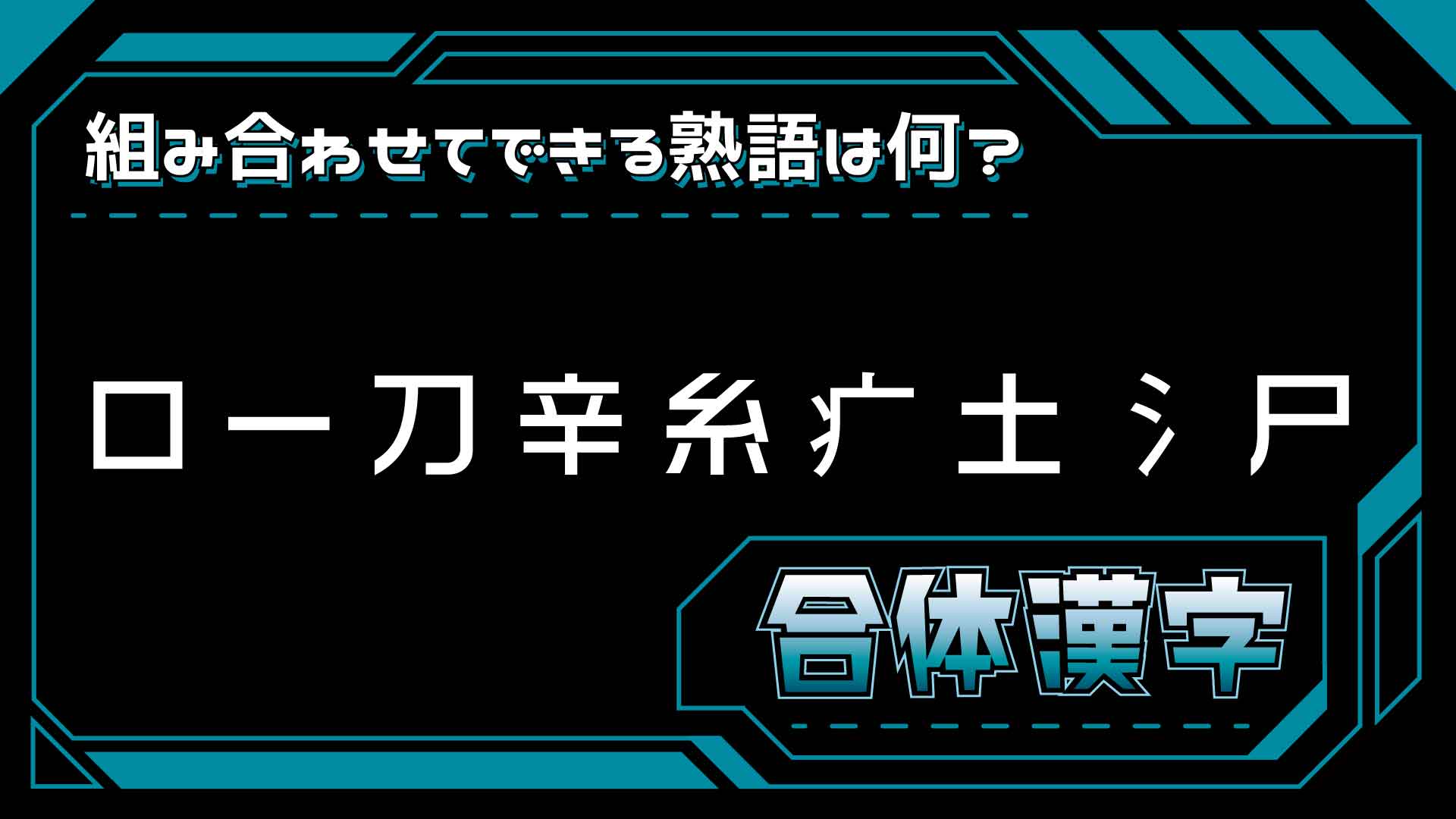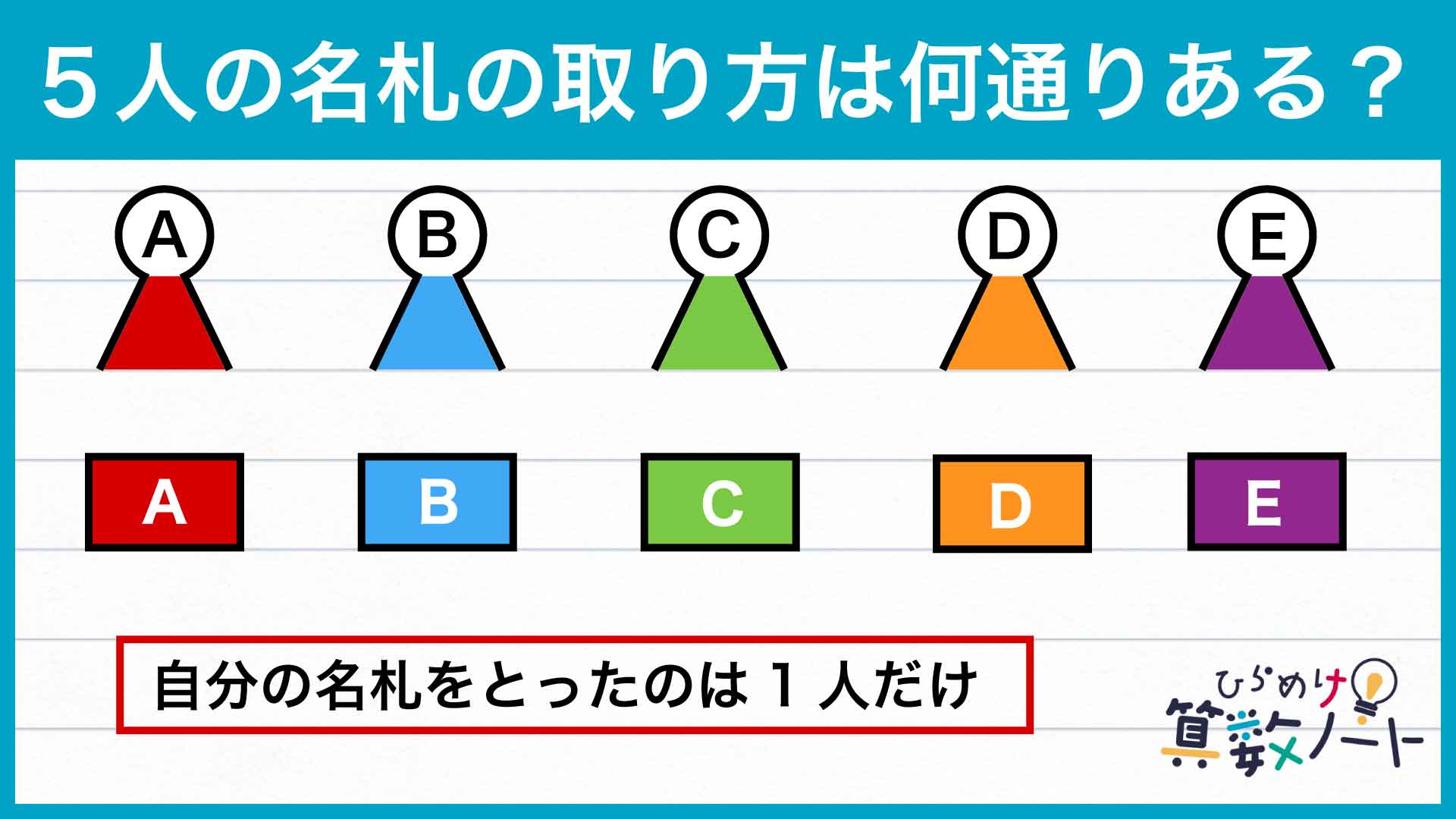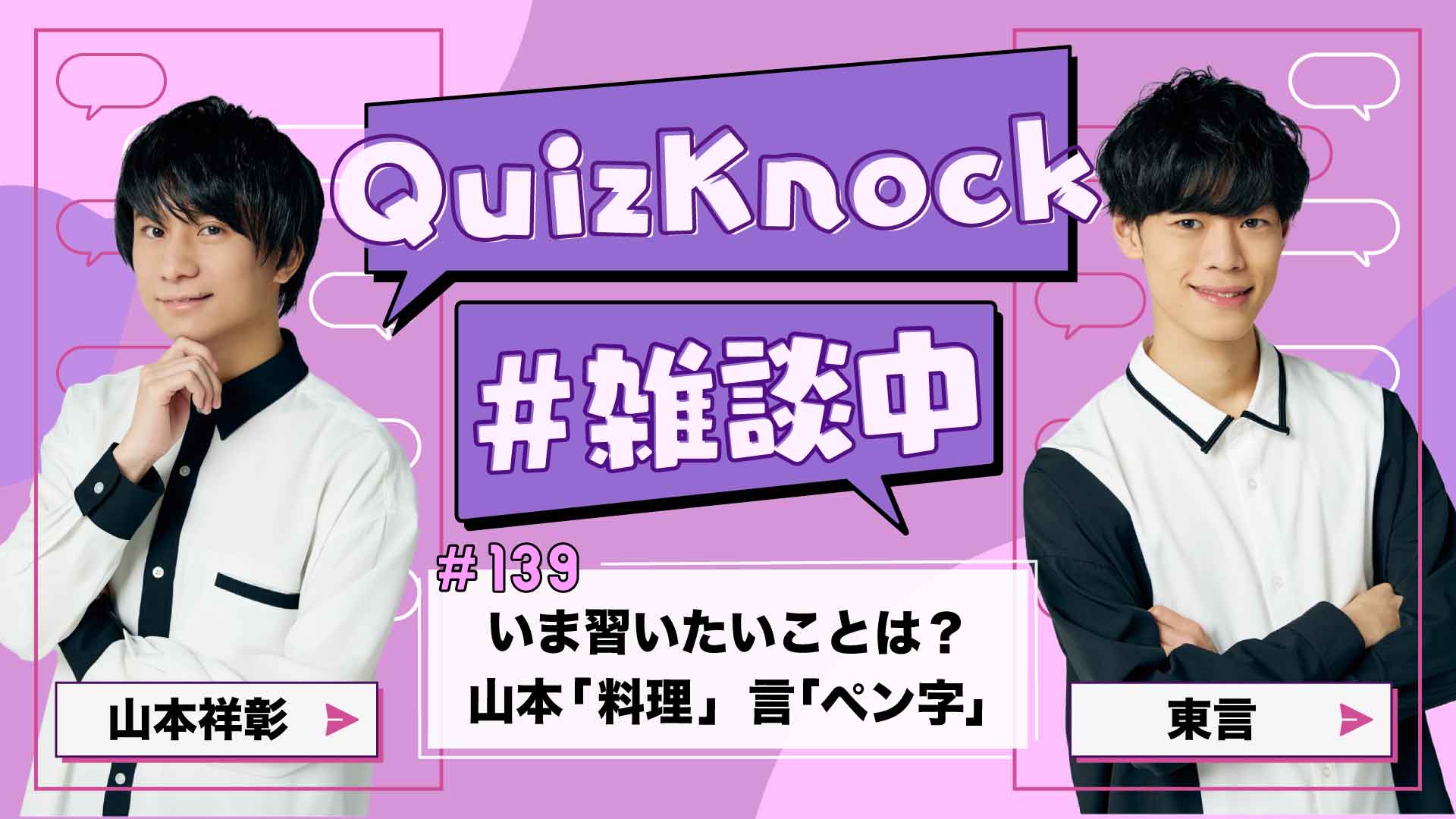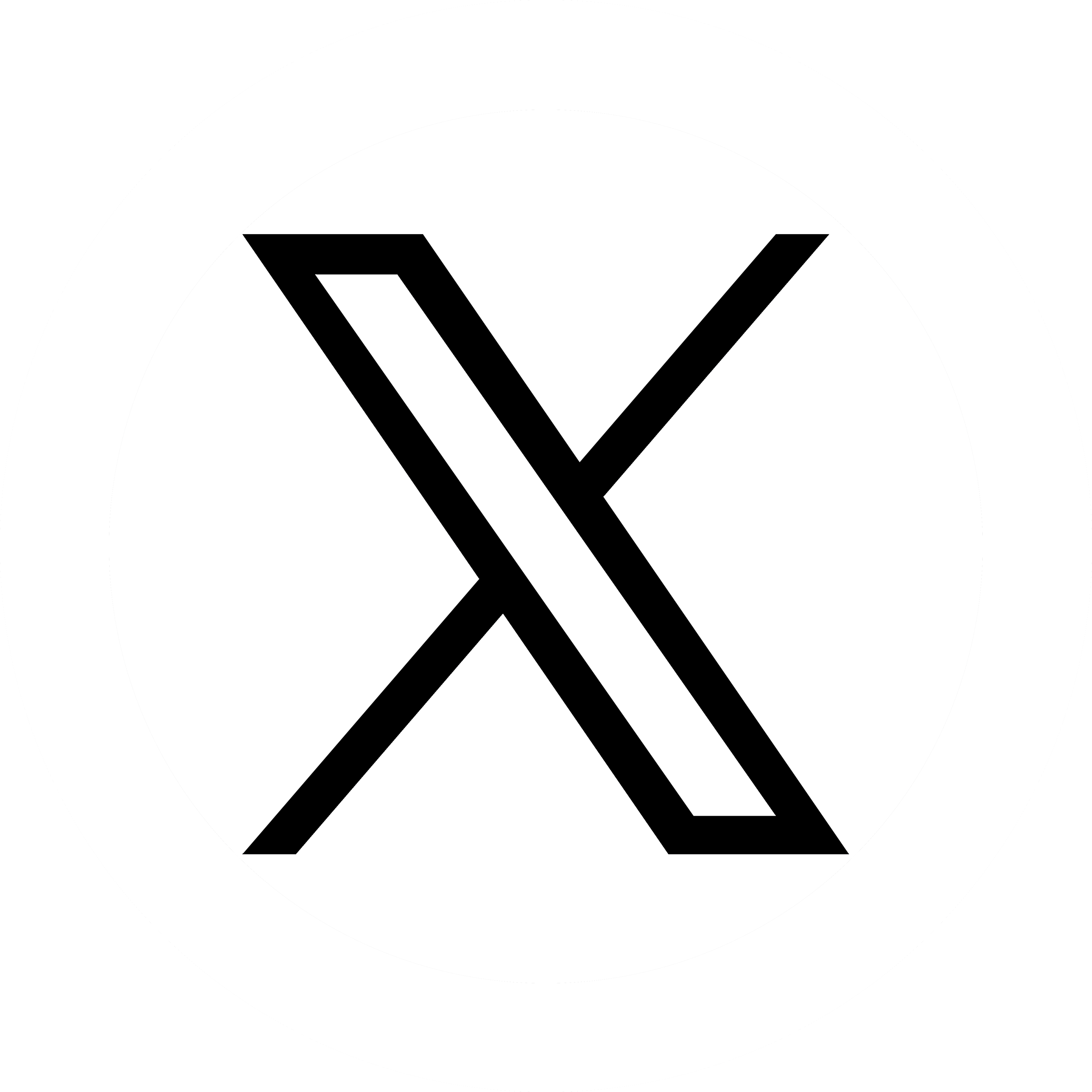青松輝と「クイズ」
クイズも短歌も「自己表現」
――青松さんは以前、東京大学クイズ研究会(TQC)に所属されてクイズに取り組んでいましたよね。
青松さん はい。灘高校でもクイズ研究会に所属していました。僕も、今みたいにクイズが人気になる前から「クイズが面白い」とは気付いてたんですよ。先見の明は当たったのに、肝心のクイズブームに乗り遅れて、おいしい思いをしそこねた(笑)。

――クイズと創作の共通点について、双方の魅力を知る立場から教えてください。
青松さん クイズは、スポーツとしての要素が大きい一方で、ある種の「自己表現」とも言えますよね。トップ層に近づくほど、特定分野に関する絶対的な強みといった「個性」の重要性が高くなると思うんです。問題集の読み込みをものすごく頑張れば、ある程度のレベルまでは行けるけど、本気でトップになろうと思ったら、ほかの人にないエッジを効かせないと勝てない。短歌に似たゲーム性を感じます。
――「クイズに助けられた」と思う瞬間はありますか?
青松さん 僕、本当に全部クイズから学ばせてもらいました。クイズをやっていなかったら理三に受かっていないし、短歌もここまで頑張れなかったと思います。
理三:「東京大学理科三類」の略称。理科三類に所属する学生のほとんどが、後期課程で医学部に進学する。青松さんは2017年に合格。
1番痛感したのは、「能力はそんなに関係ない、大事なのは向き合ってきた量なんだ」という信念ですね。クイズって極論、知識の量で決まるんですよ。もちろん、その量を支配するのは当人の能力なんですけど。

青松さん 例えば、1冊の問題集を読んで「1覚える人」と「100覚える人」がいるとする。100覚える人が10冊の問題集を読んだら、100×10で1000覚えることになるけど、1しか覚えられない人も、1000冊読めば同じように1000覚えられますよね。「才能」とか「能力」とか、神秘的に言われがちですけれど、「どんなやつでも死ぬほど問題を覚えたら絶対に勝てる」という部分にロマンを感じてやっている人は多いと思います。 そういう意味で、才能や努力に対するフラットな思考を構築してくれたのはありがたかったです。

青松さん もしクイズをやっていなかったら、初心者の頃に、「俺、文学の才能ないな」と挫折したかもしれないですけど、クイズの問題を1万問覚えるつもりで短歌を1万首覚えて、秀歌からエッセンスを抽出して、新しいのを作り続ければ、きっとそのうち良い短歌が作れるだろう、と考えました。
――確かに、言われてみれば似ている部分があります。
青松さん クイズの場合、覚えていなかったら負けるし、ボタンを押せなかったら負けるという、絶対的なフェアさがある。短歌もほかの創作も、突き詰めれば、クイズに通ずる公平性があるはずです。少し抽象的な話ですけど、その部分に関しては大きな影響を受けました。もちろん、クイズで得た具体的な語彙や知識も、短歌制作に活きています。
彼にとっての「思い出のクイズ」
――個人的に印象に残っているクイズなどはありますか。
青松さん もちろんあります! 長文難問日本一を決める『PERSON OF THE YEAR 2018』という大会の決勝の1問目、「ブライアン・カーニハン」というプログラマーを答えさせる問題ですね。
――なるほど! どのような問題だったのか、気になります。
青松さん プログラミングの世界では、どんな教材であっても「“Hello, world!”という文字列を出すためのコードを書いてください」という課題が最初に書かれている。その伝統の創始者がカーニハンなんです。クイズ大会における1問目って、「最初」に関連する問題だったり、大会名を想起させる問題だったり、工夫が凝らされていることが多いんですけど、当時の問題選定の方は“Hello, world!”を持ってきたんです。演出としておしゃれですよね。その問題を答えてから波に乗って、準優勝することができました。

青松さん 実は大会の1年ほど前、自分が主催する大会の問題を作っているときにWikipediaで「Hello, world!」に関するページを見つけたんですよね。そこでカーニハンのことを知ったんです。「これ、めっちゃ面白い!」と思いました。
――対策が活きたというわけですね。
青松さん すごくこの問題が気に入ったので、自分の大会で出題したんです。“Hello, world!”を作ったプログラマーって、なんかロマンチックじゃないですか? だから、大会の決勝でカーニハンを答えた時、問題を出した人と自分の間で、何かが確かに通じ合った気がしました。それってほとんど、詩だと思うんですよ。問題を通して感受性が一致した瞬間のことは、今でも鮮明に覚えています。
次ページ:青松さんの描く「未来」はきっとこんな色
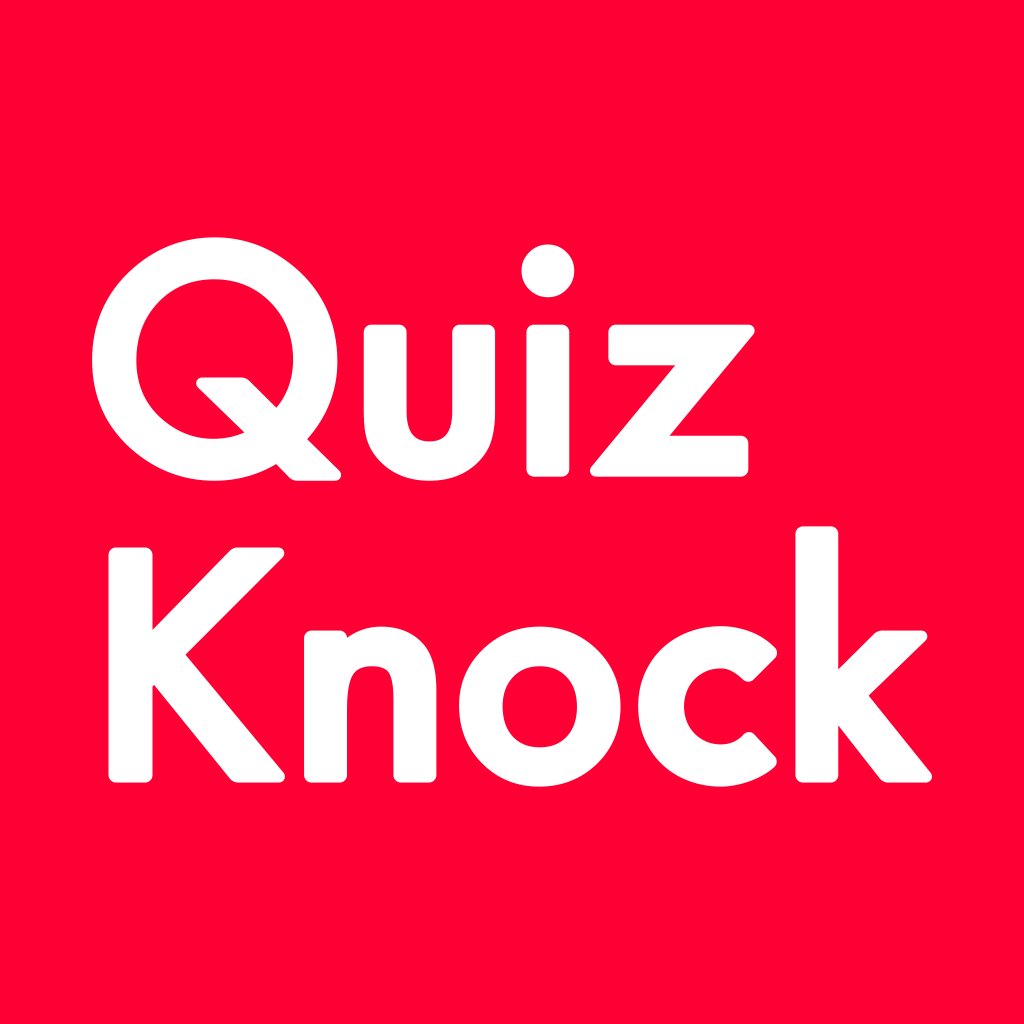



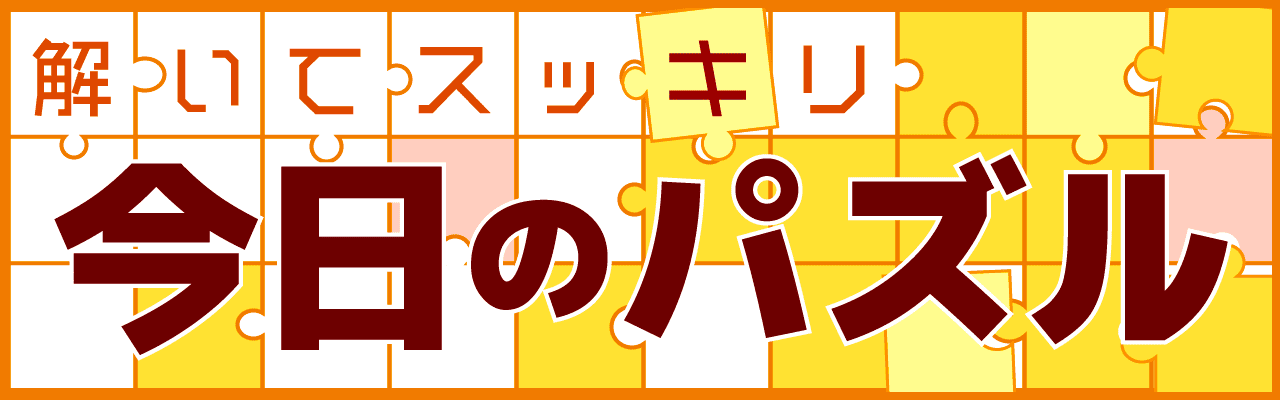
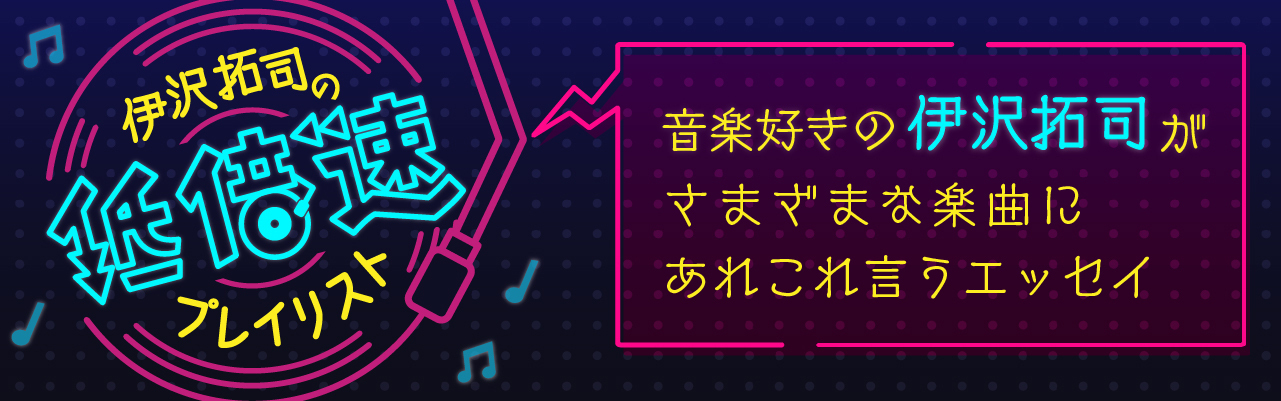

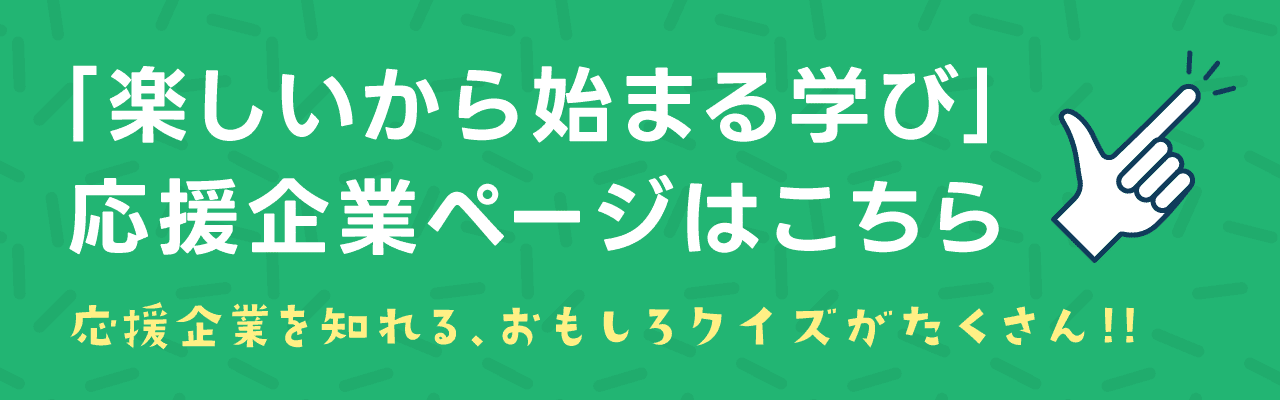



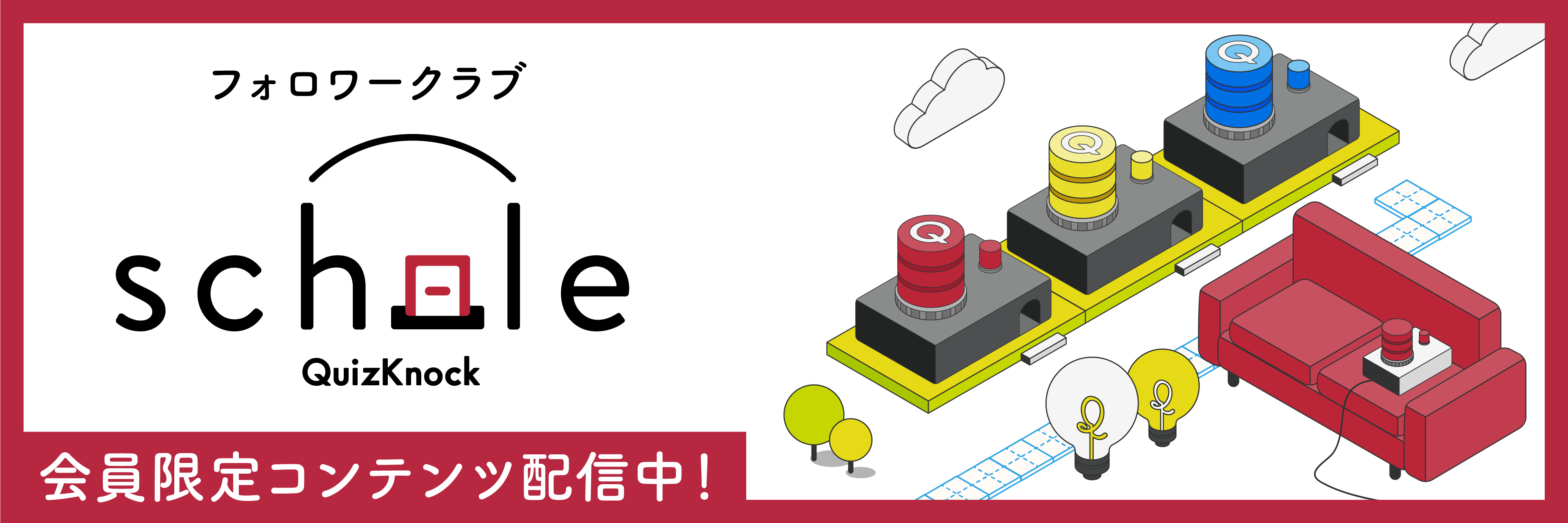




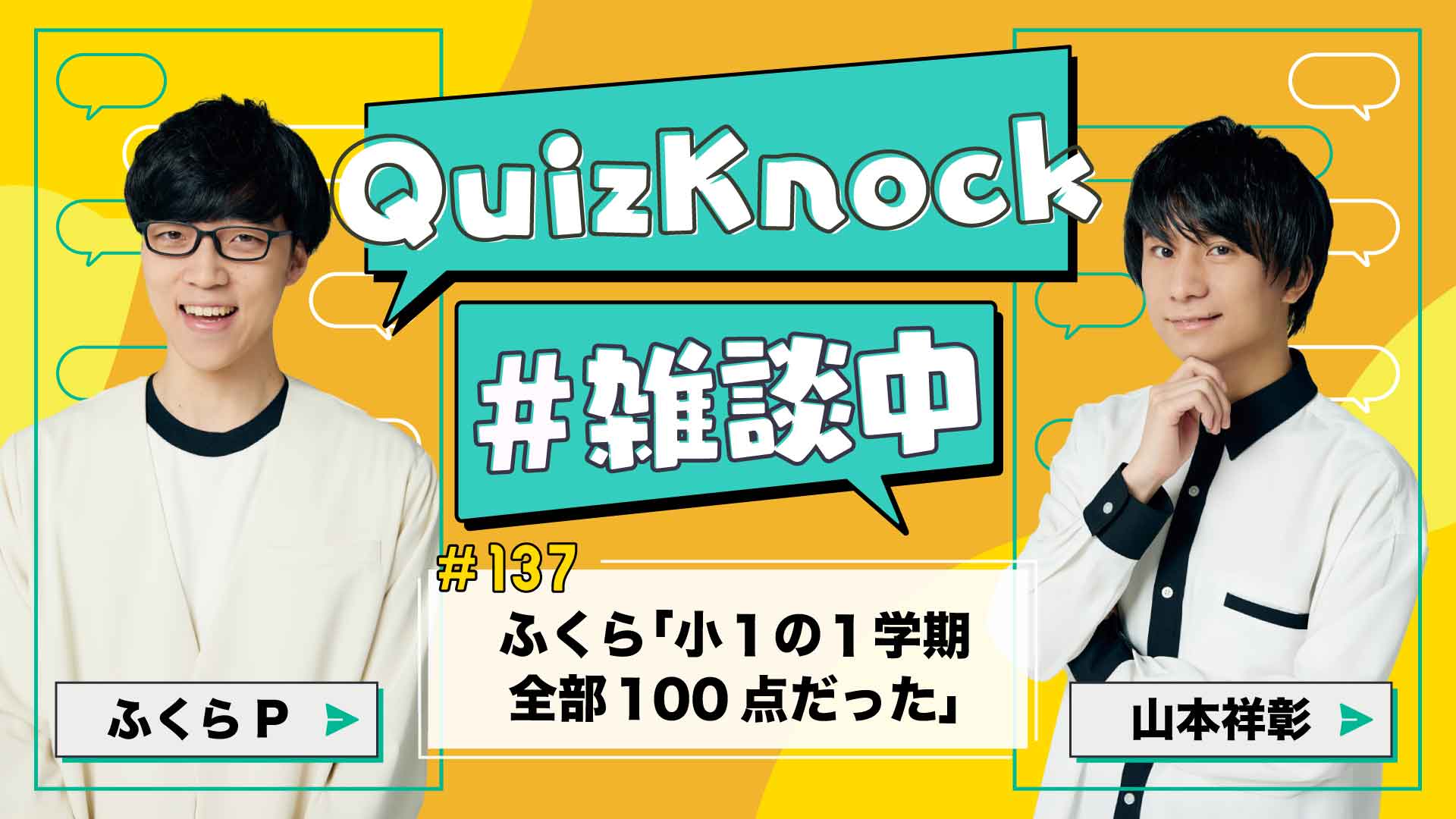

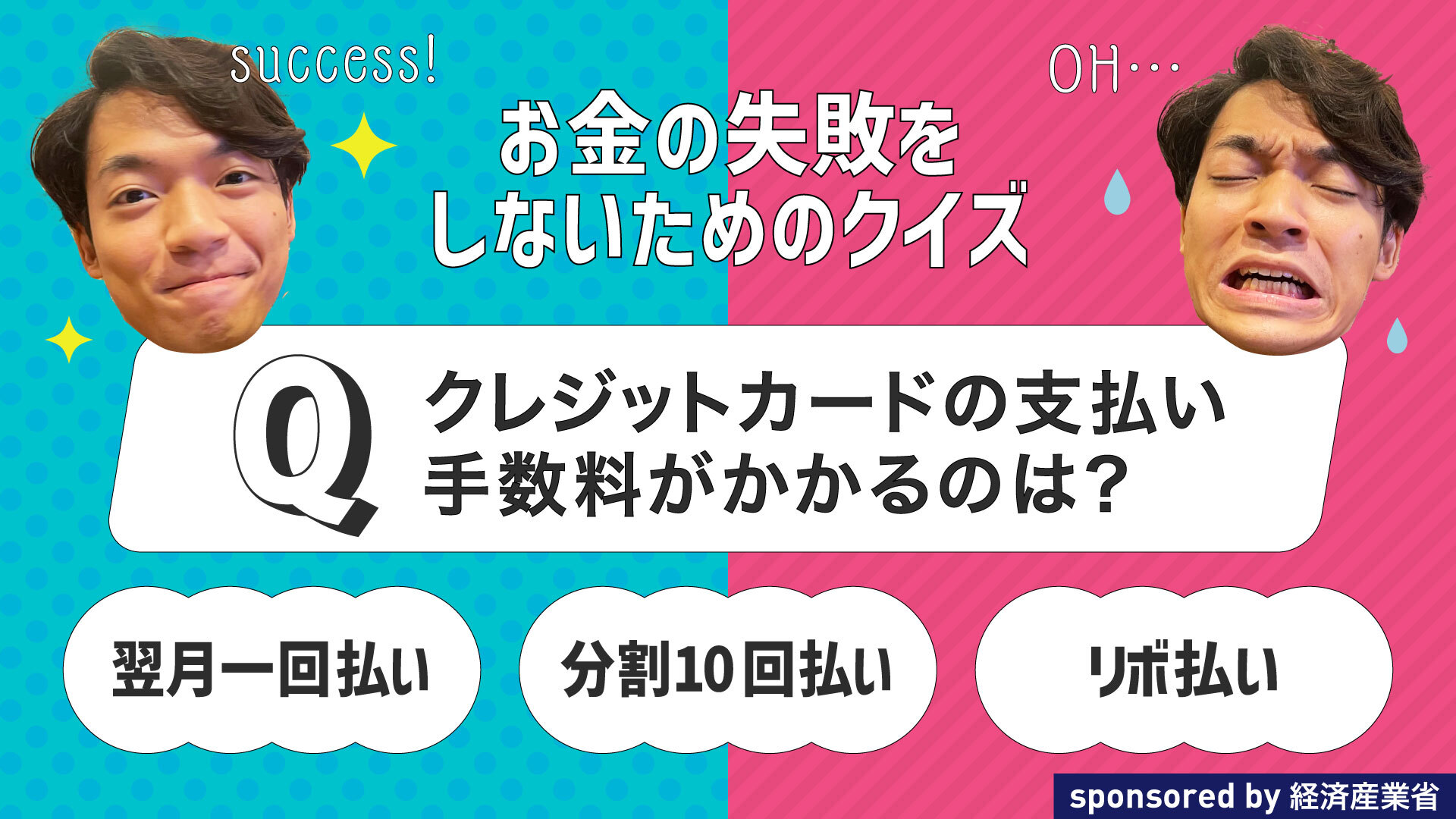
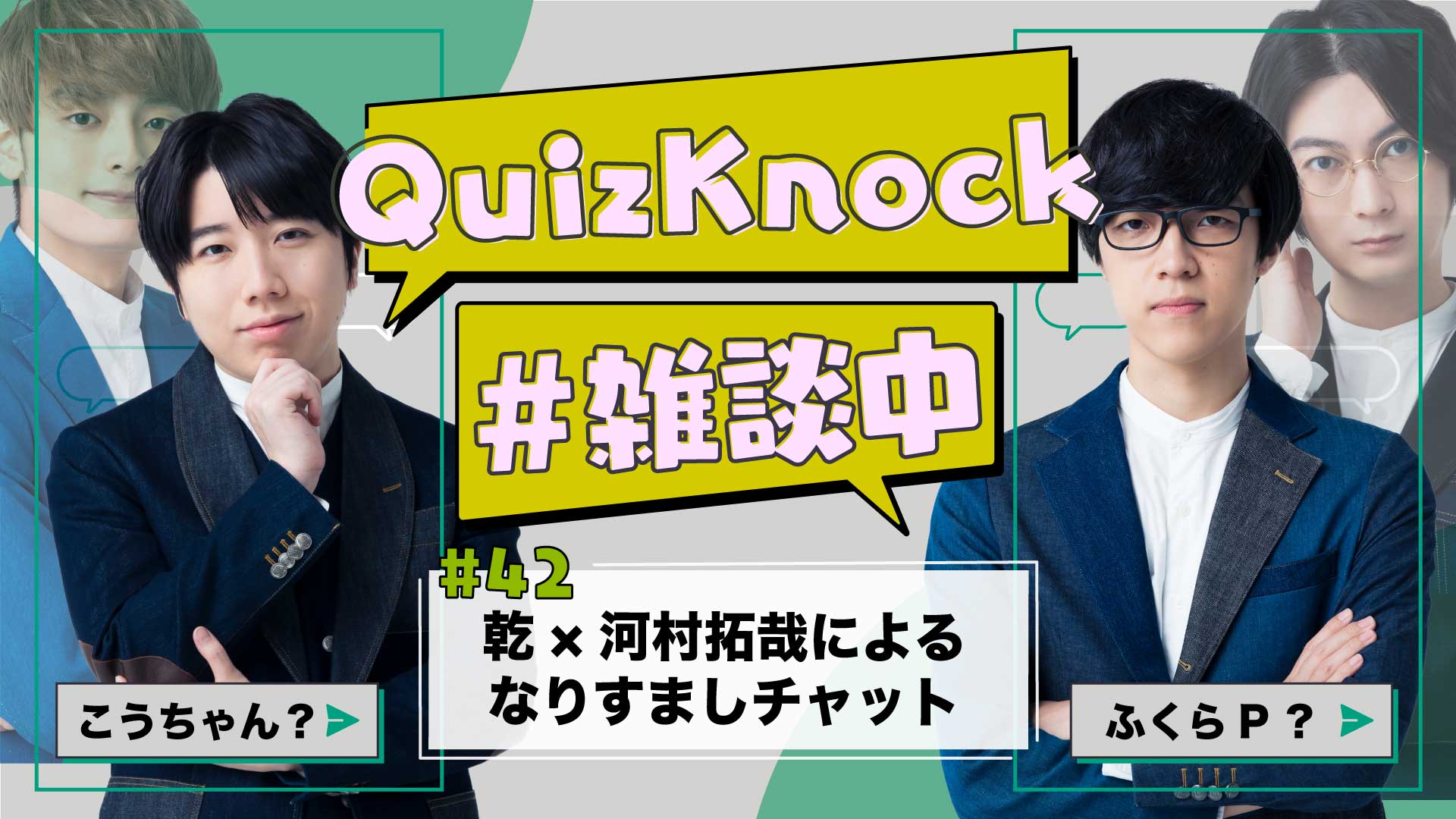


.jpg)