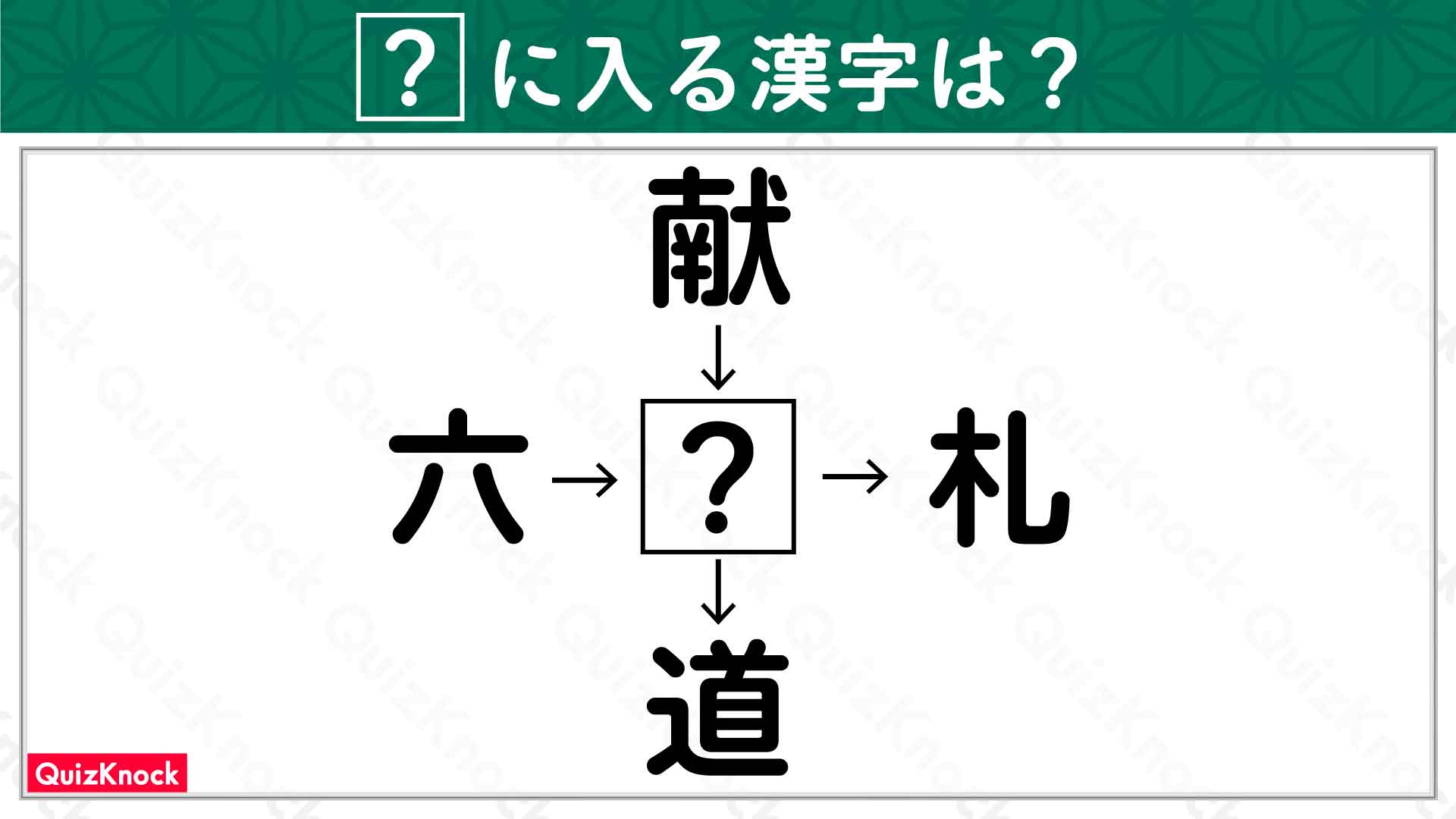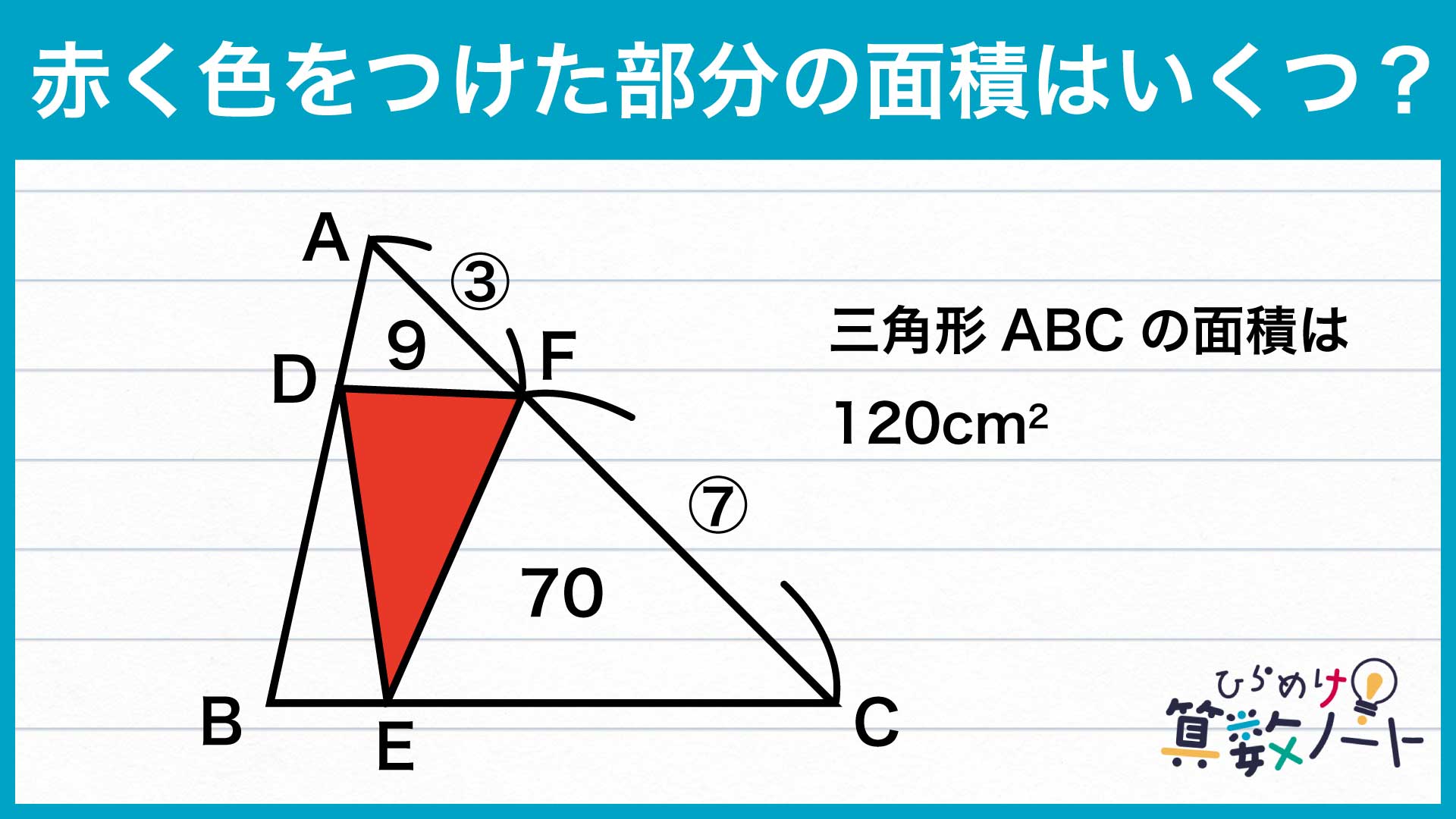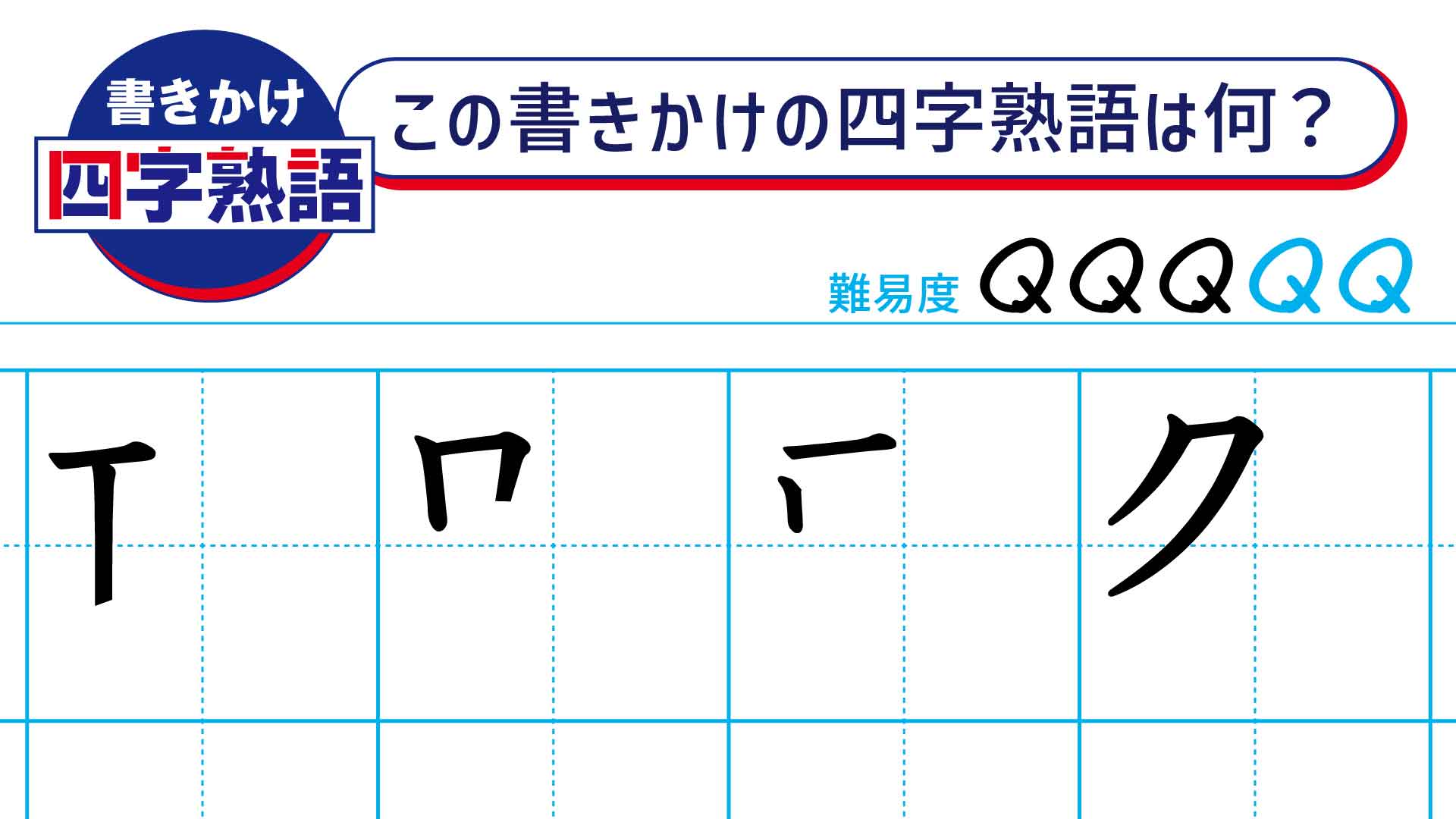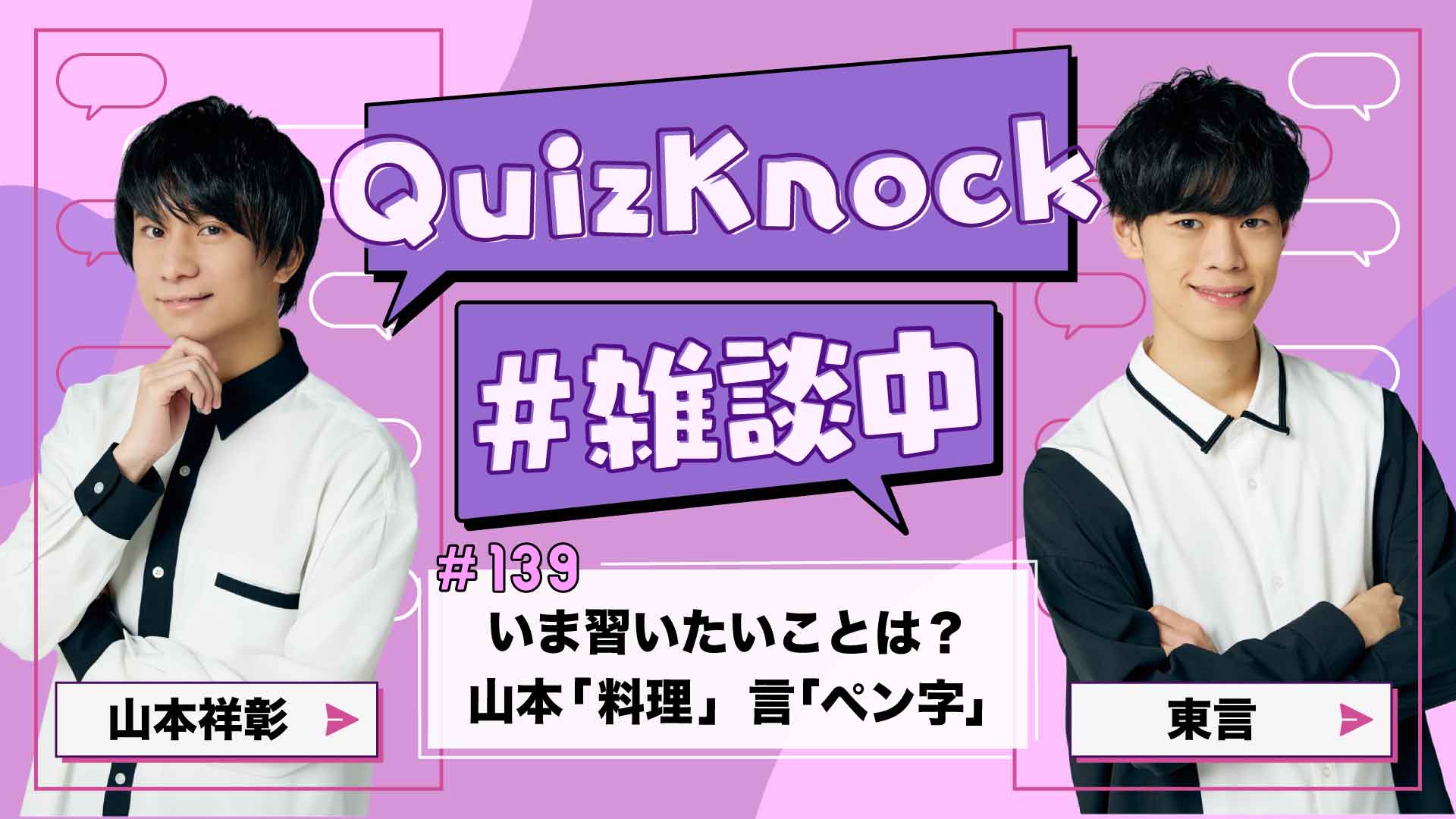こんにちは! アイヌ語大好きライターののせぴりかです。前回の記事を通して、アイヌ語を少しでも身近に感じていただけたでしょうか?
今回はアイヌ語、そしてアイヌ文化について前回よりもさらに踏み込んでお伝えしようと思います!
アイヌ語・アイヌ文化の魅力
さっそくですが、のせぴりか厳選、アイヌ語やアイヌ文化の好きなところを3個紹介させてください。
その1:アイヌ語の音や響きが落ち着く
私が思うアイヌ語の魅力、一番がこれです。百聞は一見にしかず! 早速聴いてみましょう!
▲優しく諭されるような響きをお楽しみください
最初は抑揚が日本語と全く異なるのに少し戸惑うかもしれませんが、どことなく心地よさがありませんか? 日本語にはない落ち着きと歯切れのよさが実家のような安心感を与えてくれます。
その2:「カムイ」という信仰
アイヌの人々は、「人々に影響を及ぼす存在すべてにタマシイが宿っている」という考え方をし、そうしたものを「カムイ」(アイヌ語で「神さま」のような意味)と呼びます。クマなら「キムンカムイ」、キツネなら「チロンヌㇷ゚カムイ」のように、動物の名前には基本的に「カムイ」をつけて呼びますし、臼や杵、舟など、生き物以外の身の回りの道具もカムイとして扱われます。
この考え方の豊かさを存分に味わえるお話があるので、紹介します。
フクロウは高い木に止まって、村を見下ろしながらそっと人々の暮らしを見守っている存在です。
とある村の人々が飢饉に苦しんでいたのですが、その原因は村の人々が食べ物を粗末に扱っており、カムイが村の人々に恩恵を及ぼさなくなっていたからでした。フクロウはその事実に気づいていて、人々の夢の中に入り込んでその事実をさりげなく気づかせました。
人々はフクロウのおかげとはつゆ知らず、飢饉の原因を見つけ出し解消することができたのでした。
シマフクロウ神が自らをうたった謡「コンクワ」
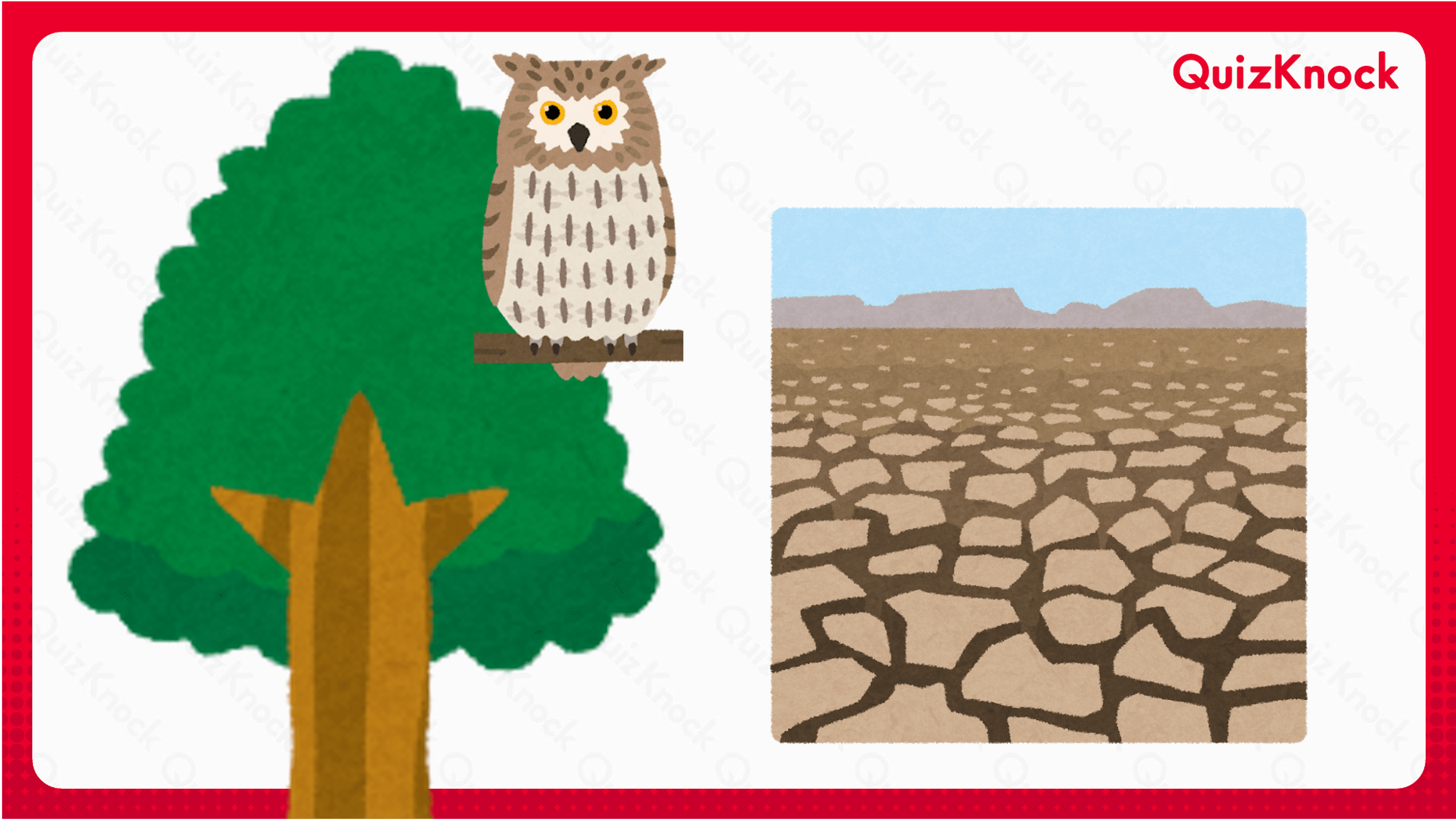
この村の人々は「自分たちの力で飢饉の原因に気づき、対処することができた」と考えたようですが、実は慈悲深く慎ましやかなフクロウの助けがなくてはうまくいかなかったでしょう。
アイヌ文化に限らずさまざまな文化圏で、「自分の努力や才能の成果に思えることも、実は周囲の支えあって成り立っているかもしれない」という教訓は大切にされています。しかし、これほど説得力のある説話を、私はアイヌ文化以外で目にしたことはありません。
その3:「アイヌ語翻訳」は自分自身を見つめ直すきっかけに
アイヌ語は話者の間でも日常生活の場で母語として用いられなくなってから長い年月が経っています。そのため、現代社会でよく用いられる概念を表す抽象的な単語が不足していることが多々あります。例えば「充電する」とか「印刷する」といった言葉に対応する単語がありません。
こういった場合、日本語の音を借用してそのまま挿入することもできはするのですが、私はできるだけもともとあるアイヌ語を使って表現したくなってしまいます。このときの「日本語をアイヌ語に翻訳する」という作業が、自分が普段何気なく使っている言葉を分解して掘り下げ、考える絶好の機会に思えるのです。
実際、私がアイヌ語の弁論大会「イタカンロー」に出場する際にアイヌ語の原稿を作ったときは、「研究する」という単語をアイヌ語に翻訳する必要がありました。
▲イタカンローにて発表する私
みなさんなら、どのように訳すでしょうか? 「研究」の対象やその手法によって、人それぞれの解釈が生まれそうです。
生物学の研究室に所属している私にとっての「研究」は、さまざまな実験に基づいてタンパク質の働きを可視化したり想像したりすることでした。そこで、これを念頭に置いて、
「ピㇼカノ(きちんと=科学的に厳密に)クヌカㇻ(わたしが・〜をよく見て調べる)」
と訳してみました。少々荒削りですが、自分が研究生活の中で普段どんな作業をしているか、そして何を目指しているかについて見つめ直すきっかけになりました。
アイヌ語という言語の特性、言ってしまえばある種の不自由さは、日頃の生活を振り返る良いきっかけになっています。
同じ日本という国に、自分が育ってきた文化と違う文化が存在し、それがこんなにも素敵だなんて、私は自分がアイヌ語に出会わなければ想像すらしなかったと思うのです。
アイヌ語に迫るピンチとは
アイヌ語やアイヌ文化の魅力、みなさんに伝わったでしょうか。ところが、そんなアイヌ語は近年、大きな問題を抱えているのです。
次ページ:危機に瀕しているアイヌ語に思うこと









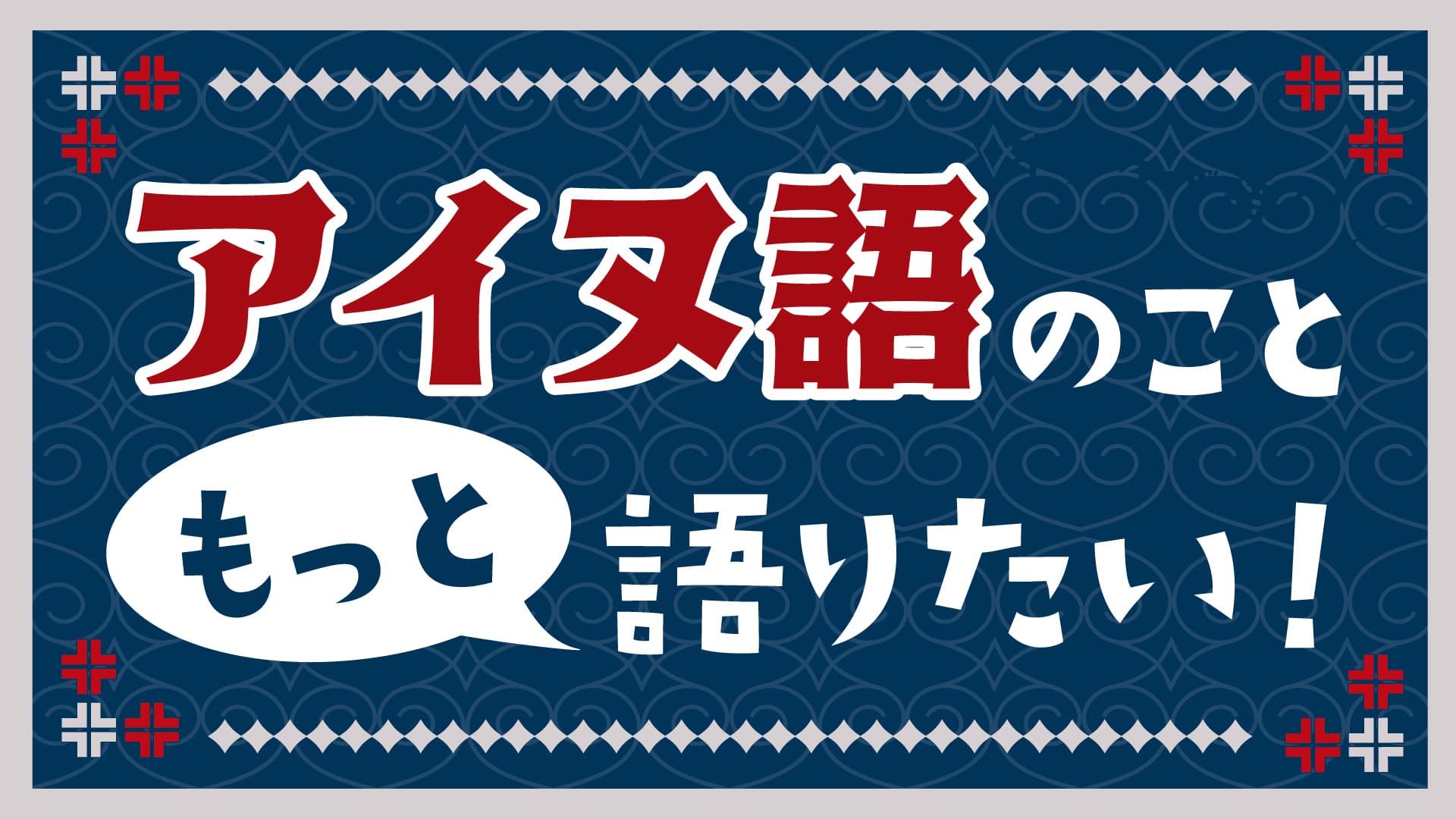



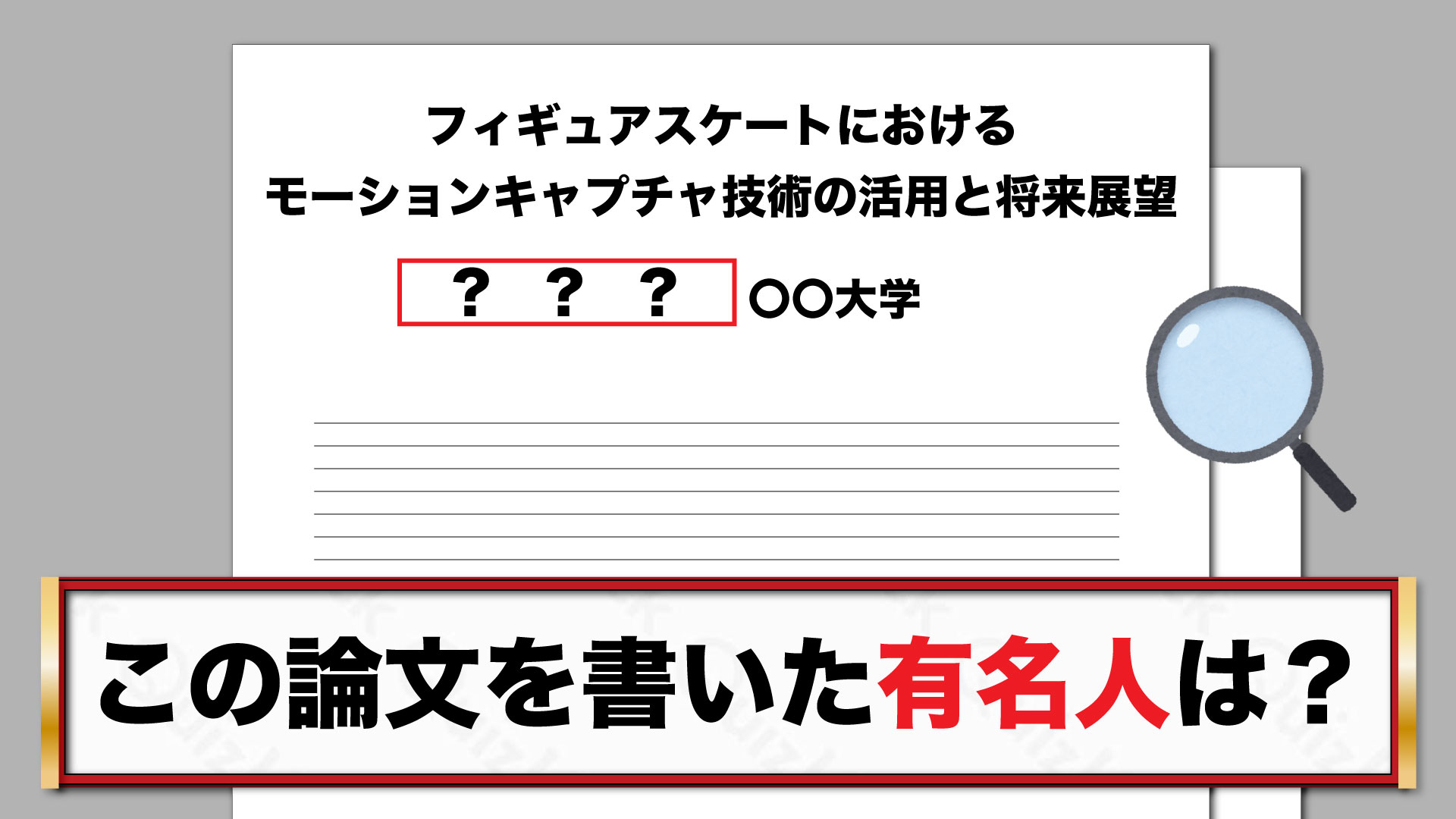




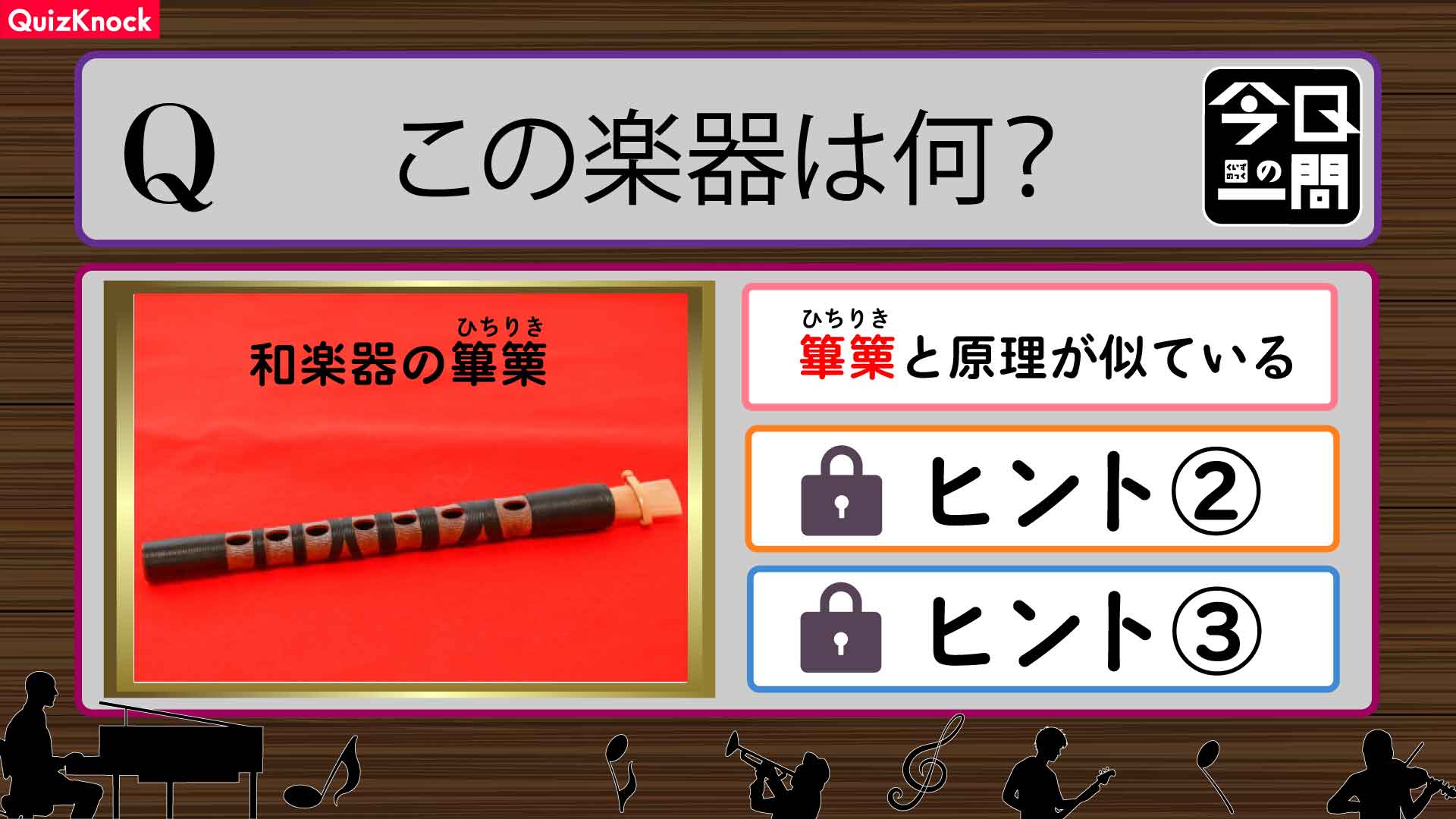

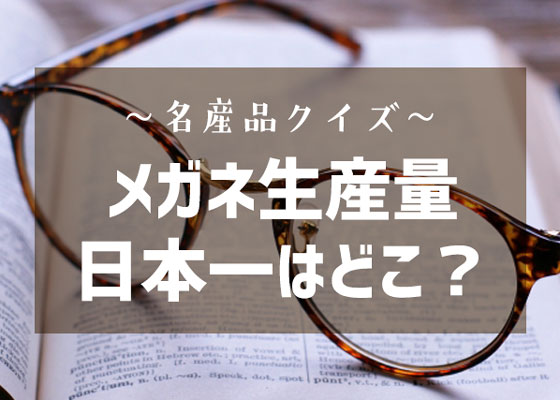

.jpg)