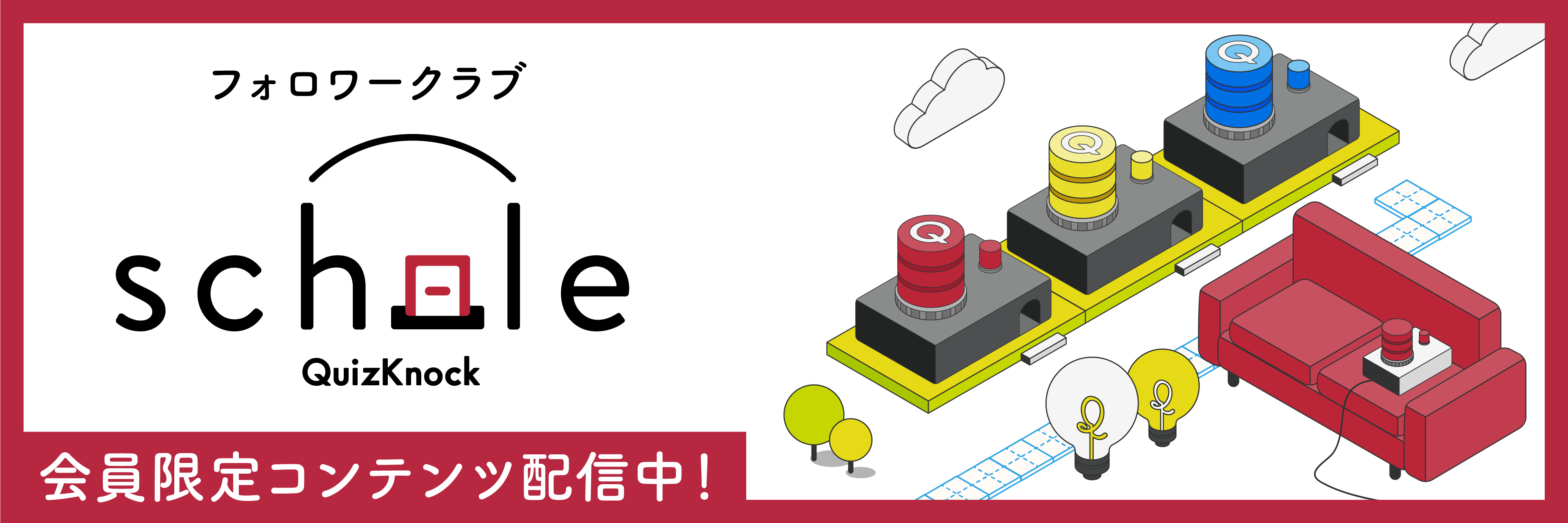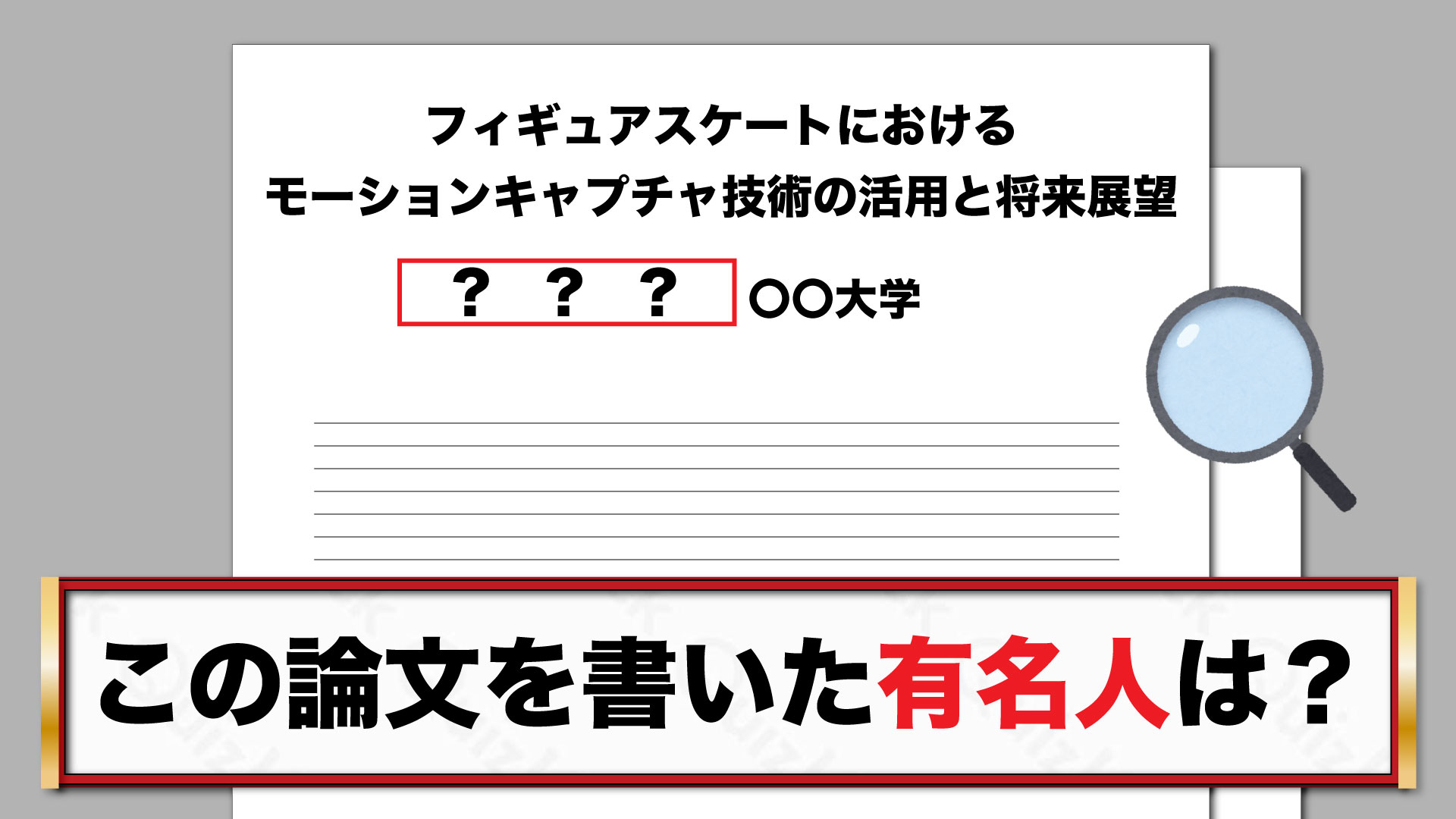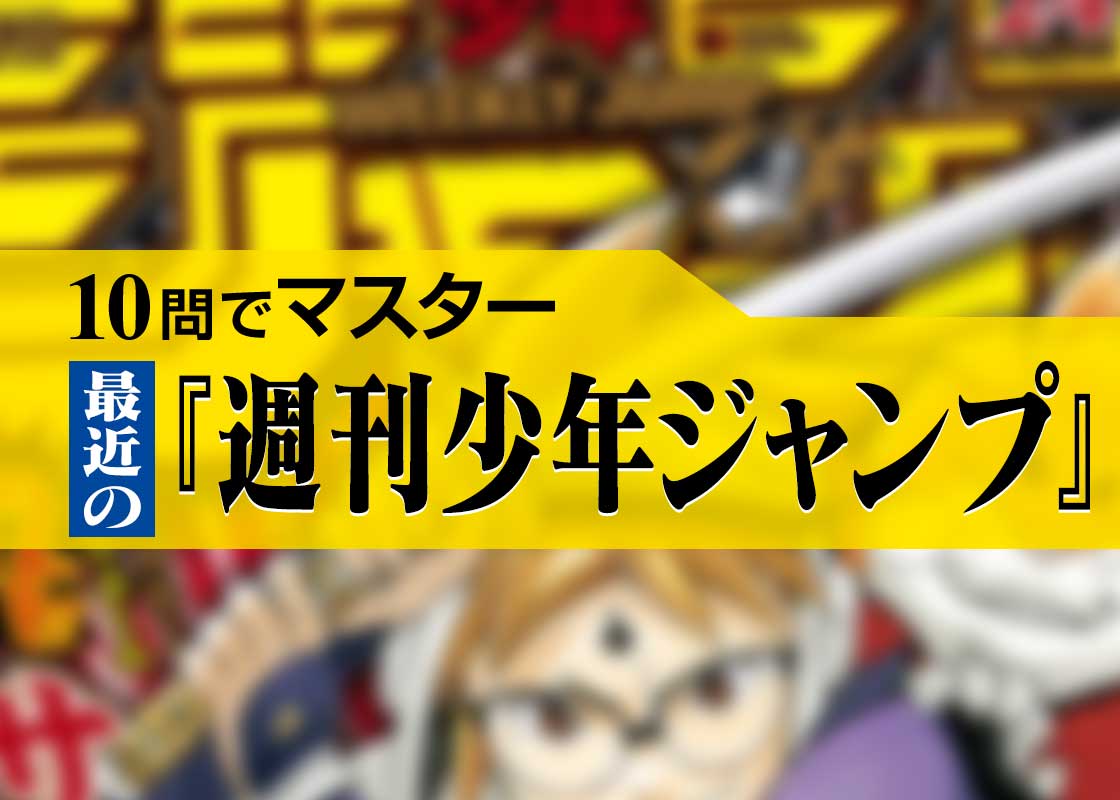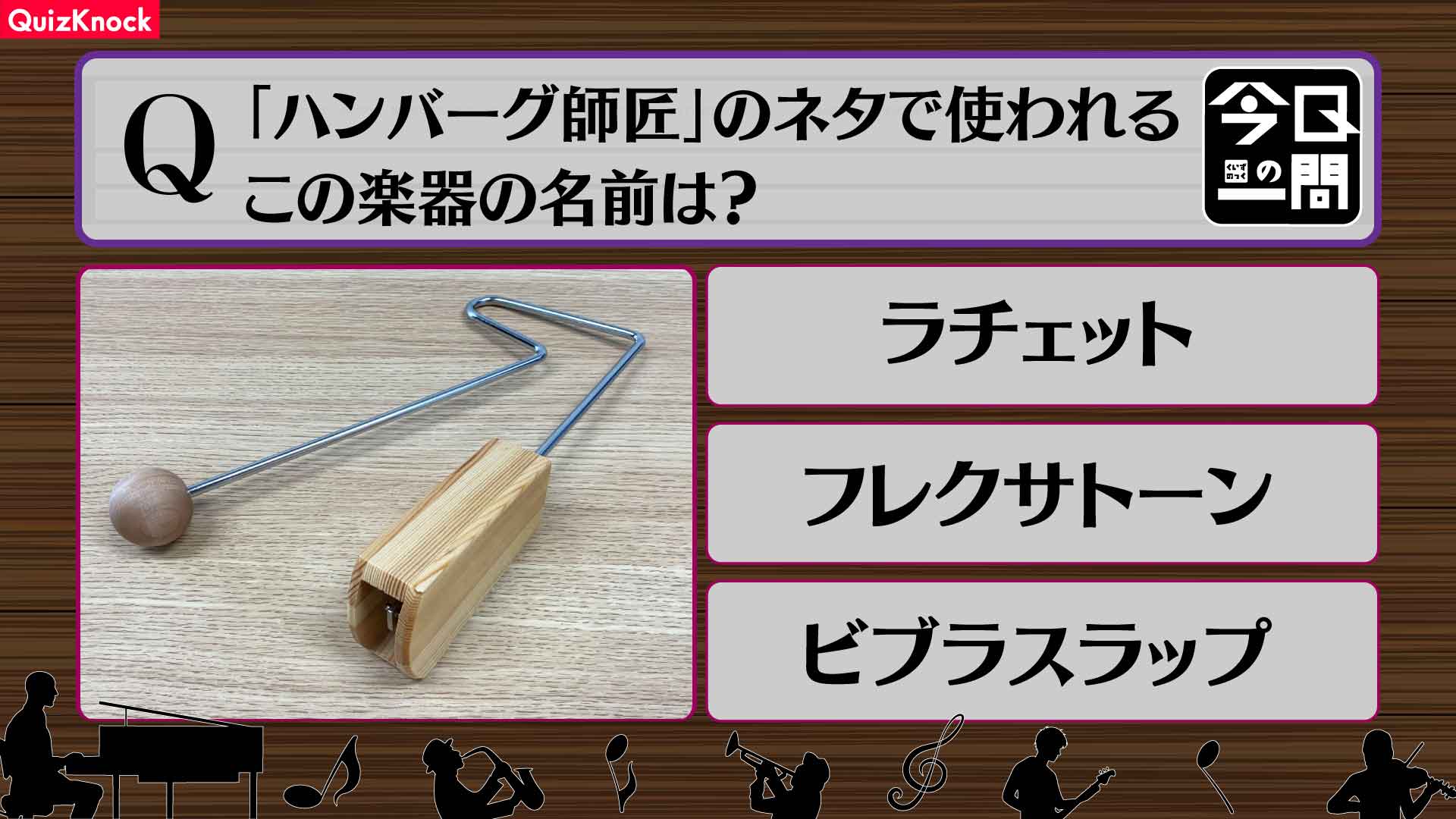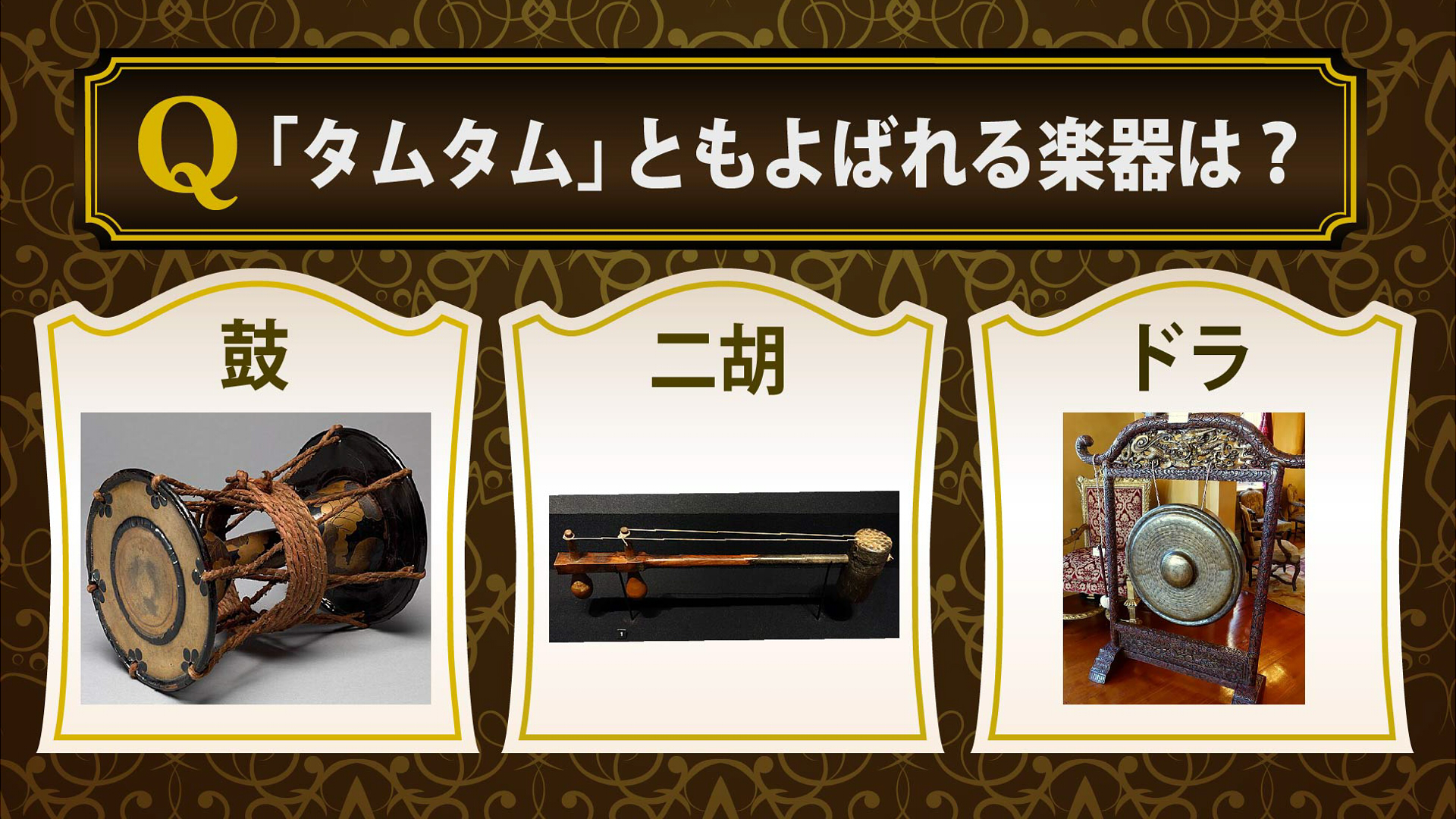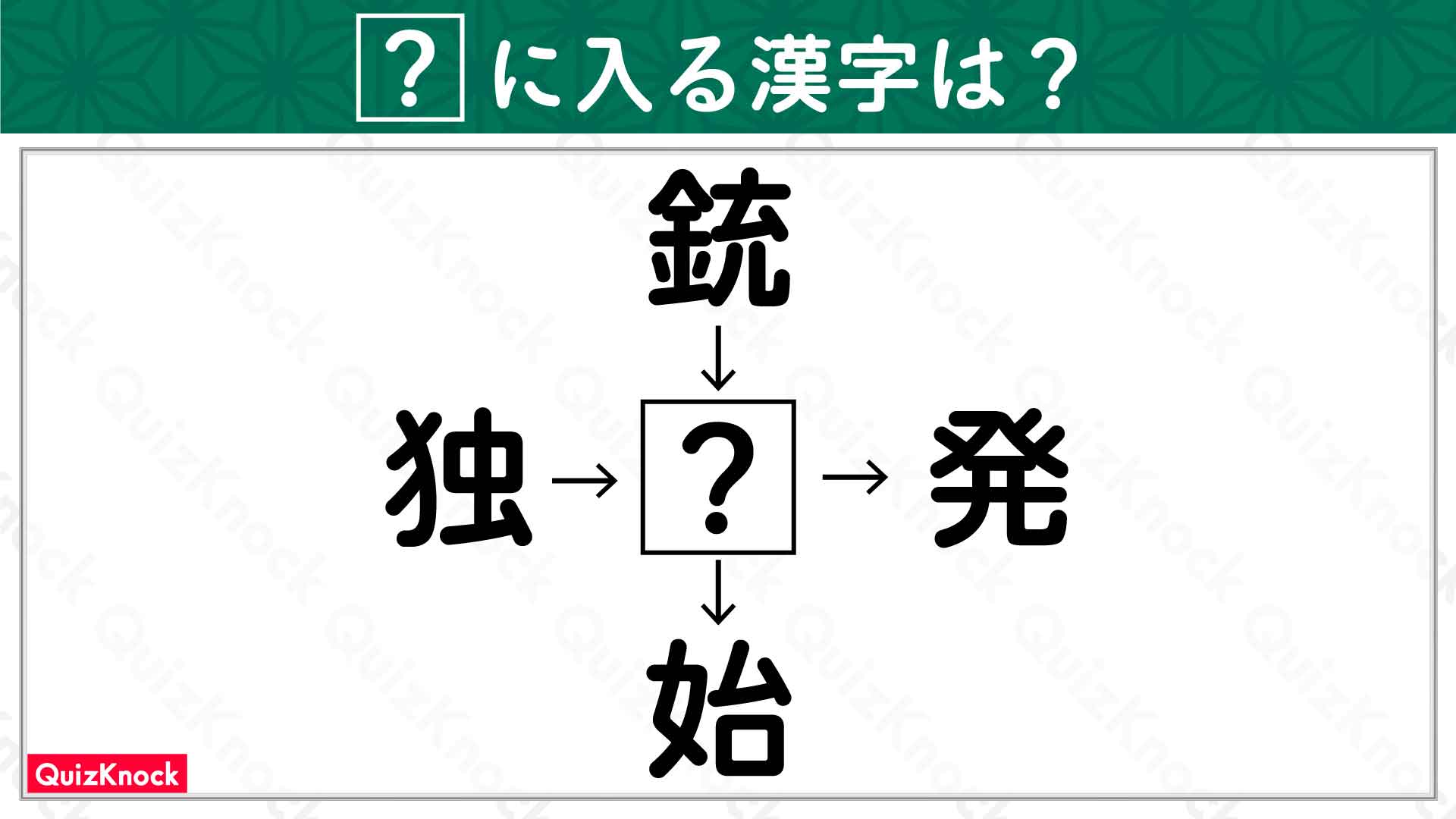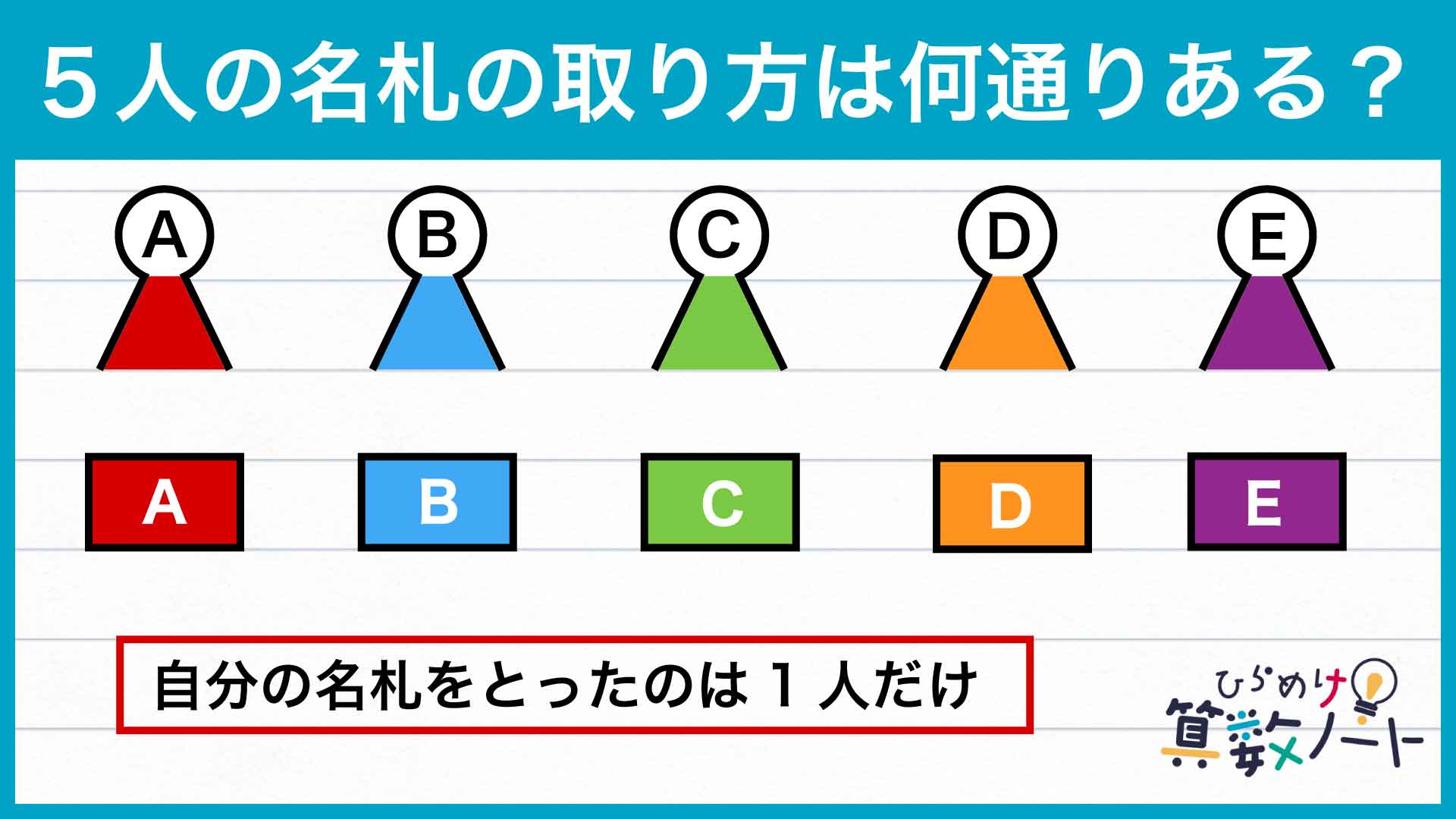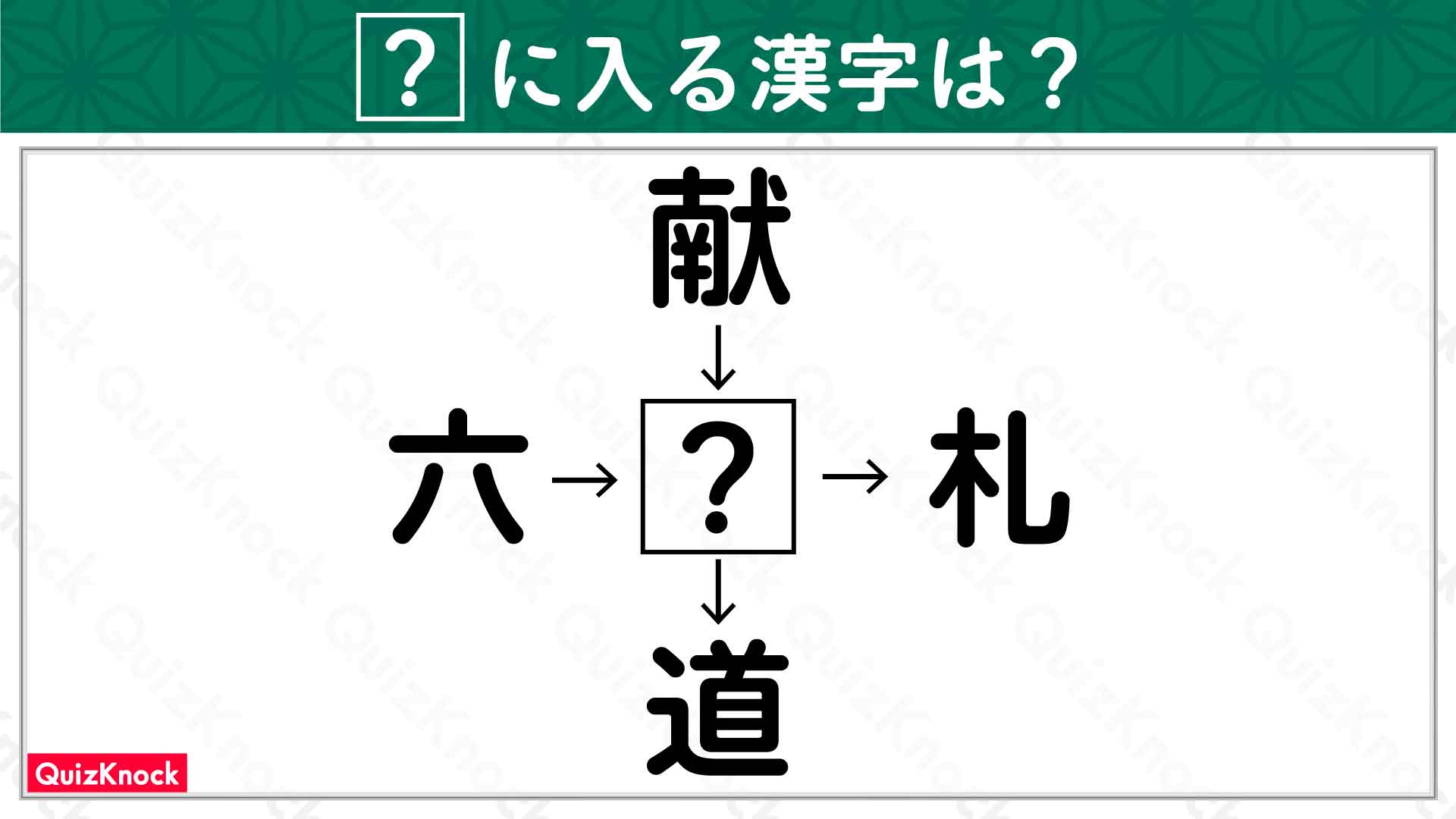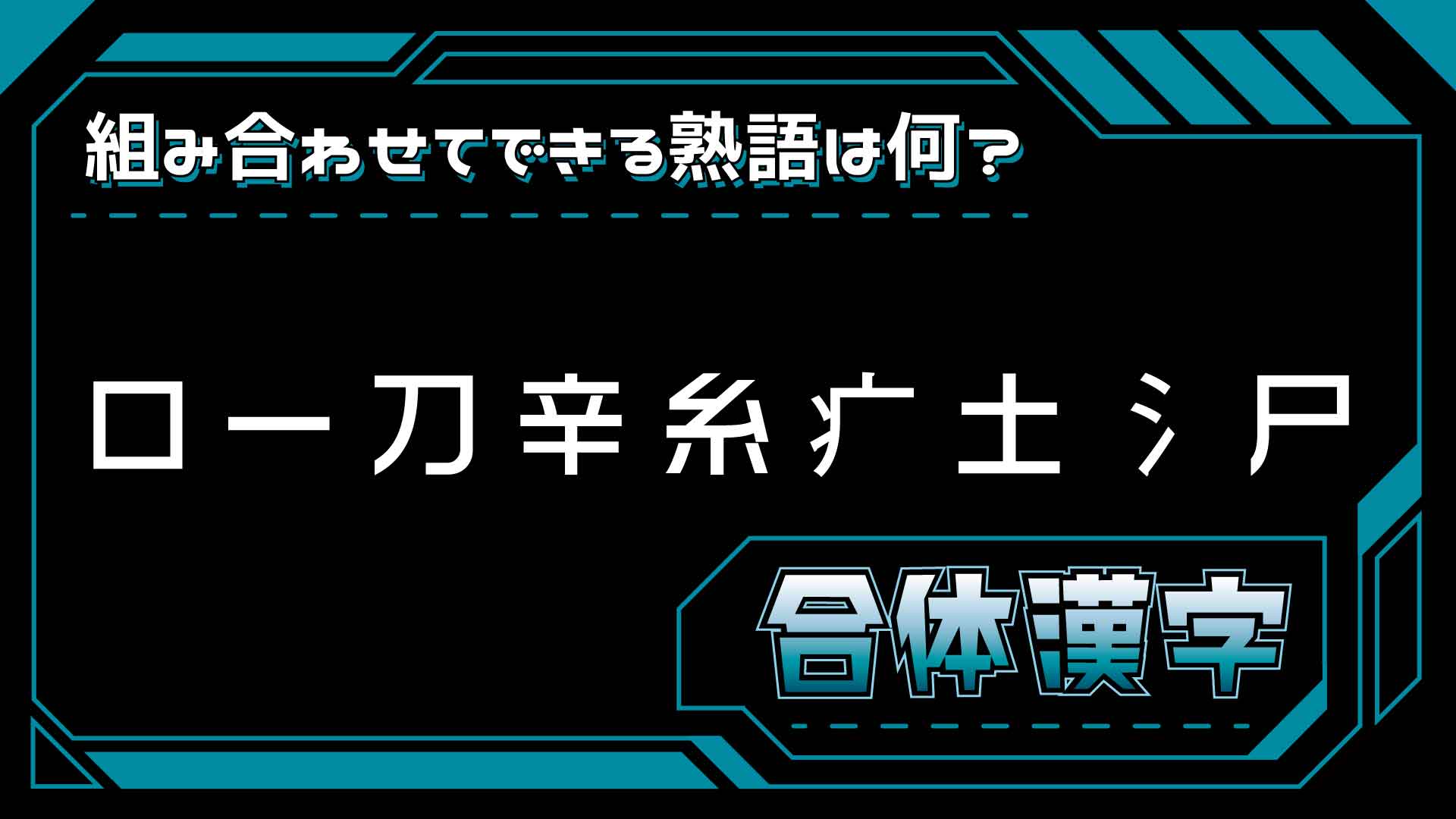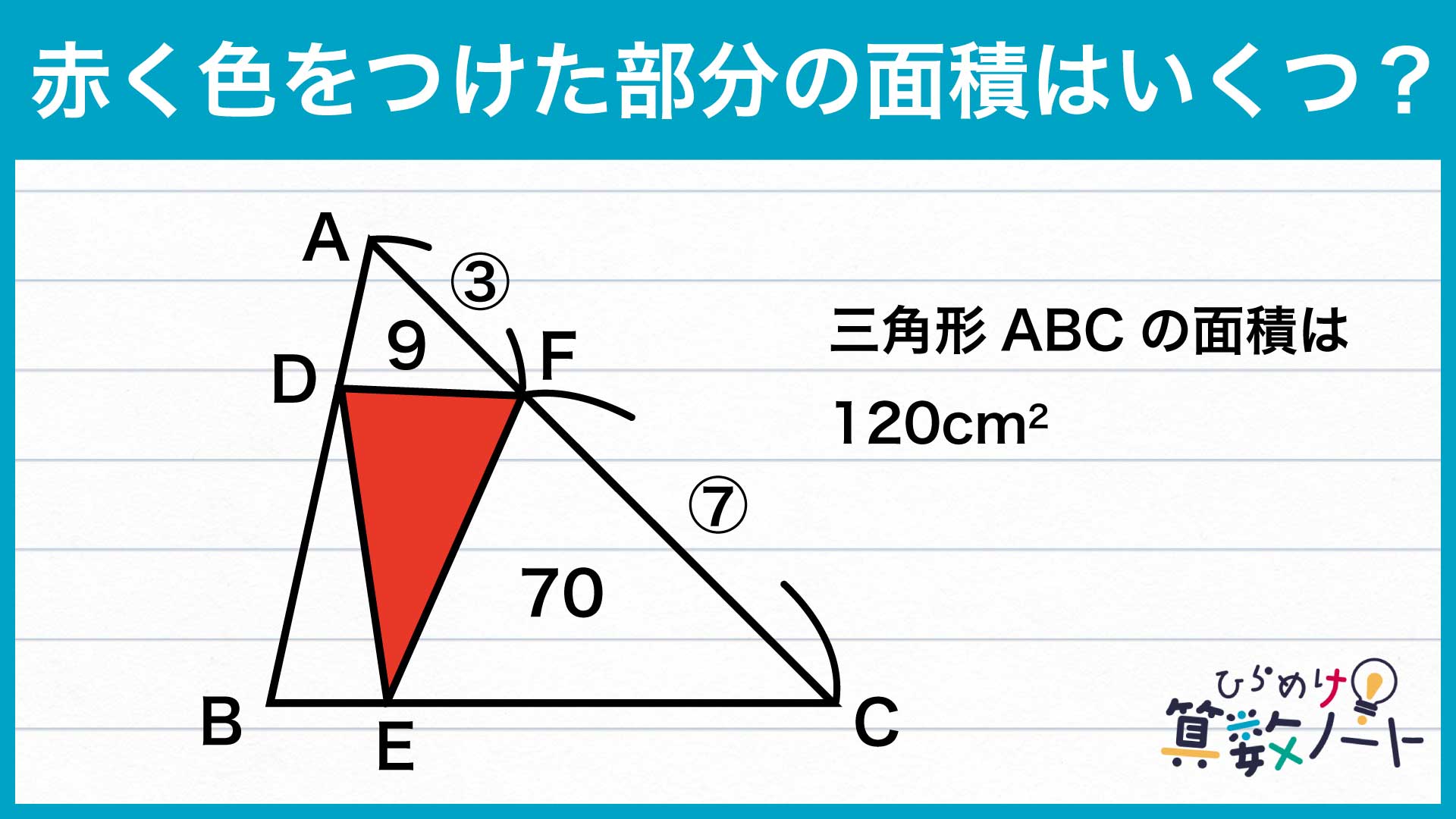こんにちは。京都在住ライターの松林 陸です。
8月16日の夜、京都の山々には巨大な火の文字が浮かび上がります。伝統行事の「五山送り火」です。
なかでも有名な「大文字」は、地元在住でなくてもテレビ等のメディアを通じて見たことがある方が多いのではないでしょうか。幅90メートルを超える炎の文字は、およそ30分間、京都の街をあかあかと照らします。

そんな「送り火」、そもそもなぜ「山に火で文字を描く」という行事が生まれたのでしょうか? また、なぜ「大」の字が灯されるようになったのでしょうか。
「五山送り火」の由来
はっきりした記録は残っていませんが、五山送り火の起源は「精霊送り火」や「
「
【#潮音寺 「#万燈会」】
— 茨城県潮来市(公式) (@itako_city_offi) August 11, 2025
本日8月11日(月)の潮音寺 万燈会の様子です。
境内一面にローソクが灯され、 幻想的な雰囲気に包まれています。
万燈会は明日12日(火)も行われます。
時間は午後6時から午後10時までです。 pic.twitter.com/4iKzgIPuEk
▲万燈会のようす(こちらは茨城県のものです)
京都市内では、

この万燈会がさらに大規模になり、山腹に火を灯す形へと発展したのが「五山送り火」のはじまりとされています。
なぜ「大」の文字?
「大」の字の灯火が始まった時期やその由来についてもはっきりしませんが、有名な説には
◎真言宗の開祖・空海が始めた
◎室町時代に将軍・足利義政が子・
◎江戸時代に書道の名人として知られた
といったものがあります。
とくに有名なのは先にも触れた「大文字」ですが、「五山送り火」では「大」の文字が灯される大文字山を含めて、5つの山に6つの文字や絵が描かれます。
点火は8月16日の20時から5分おきに行われ、夏の夜空を荘厳な光で彩ります。
毎年8月16日の夜には、京都に足を運んでみてはいかがでしょう。
現地へ行くのが難しい方は、ライブ中継で楽しむこともできます。夏の夜のひととき、歴史ある送り火をぜひ眺めてみてください。
【あわせて読みたい】
【画像出典(画像を一部加工しています】
大文字:佐野宇久井 CC BY-SA 3.0
船形:佐野宇久井 CC BY-SA 3.0
妙法のうち「妙」:佐野宇久井 CC BY-SA 3.0
妙法のうち「法」:佐野宇久井 CC BY-SA 3.0
左大文字:佐野宇久井 CC BY-SA 3.0















.jpg)