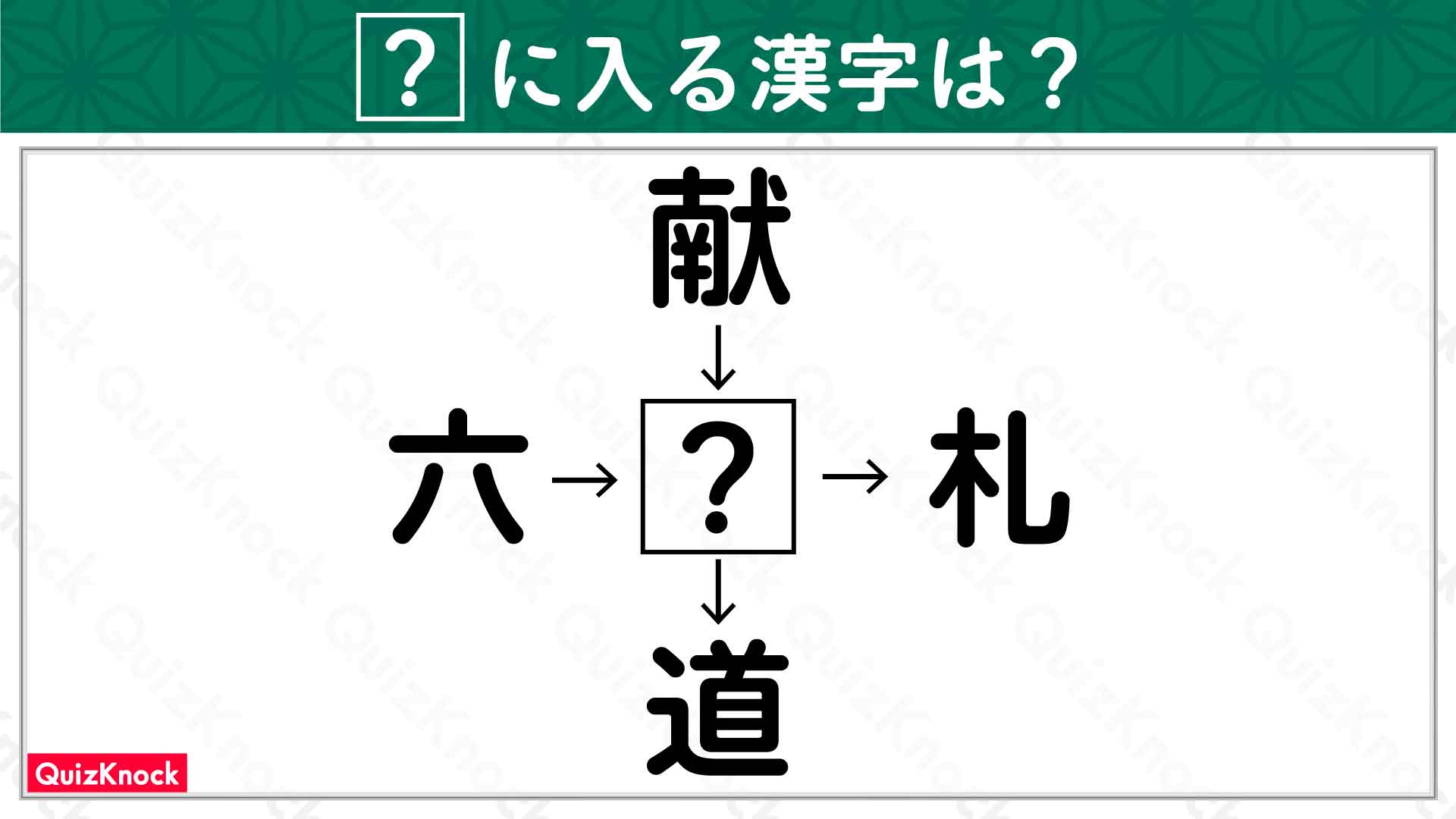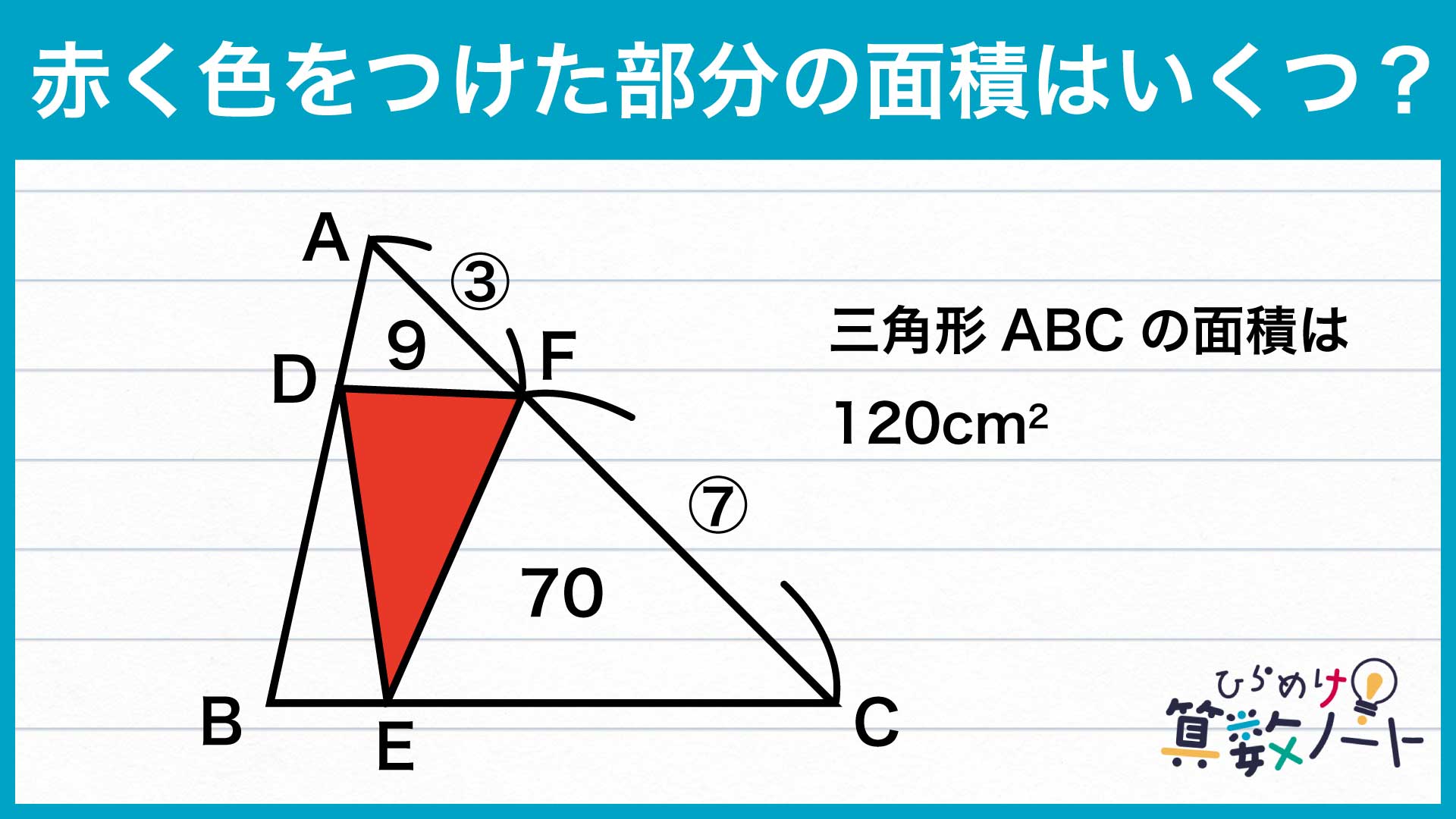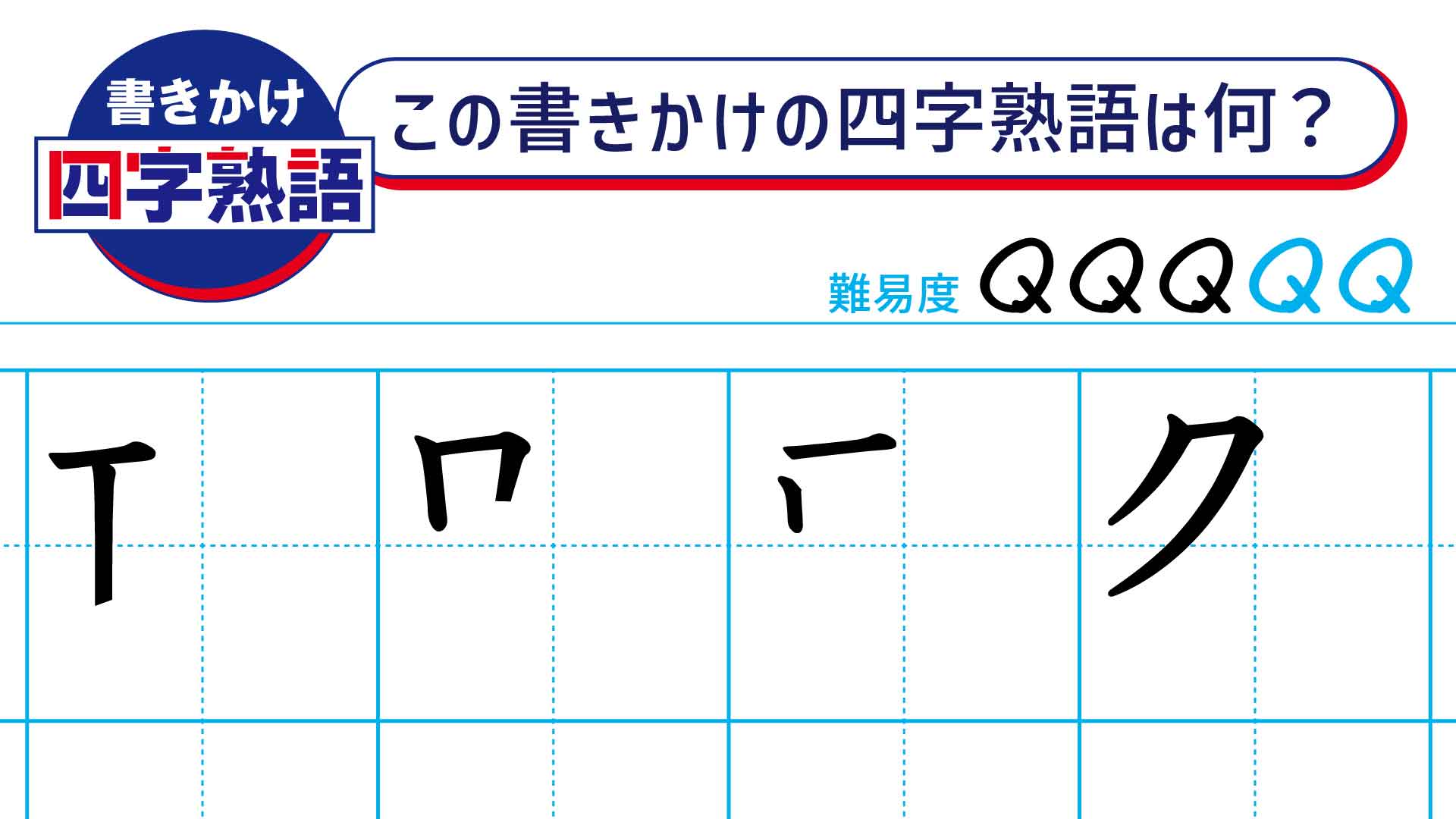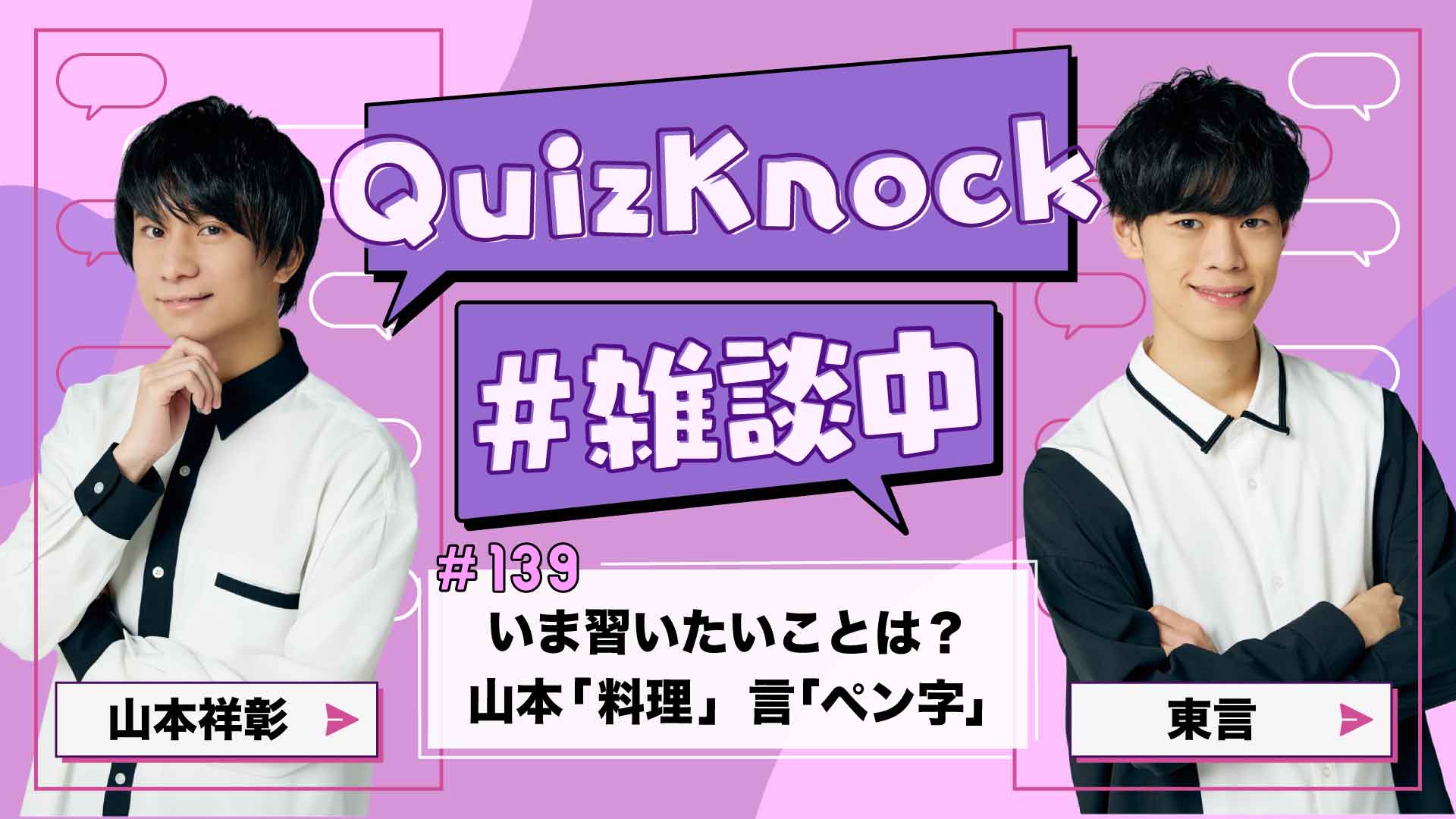* * *
「フィリピン」と聞いて多くの人が抱くイメージは、だいたいこんなところだろうか。
「これ以外に思いつかない」という方は、ぜひ続きを読んでいってほしい。実はフィリピンという国は今後数十年で急成長を遂げ、日本との距離もグッと近くなる……かもしれない、超注目の存在なのだ。
目次
フィリピンは「超・多文化の国」
まずフィリピンについて知ってほしいのは、アジアの中にありながら、非アジア的な文化が極めて色濃い国であるということ。
というのも、長きにわたりスペイン・アメリカという2つの大国の統治を受けてきたからだ。特にスペインの支配は300年に及び、そこかしこに影響がみられる。

そもそも「フィリピン」という国名がスペイン語由来だし(16世紀のフェリペ皇太子=後の皇帝・フェリペ2世から来ている)、国民のファミリーネームも「デラ・クルス」「ガルシア」などスペイン風のものが多い。公用語のタガログ語をはじめ、現地の言葉もスペイン語と似た単語がたくさんある。
料理に目を向けても、煮込み料理のアドボ・豚を一頭丸ごと焼き上げるレチョン(インパクトのある見た目なので画像検索は要注意)といった国民食は、スペイン統治時代にもたらされたものだ。

キリスト教の国
スペイン統治の歴史と関連するが、アジアでは珍しいキリスト教(カトリック)信者が大半を占める国であることも重要だ。街中で祈りを捧げている人をよく見かけるくらい、カトリックはフィリピンの生活に溶け込んでいる。

フィリピンは「アメリカンな国」
アメリカからの影響も無視できない。
19世紀末にアメリカとの「米西戦争」でスペインが敗れると、代わってアメリカがフィリピンを支配下に置くことになる。アメリカ流の政治・教育制度が導入された結果、フィリピンは一時1億人を超える人口の9割ほどが英語を話す国となった。このことは間違いなく現代フィリピンの国際的な競争力の礎となっている。

伝統文化がスペイン流なら、近代的な生活を形作ったのがアメリカだ。フィリピンの街を歩いてみれば、マクドナルドに大規模ショッピングモール……アメリカ的な大衆文化が隅々まで浸透している。肥満、糖尿病といった健康問題が取り沙汰されがちなのもアメリカそっくりだ。
フィリピンを代表するファストフードチェーン「ジョリビー」は30カ国以上に展開し(系列店を含む)、海外へ移住した人々の重要な働き口となっている。だいぶ脂っこいので日本人の口に合うかは微妙なところだが、いずれは日本へ出店、ということもあるかもしれない。
▼「ジョリビー」はマスコットも大人気
Jolliest birthday to the one who continues to inspire Filipinos with her heart and grit. ✨️ Have the best day, Queen Pia! #BidaBestBidaPinoy pic.twitter.com/1hi64ITust
— Bestfriend Jollibee (@Jollibee) September 26, 2025
フィリピンのあいさつ「もうごはん食べた?」
フィリピンの人々の強力なコミュニティ意識には驚くべきものがある。たとえば「フィエスタ」と呼ばれるお祭り文化。地域がひとつになり、ラテンなノリで思いっきり楽しむイベントだ。

多くは神に祈りを捧げる儀式としても行われるので、ここにも先述のスペイン統治時代の影響が現れている。
フィリピンならではのあいさつ
さらに面白いのが、「Kumain ka na ba?/Did you eat yet?」(タガログ語※/英語で「もうごはんは食べた?」)という挨拶だ。「やあ」とか「こんばんは」みたいな意味で使われているのだが、「ごはん食べた?」が挨拶になっちゃうくらい「みんなでごはんを食べる」という意識が強いことが見てとれる。
「ウタン・ナ・ローブ(utang na loob)」という恩返しの精神もフィリピンならでは。「受けた恩は決して忘れない」「恩は必ず返す」という強い観念が、家族や地域社会に根付いている。一見ステキな話に思えるが、時に不必要なしがらみを生む要因にもなっており、良くも悪くもフィリピンらしい習慣だ。
フィリピンはずっと「のびしろの国」
ほかにも韓国ドラマが大人気で、「フィリピン版」のリメイクが次から次へと制作されている……なんて情報もある。当たり前だが、アジアの国らしい特徴もちゃんと備えているのだ。
不安定な側面はありつつも、文化は多様で活気があるし、英語の能力も高い……ここまで見ていくと豊かな国のように思えるが、実際のフィリピンは経済格差・貧困にあえぐ、いわば「一生のびしろの国」とも言える状態が続いている。これは一体どういうわけなのか?
次ページ:フィリピンの「苦しみ」の正体、そして未来
※(2025年11月6日13:00 お詫び)記事掲載当初、「タガログ語」とすべき箇所を「スペイン語」と記載しておりました。お詫びして訂正いたします。













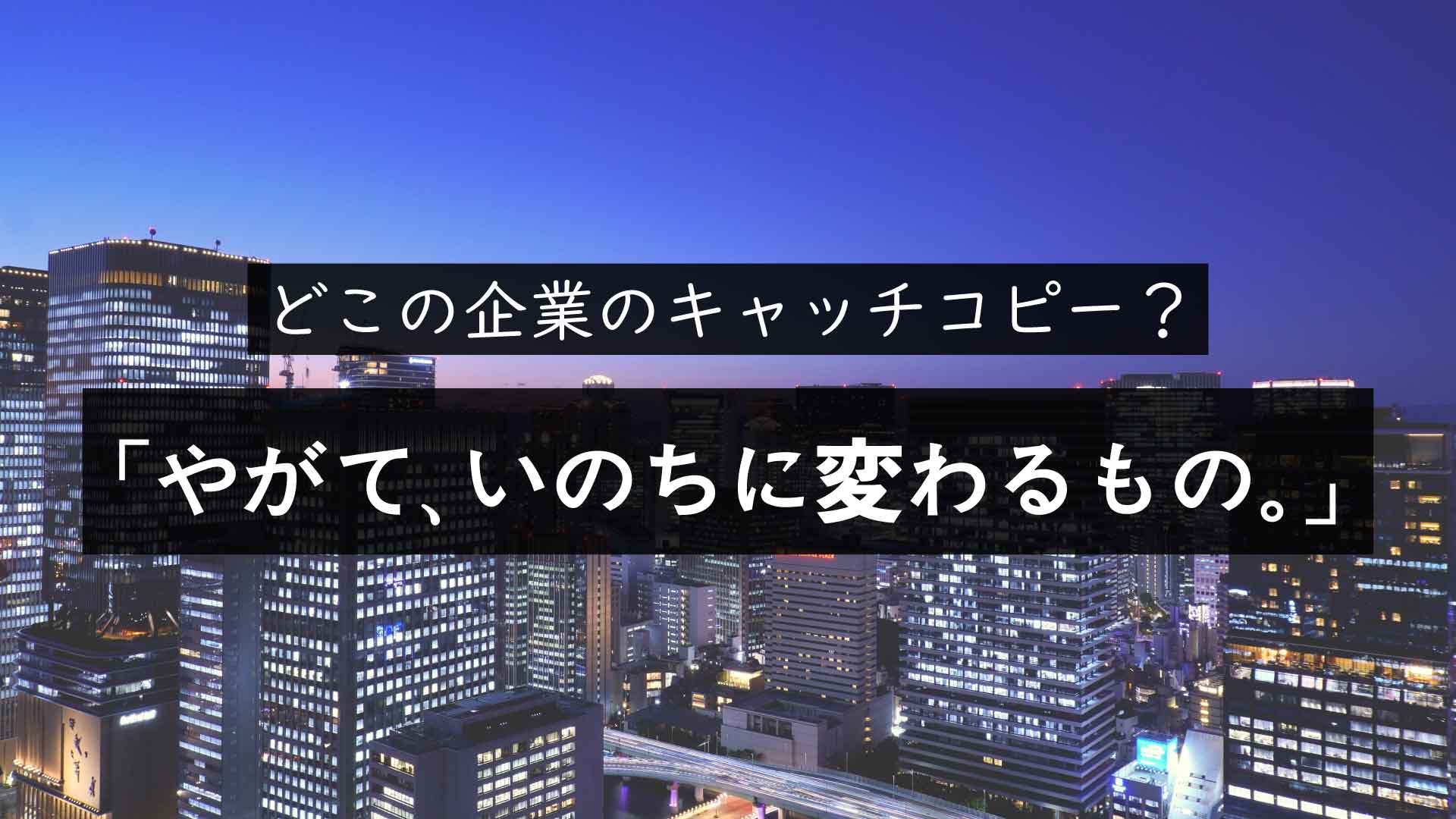

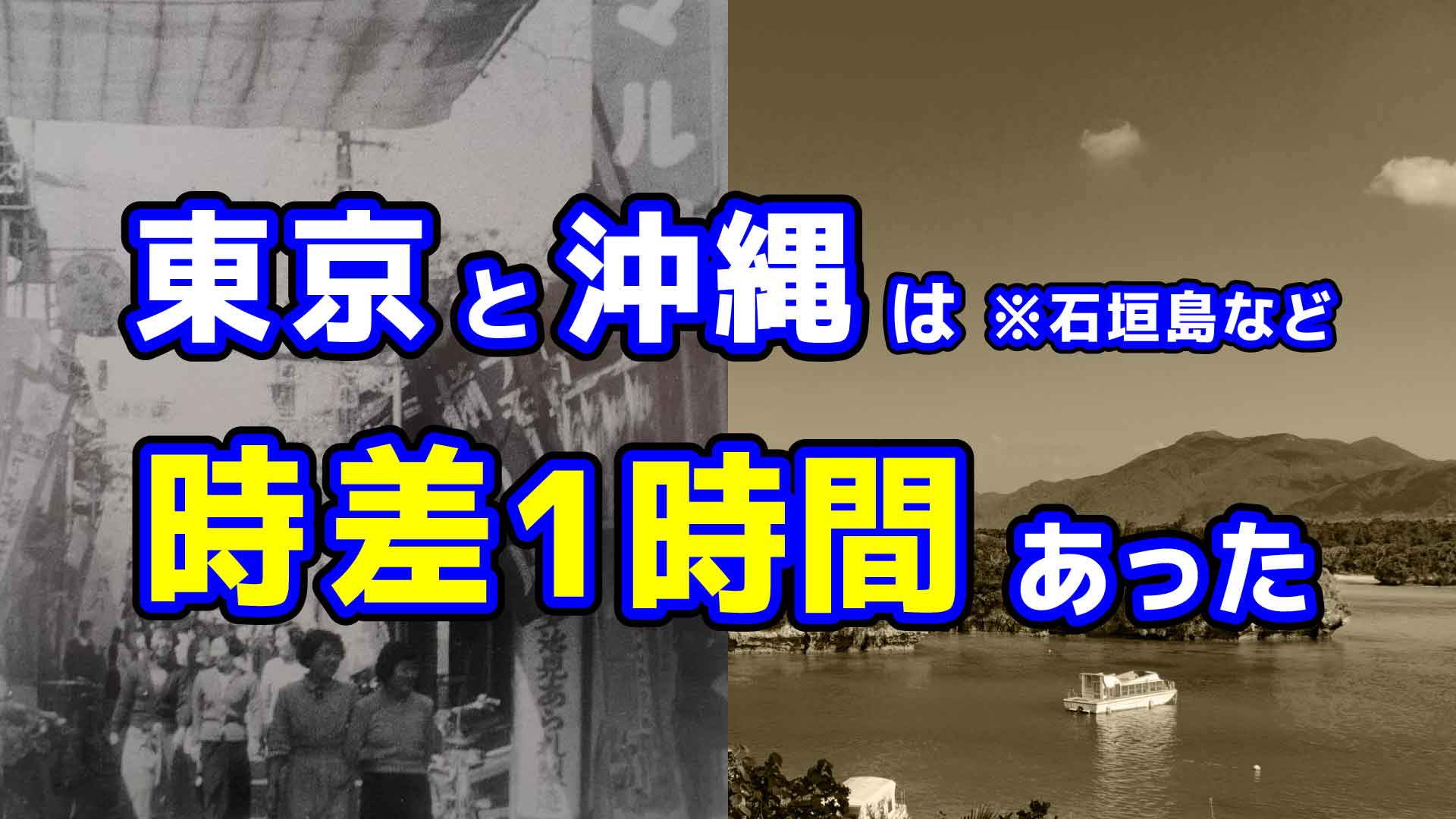
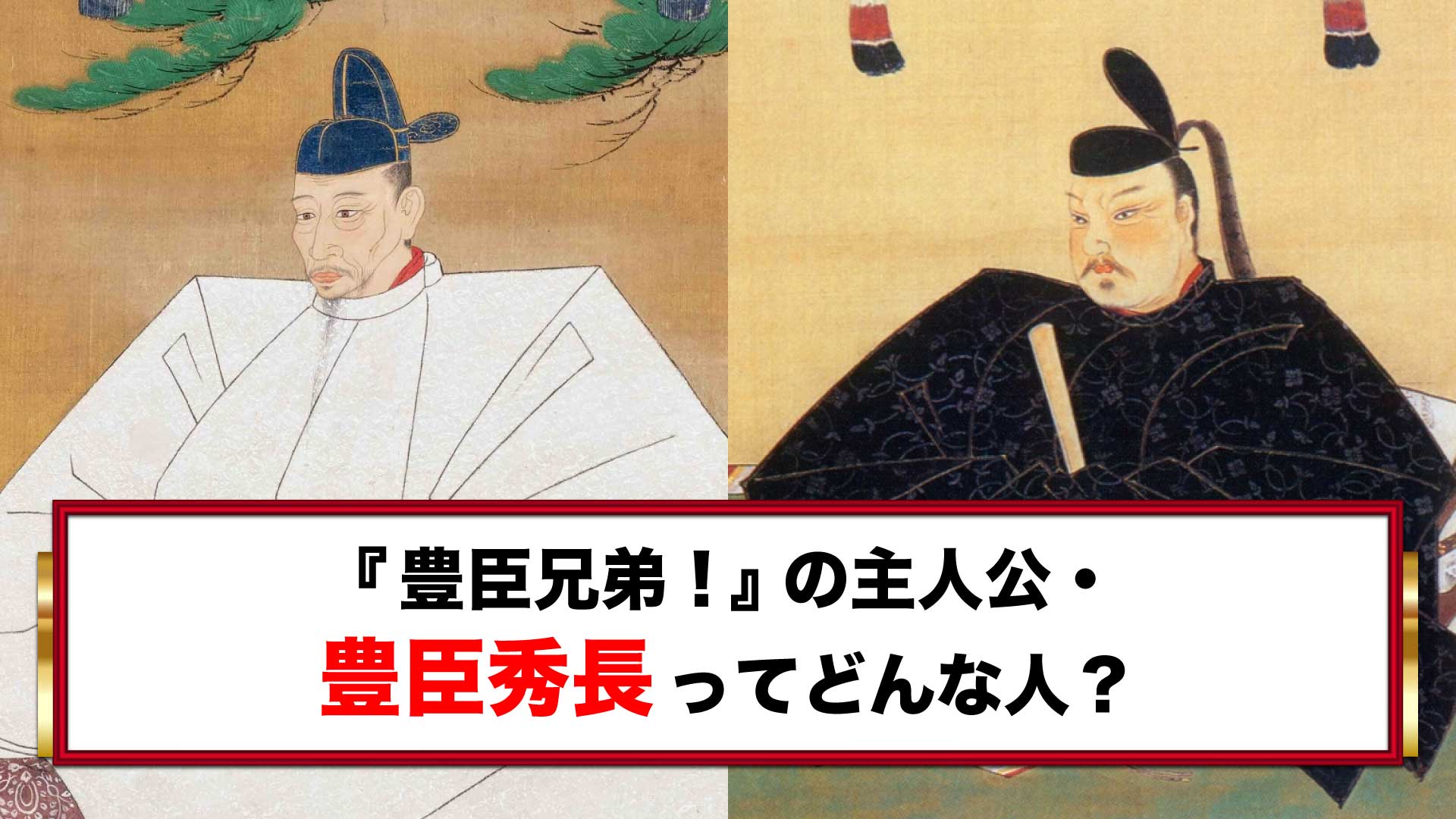

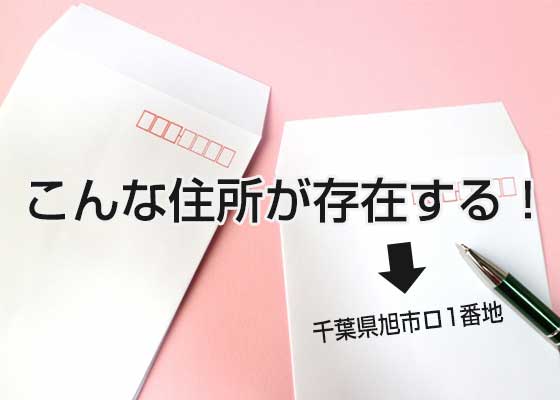


.jpg)