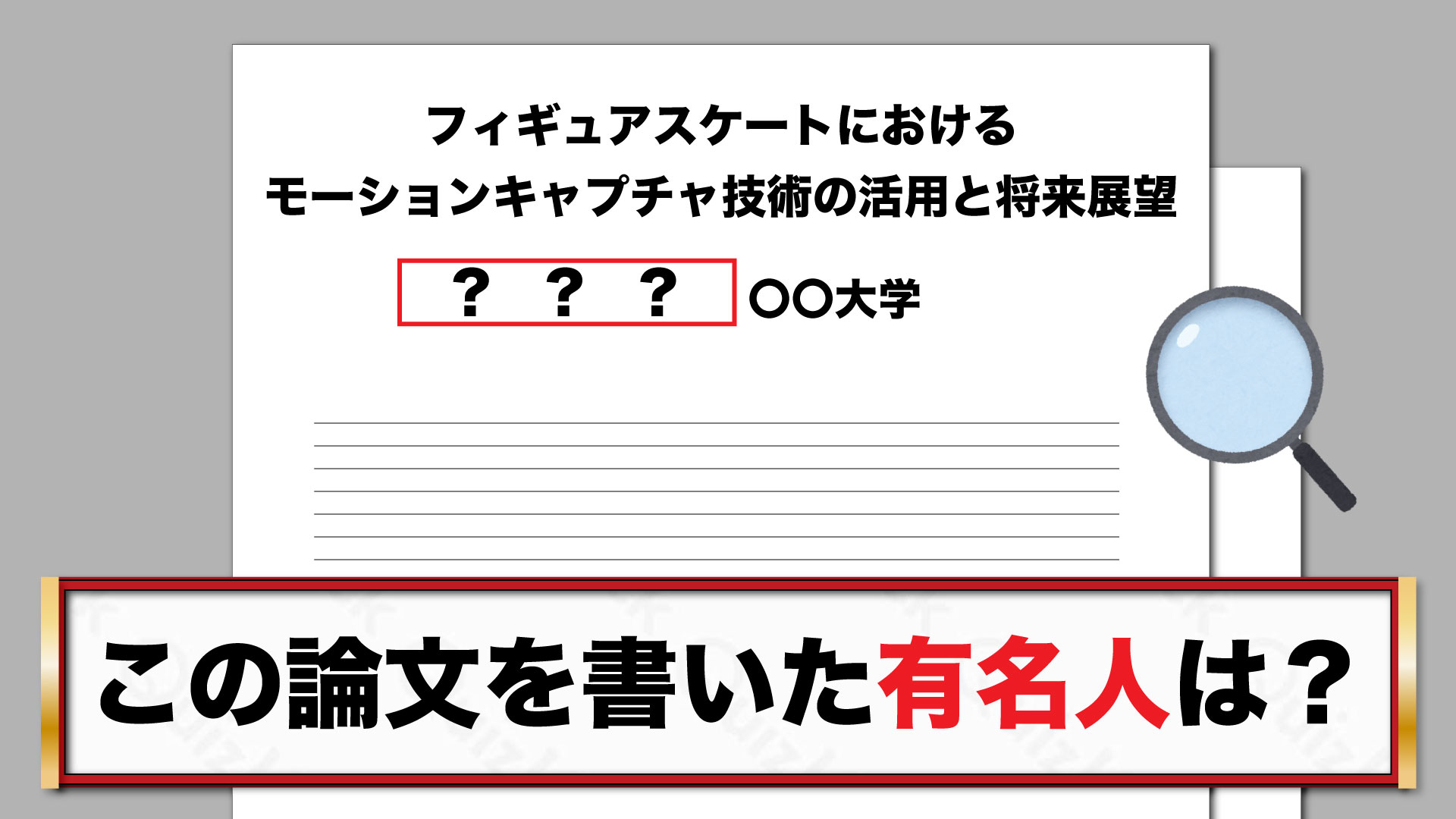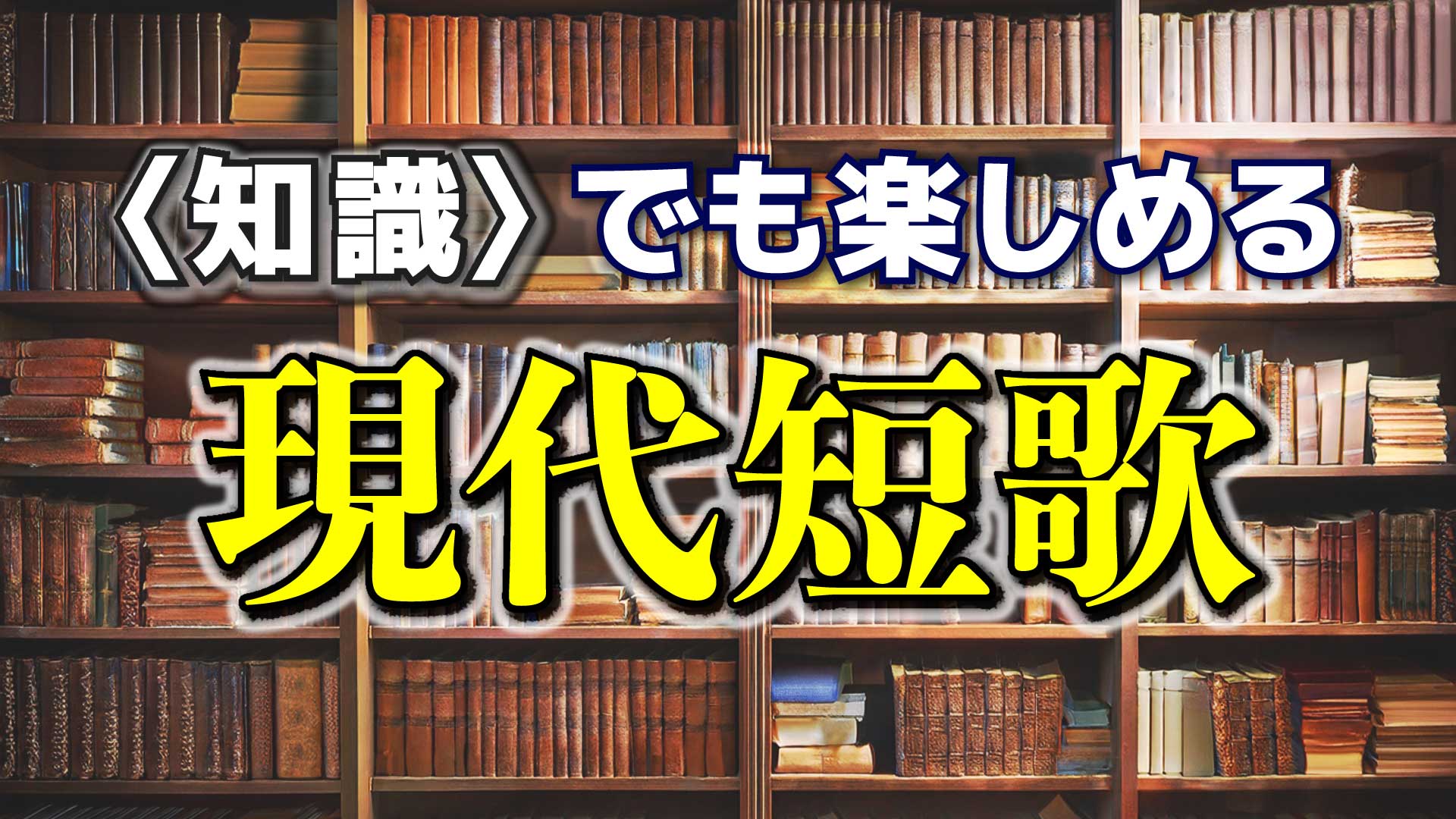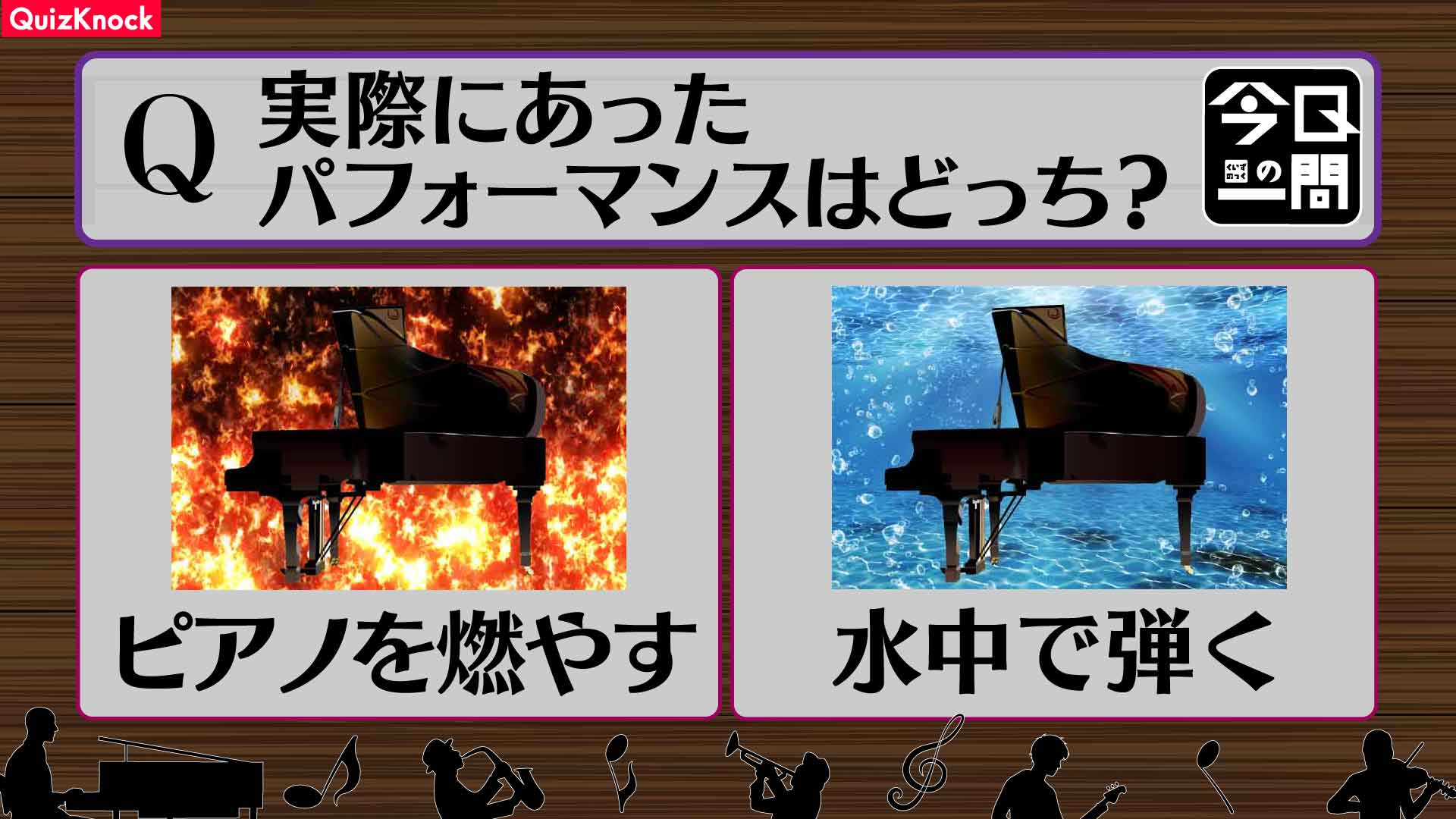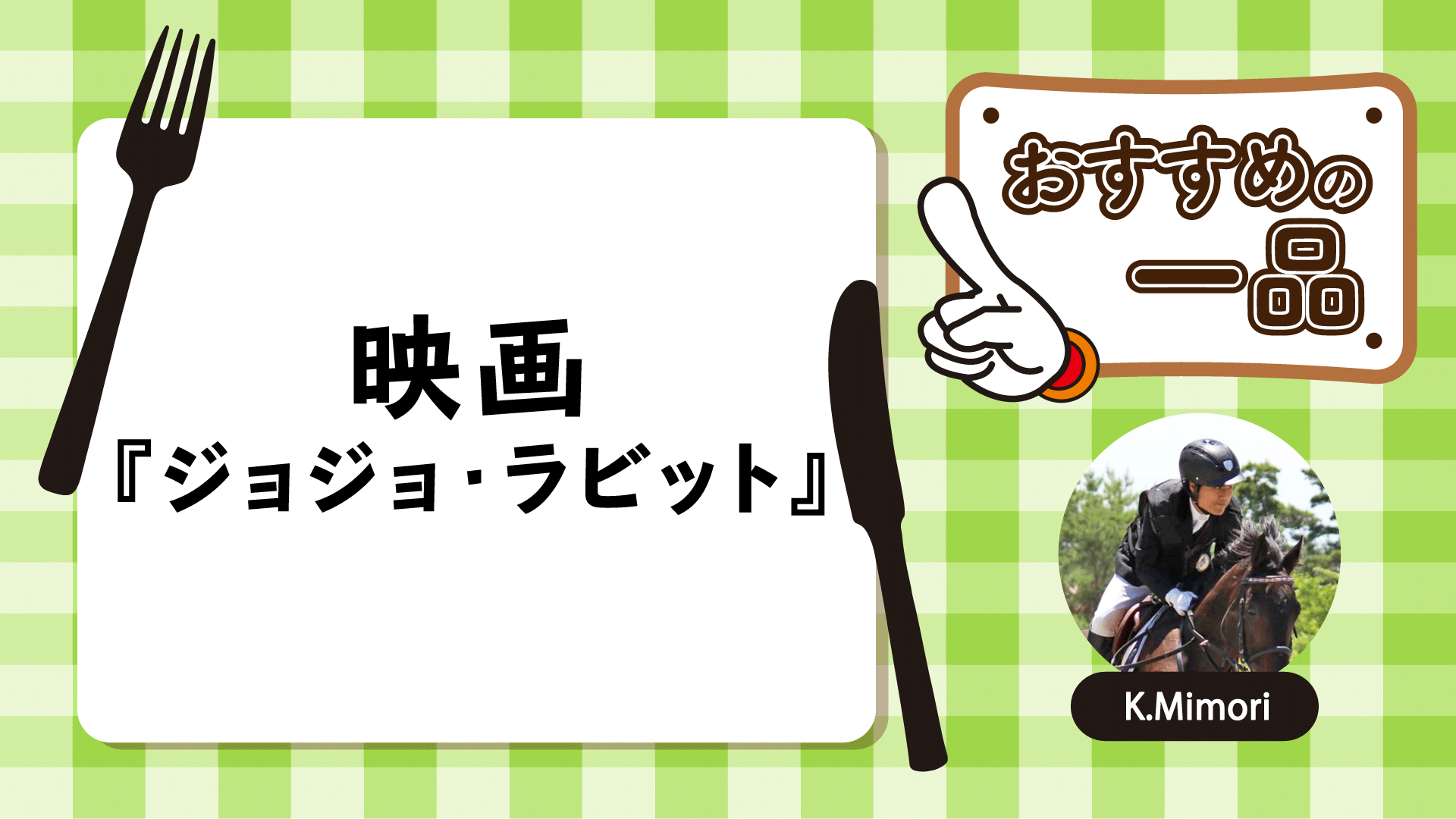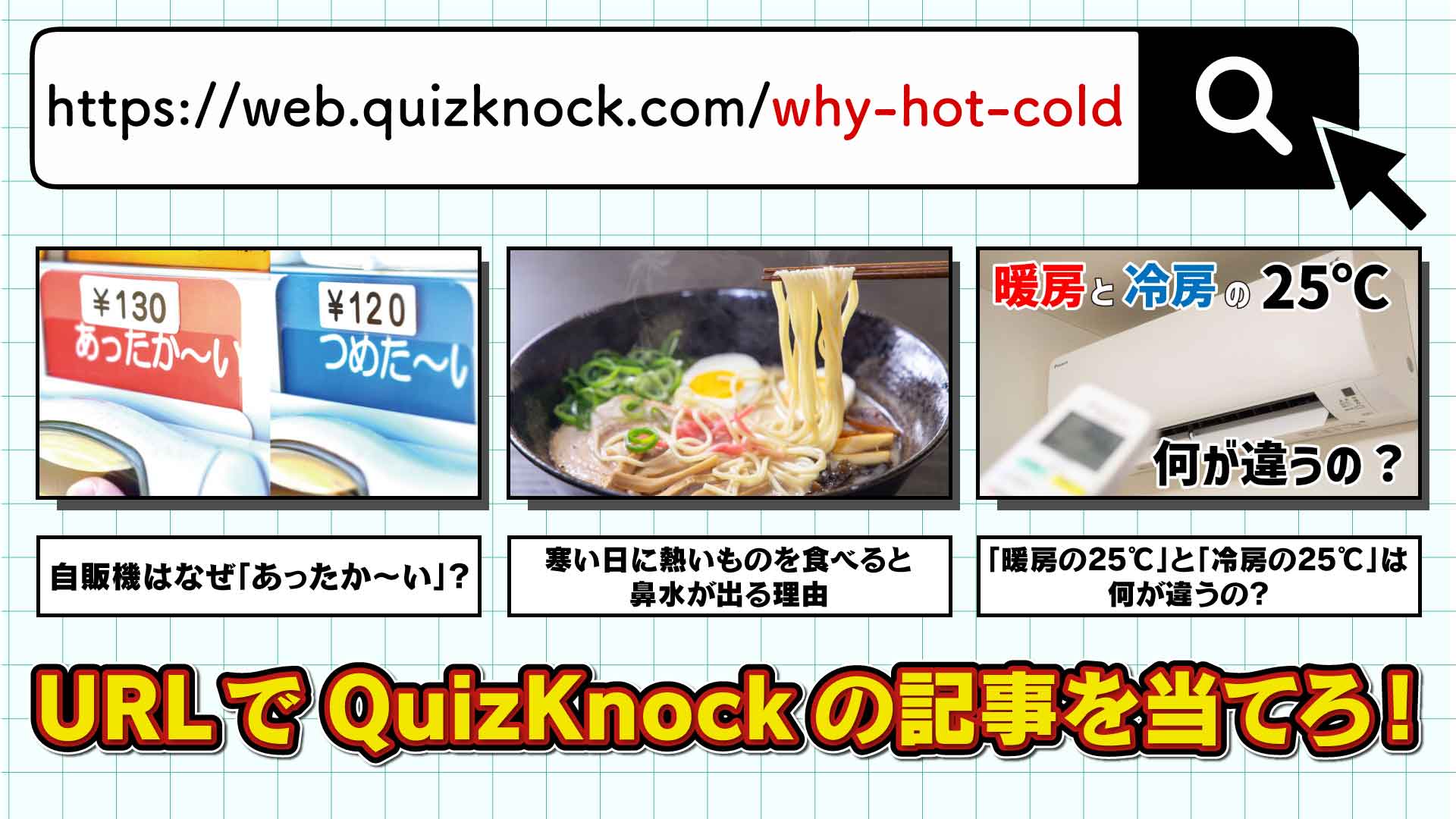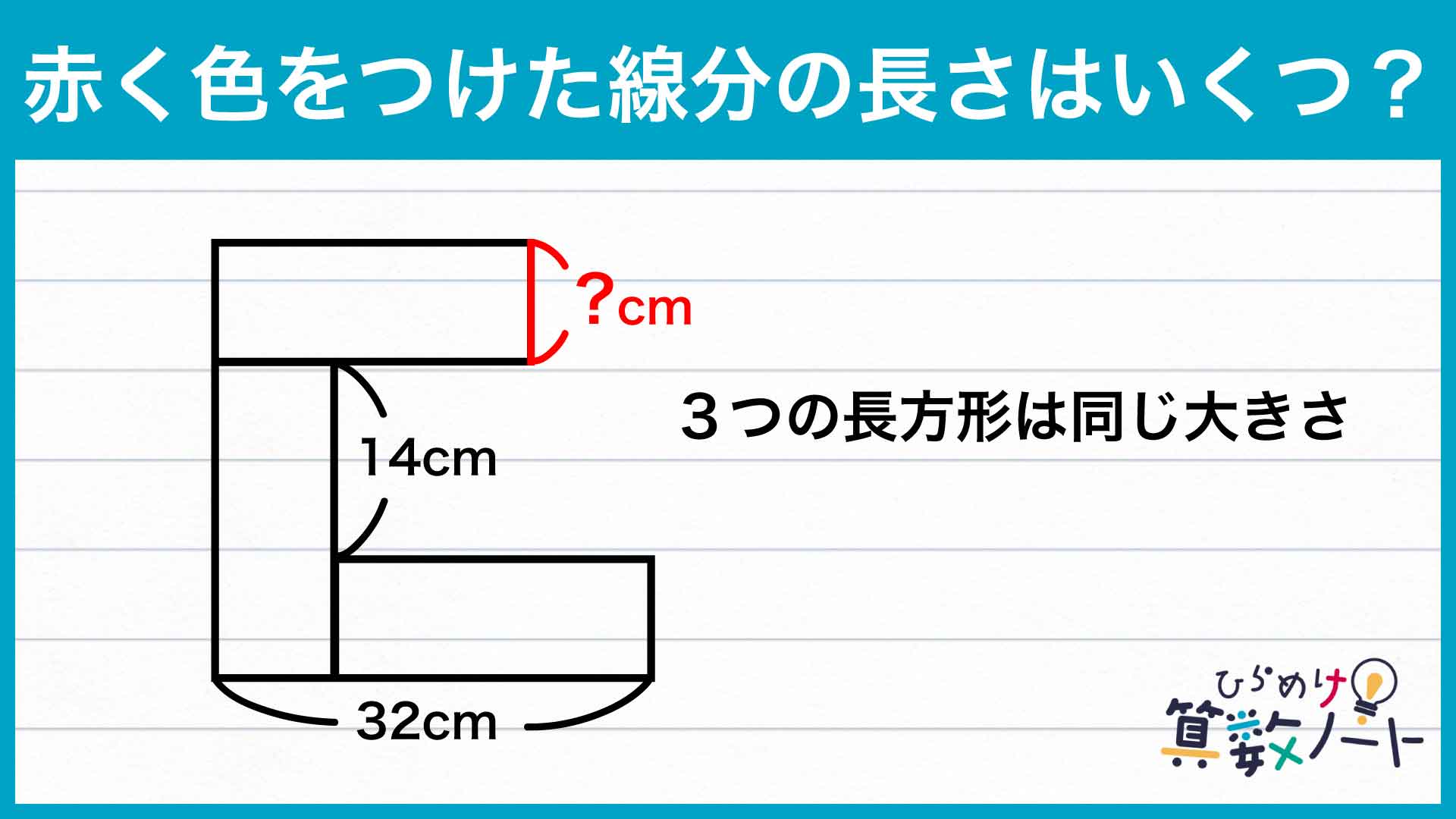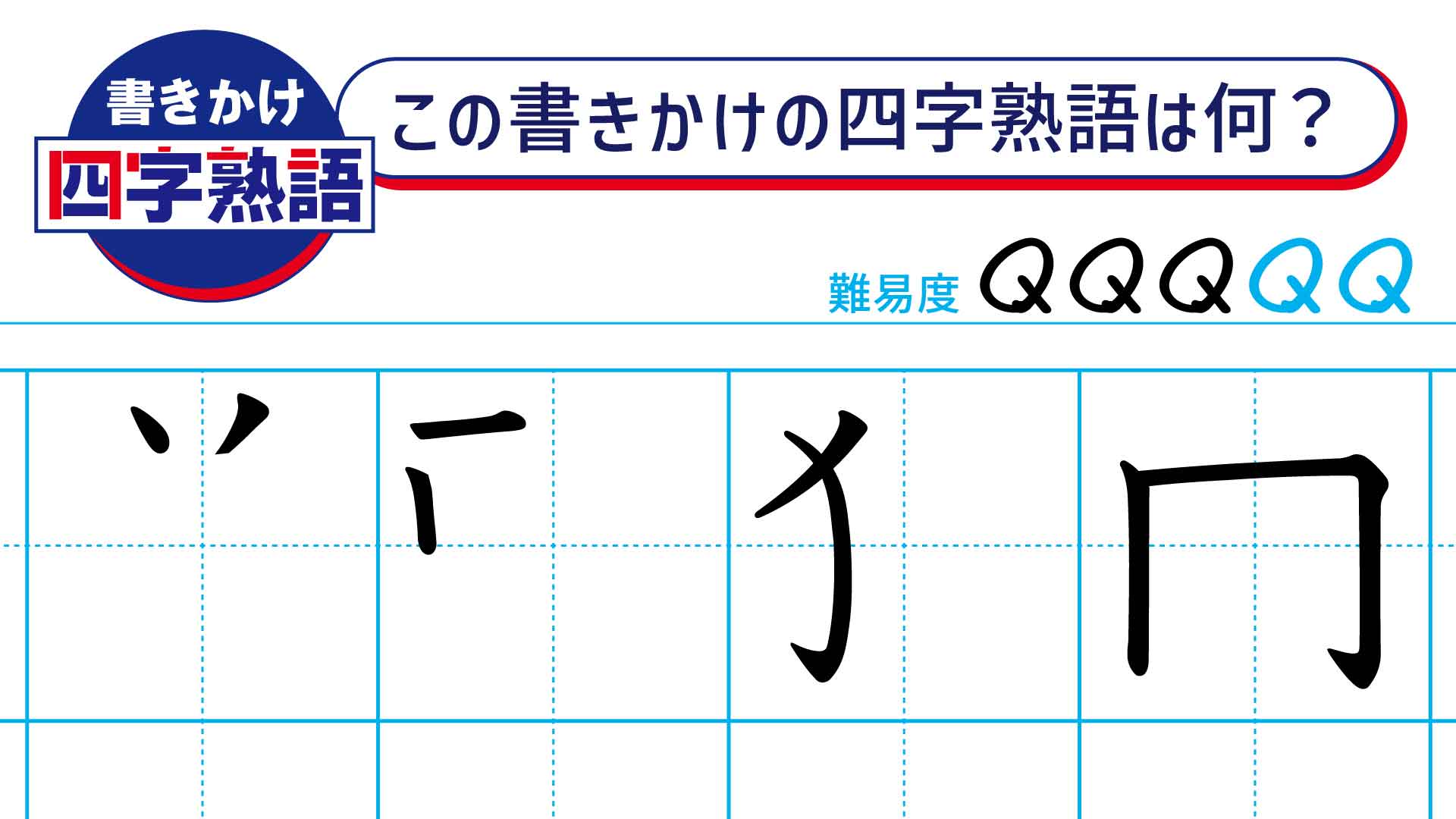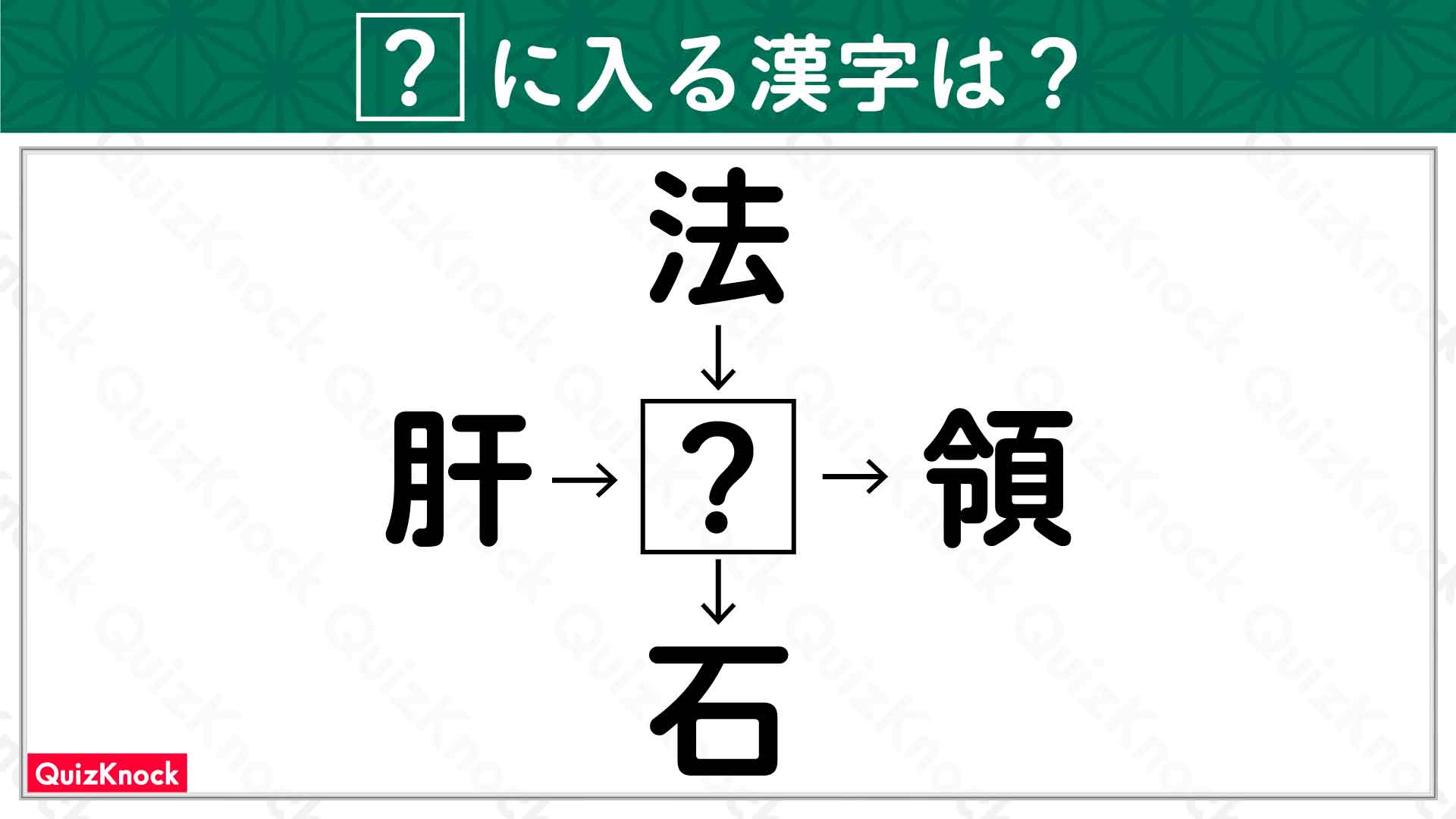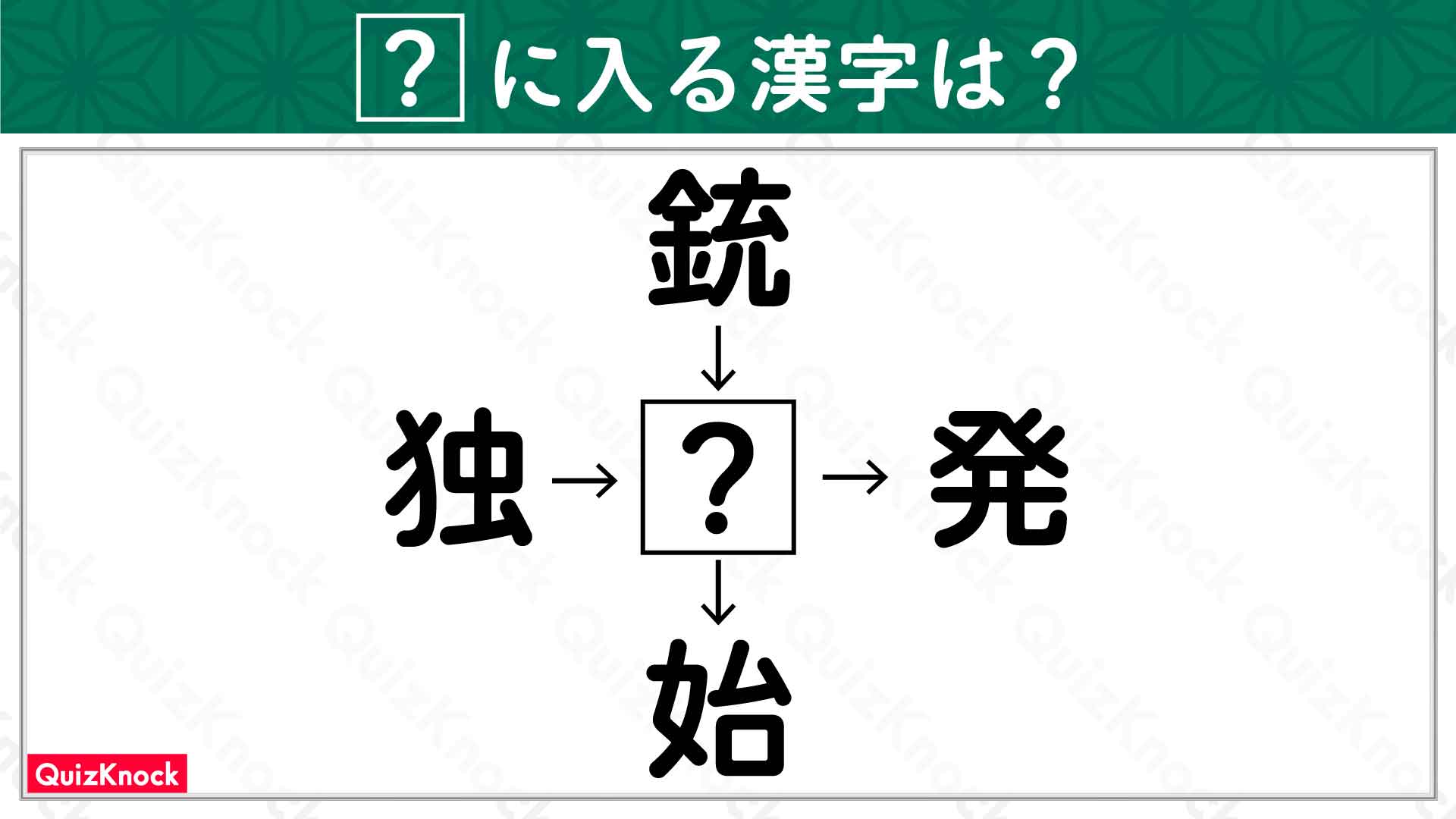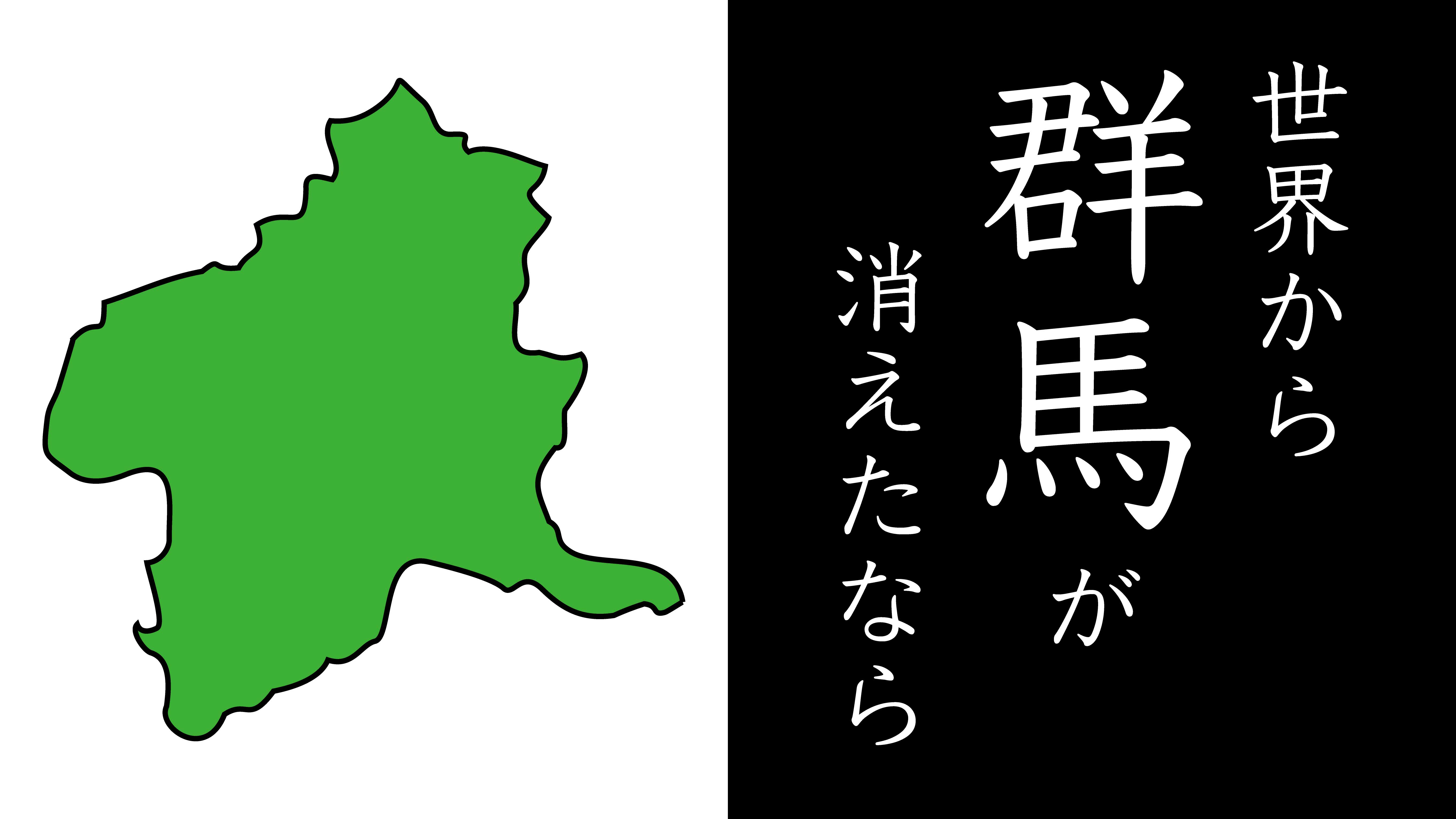昔懐かしのアイテム、風呂敷。近年ではエコグッズとしても用いられ、再評価されています。
ところで、あのただの正方形の布を、どうして「風呂敷」と呼ぶのでしょう? 「風呂敷」と言うからには、風呂に敷いて使っていたのでしょうか?

実は、当初は本当に風呂で使う敷き物だったのです。
風呂敷の上で着替えた
日本では古くより、様々なものを布で包んで運んでおり、これを「平包(ひらつつみ)」と呼びました。
室町時代頃より、この平包を風呂場で使うようになりました。当時の入浴は、全裸ではなくふんどしをして入りました。これを、着替えを持ってくるのに使った平包の上で行ったのです。
江戸時代最初期には、この平包を、風呂で敷くことから「風呂敷」と呼ぶようになったとされています。
風呂に敷かなくなった
しかし江戸時代中期頃には、ふんどしで入る習慣はなくなり、脱衣場にもカゴなどが設置されるようになったため、風呂敷を風呂に敷く必要はなくなりました。
ですがもちろん、ものを持ち運ぶための布の需要はなくなりませんでした。この布は、以後も「風呂敷」と呼ばれ続け、現在に至るというわけです。

◇参考文献
- 風呂敷の歴史|宮井株式会社
- 国史大辞典「風呂敷」








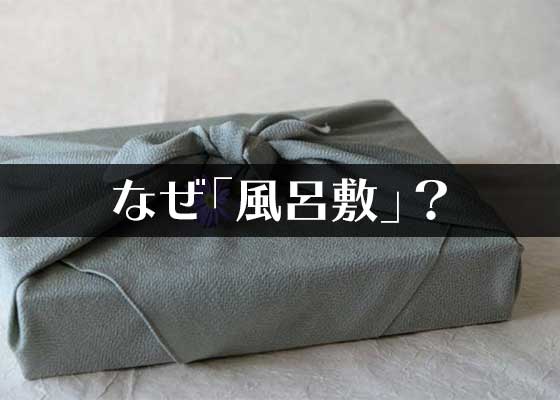

.jpg)